物語ではなくドキュメントで、しかも3時間40分と長いから、慢性寝不足の身にはずっと目を開けているのは難しかった。でも内容は知的刺激に満ちている。
本を静かに読むという「図書館」ではない。
ネットに接続できないことは人権を侵害されているとして、貧しい人にネット接続の機械を貸し出す。
ある分館では、子どもたちが入って来やすいように工夫して、数学のおもしろさを発信したら数学の本の貸し出しが急増した。
手話のおもしろさを伝える講座や、音楽のコンサート、芸術家の講演も開く。
ホームレスが昼寝に来る問題は、図書館だけでは対応しきれないから、行政に対応を働きかける。
都会で孤立しがちな人たちの関係をつむぐ場として、図書館を活用しようと試行錯誤する。
貧しい地区の分館では、学校に行けない黒人青年が学んで生きる技術を身につける。
公民館やカルチャーセンター、福祉と教育のハブのような役割を担う。そのための予算を政治家に働きかけて確保し、民間からの投資も募る。
こんな図書館があればどれだけよかろう。日本でも、評判のよい滋賀県の図書館などは似たような活動をしているのだろうか。地元の図書館に行ってみたくなった。
目次






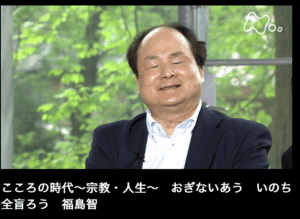

コメント