■北陸線の全駅乗歩記<澤井泰>文芸社 201403
北陸企画のネタ探しのために買った。文章じたいがよいわけではないが、北陸線とその視線の駅をすべて降りているから、北陸のそれぞれの町の概略や名所、食べ物などを知るのにぴったりだった。鉄道が好きだからでもあるが退屈せずに読めた。
==============
▽36 北陸線群に属するのは5路線。小浜線、越美北線、七尾線、城端線、氷見線。能登線と富山港線は廃止。
▽59 長浜市は住みよさランキング(東洋経済新報社)〓全国21位。
▽85 若狭街道。小浜から京都にサバなどの海産物を運ぶ街道で、鯖街道ともいう。小浜−熊川−水坂峠−保坂とたどって近江国に入りふたつにわかれる。…
▽90 北陸線の発祥区間である長浜-敦賀間の終点として、敦賀駅は1882年に開設。敦賀港に接して駅を開設したのは、敦賀に集結した北陸の貨物を早急に京阪神に輸送し、東海道線関ヶ原−大津間建設工事用の資材に搬入にあった。福井・金沢への延伸に伴い、従来のスイッチバックでは不便なので、1909年に南に2.7キロ移動させたところに二代目の駅を新設した。
▽93 寝台電車改造車 583系寝台電車。寝台撤去、出入り口増設などの改造を80年代に行った419系電車が寝台電車改造車で、中距離の普通電車として、敦賀−直江津間で運転される。
▽敦賀は昔からの貿易都市。朝鮮半島から漂着した任那の国王子のツヌガアラシトに因んだ鹿角(つぬが)が敦賀に転じたとされる。駅前には彼の銅像も立つ。(半島とのつながり〓)
平安期には、中国や朝鮮の要人・商人を宿泊させる迎賓館も設けられた。江戸から明治初期は、北陸地方の産物を集めて畿内に搬出し、さらに、北前船で敦賀港に陸揚げされた日本海沿岸や北海道の産物を中継貿易することで繁栄した。
北陸線敦賀−長浜・米原間の建設が早かったのも、敦賀が北陸道の要衝だったことに起因する。
…敦賀港は1920〜30年代に、ソ連のウラジオストクとの間に定期航路が周航し、東京−敦賀港間に国際列車も運転された。
▽95 気比神宮は越前国一宮。神宮から西へ向かい、敦賀祭りの山車を展示する「みなとつるが山車会館」などを通って、気比松原に至る(国の名勝)。
…魚の干物、塩漬け、酢漬け、味噌漬けなど、京都・大阪に運んでも鮮度と味を保てるように考案されたもの。
北海道産の良質のコンブを使ったおぼろ・とろろなどの昆布製品は140種類もあるという(海藻文化〓)。求肥昆布は、羽二重餅に昆布の粉末を練り込んだもの。
70年以上の歴史のあるソースカツ丼。
▽97 北陸トンネル 全断面工法で工期短縮。国鉄技術陣の技術蓄積がすすみ、青函トンネルなどのトンネル建設の先駆となった。
▽102 小浜線 2003年に電化されても評定速度は45キロ。
若狭 上中 北川の上中流域をしめ、若狭街道が通る。南5キロの熊川は、江戸から明治期には、納会産物の中継地、宿場として栄えた。白壁の土蔵や大屋敷の町並みは、国の重要伝統的建物群保存地区。〓
▽104 小浜 古寺が多いため、「海のある奈良」、畿内への食糧供給基地なので「御食国」ともよばれる。「食のまちづくり条例」を2001年に制定。03年に御食国若狭おばま食文化館を開館した〓。
▽109 武生 14世紀に伝えられた刀鍛冶技術を平和利用した越前打刃物の製造、絹織物、蚊帳、木工、瓦などの伝統産業を基盤に、戦後は…工業が進出し、工業出荷額は県内首位だ。越前そばも。
▽111 鯖江 江戸末期からの漆器・繊維に加えて、明治末期にはじまる眼鏡枠、合繊の発展で、…眼鏡枠は、国内で96%、世界で20%の生産量を誇る。
▽120 福井 明治初期に桐生から技術を導入して羽二重の生産を盛んに、一次大戦後は、人絹、二次大戦後は合繊を中心とする…。
名物は、越前ガニ、越前ウニ、ワカメ。料理ではソースカツ丼と越前そば。菓子では羽二重餅。絹織物の羽二重に因んで名づけられた。
▽124 コシヒカリは、福井県農事試験場で育成された。
▽126 大野 江戸期の城下町。奥越の中心で「小京都」と呼ばれる。
▽128 福井鉄道 福武鉄道が1924年に開通させた。
えちぜん鉄道 勝山永平寺線 京福電鉄の越前本線と三国芦原線を、3セクのえちぜん鉄道会社が引き継ぎ2003年に運転を再開した。
▽132 三国・三国港 江戸期に福井藩の外港、明治期以降は農海産物の移出港としての繁栄。
北潟湖は、花菖蒲園が有名。北奥の小高い丘にある吉崎御坊は、15世紀に浄土真宗を北陸に広めた蓮如上人が開いたもので、加賀や越前の国守の弾圧により、1506年、破壊されたが、18世紀前半に再興されている。
▽137 坂井市 三国・丸岡・春江・坂井の4町が合併して2006年に発足。県内第2の都市。住みよさランキングでも全国6位。
▽144 大聖寺町。大聖寺藩。歴代藩主は、九谷焼、山中塗り、絹織物などの産業を振興し、城下町を築き、文芸を奨励した。北陸道の宿場町としても栄えた。だが、錦城山に本格的な城は築けず、陣屋程度だった。(〓城下町はつまらない、という宮本常一)
実性院は、藩主前田氏の菩提寺で、萩の名所として有名。長流亭(国重文)は3代藩主がたてた別荘。
深田久弥は大聖寺出身で、「深田久弥山の文化館」が2002年に建てられた〓。
▽149 山代温泉 総湯の近くには、白山五院のひとつ薬王院があり、裏山には五輪塔(国重文)
北大路魯山人は、大正期に陶芸の修業で滞在し、当時の住居兼工房「いろは草庵」が公開される。
▽150 片山津 温泉街の北西端、柴山潟の湖畔に「中谷宇吉郎雪の科学館」。
▽150 橋立 江戸期〜明治期前半には、北前船が入港し、大聖寺藩の外港として栄えた。最盛期の19世紀中葉には、40人を超す船主、百隻を超す千石船があり、…30軒ほどならぶ船主集落は国の重要伝統的建造物群保存地区に指定。〓「北前船の里資料館」も。
▽153 山中 山中塗りは、湯治客が土産物にしたのがはじまりだそうだ。九谷焼も山中の東南12キロの九谷が発祥地とされる。
(演歌、プロテストソング〓)
▽155 粟津 温泉の南西1.5キロにある「ゆのくにの森」は、江戸/明治期の豪壮な民家を移築してつくった伝統工芸館。
さらに西2キロの那谷寺は、奇岩遊仙峡とよばれ…庭は国名勝。松尾芭蕉も「奥の細道」の旅で句をつくっている。
▽158 小松は、前田利家が金沢に居を移す1583年まで、加賀国の中心で、国府や国分寺も置かれた。
15世紀になると、浄土真宗の僧侶を中心に、土着の豪族、門徒が組織した集団は、一向一揆をおこし、加賀国守護の富樫氏を責めて1488年に滅亡させ、100年にわたって加賀国を支配した。
コマツは1916年に農業機械の業者として設立された。
▽161 安宅(あたか) 江戸期には北前船が寄港し、加賀藩の米蔵が建ち、北陸道の中継基地に。明治以降は、漁業とともに繊維産業が盛んだった。
義経が奥州に逃げる途中、家来の弁慶が勧進帳を読み上げる機転によって危機を逃れた土地と伝えられる。
▽163 根上町 江戸期には加賀藩の製塩事業をおこない裕福だった。松井秀喜の出身地。
寺井町 江戸期以来の繊維産業に加え、江戸期末にはじまった九谷焼の町として発展。県内生産量の7割を占める。九谷陶芸村には作家の工房や陶芸店が20軒ほど集まる。
▽164 能美市
▽167 美川町 能美郡湊村と石川郡本吉村が1889年に合併して成立。江戸期には北前船も寄港した。維新後、混乱している金沢を避けて1872年、美川に県庁を設置。その所在する郡名にちなんで金沢県を石川県に改称した。翌73年に金沢に県庁は復帰したが、石川県という名の発祥地となった。「石川ルーツ交流館」が建てられている。
仏壇、刺繍、海産物加工(フグの粕漬けなど)の伝統地場産業、豊富な伏流水を使った染色など繊維産業が盛ん。平成の合併で白山市に。
▽170 加賀笠間 太鼓の里資料館。和太鼓の老舗浅野太鼓が1988年に開館。世界の打楽器100点余を展示する。
▽175 松任市 円八のあんころ餅。小型の餅をあんこで包んで、包装は竹の皮。手取川や天狗舞などの清酒も。甘辛両刀遣い。
▽178 北陸本線は、特急列車の本数・種類とも多いので「特急王国」「最後の在来線」と言われる。
▽183 金沢 10村程度を1区画として民政を司る十村制などの藩政改革。藩主は華美に流れ、反省は上級家老(八家)に握られ、保守的だった。江戸後期には財政が逼迫し、藩内のの権力抗争が絶えず、打ち壊しや一揆も多発した。
▽185 三十間長屋は、鉄砲や火薬の製造兼貯蔵庫だった。
大手堀は、辰巳用水から運ばれた犀川の水をたたえる。(コマツの町人・板屋兵四郎が辰巳用水をつくった。〓千枚田)
▽192 卯辰山 金沢城を見おろすため、藩政期には町民の登山が禁止されていた。
1858年、民衆2000人が卯辰山に登り、、米価高騰による窮状を城に向けて訴えた。「泣き一揆、安政の騒動」で刑死・牢死した7人の供養で稲束を抱えた地蔵7体がちうくられ、この七稲地蔵が、茶屋街の寿経寺の門前に安置される。
▽194 金箔の生産は、金沢がほぼ独占している。加賀象眼も…。
カブラずし 輪切りのカブラに寒ブリの切り身を挟んだもの。できあがるまで40日もかかるという。
治部煮は、かもや鶏の肉に小麦粉をまぶし、シイタケ、ネギなどの野菜や加賀麩と一緒に煮込み、わさび味で食べる。ゴリ料理は、淡水魚のゴリを唐揚げ・刺身・味噌鍋などにして多部、佃煮にして保存食や土産ものに。…加賀麩は、煮物や汁物が多い金沢の郷土料理には欠かせない。
金沢の菓子文化。代表は森八で落雁の「長生殿」は、越乃雪(長岡市)、山川(松江市)とともに日本三名菓と称される。
俵屋の「じろ飴」は、米と大麦だけを原料として、菓子や料理の甘味料として用いられる。
▽197 石川県という懸命は、旧加賀国の中央に流れる手取川の別名の「石川」からとった。
▽201 鶴来 白山比メ神社 「しろやまさん」全国3000社の白山神社の総本宮で加賀国一宮。名産は「加賀の菊酒」と呼ばれる清酒で、菊姫や万歳楽が有名。
▽203 金石(かないわ) 幕末の豪商・銭屋五兵衛の出身地。北前船の回船問屋経営で財を築いた。晩年、河北潟の干拓工事で不正があったとして逮捕され、獄死した。銭屋五兵衛記念館もある〓。
▽205 湯涌。北陸の軽井沢。
▽213 輪島駅は「ふらっと訪夢」に。シベリアの看板。
▽215 羽咋 気多大社 能登国一宮 国の重文。
鹿島郡は、手織り麻織物「能登上布」の産地。
▽219 小丸山公園 利家が築いた小丸山城の跡地。眺望はすばらしい。…標高300メートルの城山にある七尾城は中世の山城の面影をとどめ、国史跡。
▽223 小矢部 市内のいたるところに建つメルヘン建築。1970年代の市長が一級建築士で、35の公共施設を自ら設計した。〓…老朽化が目立つ当今では、使い勝手や維持管理費の面で問題があるようだ。
▽224 福岡町 小矢部川流域の湿田で栽培される菅で作った菅笠、庄川扇状地の湧水で養殖した鯉が特産。
▽227 高岡 7世紀末に古代の越国(こしのくに)から分立して以来、1639年に富山藩が成立するまでの1000年近くにわたって、越中国の中心で、国府・国分寺・一宮などが置かれた。大伴家持が越中守として5年間滞在し、「万葉のふるさと」と言われる。〓
街道も分岐し、北陸道の宿場も置かれ、伏木港との河川水運も通じ、交通の要衝・集散地として発展。
商工都市として成長。梵鐘・燈籠などの銅鋳物の高岡銅器、高岡漆器、仏壇などの特産品は、江戸期の城下町から発祥し、伝統的工芸品に指定される。
戦後、銅器業者は、余剰施設を活用してアルミ鋳物の生産に進出し、その後大手アルミメーカーや重化学工業が立地した。工業出荷額は、北陸地方の都市で2位。
▽228 庄川 上中流域には、大家族制と合掌造りの白川郷・五箇山集落や水力発電所、下流域には砺波平野の散居村がある。
高岡大仏は、奈良・鎌倉に次いで3位の大きさ。高岡銅器の技術を結集して1933年につくられた。北西1・5キロの金屋町は、高岡鋳物の発祥地で、銅片が敷きこまれた石畳の金屋通りの両側には、銅器職人の格子造の家が並ぶ。
▽234 下村(平成大合併で、射水郡の大門・大島・小杉・下の4町村は、新湊市と合併して射水市が誕生)
▽235 呉羽(富山市呉羽町) 7世紀に呉(中国)から渡来した機織技術者が開いた村落。呉羽紡績の発祥地で、工場跡地に、桐朋学園大学のオーケストラアカデミーと富山市民芸術創造センターができ、「芸術を紡ぐ町」として再興した。〓(繊維から芸術)
▽238 砺波 屋敷林(カイニョ)に囲まれた農家数軒が、50−100メートル間隔で、農地の中に点在する散居村。住居が大きく、敷地も広く、持ち家が多く…
チューリップなどの花の栽培。…住みよさランキングでも全国3位。
砺波のチューリップは1920年代に水田の裏作として導入され、50年代から急速に普及し、新潟を抜いて全国一位の球根生産地となった。砺波チューリップ園は、400種100万本のチューリップが植えられ、4月から5月はみごとだ。〓
▽240 城端 善徳寺(浄土真宗)の門前町。寺は、1580年代に豪族の荒木氏が中世の城跡に建立した。城の前端に門前町が形成されたのが町名の由来という。
特産の絹織物は中世後半に発症し、江戸から明治期は、耕地の少ない山村の五箇山で養蚕をすすめ、城端で織物に加工した。
▽244 雨晴 氷見線の駅。義経岩は雨晴岩ともいわれ、義経一行が岩陰で雨が上がり、晴れるのを待ったことに由来。
氷見 耕地が少ないため、木工・縫針・釣針・行商などの副業が発達。なかでも五箇山や白川郷の合掌造りの民家を建てた氷見大工は優れた技能集団だ(〓港だからその技術が培われた? それが合掌造りを生みだした?)
藤子不二雄Aの出身地。
▽246 万葉鉄道 新湊線は加越能鉄道に譲渡されたが経営が悪化、高岡線・新湊線の廃止とバス転換が検討された。そこで、高岡市などが出資して3セクの万葉線会社を創立し、高岡線・新湊線を継承し、2002年に「万葉線」として再生開業した〓(鉄道再生) 高岡市が、市営駐車場建設をとりやめ、その予算を万葉線に充当した。LRVに。黒字化はしていないが、輸送人員は15%ほど増加。
▽249 呉羽山東麓 富山市民俗民芸村。環日本海沿岸の埋蔵文化財を展示する考古資料館、雪国の生活用具を集めた民俗資料館、売薬の資料を展示する「売薬資料館」などがある〓。
▽255 富山藩 二代目藩主は和漢薬の製薬技術・品質の向上・生産につとめ、先用後利と呼ばれる越中売薬特有の販売方法を構築した。…全国各地の家庭を回って、まず薬を置き、1年後に使った分の代金を受け取る。富山藩は反魂丹役所を設けて、製薬・売薬の保護と管理をした。
(〓塗師屋と同様、全国をまわることで文化が育まれた?)
…平成の大合併で、大沢野、八尾、婦中、細入など6町村と合併し、2000メートルの標高差、1241平方キロ(全国9位)のある市に。
▽256 空襲で市外の大半は焼失。日本海側都市では工業出荷額は北九州に次いで2位。売薬行商人4000人は日本1。全国都市の住みやすさランキングで37位(県庁所在都市では2位)
▽258 市街東部 売薬の老舗の広貫堂と池田屋安兵衛商店。反魂丹(胃腸)・通じ丸(便秘)・六神丸(心臓)などの生薬を販売。資料館では薬の歴史と製造工程を展示する〓〓両店とも、薬膳料理や薬膳喫茶を営む。
▽259 駅北口 06年にライトレールの起点の富山駅北駅ができてから整備された。富岩運河環水公園は、富岩運河の旧舟だまりを利用した親水公園。
…名物鱒寿司は、神通川などでとれた鱒を酢飯にのせて圧し、笹の葉で包んだもの。
かまぼこは、昆布で巻いた「蒲鉾昆布巻き」、鯛やエビの形をした「お祝い蒲鉾」「お祭り蒲鉾」が代表。
半透明の白エビは4〜6月が食べ頃で、春の料理によく出てくる。富山駅特選館(民衆駅)3階の白えび亭の白えび天丼。
▽262 富山地方鉄道 専用軌道が4線93.2キロ、路面電車が富山市内線の7.3キロ。市内線は2009年に万葉線などと同様に、超低床型のLRV車両「セントラム」を導入。黒字経営。
▽264 富山ライトレール 1924年に富岩鉄道として開業。43年に国有化されて富山港線に。2004年に富山市が中心になって富山ライトレール会社が設立。06年3月、富山港線は廃線となり、下奥井以遠はTLRに浄土され、4月に路面電車となって営業開始。
▽268 東岩瀬から岩瀬浜までの線路左側には、往時の繁栄をしのばせる街並みが1キロつづく。古くから漁業の中心地で、江戸期から明治期にかけては北前船の寄港地となり、コメの移出、北海道産の昆布やニシンの中継で栄えた。
北前船廻船問屋の森家など、大きな商家や料亭が並ぶ。玄関から家の裏の船着き場まで、東西に100メートル以上の奥行きがあり、土間・回廊・庭などで一直線につながる。集落内には、航海・漁業・商売などの神社である琴平社や諏訪社があり、「満寿泉」の醸造元もある。
1930年代以降、神通川の河口東岸が港湾整備され、伏木富山港の一部に。富山港展望台からは、東西30キロにつらなる港の全容、臨海工業地帯の状況を理解できる。
▽270 水橋駅 1908年建築の木造平屋の駅舎。
▽273 婦中町 イタイイタイ病患者が大勢発生。郡名は、この地方を治めた女酋長婦負の名前に由来。1942年に合併して町制を敷くさいに婦負郡の中央を意味して決めた。
▽275 八尾 室町期に聞名寺が開かれ門前町として発展。江戸期には商業の町に。養蚕、手漉き和紙などの地場産業も興した。特に和紙は、富山売薬の包装紙として使用された〓。
9月1〜3日の「風の盆」は300年以上の伝統。
▽277 国鉄神岡線は、84年に神岡鉄道になり、06年に廃止された。
▽280 早月川 剱岳周辺の谷に発して…27キロの河川。9カ所の水力発電所。
滑川 養照寺は滑川宿の本陣が置かれた。立山や大岩山への参道の分岐点なので、周辺には道標や石仏が多い。
ホタルイカは特別天然記念物。春の産卵期に海上に浮上。海上観光船やホタルイカ博物館も。
▽283 魚津 明治初期に新川県庁が一時置かれた。1918年、「米騒動」の発端に〓。
市域の7割が標高200メートル以上の山間部。
埋没林は特別天然記念物。魚津埋没林博物館も。蜃気楼資料館も併設。魚津水族館は1913年に日本海側ではじめて建設された水族館。
魚津漁港は、水揚げする魚の種類と量が豊富。尾崎と河内屋の趣向を凝らした蒲鉾。
▽288 黒部 生地駅近くに起業した吉田工業(YKK)
立山の雪が、伏流水となってわき出す。生地地区は湧水がとくに多く「名水の里」。「名水公園」は園内の流水が黒部川の生成過程を示す。名水を利用して、銀盤・皇国晴などの地酒も。
▽290 入善 立山の伏流水の名水の里。「扇状地湧水公苑」。海洋深層水施設も。
▽292 越中宮崎駅。ヒスイ海岸を東にすすむと県境。朝日町から新潟県青海町に入る。(ヒスイ〓梅原の学説)
朝日町 中心部の泊は、北陸道の宿場町だった街並みがつづき、大庄屋で本陣だった伊東家が残る。不動堂遺跡は、縄文中期の公共的建物と推定され…
たら汁が名物。
宮崎から県境までの4キロの海岸は、ヒスイの原石が打ち上げられるので「ヒスイ海岸」と呼ばれる。
▽295 富山電鉄・越中舟橋 駅は村立図書館と合築(〓図書館と駅の組み合わせ)。舟橋村は面積は県内最小。戦後1600人だった人口は80年代に1300人に減っていた。
村立図書館は5万5千冊の蔵書。交流・文化の拠点に。1人あたり50冊の貸し出し。宅地造成を村がおこない、今では人口3000人に。富山駅まで13分。
合併の誘いを断り、住民自治により独自の路線を歩む。(〓生き残る「村」)
▽298 宇奈月1923年に日本電力(関西電力)が電源開発の際、上流の黒薙温泉から湯を引いて温泉場を開いてから急発展した。
▽300 黒部峡谷鉄道 20キロの軽便鉄道。1926年に日本電力が水力発電所を建設するために敷設。10駅あるが一般客が乗降できるのは4駅のみ。冬季休業する鉄道〓。
▽303 富山地方鉄道立山駅 駅裏には立山砂防軌道(17.6キロ)の車両基地。
▽305 室堂 駅裏の「玉殿湧水」 立山室堂は、加賀藩がたてた最古の山小屋。
▽317 新潟・青海 姫川は構造線に沿って下る急流。流域でヒスイを産出。
▽320 糸魚川市 この地を支配した奴奈川氏の娘の奴奈川姫と、姫川の支流小滝川で産出されるヒスイを求めて、出雲国から接触してきたという。
▽322 糸魚川駅「ヒスイロード」。長者ケ原遺跡は縄文中期。最初にヒスイの原石を加工して勾玉などの玉を生産した場所。
▽326 小滝駅「ひすいのふるさと」の看板
▽348 日本の鉄道は1872年の新橋−横浜間、74年の大阪−神戸間の開業後、東京−京都の間の幹線鉄道を建設することにし、東海道と中山道を比較検討した結果、83年に中山道経由に内定した。84年には上野−高崎、85年には高崎−横川が開業した。86年には直江津−関山間が開業。ところが横川−軽井沢の途中の碓氷峠の地形が険しいため、86年に幹線鉄道の経路は中山道から東海道に変更された。高崎−直江津の全通は93年だった。
宇奈月温泉


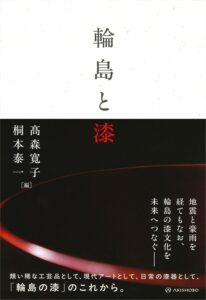

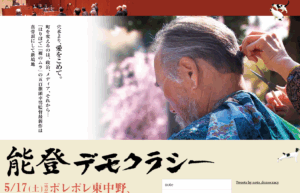
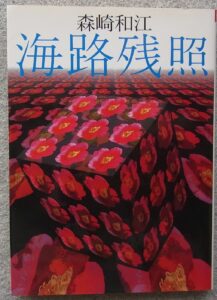

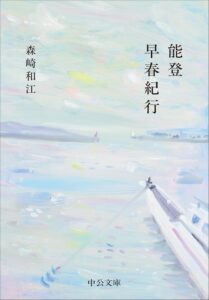
コメント