■北国新聞社 20230528
北陸から相馬・中村藩(福島)への真宗移民について知りたくて入手した。
天明の飢饉で、奥羽では、農民が故郷を捨てる流亡が相次いだ。50年後の天保の飢饉でも多くの農民が餓死し、町への逃亡者が続出し、人口が3分の1に激減した。田畑は荒れ放題となった。
子を養育できない農民が嬰児を殺す「間引き」を相馬中村藩は禁じ、子供の出生にあたって養育費を支給するなどの措置を講じたが効果はあがらない。
一方の加賀は真宗王国で、生命尊重の教えから「間引き」が禁じられていた。人口が急増し、加賀藩農民人口は1648年の15万人が1787年には4倍の59万3000人になり、土地をもたない頭振(小作人)が増えた。
東西本願寺は、天明・天保の飢饉以後、加賀藩領内に移民使僧を密かに送りこみ、まずしい農民を北関東・東北におくる工作をした。幕府代官領間での入百姓は日本海側の「飛地」から合法的に浄土真宗門徒を送りこんだが、相馬藩や笠間藩への移民は非合法だった。
相馬藩では藩主に累がおよばないよう藩士が職を辞し、飴売りや旅芸人に変装し、富山の薬売りが全国を渡り歩くのをまねて加賀藩領にはいり、北陸農民をリクルートした。
相馬をたたえる民謡はその武器だった。隠密としてもぐりこんだ彼らは、加賀藩によってとらえられ、処刑されることもあった。
農民のしるした「加賀泣き」巻頭文は「相馬節」ではじめられている。
「相馬よいとこを夢にまで見た私たちの先祖は懐かしい故郷を捨て、御仏壇の阿弥陀如来の御影像をまるめて、これをふところにおさめ、はるばる北陸の地からこの地にやってきた。あこがれの夢はたちまちに消えてしまった。なるほど、天明、天保の飢饉のため住民は3分の1に減り、あちこちに空き家もあったし、土地もあったが、よい土地はみな土着民のものになり、山間の荒れ地や、やせ地しか残っていなかった。…本当に寝る夜も寝ないで働いた。…」
暮らしが向上すると、今度は土着民の排他心をそそり、「よそもの」「加賀のどん百姓」などとののしられた。
「今に見ていろ、と涙をおさえて我慢したが、家に帰ると涙がどっとあふれ、むせび泣いた。このくやし泣きを当時「加賀泣き」といった」
彼らは寺にあつまって慰めあい「南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏」と念仏を唱えた。すると今までの悲しみも苦しみも不思議に消えて、すがすがしい気持ちになれた……。
当時は浄土真宗の信仰が生き方をささえるものとして生きていたのだ。
真宗移民の実情がわかって興味深かった。
本の後半2/3は、明治以降の北海道移民の話だ。失業した士族は屯田兵となった。屯田兵の数は石川県出身がもっとも多かった。一般移住をふくめると石川県は9万5000人あまりで1位だった。北前船のつながりで北海道移民が多かったとは聞いていた、明治政府の北海道開拓を支持することで、廃仏毀釈で弱体化した教団の再興をはかる東西本願寺の方針も背景にあったという。
=======
▽5 廃藩置県後、県境をこえての交流が衰え、山間部の宿場や山道街道は寂れた。貨幣経済に移行するや、働き手は鍛冶職人、運搬人、温泉場の奉公人として、遠くは都会へ風呂たき、大手鉱山のコウフとして出稼ぎにでなければならなかった。…過疎化現象へ。
…海浜の村では、県、市町村間の道路建設が進行していった。天候に左右される海上輸送は衰退していった。
…城下町では、士族たちが失業の身となった。失業士族授産対策の一環として、政府は北辺の守りと称して北海道屯田兵制度を設置し…般人にも北海道移民としての渡道の便宜をはかった。
廃仏毀釈により多くの寺院が廃寺、転出を余儀なくされた。各宗派は寺院拡張路線の場を北海道にもとめた。
▽8 苗字 神社の下にあったから「宮下」、川下の人は「下野」…姓はつけたが、まともに呼ばなかった。「天井」「上井」の姓は川上に居住地があり、村の中心地には「元谷」があり、山の傾斜地には「荒井」、川辺には「河原」、山手の雑木林は「木谷」。
▽11 江沼郡と北海道は古くからつながっていた。「松前」の地名は、松平の「松」、加賀前田藩の「前」の字を一字ずつあわせてつけられた。
江沼郡橋立・塩屋・瀬越からは豪商と名の付く北前船主が数多く輩出。…西出孫左衛門は明治中頃まで函館山の大半を手中にしていた。
▽12 加賀は真宗王国。「間引き」は禁じられ、それ故土地をもたない「頭振」が多く、その対策として東西本願寺は江戸中ごろから寺院拡張のため、天明・天保の飢饉以後、外様加賀藩領内に移民使僧を密かに送り込み、名高百姓・頭振を北関東・東北に欠落させた。非合法的に送り込んでいた。…巡拝にかこつけて欠落させることもあった。
幕府代官領間での入百姓は日本海側の「飛地」または前赴任地から合法的に浄土真宗門徒を送り込むもので、寛政5(1793)の早くから移民を引き入れる先駆となった。北陸農民の走り移民は明治二年までつづいていた。
▽12 江戸時代、東西本願寺は幕府側に協力的だった。新政府が誕生すると、維新政府の北海道開拓政策に便乗し、信徒移民の北海道導入を積極的に推進した。これが結果的に本願寺寺院教線拡張と相関連した。
大谷派は、農民を送り込むため、社会的ムードづくりとして「醉歌」をつくり流行させた。
▽13 かつてこのような醉歌による宣伝で、相馬藩の隠密が本願寺使僧と結託し、旅僧に身をやつして北陸農民を相馬に欠落させた。特に相馬藩では藩士が藩に累が及ばないように職を辞し、飴売りや旅芸人に変装し、富山の薬売りが全国を渡り歩くのをまねて加賀藩領にはいり、相馬民謡を流行させた。相馬をたたえる民謡によって移民誘致は成果をあげた。
農民の書き記した「加賀泣き」巻頭文が相馬節ではじめられている。
「相馬よいとこを夢にまで見た私たちの先祖は懐かしい故郷を捨て、御仏壇の阿弥陀如来の御影像をまるめて、これをふところにおさめ、はるばる北陸の地からこの地にやってきた。あこがれの夢はたちまちに消えてしまった。なるほど、天明、天保の飢饉のため住民は3分の1に減り、あちこちに空き家もあったし、土地もあったが、よい土地はみな土着民のものになり、山間の荒れ地や、やせ地しか残っていなかった。・・・本当に寝る夜も寝ないで働いた。・・・
お陰で少しずつ暮らしは楽になったが、これが却って土着民の排他心をそそり「よそもの」としてさげすまれ「因幡もの」あるいは「加賀のどん百姓」とののしられ、いじめられた。そのたびごとに「クソ今に見ていろ」と涙をおさえて我慢した。でも我が家に帰るとさすがにこらえていた涙がどっとあふれ、声をしのんでむせび泣いた。このくやし泣きを当時「加賀泣き」といったのである。
・・・彼らは自分達のお寺に集まった。
慰め励まし合い「南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏」とお念仏を唱えながら、ただ一筋に阿弥陀様におすがりした。すると今までの悲しみも苦しみも不思議に消えうせて、すがすがしい気持ちになることができたという。・・・げにこの「加賀泣き」の涙こそ尊いものであり、私たちはご先祖の苦難をいつも思いおこしいつまでも忘れてはならないと思う」
▽15 天明年間の飢饉で、奥羽地方では、農民が故郷を捨てる流亡が相次いだ。さらにつづいて50年後の天保の飢饉でも数多くの農民が飢えで死亡したり、町へ出て食い扶持を探し、転業を図ろうとする逃亡者が続出したため、人口が3分の1にまで激減した。空き家が続出し、田畑は荒れ放題となった。
…相馬中村藩では、対策として農民に間引きを禁じさせ、子供の出生にあたっては養育費を支給するなどの措置を講じたが、急場しのぎにはならなかった。
▽19 天明・天保の飢饉は東北地方を中心に全国で数十万の餓死者をだした。農民の間では、子を生んでも養育することができないので、間引きといって、生児を圧殺する風習が続出した。
…江戸時代の人口は2500万から3000万の間(そのうち武士は約200万)を上下するだけで停滞していた。
…相馬藩では、天明7年は人口32247人。元禄15年に比べれば57250人の減少で、6割3分9厘の減少。おれより後は増加し、文久元年には、52600人にいたった。
…文化・文政以後、合法・非合法的手段で北陸農民の移民がはじまる。
白河藩主松平定信は越後に飛領地があることから「女を呼び寄せる」政策をすすめ、寛政2年には元の人口に戻すことに成功していた。これら多くの農民は間引きを禁じる浄土真宗門徒たちであった(合法)
…飛び地がない笠間藩・相馬藩は、加賀藩城下に本願寺使僧や商人に扮した武士をひそかに送り込んで加賀農民の欠落による移民の引き入れを図った。非合法的な手段でしかおこなえなかった。
…浄土真宗大谷派西念寺良水は、間引きを否定する北陸の浄土真宗信徒を移民として導入し、…と提言。北陸は関東とは逆に人口過剰で土地が不足し農民は窮乏していることを北陸勧化の折りに知ったという。労働力解消、農民の生産意欲を向上するには北陸より浄土真宗門徒を移民することが先決だと説いた。(笠間藩)
親鸞は1214年、茨城郡稲田村西念寺を拠点として20年間布教にあたったところであり、稲田禅坊とも称され、親鸞の関東遺跡寺院の筆頭に位置していた。江戸時代にはいると、江戸への農民流出で門徒が減少し、西念寺の維持が困難になっていた。寺も藩主同様寺院の維持に苦しんでいた。
良水は、笠間藩の入り百姓として定住していた2人を加賀に向かわせ、零細農民、頭振などに移民の勧誘にあたらせた。その条件は当初農具代4両、他に家作・馬糧・種穀十カ年賦で貸し与えることで交渉した。この好条件によって笠間藩領への移民は順調に進んだ。
…ところが、農民の逃亡・欠落による移民計画を加賀藩が察知、…良水は藩に責任がおよぶのを恐れて文化2(1808)年に自刃した。
▽27 5年後の1810年、加賀藩から相馬へ布教のために訪れた大谷派の僧・闡
教が陸奥宇多郡馬場野村(現福島県相馬市)に東福
庵を開き、〓教。相馬中村藩と移民について交渉。浄土真宗寺院拡張を条件として加賀藩から水呑百姓・頭振をおくりこむこと。非合法。以後、本願寺使僧が移民の中心的役割を果たすことになる。…家老職の久米泰翁が、藩主に累が及ばないよう要職を辞退し一個人の計画として移民を勧誘することにした。
▽30 「温故知新”先祖十右衛門を偲んで」の著者杉内氏は石川県石川郡小島村で東福庵を開いて仮住まいをしている東本願寺の密使であったと私に語った。
▽32 伏見儀助は、加賀藩に侵入して相馬移民の宣伝をしたことから捕らわれの身となって処刑されたと…
▽34 相馬の杉内氏は私にはっきり〓教は「石川県石川郡小島村に東福庵を構えて居られた」と断言する。
▽36 加賀藩は浄土真宗が深く浸透し、真宗の生命尊重精神の立場から間引きをしないため土地の割合に対して人口が過剰だった。
加賀藩農民人口は1648年の15万人が1787年には4倍の59万3000人に。(北陸農民の北関東・東北移民の著者竹内氏)
▽38 江戸時代中期以降金沢は個数12万、三都に次ぐ大都市になっていた。人口密度は超過密。
▽43 明治2年以降、東西本願寺は浄土真宗農民を北海道に団体移民として送り出し、浄土真宗寺院拡張に乗り出す。
廃仏毀釈令で真宗寺院の教線拡張の道はたたれた。…新政府の北海道開拓政策に呼応する。
▽107 「橋立漁港は、浅瀬で船を横づけできない。北前船主の伝馬船で沖合に停泊中の船まで運んでもらい、やっと北海道に渡った」
▽170 北陸地方、冬場に積雪で仕事がなく「口減らし」のため、大阪、京都、名古屋方面に出稼ぎにでかけた。主に風呂屋の下働きが多かった。そのうち、その地で独立し、僻地、寒村を去っていった。
▽183 三国港は九頭竜川の河口にあって水深25メートルで汽船が横付けできる。塩屋港は文久、文政のころ、大聖寺川の土石で浅くなっており、良港とは言えません。
▽196 屯田兵の出身者は石川県が492人で全国でもっとも多い。一般移住を含めると石川県は9万5000人あまりで1位で、富山県は8万人で4位。
▽214 那谷寺は、西国1番の那智、最後の札所の谷汲の頭文字をあわせて花山天皇が命名したことに由来。
当時の開拓のリーダーはすごい行動力 勇気。人間のスケールがちがう


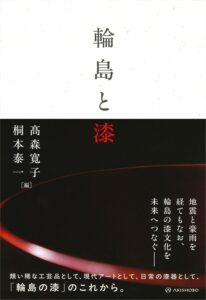

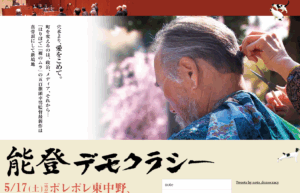
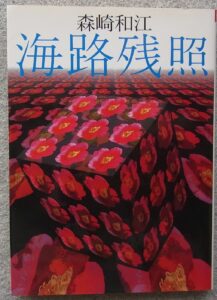

コメント