■医師藤野厳九郎<土田誠> 20141004
著者87歳で書いた本。元新聞記者。小説風に記してあり、とても読みやすい。幼いころ藤野の診察を受けた。新たに20人に取材したという。
・見渡すかぎり水田がつらなる越前平野に20数年ぶりに帰ってきた。
・父も祖父も、福井藩の御殿医にもなれるところだが、代々公職には就かず、この地で開業してきた。
・あわら温泉は、厳九郎が小学校を卒業するころ、農業用水の井戸を掘ったところ60度を越す湯我出た。次兄の明二郎は温泉に病院を建てていた。
・「うーん、国か。国は悪いことをするな。国なんぞ信用せんぞ、おれは」。制度改革で生まれた東北帝国大学教授に残れず、退官させられての帰郷だった。
・赤い目をしてヤニを出している子。鼻水がとまらない子、耳だれの子が多い。子どもたちの病気の勉強会を開く。母に頼んで無地の木綿の布を手ぬぐいの半分ほどの大きさに裁断したのを、30枚ほどつくってもらった。歯を磨くこと、よくかむこと、手を洗うこと。
・三国町で開業。新しい妻は20歳年下。
・次兄が死んで、下番に医院をつぐ。「患者覚書帖」を作成。65歳以上の老人を往診しはじめる。
・米のとれ高の五割近くを年貢で納めなねばならないのでは、身体がつらくても仕事を休めず、医者にはかかれない。
・腹が痛いという子どもには、口に入れた物はよくかめという。とにかくかみなさい。薬は別にいりませんという。「腹八分目医者いらず」といって、食べ過ぎはいかん、胃が下がると内臓全体が下がることがあって長い病気になる。「中学校へ入らんでもよい。勉強させたいのだったら、午前中勉強、午後は軽い野良仕事をして、身体を鍛える農学校に入れなさい」と進学指導までする。
・「国か、国は悪いことばかりするな」
・日本は中国から文化を教えてもらっている。韓国はその仲立ちをしてくれた仲間である。なのに、植民地化したり攻撃するようなことをするのは間違っていると厳九郎は思った。「中国と戦争するのはあかん」と患者の前で軍を批判したりした〓。
・治安維持法 特高にみはられる。農民組合の幹部が来ていたから。
・おいが下番の診療所をやることになり、中番に移る。
・東京から3人の男が来た。地元出身の新聞記者ら。魯迅という世界的な文学者がおりましたが、つい先日亡くなられました。「先生にもう一度お会いしたい」「お会いできないなかったら、消息でも知りたい」といいながら亡くなってしまわれた。
…「彼は偉大である。自分が師と仰ぐ人の中で、彼は私を最も感激させ、励ましてくれた一人である」と書いています。
・長男の恒弥が東北帝大の医学部に入学。次男は海軍兵学校へ。
・長男の徴兵に際し、軍刀は800円近くもし、手持ちのカネがなかったので、分家や円右衛門など地主から300円ほど借りた。「薬を売ったら」というと「薬は医者のものではない。患者のものだ。特によい薬は手放せない」。
・長男は広島で戦病死。半年後の昭和20年8月10日に倒れる。「戦争は…戦争は…」「国のない国はないか」などとわけのわからないことを言った。翌11日死去。
■魯迅と藤野厳九郎 芦原町教委 20141001
・魯迅(周樹人)の「藤野先生」に書かれた「ひどく上がり下がりのある口調」とは故郷の福井なまりだった。
・他の中国人のいない土地で勉強するため、仙台医学専門学校に来た。
・藤野の祖父は蘭学を学んだ。父は緒方洪庵の適塾で学んだ。
・中国人がロシアのスパイとして処刑される画像を見た。それを見守る中国人の無表情さがたまらなかった。からだが強くても、精神が生きていない国民はだめだ、と。医学をやめる決心をする。
・藤野は中国人留学生に親切にした。
・魯迅逝去の記事を手にして地元出身の新聞記者らが藤野を訪ねてきた。そのときの取材内容が雑誌に計刺され、「藤野先生」が福井にいることが知られるようになった。
・「中国は日本に文化を教えてくれた先生だ。こんな戦争は早くやめなければならない」と言っていたという。
・藤野の故郷・下番にも、魯迅令息周海嬰が碑銘を書かれた碑が建てられた。
・三国町宿にあった旧宅が芦原町に寄贈された。
・魯迅が仙台で出会ったのは、中国に対する別紙であった。日本人が中国人を見下すようになったのは、日清戦争からだといわれる。
・藤野にとって漢学は、その倫理性によって、生活の中心を占める重要な理念だった。


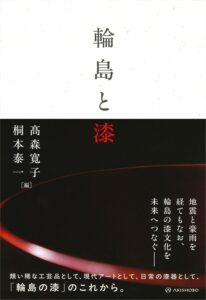

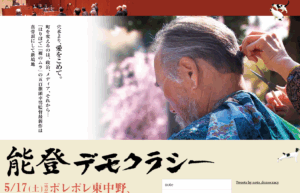
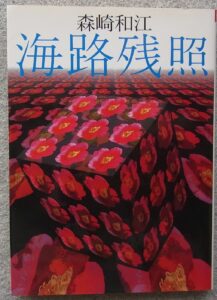

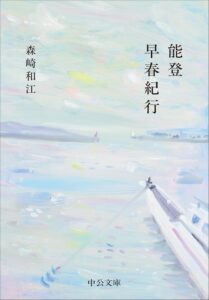
コメント