■彩流社202307
東京新聞の女性記者が、阿武隈山地の里山の人々と、稀有な写真家の導きで成長する物語だ。
舞台は福島県の阿武隈山地にある旧都路村(2005年から田村市)。
都路は、全国でも有数のシイタケ原木の産地だった。
「シイタケを栽培するための原木の一大生産地であったのに、放射能による汚染のために、生産ができなくなり、原木シイタケの生産もとまっている」
写真家の本橋成一さんのそんな言葉をきっかけに2018年から筆者は都路にかよいはじめる。
福島第一原発事故の「被害」の取材のつもりだったのだろうが、当初から山の暮らしの豊かさに圧倒される。
都会で生まれ育った筆者は、広葉樹と針葉樹の区別はわかっても、クヌギとコナラを見わけることはできない。当然、シイタケ栽培法など知らない。
シイタケはほだ木に穴を開けて種駒を植えてそだてる「原木シイタケ」と、おが粉や糠でできた培地でそだてる「菌床シイタケ」があり、日本のシイタケの9割は「菌床」が占め、「原木」は1割に満たない。両者は栽培方法だけではなく、味も香りもまったくちがう……。
「都会のおばちゃん」である筆者が阿武隈山地の山の民の暮らしにおどろき、まなぶ。その過程を、「都会のおっさん」読者である私も疑似体験していく。
シイタケの原木生産がはじまるのは1960年代以降というのも意外だった。
その前は、冬場は炭焼きで生計をたてていた。クヌギやコナラを根元から伐採し、木炭を焼く。切り株から脇芽がでて、20年もたつとふたたび伐採できる。そんな暮らしを何百年とつづけてきたが、電気やガスの普及で木炭の需要は激減した。
薪炭林の活用をかんがえたとき、20年に一度、直径10㎝ほどになったら伐採し、萌芽更新をするあり方が、シイタケ原木にぴったりであることがわかった。
都路の山の民は、炭焼きからシイタケ原木へと生業が変化したにもかかわらず、20年を1サイクルとして、一生のうちに2回か3回、おなじ山で「収穫」する仕事を何百年とつづけてきた。
2011年3月の福島第一原発事故はそんな里山の循環生活の基盤を完膚なきまでに破壊した。
フキノトウなどの山菜も、マツタケやコウタケなどの天然のキノコも、清流のカジカも口にできない。放射性セシウムをふくんだ木々は「原木」の4分の1の値段で紙パルプ用に売るしかない。
放射能に汚染された山で子育てはできないと、多くの人がムラをはなれる。原発事故時3000人だった人口は10年で2200人に減った。経済性も後継者も放射能汚染からの回復も見通しがたたない。あと20年もしたら、多くの集落は山にのまれてしまうかもしれない。
きびしい状況だが、都路の人々はあきらめない。
2021年、今ある木々を皆伐して萌芽更新をうながすことにした。樹木にふくまれる放射性セシウムがどれだけ減るか確認し、20年後に「原木」をうみだす里山を再生したいという。
さらにすごいのは2020年に立ちあげた「150年の山づくり」だ。半減期30年のセシウム137は150年たてばほぼ無害になる。まだ見ぬ曾孫の世代に里山の環境と暮らしの知恵をひきつぐプロジェクトだ。
「木を伐るときに、先人はどういう思いでこの木を植えたのかとよく考える。木を植える時には未来のことを考える。木の生長は時間がかかるから、植えた人は完成した姿を見ることはできないけれど、山に携わる人の意志や思いはつながっていくといいな」
クヌギやコナラの伐採周期20年を最小単位とし、100年後の子孫の利益をかんがえて里山を管理してきた山の民の時間感覚は今も生きているのだ。
筆者は、そんな山の民をとおして、現代人が失った時間感覚と知恵をまなんでいく。
本橋成一さんのモノクロ写真、とくに、炭焼窯の真っ暗な穴を中心に据えた作品などは、人の一生をはるかに超越した豊かで長大な時間をうつしだしている。
近世以前の時間感覚を生きる山の民と、世代を超えた生命のつながりを実感する写真家は、筆者にとってかけがえのない師匠だった。
======
▽ 原木、とはなにか。
▽17 「原木林」切った切り株の脇から、萌芽が10本くらい出てくる。2,3本を残して(芽かき)成長させて、22,3年で収穫する。
▽19 1本の木を更新しながら2,3代と人が切らせてもらえる。
▽19 もともと都路は薪炭林。萌芽更新。
…阿武隈山地では戦国時代には製鉄がおこなわれ、鉄1トンの製造に木炭20−30トンを要したという。
▽21 1960年代、…木炭の需要が激減した。かわりに木をどう使うか考えたときに、太く育っていない木が、シイタケ原木にちょうどぴったり合った。…炭を焼いていた時代からの積み重ねの上に、シイタケ原木の生産はなり立っていた。
…シイタケ原木用のコナラやクヌギは約20年に一度、伐ることができる。…山を循環利用しているのだ。
▽27 種駒 原木に穴を開けて、種駒を植える。この生産方法は、乾燥シイタケの9割に用いられている。
▽28 種駒を使った人工栽培が1942年に開発された。
▽30
▽34 商社は利益一辺倒で、無差別に大量伐採し、伐った後は放置する。(紀国〓)
中央森林組合都路事業所
▽35 菌床栽培とは、おが粉にぬかなどの栄養剤を加えた培地にキノコの菌を混ぜてキノコを栽培する方法。
…おが粉を使用した菌床栽培は、今では日本のシイタケ生産の中心になっている。…2019年は生シイタケ生産量71000トンのうち、菌床栽培が65000トンをしめ、原木栽培は一割に満たない。
▽37 農閑期になる冬に、シイタケ原木がりの仕事。「出稼ぎに行くより、うちから通ってできるからいいと、20年くらい毎年やったか」
▽40 原発事故後は、木を伐っても売れる用途はパルプだけ。価格はシイタケ原木の4分の1程度だ。
…事業費に占める公費の割合は、事故前は8割程度だったが、事故後は個人や民間から仕事が減り、2021年度で公費で9割9分を占めるという。
▽46 頂上付近のセシウムがもっとも他界としたら、頂上付近の幹に含まれるセシウムの価を調べて、指標価を下回っていれば、その山の他の木も下回り、原木として利用できるのではないか……
▽63 「丸一」1983年まで木炭をつかっていた。
▽66 日本最古の木炭 約30万年前に製造・使用されていたと推測される木炭が、愛媛県肱川村の洞窟で見つかっている。
▽70 1933年、県内の木炭生産量の55%が、東京、千葉、埼玉、神奈川の関東地域に出荷されていた。(エネルギー供給地)
▽82 今も残る「結」は、葬式の手伝いぐらい、という。原発事故後に避難していた間は、お葬式を葬儀場でするようになり、それがそのままつづいているという。それでも、各家から1人は出て、受付や会計を手伝うのだそうだ。
【阿蘇。結いが消えていく〓高度成長による崩壊を一気にすすめたのが原発事故】
▽102 山林所有者の山離れ。30ヘクタールで600万円。昔は1ヘクタール100万とかあった。
▽104 震災で組合に人が入ってこなくなった。高齢化が進んだ。
…おが工場があり、おが粉もかなりつくっていた。…ナメコ、シイタケの菌床栽培の培地の元に使われていた。
【すべてを使い切る。もったいない、と、活用してカネにする。循環する。】
▽106(皆伐して〓)20年たって、原木使えますよ、と宣言したとしても、そのころいはもう産地は移動してるんじゃないのかな。…
▽108 組合の山づくり。「一発屋だったら、木を伐って、さよならって言って終わりなんで。組合はずっとここにいるので…伐れば、またいつかは保育でもどらなくちゃならないんで。
…山を保育することによって山はよくなるんで、…他の人が切った山を、保育をかけてよい山にして、また次の20年、40年後、売って個人の収益を上げる。うちは補助金を使っているので、そういうふうにできる
【公共の福祉としての森林組合 環境と林業と経済を守る】
▽110 原発事故の賠償金額は、旧警戒区域をのぞき、原木林はヘクタールあたり68万円と、他の山は10万…
…2021年、原木林の再生を目的にした皆伐事業が都路ではじまりました。
▽116 2021年、都路では、国と県の「広葉樹林再生事業」がはじまった。シイタケ原木林の「再生」を目的として、今ある木々を皆伐して萌芽更新を促す。苗を植えて木も増やす。経費は国がもち…所有者の負担はない。木々を伐採することで、どれくらい放射性物質が減るのかを調べることも目的。
…今回伐った木は原木にも薪にもつかえない。パルプチップに直行だ。
▽122すべて手作業。
「空調だってなんだって、(菌床栽培)はエネルギーがいっぱいかかるんだよね。俺らは原木自然栽培だから。ほだ木だって,使い古せば風呂の薪に使ったし、カブトムシのエサにもなった。意外にローテーション回ってたの」(菌床と原木とは似て異なる〓)
▽126 2015年からはじめて、最初にできたシイタケは600ベクレル/キロを超えていた。「自分たちで食べちゃう」。なんともないよ、と苦笑し…
▽127 日本のシイタケ生産は、おが粉などを培地にし、温室内で温度や湿度を管理して生産する菌床栽培が中心だ。原木栽培は生シイタケの1割に満たない。
▽130 2013年秋、原木シイタケの農家9人はチェルノブイリへ。
▽131 都会の人は、山はだめなんだということまでは知らない。…「里山が奪われて、我々の生活が奪われた。この現実をこれからどう発信するか。どうしていくのか」
▽137 マツタケ…フキノトウもウドも撮れた。今はだめ。
▽141 山口県柳井市の「レンタカウ」。耕作放棄地などの草刈りに牛を放牧。
▽151 合子集落の共有林。取り戻した山 官有林からの引き戻し
「冷害の年も、合子には山に米がなっている」
地租改正→共有林が官有林に→村人が入れなくなる。「とりもどす運動」へ。
共有林のカネで、(昭和に)小水力発電を整備。
原発事故後、共有林の登記を手がける。400ヘクタールのうち50ヘクタールを、個人や数人で所有する私有林に。実際の利用の仕方に合わせて整理。「今ここでやらなかったら、子どもたちは誰もできねえぞ。それが合言葉みたいなものだった」


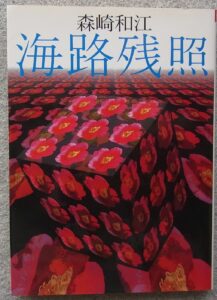


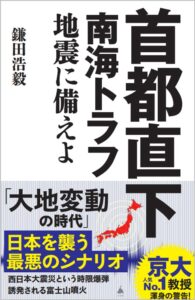
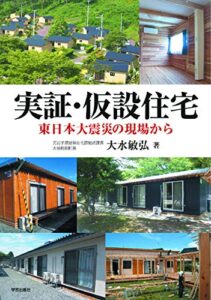

コメント