■みずのわ出版 20211127
梁瀬は、いちはやく農薬の健康被害を告発し、自ら有機農業も実践した。有吉佐和子の「複合汚染」(1974〜75)では「昭和の華岡青洲」と評され、患者からは「現代の赤髭」「仏様のような先生」と慕われた。
戦争中、軍医としてフィリピンに出征し、所属した部隊は全滅した。戦後、尼崎の病院勤務を経て、奈良県五條市の実家の寺に1949年に診療所を開く。
1957年ごろから、奇妙な患者が診察室に来るようになった。肝炎を疑わせるが、口内炎がはげしく、脳障害や神経障害も訴える。
農薬のパラチオン(商品名ポリドール)が軍の毒ガスと同じであることを知り、梁瀬は自ら、畑のキャベツにパラチオンの1000倍溶液を散布し、葉のしぼり汁を飲んだ。15日後に下痢がはじまり、体がだるくなり、些細なことで子どもを怒鳴りつけるようになった。パラチオンによる自他殺は毎年数百人にのぼっていた。除草剤のパラコートはさらにひどく1985年には1021人の死者を数えた。
1959年、「五條市でポリドールの集団中毒事件が発生している」と新聞記者に訴えると、大阪中央卸売市場から五條の野菜が締め出され、市場関係者からつるしあげられ、狂人扱いされた。
レーチェル・カーソンが「沈黙の春」(当時は「生と死の妙薬」)を連載して衝撃を与えたのが1961年(出版は1962年)だから、その2年前に「農薬の害」を告発し、61年には「農薬の害について」というパンフレットを自費出版した。
「沈黙の春」が1964年に日本で出版されると、梁瀬の主張にも注目が集まったが、猛毒の農薬の使用はつづいた。出荷する蔬菜にポリドール1000倍溶液を噴霧していた。有機リン剤特有のホルモン作用で、数日たってもとれたてのように生き生きしたからだ。
梁瀬は1970年に「慈光会」を結成し、山の畑で無化学肥料、無農薬での野菜作りを実践する。
1971年2月、協同組合運動家の一楽照雄に「有機農業は個人の努力だけでは影響がとぼしいので、全国的に運動を展開する組織ができれば」と求め、一楽は10月に日本有機農業研究会を立ち上げた。
梁瀬の長男は、農業を志して三重県の愛農高校に進学した。PTAの梁瀬が愛農高校で講演したことで、愛農会創設者の小谷純一は生産量第一主義から有機農業に舵を切った。
梁瀬の行動力と無私の活動の背景には仏教への帰依がある。キリスト教を信じた小谷純一もそうだが、無私の生き方をする人には信仰心があることが多い。神仏から託された自分使命を自覚するからだろう。
亡くなる直前、呼吸困難でほとんど眠ることができなくなっても、一心に「南無阿弥陀仏」と唱えた。最後は「あるがとう」と言って息を引き取った。
農薬や化学肥料が、戦争に使う毒ガスや火薬と密接な関係があったこともくわしく紹介されている。
ドイツの学者が唱えた、窒素、リン酸、カリウムにより植物は成立しているという説が化学肥料を生みだした。
硝石は火薬の原料にもなるため、肥料工場は火薬工場へと転換できるように設計されていた。ドイツは、火薬の原料である硝石を南米に依存していたたが、空中窒素を固定してアンモニアを合成する技術を開発し、自前で火薬を生産できるようになり、第一次大戦に参戦する物質的条件を整備した。
化学肥料やトラクターは農業のためにつくられ、後に火薬や戦車に転用された。
一方、農薬は逆パターンで、人を殺すために開発された毒ガスが「平和利用」されたものだった。
第一次大戦後、備蓄米につくコクゾウムシの駆除に日本に入ってきたクロルピクリンも毒ガスとして開発された。1946年には日本最初の合成農薬として、三菱化成が製造を開始した。
第二次大戦で、ナチスが強制収容所でつかった「チクロンB」は、殺虫剤になった。
戦後の日本では1947年、GHQが全国の農事試験場にDDTを配布し、ニカメイチュウを防ぐために使われた。
1950年代に入ると、ドイツのバイエル社から有機リン殺虫剤パラチオンが輸入され、71年の失効まで使用された。ナチス・ドイツが開発した毒ガスのサリンを改良したものだった。
=================
▽5 奈良県五條市。「現代の赤髭」「昭和の華岡青洲」といわれた梁瀬義亮。
レイチェルカーソンが「沈黙の春」を連載してセンセーションを巻き起こしたのが1961年。その2年前の1959年、「農薬の害」を公式に発表。
▽……寺に生まれる。……フィリピンの機械化部隊へ。……1945年7月19日、右足を撃たれた。そのとき部隊は全滅。
▽梁瀬の調査 野菜や大豆、海藻類、小魚、乳製品を適度の摂取する人たちは、おおむね健康的なな生活。反対に、米食や白砂糖、肉類の過剰な摂取は、健康を損ねる。……
真面目な信仰心を持つことが、精神衛生良好にし、健康状態の良否を左右している、ある程度食生活に気をつけてくらしていれば、定められた寿命を健康に生きることができる蓋然性が高まる、ということだった。
▽45 県立尼崎病院で勤務。亜硫酸ガスの影響で、公園の滑り台や家庭のガスメーターなどは、設置後数年で、腐植しボロボロになる。小学校の草花は枯れ、公園の樹木も育たない……
……梁瀬も、激しいぜんそくに悩まされるようになる。……
▽49 ベートーベンの第5交響曲。ベートーベンを聴きながら高揚感を覚えた。……あれほど絶望的なだった病状に変化の兆しが現れるようになった。奇跡のよう出来事が……
それを機に尼崎病院を退職して大和五條に帰った。
▽53 梁瀬義亮1949年、五條市の宝満寺に診療所開設。
妻のみつが菜園を作っていた。硫安を使っていた。ところが、農家の患者からもらう野菜の方がおいしかった。その人は「うちの野菜は堆肥をたくさん入れてあるからおいしい」と答えた。硫安でつくると、見た目は大きく立派に見えるが味は劣る。
……農家の専門書には、窒素、燐、カリの3要素を強調し、化学肥料を絶賛している。化学肥料はドイツの科学者リービッヒが植物の灰を分析して、窒素、リン酸、カリウムが多量に含まれているのを確認したことに由来している。植物はこの3要素により成立していると結論づけた。リービッヒは3つの元素を投与しさえすれば生育すると考えた。
……有吉佐和子の「複合汚染」朝日新聞に1974年10月から75年6月まで連載。
▽56 リービッヒは、「植物は根から無機物を吸収しさえすればよい」と主張した。これを「無機栄養説」。
19世紀になり、南米でグアノ糞鉱やチリ硝石がみつかり、大量に輸入されるようになると、一気に無機質肥料の使用が広がった。「無機栄養説」で世界の農業を一変させることにつながった。
同時に硝石は肥料としてだけでなく、、火薬の原料にもなることから、軍事的な引き合いがあった。有事になれば、肥料工場は即座に火薬工場へと転換できるように設計されている。
……ドイツは、火薬の原料である硝石を南米チリに依存していたため、開戦に踏み切れない。状況を打破するため、研究。フリッツ・ハーバーが空中窒素を固定してアンモニアを合成する技術を確立した。つぎにカール・ボッシュによって、高圧下でアンモニアを大量に合成する方法へと発展する。
アンモニアから硝酸をつくることは容易だ。これにより硝石の輸入を気にせず、、火薬の生産ができるようになった。第一次大戦に参戦するための物質的基礎を獲得したと言える。
▽57アンモニア合成技術のひとつであるイタリアのガザレー法を、日本窒素(後のチッソ)の創業者野口遵が買い取り、延岡工場(現旭化成)に導入し、後に数倍の大きさに改良した機械設備を水俣工場に時前でつくった。
空中窒素を固定してアンモニアをつくり、これに硫酸を吸収させると化学肥料の硫安が生まれる。同時にアンモニアから硝酸をつくることが、火薬づくりにつながっていう。
……化学肥料の生産が、火薬の製造技術に転用された。戦争のために開発された毒ガスが、のちに農薬につながっていくのと軌を一にしている。
……植物を、窒素、リン酸、カリウムの3要素だけに単純化してとらえる分析的な手法は、西欧近代の精神を特徴づけるもの。
▽61 各国に先駆けて毒ガス開発に成功したのはドイツ。毒ガス研究チームのリーダーは、化学肥料の大量生産に道を開いたフリッツ・ハーバーである。
……トラクターや化学肥料は農業のためにつくられ、後から戦車や火薬に転用されたが、毒ガスは先に人を殺す目的があって開発された。農薬は戦争が終わり毒ガスを「平和利用」する目的で、スピンオフされたものだった。
第一次大戦後、余った毒ガスが平和利用の名のもとに、害虫駆除に使われる。ドイツでは毒ガスを開発した科学者らが、消毒会社をつくり、小学校や電車内を消毒する事業を始めた。青酸カリを薄めて、穀物倉庫に頒布し害虫駆除にもつかった。これが農薬として広まっていく。
第二次大戦で、ナチスが強制収容所でつかった「チクロンB」は、殺虫材としてヒット薬剤が使われた。
▽63 1947年、GHQ天然資源局は、、全国の農事試験場にDDTを配布し、圃場試験を命じた。ニカメイチュウに有効であることがわかり、農薬として使用されるようになった。……
▽64 1952年、稲のニカメイチュウやカメムシ、ウンカなどの防除にパラチオンが登録され71年まで使用される。梁瀬は機械化部隊の隊つき軍医だったこともあり、毒ガスの教育も受けていた。パラチオンという物質は、ナチスドイツが開発したリン性の毒ガス・サリンを少し改良したもので、猛毒であった。
▽65 ドイツにおける神経ガスの開発は1936年にさかのぼる。シュラーダーが殺虫剤の研究をしていたとき、リンを使った試供品を1滴シラミ20万匹にたらしたところたちどころに全部死んだ。これが軍部に報告され、……37年に軍に毒ガス開発の研究所が設立され、シュラーダーはそこに移る。38年にはさらに毒性の強い物質を発見する。これがサリン。戦後、こうした毒ガスの研究が「平和利用」される形で農薬が生み出された。
▽66 1957年ごろから、奇妙な患者が診察室に現れるようになってきた。肝炎を疑わせる症状だが、ウイルス性肝炎にしてはおかしい。口内炎がはげしく、脳障害や神経障害を訴える患者が非常に多い。五條周辺では、流行性肝炎と呼ばれていた。
……1955年7月半ばから、発熱と肝腫脹という症状の乳児が増えた。……みな母乳ではなく粉ミルクを飲んでいた。幼かった梁瀬の長男義範もそのひとりだった。粉ミルクを他社製に変えさせると体調はすぐによくなった。=森永ヒ素ミルク
▽69 出荷する蔬菜にもポリドール1000倍溶液を噴霧していたという。有機リン剤特有のホルモン作用で、野菜が数日たってもとれたてのように、生き生きして高値で取引されるらしい。
……梁瀬は、自分の身体で残留農薬の人体実験。畑のキャベツに1から14までの番号をふり、1から毎日ひとつずつ、ポリドールの1000倍溶液を散布した。14番に散布を終えた翌日から順番に、1番からキャベツの葉をとってすりつぶし、そのしぼり汁を飲みはじめた。葉をとったキャベツには新たにポリドールを散布していく。
15日を過ぎると下痢がはじまった。夜中に目が覚め、体がだるく、……子どもに対しても妙に怒りっぽくなり、些細なことで怒鳴りつけてしまう。放心状態のように、まるで霧のなかをさまよい歩くような気分。1カ月で実験を打ち切ったが、以前の体調を取り戻すまでには3カ月かかった。
▽69 農薬のみならず、食品添加物をはじめ多くの薬物に囲まれている。ひとつひとつの影響は軽微でも、多くの毒物による相乗的な作用が……人体はさらされている。「複合汚染」
▽72 1959年4月、「五條市でポリドールの集団中毒事件が発生している」と新聞記者に訴えた。大阪中央卸売市場から五條の野菜が締め出される。……卸売市場関係者からつるしあげ、糾弾。……1961年2月のサンデー毎日で梁瀬の訴えが紹介されると潮目が変わっていった。
▽73 厚生省の調べでは、パラチオンの本格使用が始まった1953年には散布中に70人が死亡、1564人の中毒者が発生している。56年には86人が事故で亡くなっている。69年までパラチオンは使われたが、53年から66年までの13年間に、同農薬による自他殺は、毎年237−900人にのぼっている。
▽77 梁瀬は、化学肥料を使用すると、土が弱って農作物も病弱になり、病虫害が多発して、農薬を使用せざるを得なくなるという、負の連鎖に陥ることがわかるようになった。
▽79 強力な農薬でも、遠からず効果が乏しくなる。こうした農法は結局「土を殺し、益虫を殺し、やがては人を殺す」「死の農法」だと梁瀬は批判した。
……悪循環を断つには、農薬や化学肥料をやめて……しかないという結論に梁瀬は達した。
▽86 屎尿の利用。野壺にため、たびたびかき混ぜて空気を入れながら3−6カ月放置すれば、バイキンや寄生虫卵も死滅し、よい有機質肥料になる。
▽88 藤原辰史「ナチス・ドイツの有機農業」
▽89 日本で最初に有機農業と命名し、のちに日本有機農業研究会の設立に尽力したのが、一楽照雄。ハワードやロデイルの系譜。
それとは別の潮流として、ルドルフ・シュタイナー(1861−1925)による「バイオ・ダイナミック農法」がある。農場内の物質循環を基本とする。だが、バイオ・ダイナミック農法はナチス・ドイツに接近し、「ナチス・エコロジズム」において大きな影響力を持った。強制収容所の敷地内にも同農法による菜園があった。
……ヒトラーは菜食主義で、酒や煙草をきらう。ヒトラーは動植物を愛で、種の境界を取り払い、すべての自然を平等に扱う共生を目指した。国民すべてを菜食主義者にさせようとも考えていた。狂信的ともいえる禁欲主義の内面において、矛盾なくホロコーストが同衾していた。
……日本の自然食や有機野菜の愛好家にも、一部に物事を単純な善悪二元論で歳男子、農薬や食品添加物を、ことさら排撃しようとする傾向をみることがある。世の中から「悪」さえとりのぞけば、社会に平和や幸福が訪れるとの単純明快な世界認識。
……中国産の農産物や加工食品を害毒であるかのごとく、こきおろす論調。
▽100 窓を開けると、一日中食欲がなく……パラチオン(商品名ポリドール)を散布していた。
▽104 パラチオンは、多数の農民が散布中の事故で亡くなっている。除草剤のパラコートによる犠牲者はそれ以上。自他殺に使用されることも多く、1985年には年間1021人の死者。
……農薬問題がクローズアップされるようになったのは、消費者が残留農薬への不安に、声を上げはじめたからで、農民の被害に注目が集まったことがきっかけではない。
こうした状況下で、1978年に「虫見板」を使い、「減農薬運動」を推進しはじめたのが、福岡県農業改良普及員だった宇根豊だった。それまではふつうの普及員だった。虫害が発生して減収になるのは避けたい。責任回避もあり、防除回数を多めに指導する傾向があった。いったん回数を増やすと、その後は怖くて減らすことができない。
……「虫見板」 稲に付く虫を板に落として種類や数を観察し、防除するかどうかを農民自身が主体的に考える。取り組みはじめると、農薬使用量が目に見えて少なくなっていった。
……「減農薬運動」は、近代の農業技術から阻害されていた農民が、主体性を取り戻そうとする運動でも会った。最大の功績は、これまで受け身で農作業に従事してきた農民自身に、意識改革を迫ったこと。……自分の目で田んぼを観察して、主体的に農業に取り組むことにつながる運動だった。
▽107 明治に入り、害虫駆除のため最初におこなわれるようになったのは、天敵さらに導入。誘蛾灯。第一次大戦後、化学殺虫剤。江戸期から水田にクジラの脂を注ぎ、イナゴを駆除する「注油駆除法」が知られていたが、石油乳剤が一般化していった。
次に、アメリカから種子を輸入して除虫菊が利用されるようになった。昭和初期には、世界生産の90パーセントを占める、輸出産品となった。除虫菊は明治期には農業用の殺虫剤に利用された。
1922年に古河電気工業が「砒酸鉛」の国産化に成功。足尾銅山から出るヒ素による公害に悩んでいた。ヒ素を亜ヒ酸として回収し、それを砒酸鉛に合成し殺虫材として売り出した。
第一次大戦後、備蓄米につくコクゾウムシの駆除に、入ってきたのが、クロルピクリン。毒ガスとして開発されたもの。
それまでは二酸化炭素を倉庫内に充満させて駆除していたが、引火性が高く危険だった。クロルピクリンは引火しにくく……1946年3月には日本最初の合成農薬として、三菱化成が国内で製造開始。
1950年代に入ると、ドイツのバイエル社から有機リン殺虫剤が輸入される。パラチオン(商品名ポリドール)である。71年の失効まで使用される。
パラチオンが普及するとともに、農業者のみならず、周辺住民にも被害が発生するようになる。
▽124 1970年7月、、光化学スモッグで杉並の高校生が倒れる。
▽127 チッソ イタリアからアンモニア合成の技術を導入し、日本初の合成肥料生産に成功。1932年、カーバイドを原料にアセチレンを作り、水銀触媒を使ってアセトアルデヒドに変え、酸化させて合成醋酸をつくった。
1940年ごろから、水銀触媒による塩化ビニールの生産開始。有機合成化学の有力企業となった。
1950年代、アセトアルデヒドのトップ企業だった。……カーバイド滓と、アセトアルデヒドの製造過程でうまれた有機水銀、無機水銀などを含む排水を、1932年から68年まで排出しつづけた。
▽135 上賀茂神社前の「すぐきや六郎兵衛」 複合汚染に出てくる「本物のしば漬」
▽137 合成着色料をはじめ、砂糖の代用品にサッカリンやズルチンが入りこむなど、食品添加物が定着していく。昔の漬物は塩だけしか使わないから見た目は地味で、ぺちゃっとした歯ざわり。「シャリシャリパリパリ」と生野菜のような歯ざわりのよい漬物は浅漬けを除けば非常に稀で不自然。
▽139 日本酒も三倍増醸法でつくった粗悪な酒が主流をしめつづけた。酸味料、化学調味料を加えて目方を3倍にした酒。
▽144 70年代、駄菓子屋で、毒々しい色の菓子類。目をむくような色とりどりの着色料が氾濫。
▽146 食品の保存性を高め、安全性を維持する手段として、厚生省は合成殺菌料の使用に積極的だった。食中毒が多発する日本では薬剤を使用させるほうが衛生的にも+になるという考え方だった。
▽160 保田茂 1973年兵庫県有機農業研究会を立ち上げ。
かつて全国愛農会会長をつとめた市島町の近藤正は梁瀬や一楽照雄とあい、63年に有機農法に転換。1975年には市島町有機農業研究会を立ち上げた。
▽165 日本でもともと栽培が盛んだったのは、中国から熊本をへて、和歌山に伝わったとされる紀州みかんだった。温州みかんは、紀州みかんの花に、インドネシア原産のクネンボの花粉がついて誕生した。温州みかんが本格的に広がったのは明治に入ってから。それ以降、実が小さく種が多い紀州みかんは、すたれていった。
▽170 ビワはみかんにくらべて無農薬でつくりやすい。
▽177
▽183
▽197 慈光会 1959年、農薬の害を訴える梁瀬の記事が新聞に載り、卸売市場関係者から猛烈な反発があった。梁瀬を助けようと、町の有志50人が「健康を守る会」を結成。梁瀬は「農薬の害について」というパンフレットをつくり、全国を講演に飛び回った。守る会は、当時としては非常に珍しい、有機野菜の直売を定期的におこなった。
……レイチェル・カーソンの「沈黙の春」(当時は「生と死の妙薬」)1964年に日本でも出版。突然、梁瀬の主張に注目があつまりはじめ……
1970年、「慈光会」
▽203 1971年、日本有機農業研究会 呼びかけたのは協同組合運動家の一楽照雄(1906年生まれ)
英米で30年前からOrganic Gardening and Farmingという農業が普及している。これを直訳して「有機農業」という言葉にした。
日本で最初にのうやう被害の声を上げたのは有明海の漁民。干潟の会が大量に死に、福岡県から流れてくる農薬類が原因だと農協へ訴えた。当時、一楽は全国中央会の常務理事をしていた。これをきっかけに無農薬の農業に興味をもつようになった。
……1971年2月、〓セミナーで、講師として招いた梁瀬と話した。その時「有機農業は個人の努力だけでは影響が乏しいので、全国的に運動を展開する組織ができればよいのだが」と梁瀬は語った。一楽は10月17日に日有研を発足させる。以来、梁瀬は16年間、同研究会の幹事をつとめた。
1975年、有吉佐和子が慈光会を訪問。
▽209 複合汚染「『サイレント・スプリング』を発表した1962年。それより1年も前に日本では奈良県五條市の一開業医が「農薬の害について」というパンフレットを自費出版していた」
▽220 全国各地から、医者に見放された農薬中毒とみられる患者が訪れた.……いずれ財政がたちいかなくなると、梁瀬医院では保険診療はしなかった。でも診療費は格安だった。余裕のない患者からはお金を受け取ろうとしなかった。
……有吉は「複合汚染」のなかで、梁瀬のことを「昭和の華岡青洲」と呼んだ。
「梁瀬先生は仏さんのような方や」「仏様の生まれ変わりや」
1975年、吉川英治文化賞 「農薬パラチオンが人体に害を及ぼすことを発見して以来、無農薬農業の啓蒙活動を進める一方、「慈光会」を設立して独自の農法を実践し、成果をあげている」
長男義範(1954年生まれ、現慈光会理事長)三重県の愛農学園に進み、農業を勉強した。
▽226 1992年11月ごろから呼吸困難がひどくなり、横になると息苦しいので、布団の上にすわり、ほとんど眠ることができなくなっていた。一心に「南無阿弥陀仏」と念仏を唱えていた。
1993年5月、長男の義範に梁瀬は「僕に間違いがあれば、今言ってほしい」と問いかけた。そして笑みを浮かべた後、二度「ありがとう」と言った。すると、意識がすうっとなくなっていった。5月17日の夜、仏陀のもとに旅立った。




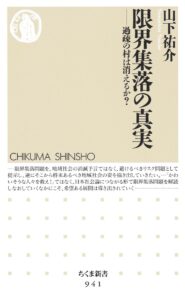
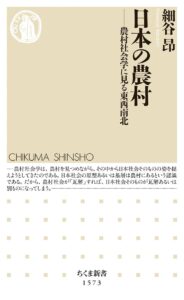


コメント