20080522
瀬戸内海の真ん中、どこからも高速船で1時間かかる孤立した村。そんな離島の村で下水道100%、電話普及率日本一、CATV導入、Iターンの呼びこみ……といったユニークな村おこしを実践してきた村長の体験記だ。
「村」という自治体だったからこそ、人口数百人の島に数億数十億円単位の事業ができ村おこしが実現できたことがよくわかる。
「無駄な公共事業」という批判もでそうだが、港を整備したから台風のたびに漁船が破損していたのが解消された。下水を完備したから、毎月1度、バケツで糞尿をかきだして港まで運搬するつらい作業をまぬがれ「年をとっても島におれる」という安心感をもたらした。巨大井戸を掘り、足りない水を購入し、さらに海水淡水化装置を導入したから、週2日しか水がでない、という状態を脱した。
「生活状態をよくすれば過疎を食い止められるのでは」との希望をいだいて努力してきた。過疎はとまらなかったが、こうした努力がなければ、今ごろは無人島になっていたろう。
大幅な生活改善をはたしながら、周辺自治体とくらべるとはるかに健全な財政だった。2004年に周辺4町村で合併して上島町になったとき、4町村の基金の残高の合計の5割弱は、人口では5%に満たない旧魚島村のもちぶんだった。ほかの町村はリゾート開発や小渕首相時代の「景気対策」におどらされ、ゴルフ場やらリゾート施設をつくりつづけた。魚島はそういう風潮におどらず、ひたすら生活改善に集中していた。「良い公共事業」と「悪い公共事業」を峻別して考える必要があることがよくわかる。
健全財政を維持してきた魚島村だったが、地方交付税が激減するなかで、単独での生き残りをあきらめざるをえなかった。
日本中どこでも、山村でも離島でも、「最低限度の文化的生活」は保証されるべきなのに、今では「自治体間競争」などと言って、非効率な自治体を切り捨てようとしている。「自立」にむけてひたすら努力してきた魚島村の消滅は、その残酷さを象徴している。
---------覚え書き・抜粋----------
▽11 はげしい村長選 夜になると運動員の見張りが各所に立っているので、一般村民は夜間の外出も思うにまかせぬほど。村議と村長の同時選挙だったから、議員の票と村長の票を巡って、裏工作で取引をしたとの噂も流れるほど。
21 昭和48年、無投票で佐伯が村長に。住民はどちらかに色分けできる。当落のカギを逃げるのは島外からの転入者……といわれたほど。
▽25 1期目 水不足にとりくむ。簡易水道はあったが、給水は週2日程度。まず地下に水タンク建設し、三原市から買い水をはじめた。次に島内水源開発。浅井戸を各所にほり、簡易水道も24時間給水に。
▽35 海岸線に鉄筋の高層建築物を新築。テレビが見えないと苦情がでて、共同アンテナをたて、各戸に配線した共同受信施設。各家屋のアンテナは不要に。住民の負担はなし。最低7局。多ければ9局見られるようになった。全国で最も受像局数が多い!と
▽42 定例議会や臨時議会が開催されない月には、必ず議員協議会を開くことに。
▽54 大正12年に個人経営の自家発電装置で電灯がつく。スチーム機関で湯ができるから公衆浴場も経営。昭和24年から村経営の公営企業になりディーゼル機関に。点灯は日没から午後11時。高井神島に村営自家発電ができたのは昭和30年。
24時間点灯するには海底ケーブルが必要。一番近い弓削町から15キロ。愛媛県で離島振興法によって海底ケーブルによる電気を導入したのは、最初は釣島(昭和37)、次は日振島(39)、3番目は二神島(42)。弓削から豊島、高井神島を経由して魚島に届いたのは昭和43年。村民あげての猛運動。陳情、要望、地元負担金を住民が負担するための積み立て預金……。点灯式には200人が出席。村外来賓の乗船した村営旅客船が港に近づくと、大漁旗をなびかせた漁船40隻が歓迎の出迎えをし、港では日の丸を手にした村民200人がむかえた。
「いままでは島に肉屋がないため弓削町より買ってきても、冷蔵庫が昼間使えないので保存がきかず、また洗濯機、掃除機、アイロンかけも夜しかできませんでしたが、これから思うようになり、便利さははかりしれません。本当にうれし涙がでます」と主婦。産業振興にも役立つ。海苔の加工場、全自動だから人手が少なくてすむ。漁協の冷蔵も。
▽70 電話 地域集団自動電話 全国一の普及率に。普通電話にきりかえ。
▽72 昭和20年頃の水源。計33カ所。1カ所の井戸で湧出するのは0.5トン程度。洗濯は井戸でしていたが、当分雨がふらないと、ツルベに入ってくる水の量は半分以下に。くみ上げる回数も多く深い井戸に苦労。極端に水が少なくなると、昼間は水がないから、夜中になって水を汲むか、朝早く起きて水を確保したが、井戸の近くに住む人は水くみの音で夜も眠れないとこぼしていた。
昭和27年に簡易水道ができたが、貯水用ダムも800トン程度で小さかった。週1,2回しか給水してもらえないもの、しかも時間給水しかできないもの、と、村民はあきらめていた。
昭和42年から45年まで、毎年井戸を掘り、23基に。個人で掘った井戸もふくめると57基をほり、計90基の井戸が魚島にできた。村有井戸は動力ポンプを禁じていた。水の使用が多くなり、井戸水がすぐ枯れるからだ。
高井神島はさらに条件が悪く、水道施設がないということは、もし伝染病でも発生したらという心配がある。水のため島民間でいざこざも多かった。
今日の水をどうするか? 船舶で水を運ぶことが思い浮かぶ。三原市の山本給水。1トン350円。(当時は)数億円以上の海水淡水化は1トンあたりの造水費は1000円程度と高かった。
貯水施設はどうする? 排水池へ配管をつなぐ。昭和50年にはじめて水を購入したときは、極端な水不足で、配水タンクはもとおり村有井戸にもこの水をいれた。購入水量は260トン。
貯水タンクを建設しようにも用地がない。海中に貯水施設をつくることに。本来は埋め立て用地が完成してからつくるべきだが、それでは水の確保が1年おくれる。県幹部に陳情したが前例がないから補助金がでない。陳情をくりかえし、採択される。港内に260トンの貯水施設が昭和50年5月に完成。この施設ができて1週間に2日は確実に給水できる簡易水道になった。さらに鉄筋コンクリート3階建て集会所をたてることになり、この建物の地下1階を400トンの貯水槽に。貯水量は計660トンに。水に困れば660トンの水を購入して、いつでも給水できる体制ができた。水が豊富なときに水を貯えるのにも利用できる。これで昭和51年4月からは週4日は給水できることに。
さらに、購入するのは高いから、完全給水をめざす。こまめに歩いて調べると、ここならば水がとれるというところがみつかる。井戸を掘り、井戸の底から横穴を掘って取水範囲を広くする。直径4メートルほどの大きい井戸。その井戸の底から山手にむけて横穴水平ボーリングを掘る。昭和50年から54年度にボーリング20本井戸5基を工事して、日産40トンの水を渇水期にも得られるようになった。これでほぼ完全給水が実現した。
▽104 小中学校の児童生徒数調べ
▽105 社会教育 魚島集会所76年地下は貯水槽
離島開発総合センター83年完成予定 離島公共施設ではめずらしくエレベーター付き 郷土資料室と図書室を大きく。
テレビは共同受信 80年に魚島テレビ開局
▽134 魚島1周道路6キロの各所に島四国八八カ所の石仏があり、老人クラブは毎月21日にお大師参りをしている。信仰と健康に大変よい。
▽136 昔の役場は、村長・助役・収入役・書記二名・小使さんの6名位。役場が大きくなったのは地方自治法のできた昭和22年から。昭和30年は、村長・助役・収入役・書記6名・使丁1名の計10名。それ以外に船舶職員3名、診療所職員3名、学校使丁1名で、計17名が魚島村の全職員だった。船舶事業公営化、診療所開設、役場事務量増加で職員が増えた。
昭和58年は村長以下の役場職員17名、船舶職員6名、診療所職員4名、保育所職員2名、合計31名。
人口わずか450人の村だが、地方自治をおこなうには最低でもこれだけの公務員を必要とする。
村民は役場で相談したらなんとかなるだろうと思って、なんでも相談にくる。
▽145 お役所小唄 役場職員15名全員の氏名が歌詞にはいっている。
▽148 新婚住宅から公営住宅へ 昭和49年に新婚住宅4戸。
▽160 簡易下水道完備。昔は簡単な石積みの水路で覆っていなかった。排水も流すから悪臭はあたりまえ。汚水が浸透すれば井戸水も汚染される。そこですべての簡易下水道が四方張りとなった。
▽167 漁業の漁獲高 純漁村にしては漁獲金額が低いのは、違反漁業をほとんどしないから。違反漁業をやれば、漁獲金額は5割増になるだろう。
▽171 漁港整備 昭和38年度から整備。整備をはじめたころは、防波堤も石積みの小さな漁港で集落の片隅に置かれていた。泊地も8330平方メートルと小規模。船の乗降は旅客船も小さな石段を利用した。20年間に11億4000万円の事業費をかけた。防波堤362メートルの延長。集落をすべて波浪から守ることに。泊地も3倍になり、漁船の破損する心配もない。港内に物揚場延長482メートルができたことで、その内側に12600平方メートルの埋め立て地が造成された。そこに、漁港道路、浮き桟橋、フェリー発着場、村集会所、貯水タンクなどを建設した。10坪の用地もなかった篠塚漁港にとって、埋め立て地の恩恵は計り知れない。
▽農業 昔は女の人が畑仕事で男は漁にでた。畑は、麦と甘藷と除虫菊と自家野菜。敗戦後、昭和22年に1755人に人口が急増。麦飯さえも腹いっぱい食えず、おかゆの食事が多くなる。無人島の江ノ島にも開墾にでかけた。畑の面積は70町歩を超していたろう。農道はすべて復員
メートルもない兎道。肥料や農作業を頭上か肩で運搬した。カボチャは生育がはやく量も多いからよく植えていた。
昭和30年ごろからいかに所得を増やすかを考えはじめる。県の指導をうけ昭和36年から、大規模なミカンへの転作を図った。「ミカンだけは将来ともに有望である」と、太鼓判を押しての指導ぶりだった。自衛隊にお願いして上陸用舟艇にブルドーザーをつみ、高井神島で10町歩のミカン畑を開墾。江ノ島にもブルドーザーで5町歩の機械開墾をした。普通畑から蜜柑畑への転作も15町歩となり、計30町歩の蜜柑畑が誕生した。莫大な開墾費用と苗木代、多くの労力をつぎこんだ。
ところが昭和42年ごろ、蜜柑が暴落する。魚島は地形の関係で、他町村に比べ労力負担が大きい。資本と労力を注いだ蜜柑園を休耕する者もふえ、漁業に専念することになった。
魚島村には60町歩の農地がある。戦後食糧不足時代は70町歩にふやしている。蜜柑園の時代には蜜柑園が30町歩、普通畑も30町歩はあったという。それが年とともにミカン園も普通畑も休耕となり、現在耕作しているのは、蜜柑園3町歩、野菜畑5町歩の計8町歩が全耕作面積である。〓
段々畑で労働が大変。だが、自給用の畑をつくって、魚中心の副食から、野菜中心の副食にして、健康を守ることが大切だ。
▽186 魚島の農林道は1メートルもない兎道だった。昭和46年から7年で1周道路を完成した。復員3メートル、延長4630メートル、総事業費2億4000万円。
▽188 観光事業 観光客に魚を釣らせたら漁獲量が減ると心配する者がいたから、漁協も観光には反対していた。……原油が高くなり、1日操業するのに1万円燃料費がかかる。そこで燃料消費の少ない、観光漁業でもという考え方がでてくる。どうせ遊漁船を禁止できないなら、地元の遊漁船を利用してほしいと。
▽203 父は朝鮮で漁船の村長をしていた。その後、魚島で旅客船・魚島丸の船長をやり、50歳で海軍軍属として徴用され、徳島県で戦死。私もオヤジと一緒に機関士を2年ほど。機関室でエンジンをかけると、次の島に船が着くまで本を読んでいた。
▽212 難しい事業を国や県に陳情に行って、一度で「ハイよろしい」といってくれる役人はいない。一度でダメなら二度、三度とやってくれるまで陳情する。(〓渡部・三好村長)
▽238 老人憩いの部屋 週2回は風呂にも入れる。魚島には常勤ヘルパーを配置し、高井神島ではパートのヘルパーでお世話する。
▽247 理想社会の建設はせめて500人か千人、多くても2千人じゃないと。魚島村は小さいけれど村。だからかなりの事業ができる。国や県の補助金を受けてやりたい事業をやれるのは地方自治体があるから。……魚島村は4%自治。不足分を交付税として配分されるから地方自治ができる。500人の村で6億5000万円の一般会計予算を組んでいる。そのほか特別会計として、船舶、国民健康保険、診療所、簡易水道の予算が2億円あるから計8億5000万円。6億5千万のうち4億円を公共事業にあてている。だから、桟橋前の道路にそって鉄筋の公共建物がズラリとならんでいる。
今治市では千人程度の町内会で集会所を新築したいと陳情すると、木造づくりの千万円か1500万円の集会所ができる。が、受益者負担金としてかなりの額を納めないといけない。高井神島という100人の島にコンクリート3階建ての公民館を新築するのに8000万円の予算を組んだが、負担金はなし。
▽256 離島振興法を昭和32年から適用をうけ、過疎対策特別措置法は45年から適用を受けた。この2つの法律が制定されてなかったら、離島や過疎地は現在のようには住みよくなってはいなかった。
離島振興法は、港湾や漁港の補助率が高く、とくに防波堤は95%の高率。離島振興法の適用されない補助率は50%。……いかに法律による恩恵を受けているか。、


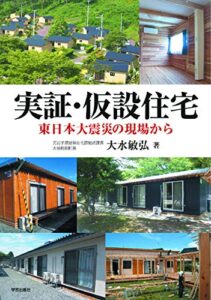
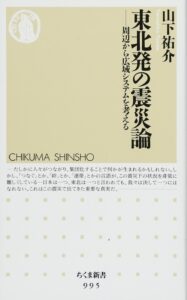

コメント