NHK出版 生活人新書 1091004
三位一体の改革で交付金が減らされ、基金が取り崩され、いつ破綻してもおかしくない状況に追い込まれた市町村に、「平成の合併」がおそった。合併しても改善は望めない、かといってこのままでは破綻してしまう。じり貧状態のなか、多くの町村は合併に追い込まれた。
そんななか人口2千人余の海士町は「単独」を選んだ。町長自ら給料を半減させ、意気に感じた課長が自ら給料削減を申し出、一般職員も申し出る。ラスパイレス指数70台という日本一給料の安い自治体になった。
だが予算を削るだけでは、対症療法にすぎない。
そこで、「島のまるごとブランド化」と称して、「島の宝物」で外貨を獲得しようと考える。サザエカレー、イワガキ、CAS凍結装置、天然塩、隠岐牛……次々に手がけていく。ついには3年間で78世帯145人のUIターンを受け入れた。
最初のサザエカレーやイワガキ養殖は、専門家に指導をあおいだが、それでも丸投げはせず、町職員が積極的にかかわった。自分の頭で考え、形にする経験を重ね、生産者と職員が一緒に市場をあるいて料理店や仲買業者の感想を聞いてまわった。今では職員が成長し、コンサルを使う必要がなくなった。
問題はなぜ2500人の町でそんなことができたか、だ。町長が優秀なのはまちがいない。が、町長が自分の給料を削減するかといって、全職員がすすんで「自分の給料も」と申し出るなどふつうは考えられない。日本一安い給料で土日も含めてサービス残業もこなして働く町職員の意欲の源泉はなんなのか?
それはたぶん青年団運動なのだ。
町長自身、郵便局員だったときに青年団運動に没頭した。町長の思いにいちはやくこたえた課長連中も、青年団運動が盛んだった時期の仲間同士だった。個人的な欲ではなく、仲間といっしょに「自分以外のなにか・だれか」のためにナニカをつくりだすことに熱中した経験が、独特の団結を生み出している。個人的な欲を超える楽しさややりがいを知っているからこその行動力ではないか……と感じた。
やっぱり良質な町おこしの基盤には「人づくり」があることを再認識する。
今は青年団活動は衰えているが、「商品開発研修生」という名で全国の若者に1年間月給15万円で住んでもらい「宝探し」をしてもらっている。1年間ぶらぶらしてもらって、1年後に「宝」を形にしてくれることだけが条件という。「君にすべて任せた。自由にやってくれというのは研修生にとってはいちばんたいへんなこと、難しいことです」という町長は、人づくりをよく知っている。
=============抜粋・覚え書き================
▽27 交付金減。平成16年は一気に1億3000万円も。町税収入に匹敵する額。借金返済で基金を取り崩し、このままでは夕張に……
▽42 合併問題 人口2千数百人。住民投票の必要はない。その気になれば住民ひとりひとりと話ができる。14地区で住民集会を開き、住民の声を直接聞いた。合併問題だけでなく、住民集会は折をみて開いている。
合併のメリットはないが、単独でも危機的だ。どちらも前途多難。どのみち、苦労は避けられないのならば、自分たちの力でできるだけのことをした方がよい、と考えた。
▽53 NTTをH3年にやめて52歳で帰郷。3セクの仕事を引き受け、マリンポートホテルの開業からかかわり、のちに総支配人に。新しいことをしようとすると町議会から横やりがはいる。事業を円滑に進めるため、自ら町議に。
▽57 建設業の社長が「もう公共事業に頼る時代は終わった。これからは行政も民間の感覚でやらないと島は生き残れない」と町長選出馬を促す。企業の経営者だから、いまの行政では生き残れないことがわかっていた。
▽73 交流促進課 地産地商課 産業創出課 は拠点を役場本庁舎から移した。観光は「キンニャモニャセンター」へ。観光を担当する職員が役場にひっこんでいてもしかたない。
▽86 自らの給与カット。それを知った課長たちが「自分たちの給与も」と言ってきた。〓青年団の効果か? 一般職員も自主的給与カット、町議も教委も申し出た。日本一給料がやすい役所。
▽94 住民から「役場が頑張ってるのは分かったから、そろそろ職員の給料も上げてやれよ」。まだまだ状況が厳しいことには変わりはないが、少なくとも以前よりはよくなっている。自分たちのやっていることはまちがっていない、この先に希望はあるのだということを、実感してもらえている。希望があるからこそ、人は働くことができる〓。(幸福追求)
▽104 サザエカレー 各家庭に独自のサザエカレーがある。いままで気づかなかった島の宝物を使って外貨を獲得していこう、というのが「島のまるごとブランド化」戦略。第2弾はイワガキ。
▽109 CAS凍結。自治体としてははじめて導入。CAS導入ではじめて、ケンサキイカ(白いか)が商品になった。鮮度が落ちやすいから市場が遠くて無理だった。島内消費ばかりだった。
▽114 天然塩「海士御塩司処」。天川のきれいな水をつかってなにかできないかと考えた。保々見湾は、とくに海水がきれいなところで、イワガキの養殖もここでやっている。海水のミネラル分も豊富で、塩をつくるにはうってつけ。海士の自然がいっぱいにつまった塩。
▽121 隠岐牛。成牛を本土まで運ぶコストを考えると、1キロ2500円以上で売れないと利益が出ない。ブランド牛なみ。それは無理だとだれもが考えて子牛生後30カ月で出荷していた。あえて挑戦したのが建設会社の田仲寿夫さん。民間企業の農業への参入には農地法による制限がある。そこで国の構造改革特区の農業特区認定を受けた。「隠岐潮風ファーム」には町からの補助金は出していない。
▽133 あえて高いハードルにして、東京の食肉市場に出した。高いハードルを作らず背伸びをしないでやることは現実的な方法なのではない。それは成功の可能性をも低くしてしまう。
▽140 2500人の島に3年間で78世帯145人のUIターンを受け入れた。
▽152 郵便局につとめていた昔、青年団活動に精を出した。とても楽しく、この活動がいまの私のベース。〓
▽154 外部の目 商品開発研修生として全国の若者を募る。月給15万円。1年間。こちらの要望は「この島で宝探しをしてください」だけ。宝探しをして、1年後に宝をきちっと形にしてくれることだけが条件。「君にすべて任せた。自由にやってくれ」というのは研修生にとってはいちばんたいへんなこと、難しいことです。〓人づくりの発想は青年団から?
▽156 「海士御塩司処」で塩をつくっている田中くんはもとは商品開発研修生。うどんを作るため島に残る人もいる。「ふくぎ茶」商品化の作業を福祉作業所の人たちと始めたのも研修生。
▽162 東京の新宿日本語学校と連携して、外国人学生との交流も。日本にやってくるとまず海士に来て10日間をすごしたあとに東京に行く。日本語がうまくない状態で中学生と交流し、ホームステイする。
▽171 事業は外部のコンサルに委託することはほとんどしない。サザエカレーやイワガキ養殖は、何もわからなかったから、協力を専門家にお願いしたが、それでも丸投げはしない。あくまで協力を頼んだだけ。サザエカレーは全国各地で試食会をしたが、すべて町職員が積極的に関わってきた。どうすれば島のイメージを商品に反映できるか、情報発信をどうするか、管理体制・販売体制をどう作り上げるか、自分の頭で考え、形にする経験をしなければ、次の商品につながらない。イワガキのときは、生産者と職員が一緒に市場をあるきまわり、料理店や仲買業者の感想を聞いてまわり、流通の障害を取り除いてきた。答えはすべて現場にある。現場で汗をかき、知恵をひねりださなければ答えは見えてこない。今ではコンサルを使う必要がなくなった。
▽176 役場職員にバイタリティがある。これはおそらく青年団活動がはくくんだ。課長連中は同年代で青年団の仲間だった。私たちの世代のあと、しばらく青年団はなくなっていたが、それを復活させたのが課長たちの世代。人形劇をつくって全国大会にでたりもした。
課長連中のあと、また活動は下火になっている。〓NPOの動き
▽190 隠岐島前高校 「守る」というより、売り出す方向で考えるべき。島外の人を呼び込む材料に。「売り」をどこに持っていくかは、これからの検討課題。ほかのどの高校でも受けられない教育が隠岐島前高校で受けられる。そんな価値を作っていかなければならない〓


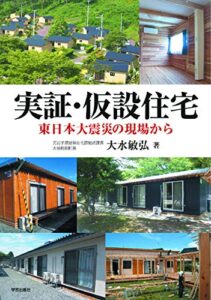
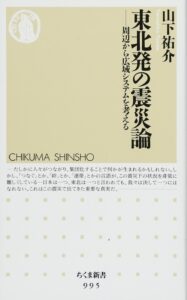

コメント