ちくまプリマー新書 20050529
「戦争になだれ込み破滅していった昭和史を少し丁寧に読み解けば、その前段に地方行政の手詰まり、怠慢、無能力があったことがわかるだろう」
冒頭、こんな言葉が出てきて、そうだったんだ、と目の前が開けるような気がして買った。
新潟県黒川村の物語だ。豪雪と天災とに悩まされる貧しい出稼ぎの村だった。そこにあらわれた31歳の村長が中心になって、集団農場をつくり、冬場に出稼ぎをしないですむようスキー場をつくり……いつしか過疎から脱却し人口増に転じた。その足跡を何年にもわたって関係者に丹念に聞き取ってまとめている。
まずは青年たちを集めて集団農業の新しい村をつくる。冬場の働き口を求めて手作りでスキー場を開き、泊まってもらうためにホテルを開く。減反対策と農家の収入安定をはかるため畜産団地をつくり、その肉を生かすためにソーセージ工場、さらにそれと関連してビール工場、そこで使う原料を供給するために大麦を植える……
「村おこし」は全国的に盛んだが、ほかと違うのは、施設のすべてが村営で、働いている人も村の職員であること。スキー場の整備をするのも山を切り開くのも村職員、インストラクターも職員、ホテルのコックも職員だ。
若い職員には海外の研修をつませる。1年間、ヨーロッパなどの農家に住みこませる。帰ってくると「チーズ工場をやらないか」などと何億円の事業を丸ごと任せてしまう。必死になって勉強してその期待に応えようとする。海外で勉強した内容よりも、異文化のななかで1年間すごした経験じたいが大事なのだという。それはよくわかる。職員の4分の1がそうした海外経験を積んでいるという。
愛媛の内子町や久万町に似ている。
内子町でも、海外に研修に出している。久万町も以前はそういった「人づくり」に力を入れてきた。
国の補助金をいかに活用し、ぶんどるか、という工夫と経験の積み重ねも、久万のWさんの話と一緒だ。
過疎の山村に民間企業が入ってくるわけがない。 「役場がやるしかなかった」という。
「村おこし」で建てたハコモノが全国各地で無残な末路を歩んでいる。そういう事例とのちがいはどこにあるのか。
農民との生活、できた産品の活用、家畜の糞尿などの活用、それと村民の生活向上との関連づけ。水ものの「観光」に過度に寄りかからず、たえず村民の生活とのかかわりのなかで考えている。この感性は内子町に近いものがある。だがヘルパーを民間にゆだねてしまった内子町にはない「役場」の責任感と意欲をも感じる。
バブル崩壊を乗り越え、多大な成果を積み上げてきたそんな村も、2005年夏に合併でなくなるという。その寂しさや悔しさ。これが危ない時代への第1歩なのではないといいのだが。
▽戦争になだれ込み破滅していった昭和史を少し丁寧に読み解けば、その前段に地方行政の手詰まり、怠慢、無能力があったことがわかるだろう。当時の国家指導者はたしかに間違えたが、市町村行政に携わっていた者たちも同じ程度に愚かで無責任だった。…いま、同じことが起きていないだろうか。シャッターが降りたままの商店街や寒々しい風が吹き抜けていく住宅街を歩きながら、人々の鬱屈と不安がしだいに臨界点にむかって渦巻いていくさまを感じ取る。
---------------------
▽黒川村 75年に6389人、今は6750人。80年代の終わり、過疎地指定を取り消されている。
▽31歳で就任した伊藤村長「高度経済成長という魔物から、村を守らなければならなかった。役場がやらなければ、村がつぶれてしまうことはわかっていたんですよ。一生懸命考えてやっているうちにこうなった。これしかやりようがなかった」
▽1959年、若者を集め「青年の村」を建設。開拓して田圃を造成し、共同経営の機械化農業を目指す。…収支を考えた農業に、と、村の商工会から簿記の専門家にも来て貰う。座学のあとは2,3人ずつ組んで北海道などの先進的な農家に行って1カ月くらい泊めてもらい、乳牛の乳搾りや農業機械の操作を勉強する。
▽2年連続の水害 「単なる復旧ではなく、改良復旧を」。「そのころは災害復旧の制度など全然知らなかった。建設省や農林省や県でもよくわかっていなかったと思いますよ。陳情に行くと、「こんな補助金の制度がある」「この制度の解釈をこう変えれば使えそうだ」と教えてくれる。1年かけてお互いわかってきたところだった。だから次の年、もっと大きい水害がきたときは、両方がある程度勉強できていたんです」。伊藤は被災地視察に来た政府要人や県知事をかき口説いた。中央官庁にも何十回となく通った。「私も勉強したし、国や県の職員も勉強していた。こちらが何をしたいかはっきり打ち出し、向こうはどの制度を使えるかを提示して、おたがいが具体的に噛み合わせることがだいじだった」
▽(昭和51年ごろ共同農場だったのを、個人に分配する)「自分で流した汗が、自分にもどってこない。仕事の配分で楽な班と苦労する班の差が出てくる。個性もちがえば、欲望の中身もちがう、生活力の差もある。大人はやっていけるかもしれんが、やがて子供が大きくなったとき、親の世代がはじめた共同労働に入ってこれるか、入るように強制できるかどうか、という問題もあった…」(共産主義の国の共同農場が直面した壁と同じ問題を抱えていた)…共同の生活と作業の場になっていた知新寮は取り壊され、跡地はスキー客用の駐車場になった。
▽減反対策で79年、畜産団地を村が建てた。村採用の職員や獣医が和牛繁殖をおこない、8カ月になるまで育て、農家に販売する。農家は生産者組合をつくって同じ敷地内の肥育牛舎に毎日通ってきて世話をし、およそ2年半をかけ成牛に育て上げる。繁殖と肥育を分業するこの仕組みは、朝暗いうちから夜遅くまで働くという畜産農家の苦労を少しでも軽減し、畜産をさかんにしようと考えられたものだった。 (〓Y町の大規模な養豚は失敗したが……)
▽スキー場。草刈りなども村職員が作業着に着替えて働く。コースやゲレンデ整備で走り回っているうちに、スキーが上達し、インストラクターになった。それも村職員としての仕事だった。
▽新人の職員は、高級リゾートホテルに半年間研修に行かされる。(K町と同じだ)「ほんとにサービス業をやったことのない公務員は口では『公務員はサービス業』と言っても実際はなかなかできません。お客に頭を下げたり、膝をついてコーヒーやお酒を出したりなんて、すぐにはできないんです」…給料は村から出ているので、受け入れたリゾートホテルにしてみれば、ただ働きしてくれる従業員が増えたようなものだった。
▽村に瀟洒なホテルを建てることで、因習的な狭さや古さを変えたいと。家に帰って「こんな客がいた」と話題にするでしょ。そうやっているうちに本人の関心も広がるし、家のなかの話題も変わってくる。ホテルの料理を見ていれば、「家でもこういうふうにつくってみようか」とか。戦後のいっときあった公民館運動的な社会教育にもなる〓。
▽中央官庁からの出向者を伊藤村長はほんとうにだいじにしてきました。
国の省庁にいくと、関連する部長、課長、係長クラスまであいさつしてまわった。県庁でもそう。「課長や係長が大事なんですよ。彼らは2,3年後に動き出す精度や補助事業の案をあたためている。村長は立ち話しながらキャッチしてくる…新しい制度ができたら最初に利用するんだ、と」
▽「力のある村長の下で働くと、大変ですよ。『それはできません』なんて言えないってことですから。村で何かつくりたいと言うと、われわれ事務屋は国や県のいろんな補助事業の書類をひっくり返して、何かに該当しないか、ここの表現をちょっと変えれば、こちらの補助制度に、と一生懸命さがす。何とか修正して、制度の上にのっける。それが仕事ですから」「ひとつの施設がひとつの補助金でできるなんてこと考えてません。この部分はこの補助金、こっちはこの補助制度を使おう、と…そば店の水車をつけるには、本当に川の水で動かすようにして、農業構造改善事業では無理そうだから、と思っていたら省エネ補助事業があったと思いつく」
▽村長は毎日3時間睡眠。公用車のなかは資料や本ばかり。移動のとき彼はいつも何かを読んでいた。「人生は、知らないことを知る、そこに意味がある。その繰り返しが人生だと思いますね。いかに多くのものを知って吸収するか、それが生きている証拠だと考えているんです」
▽「やっと若者たちが村に定着するようになったといっても、国内にいる限りはぬるま湯ですからね。自分とはどういうものか、外国で生活してはじめてわかる。自分の価値、置かれた立場、そこから自力ではい上がっていかなければ、まわりはただの一般的なアジア人としてしか見てくれない。そこで苦労しながらコミュニケーションできるようになって、何かをはじめると、周囲の見る目が変わってくる。個人としての注目や尊敬を集めるようになる。私は若い職員にそういう経験をしてほしいと期待している」本人は費用の一部として数十万円から百万円近く負担するが、村はその間、出張扱いにしているので、毎月の給料を支払わなければならない。
▽「この村では、6億円、7億円をぽんと27歳の2人に全部あずけて、『さあ、あとはちゃんとやれ』と任せちゃう。任されたほうも、何とかがんばって、やっちゃうんですよ」
▽ミネラルウォーターのプラント。農産物をかませて農家の収入増に結び付けようと、薬草をやることに。サル被害が急増していた。人里と山林が混じり合うあたりで生える竹の子や渋柿や栗などを人がとらなくなった。人が田畑で働く時間が短くなり、サルにはおそれる相手がいなくなったことも理由になった。ところがサルは薬草は好きではないから安心して育てられる。


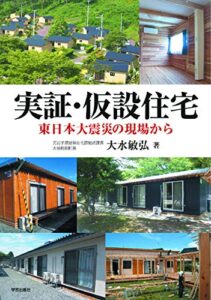
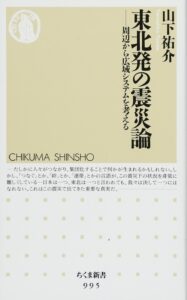

コメント