農文協 20090322
中国新聞の取材班の連載をまとめた。中国山地の山村を手始めに、輸出用作物を大量生産する中国や、自由貿易協定によって疲弊するタイの農村まで出かける。
山村の住民にとっては、「切り捨て」は農協支所の閉鎖にはじまり、市町村合併で役場がなくなり、郵政民営化で新聞は午後届くようになり……と、進んできた。
国の政策はそうしたムラの現状を理解しているとは思えない。たとえば、農民を助けるはずの中山間地域等直接支払制度は、最初は順調だったが、第2期(05年度から)は、マスタープラン作成が義務づけられ、協定に違反すると交付金返還を迫られることになった。明日をも知れぬ高齢者に「未来を語れ」とせまる残酷さである。
一方で、そんな山村でなんとか生き抜こうという動きも取材している。
炭焼きから酪農、米、杜仲茶……と特産を開発する。自家製豆腐やこんにゃく、漬け物などの食文化を復活させる。。女性主導でトマトの雨よけ栽培をはじめ、営農口座を女性名義で持たせる。農家と学生を結びつける。直売所や学校給食などの形で都市とムラを結ぶ……。
希望があるとすれば、「中国が世界最大の食料消費国に急成長している。早ければ10年、遅くても20年で、世界の食料事情は一変するだろう。自分が種をまいて育てて食べる自給型の見直しが進み、中山間地域にも光が当たるようになる」という言葉だが、それまで生き残る集落がどれだけあるか……
==========抜粋・メモ=============
□空谷地区
▽島根県中山間地域研究センター〓
▽耕作放棄地の面積〓 農業補助金
▽22 中山間地域等直接支払制度 最初は順調だったが、第2期05年度からは、マスタープラン作成が義務づけられ、協定に違反すると交付金を返還せねばならない。明日をもしれぬお年寄りに「未来を語れ」とせまる。
▽25 統合の第一歩は農協支所。それから切り捨てばかり。2町1村合併で役場が遠くなった。郵政民営化で新聞は午後届くようになった。
▽33 炭焼き> 酪農> 米> 杜仲茶を特産に 炭焼きも復活。
▽36 空谷の横山集落 自家製豆腐やこんにゃく、漬け物……手作りみそは消えつつあったが、農業改良普及所の協力で講習会を開いた。食文化の復活。自宅の納屋にみそ蔵をつくった。
農産加工部を87年に設立。だが、販売免許が06年に切れ、高齢化もあって、対外販売活動はやめた。食文化をだれに引き継ぐ?
▽40 島根県中山間地域研究センターの限界的集落の定義。
▽53 益田市匹見町土井ノ原 旧匹見町長の斎藤のぶとさん。不在地主が増える。農地一筆マップ〓づくり。耕作面積や作付け、世帯構成や周囲の空き家の状況などを調査。集落の現実を見すえ、住民自らがムラ起こしに立ち上がろうという取り組み。
▽55 山口県萩市旧むつみ村高俣地区 旧むつみ村では、農協婦人部の3人が1970年代に水稲用苗ハウスでトマトの雨よけ栽培をはじめ、女性主導で10ヘクタールまで育てた。営農口座を女性名義で持つのも画期的だった。何よりトマトの縁で地域が結束する手応えが原動力になった。
▽66 岩国市錦町向峠 行政の旗振りで集落法人の設立が中国地方でも相次ぐ。向峠は平家の落人が開いたとされる。江戸時代に住民自らが5.3キロの水路を掘った。今も各戸交代で水路を見回るなど共同の気風が息づく。
□アジア
▽86 農薬使用制限のため、日本が06年に導入したポジティブリスト制度で、小農家の葱は、仲買人がひきとってくれなくなった。「監視の目が届かない零細農家のものは危ない、と企業が言うんだ」
▽96 島根県立大短期大学部の大塚茂教授 中国の無農薬食品が国際競争力を持ったら……国内農産品は……。高温多湿で人件費が高い日本より、中国のほうが無農薬野菜を低コストでつくれる。
▽113 メコン川 ASEANと中国がFTA締結。その2年前の03年に、野菜や果物の関税を先行撤廃した。中国から野菜・果物の輸入は4.4倍にふくらんだ。とくにニンニクは、中国産はタイ産の半値。タイ全土の作付け面積は7割減った。
▽114 タイと日本のEPAは、07年秋に発効。
▽128 01年のWTO加盟を機に、中国政府は効率化の論理を農業に浸透させている。すべてカネに置き換えられたら、農村の多様性や固有性は根こそぎ失われる。
▽136 島根県浜田市弥栄 旧弥栄村は移住者が人口の15%を占める。〓 農業研修生制度 25年住めば家も土地も無償譲渡。村営住宅も次々に建設。
▽138 島根大生らの「食と農のインキュベーションNOLO」東出雲町野呂地区 〓客員教授の片岡勝さん。
▽143 島根県吉賀町 空き家紹介で成果
▽159 過疎以上に問題なのは誇りの空洞化。明治大の小田切徳美教授。
▽161 京都・綾部 水源の里条例 あきらめと悲観を乗りこえる。
▽184 島根県中山間地域研究センター 有田昭一郎主任研究員 直売所や学校給食へ。地産池消費。都市とムラをしなやかに結ぶ営みを「時代の潮流の最先端にあって、今後のライフスタイルを提案している」 直売所に詳しい。
▽187 日本農業のてこ入れに、学校給食活用を。長崎大・中村修准教授。学校がある市町村内で食材をまかなう「地場産自給率」を国内ではじめて提唱。〓〓
「学校給食会」が食材流通を牛耳るが、必ずしも安いわけではない。なのに「地場産は重量や形がふぞろいでつかいにくい」。一部の給食会は公務員の天下り先。
▽206
▽214 2006年、安倍首相が豪州とのEPA交渉入りを決断。その結果、食料自給率40%が、さらに10ポイント低下する--自民党農林水産貿易調査会の試算。
▽218 広島県庄原市一木集落 牛の飼料の稲藁とイタリアンライグラスは集落内で自給。牛糞は堆肥にする。1970年代から畜産農家と耕種農家が連携してきた「耕畜連携」の先進地。バイオ燃料ブームによる飼料高騰で脚光。ところが日豪EPA。
日豪が関税を撤廃すれば、農水省の資産では、生乳生産額の44%が減少し、乳製品向けのほぼ全量がオーストラリア産になる。
▽222 鈴木宣弘(農業経済学)東大教授 日本の農産物の平均関税率は12%。EUの20%、タイの5%などよりはるかに低い。米や乳製品、肉など、全体の1割程度しかない重要品目を何とか守っているにすぎない。
▽226 藤山浩・島根県中山間地域研究センター地域研究グループ科長
中国が世界最大の食料消費国に急成長している。早ければ10年、遅くても20年で、世界の食料事情は一変するだろう。自分が種をまいて育てて食べる自給型の見直しが進み、中山間地域にも光が当たるようになる。
それまでどう地域を維持するかが問題。特に昭和1けた生まれ主舞台から降りる5年から10年先までが胸突き八丁。彼らの知識をだれがどう引き継ぐのか。
集落の枠を超えた新たな地域運営組織の構築、放棄ではない粗放的農地の管理……が急務だ。


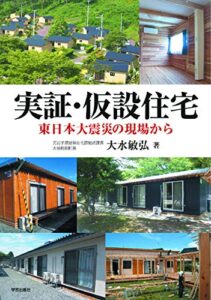
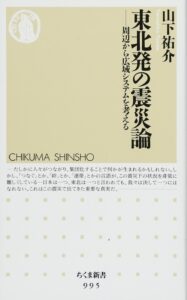

コメント