■暴走する地方自治<田村秀>ちくま新書20121215
熊本の細川、三重県の北川、鳥取の片山から橋下・石原にいたるまでの「改革派」の知事が、実は話題先行で混乱しかもたらさなかったのではないか、というスタンスの本。説得力のある部分もあるが、筆者の立場は中央官僚に近い。話題をふりまくよりも地道な取り組みを、というスタンスの本だ。
橋下が掲げる大阪都構想を歴史的な文脈で批判しているのは興味深い。
明治のはじめは政府の意向で、官選の大阪府知事が市長を兼任していたが、大都市側からの反対で、1898年に大阪府から大阪市が独立した。大都市側が運動を進めてきた結果、1947年の地方自治法で、都道府県の区域から大都市部を独立させる特別市の制度が設けられた。その後、地方自治法改正で政令指定都市の制度が設けられた。
戦時体制によって中央集権化をはかるため、東京市が廃止されて東京都になった。戦後、特別区の区長は区議会によって選ばれていたが、多党化で区長候補を絞りきれず、区長不在というケースが続出したため1975年に区長公選が復活した。特別区は他の市に比べると劣っている点が「特別」。だから、特別区長会は、ほかの市と同様、東京○○市となることを求めているという。
橋下の都構想はそうした地方分権の流れを逆行させる動きであることがよくわかる。
世界的に見ても、住民自治の充実の工夫をしながら大都市の機能を高め、存在感を強めようというの流れになっており、先進国で、都制度のようなものを導入しているところはないという。大阪や愛知が目指す都市の解体は「世界の非常識」という。
各地の自治体の紹介も、いわゆる町おこしの本とはスタンスが異なっておもしろい。
新潟県加茂市の小池清彦市長は元防衛庁教育訓練局長で、合併に反対し、市外の田上町にまで公費で作成したチラシを配って合併を阻止した。 愛知県犬山市は、教育委員会を最大限活用して、文科省や県に頼らない独自の教育政策を展開している。
=========抜粋=========
▽18 橋下 府知事選出馬に際して「2万%でも、何%でもありえない」
▽20 大阪府と大阪市の対立の歴史
大都市に自治権を与えることへの中央政府の危惧から、官選の大阪府知事が市長を兼任。大都市側からの強い反対で廃しされ、1898年に大阪府から大阪市が独立。当初は、東京市の区同様、大阪市の区も法人格と議会を持っていたが、1943年に戦時体制下で解散。
特別市制は、大都市側が明治時代から運動を進めてきた長い歴史をもつもの。その結果、1947年の地方自治法で、都道府県の区域から大都市部を独立させる特別市の制度が設けられた。……大阪市の区域には大阪府が存在しなくなるというのが特別市制。大都市と都道県の間で大論争となった特別市の問題は、地方自治法改正で政令指定都市の制度が設けられたことで一応の「解決」をみた。
▽28 大阪市を解体し、道州制への移行によって、最終的には大阪都も解体することになる。……常識的に考えれば道州と大阪都は相いれない存在。
▽95 新潟県加茂市 小池清彦市長は、元防衛庁教育訓練局長。合併に反対し、市外の田上町にまで公費で作成したチラシを配って合併を阻止した。「イラク特措法案を廃案とすることを求める要望書」(平成15年)、イラク撤退を求める意見書(平成16年)
▽108 全般的には三位一体改革は一定の成果をあげたと言われてはいるが、実際は、税源移譲が十分に進まなかった点や、地方交付税や国庫補助負担金の総額が抑制されたことなどによって、地方側の不信感も少なくなかった。……不交付団体にとっては、補助金のかわりに地方交付税に振り替わってもメリットはほとんどなかった。……地方交付税の総額が抑制され、夕張市のように財政運営に行き詰まりをみせる自治体が続出した。
▽118 鳥取県境港市は92年から北朝鮮の元山市と姉妹都市交流をしていた。拉致問題で批判も強まり、地下核実験表明で06年に提携を破棄したことで、現在では北朝鮮の都市と姉妹提携をしている自治体はひとつもない。
▽120 法律上、地方自治体には原発を作る、作らない、動かす、動かさない、の権限がどこにも規定されていないのにもかかわらず、事実上(安全協定によって)自治体が拒否権をもっている。本来は国が責任を持って権限を行使すべきところが、地元の了解がなければ何もできないことになっている。
▽130 東京都の青少年健全育成条例 全国の青少年保護育成条例 大阪の教育基本条例も原案は法律違反の可能性が高かった。しかしいくら違法でも、具体的な訴訟にでもならない限りは裁判所は判断しない。
▽137 戦後、市町村警察が財政的に行き詰まると都道府県警に変更され、国の出先機関が相次いで設立されるなど、制度改正の揺り戻し。
▽139 戦時体制によって、東京市は廃止され東京都に。戦時下の特殊事情で構築された中央集権的組織。……特別区の区長は区議会によって選ばれていたが、多党化で区長候補を1人に絞りきれず、区長不在というケースが続出した。そこで1975年に区長公選が復活した。
……特別区は他の市に比べると劣っている点が「特別」。だから、特別区長会は「都の区」制度は廃止して、ほかの市同様基礎自治体として東京○○市となることを求めている。
▽147 合併で、高山市は大阪府や香川県よりも大きくなった。
▽156 イングランドの地方自治は必ずしも分権的ではない。イングランド以外のほうが分権が進んでいる。
フランスは、コミューンの人口規模は2000人にも満たない。県は96。県制度創設時に官選知事の制度ができ1982年までつづいた。日本に比べても分権化の動きは遅かった。……アメリカ
▽170 フランスはコミューンの数が多いこともあって、地方議員が50万人もいる。成人の100人に1人が地方政治家。コミューン議員はほとんど無報酬だが。
▽172 ドイツは、州議会議員が連邦参院議員を兼ねることで国政への影響力を持っている。
それに比べると、市区町村議会議員の7割以上が無所属というのは世界的にみると異例。
▽174 住民自治の充実のための工夫をしつつ、大都市の機能を高め、存在感を強めようとしているのが世界の常識。少なくとも先進国で、都制度のようなものを導入しているところはない。大阪も愛知も、表面上は強い大都市を目指すというが、その実態は逆方向の「改悪」。都市の解体は世界の非常識。
▽194 犬山市のように、教育委員会を最大限活用して、文科省や県に頼らない独自の教育政策を展開するところも。
▽222 三重県多気町 県立高と連携した高校生レストラン コンサルなどに頼らず地域活性化。


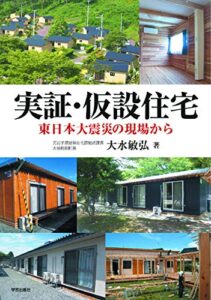
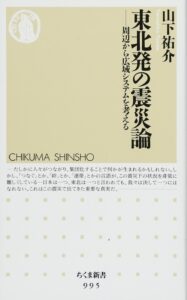

コメント