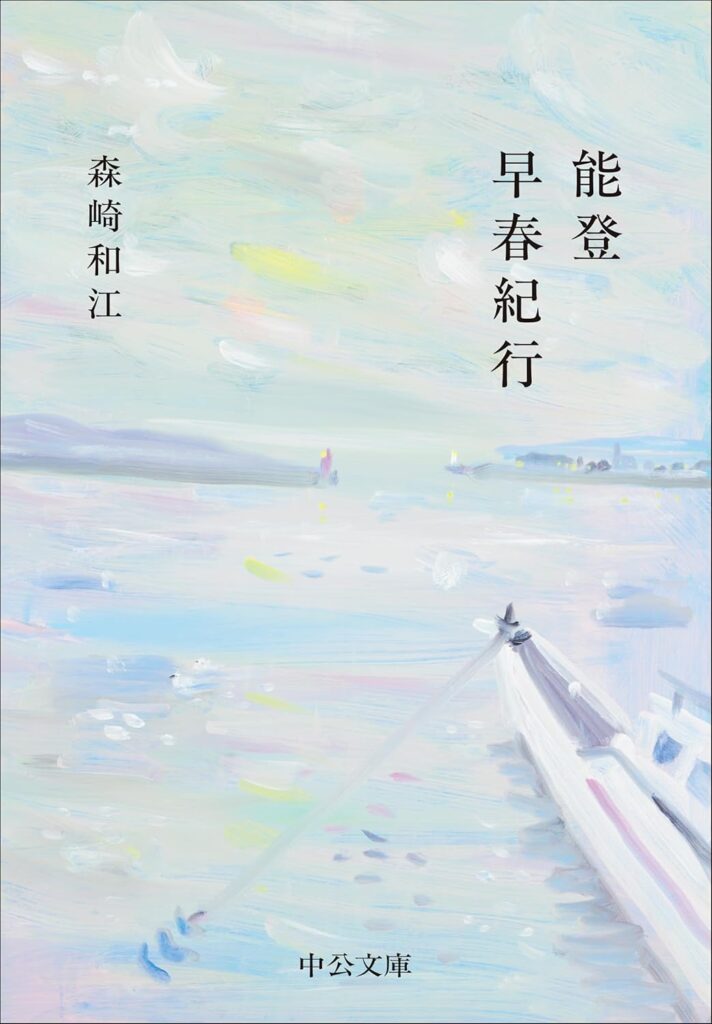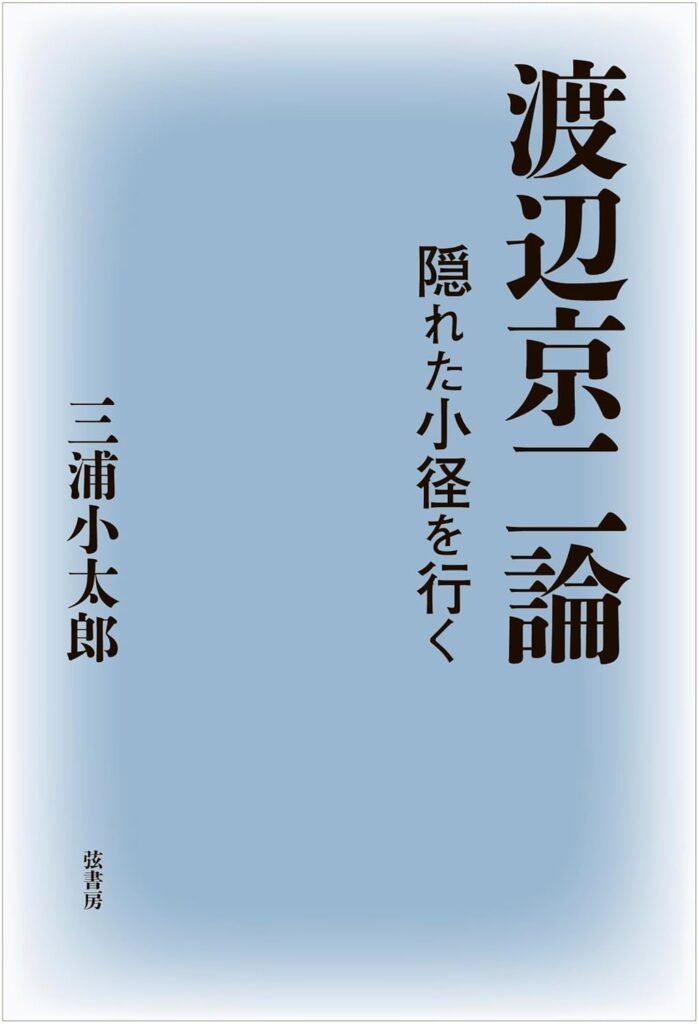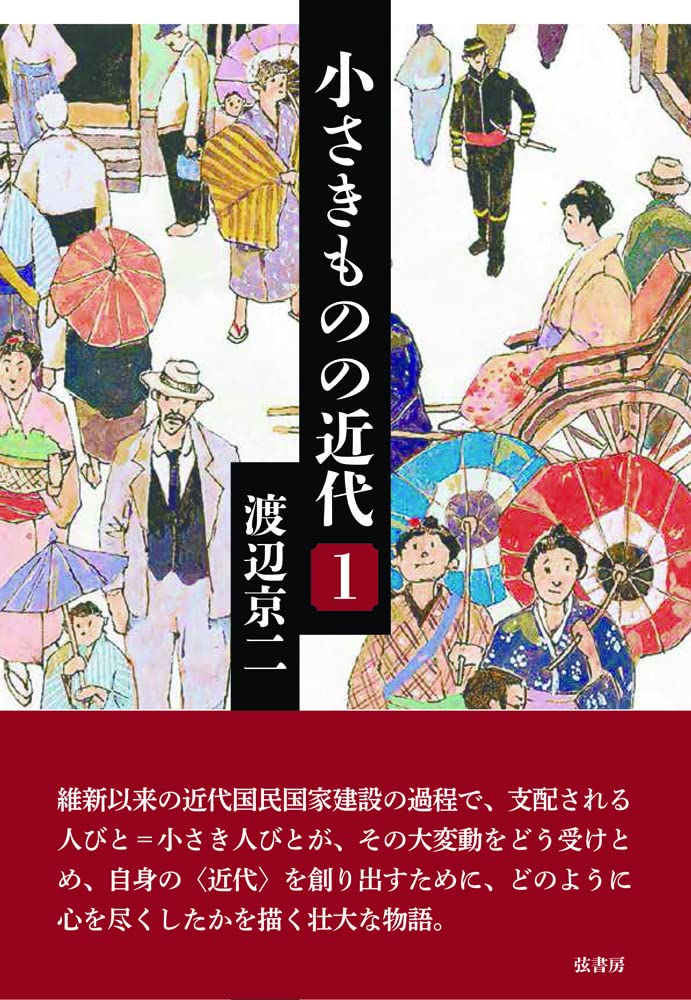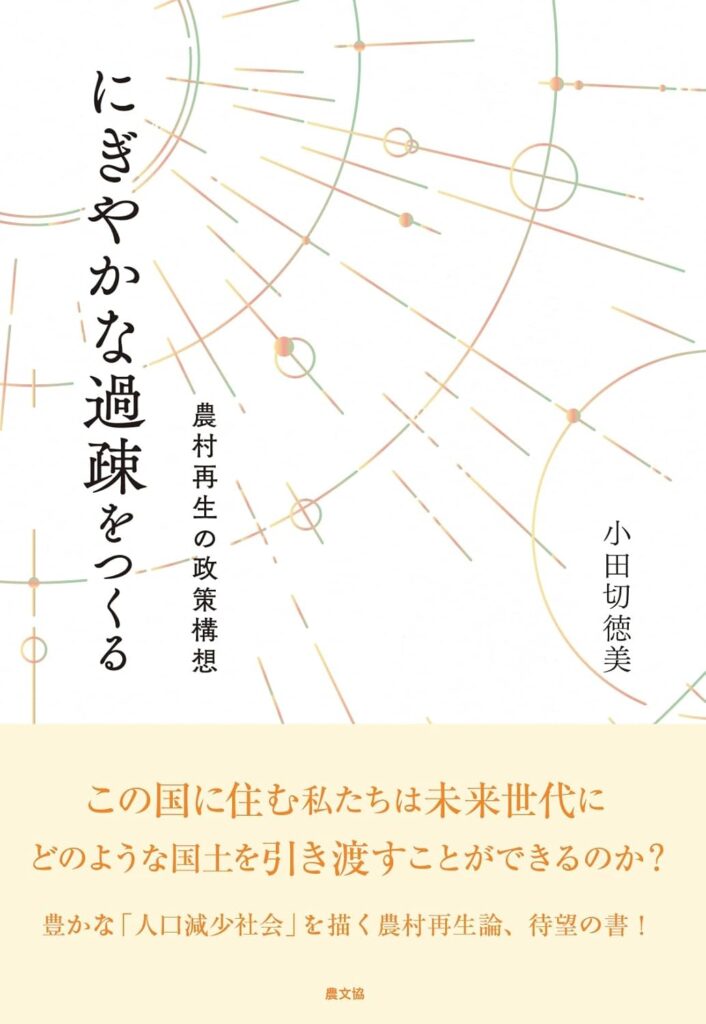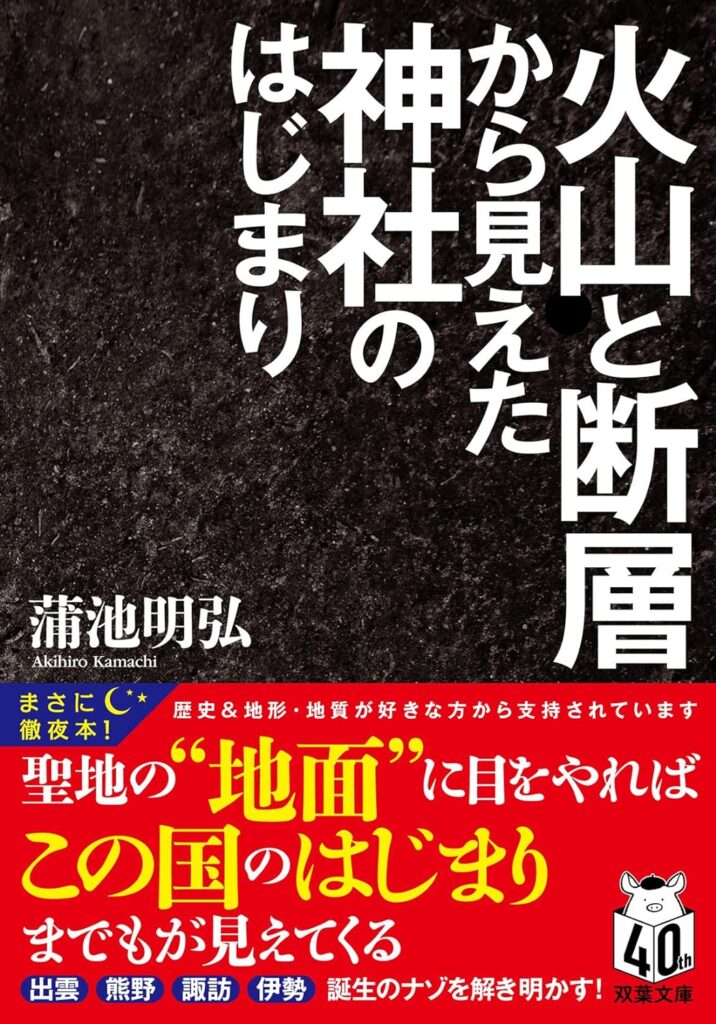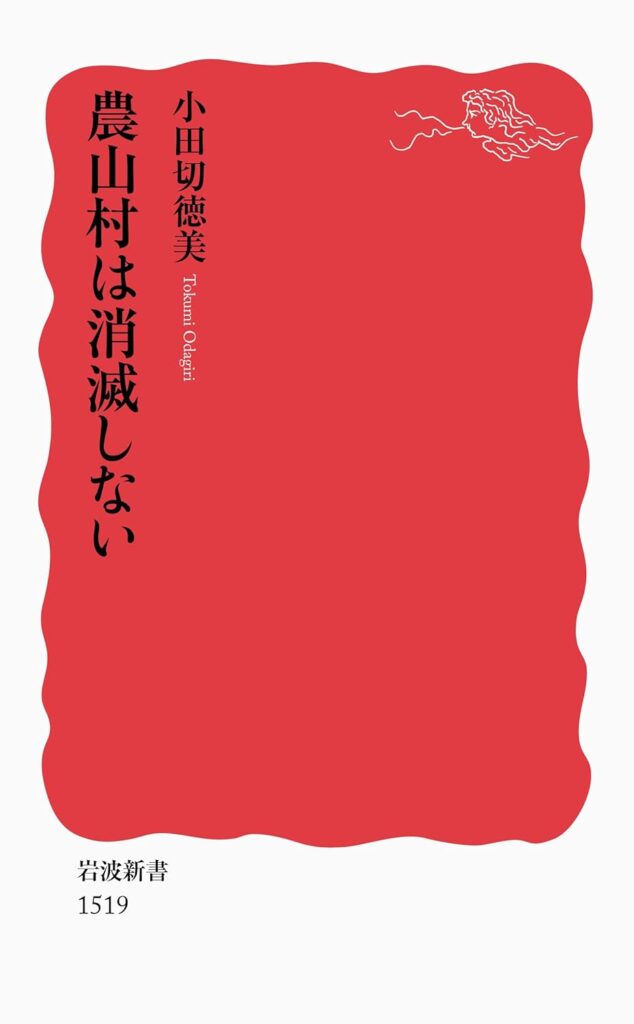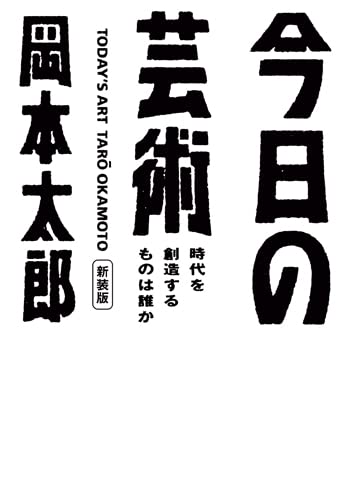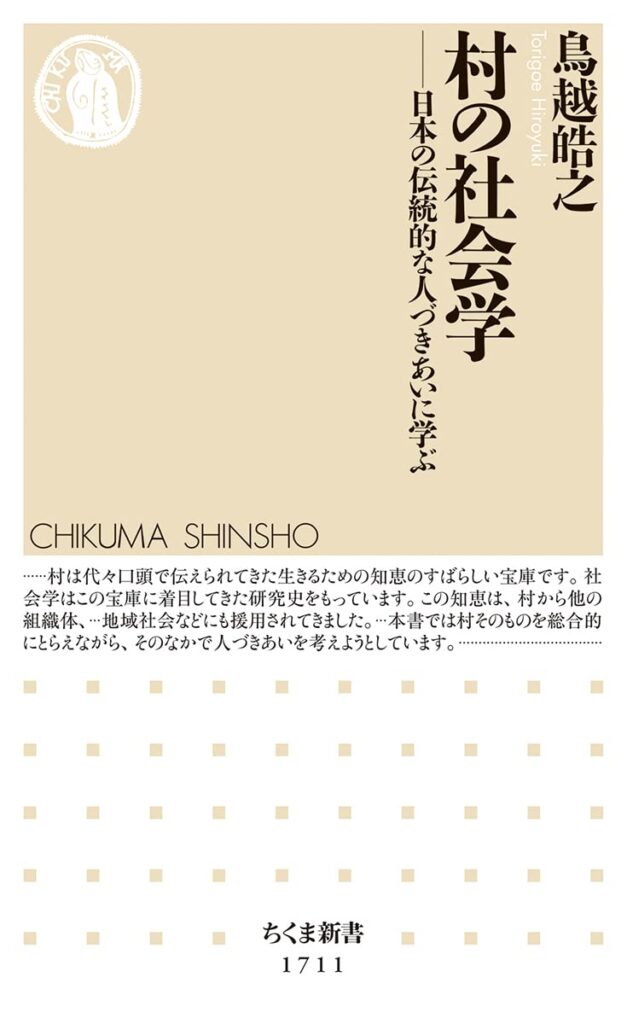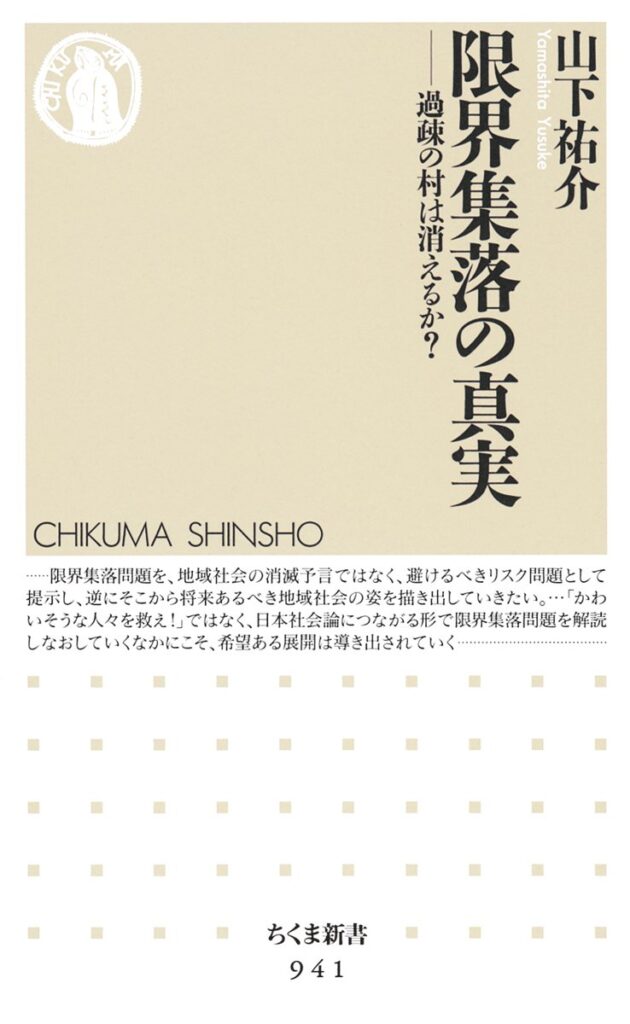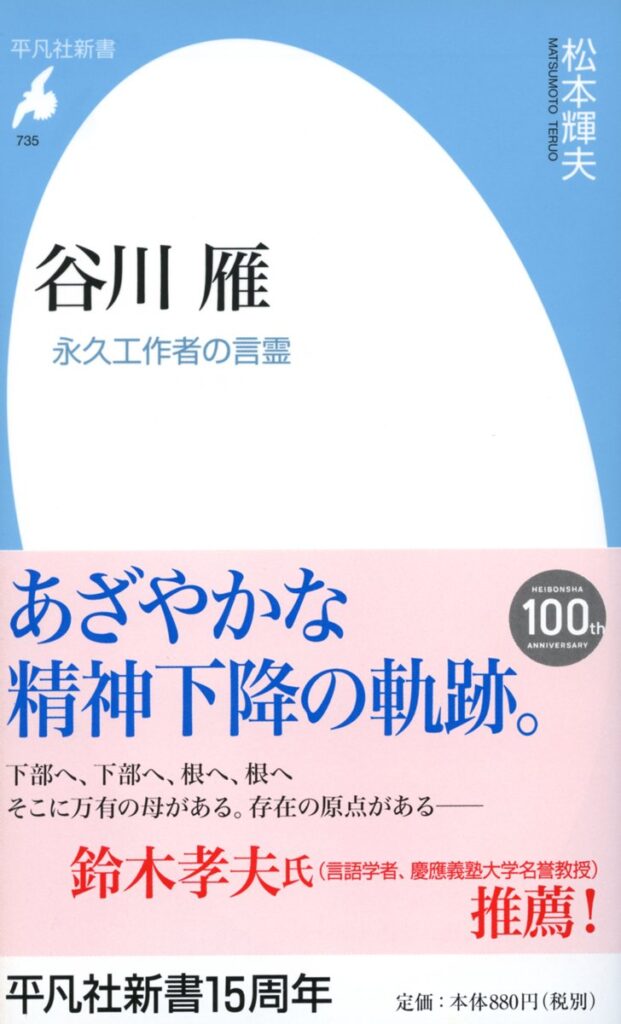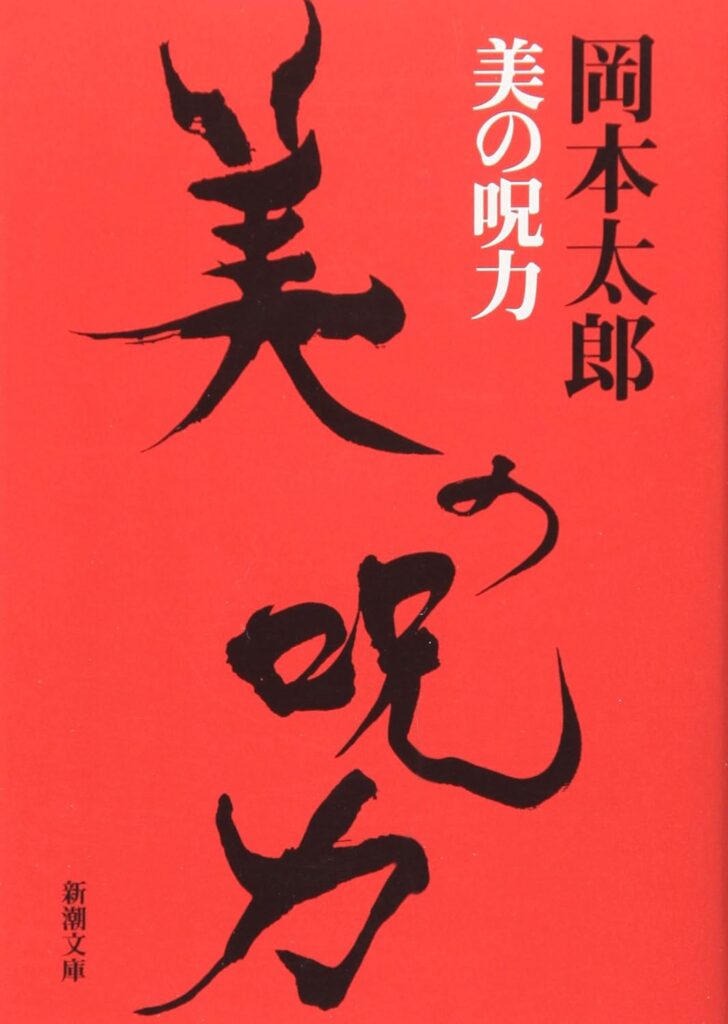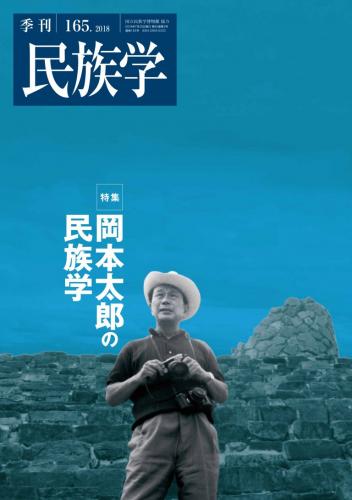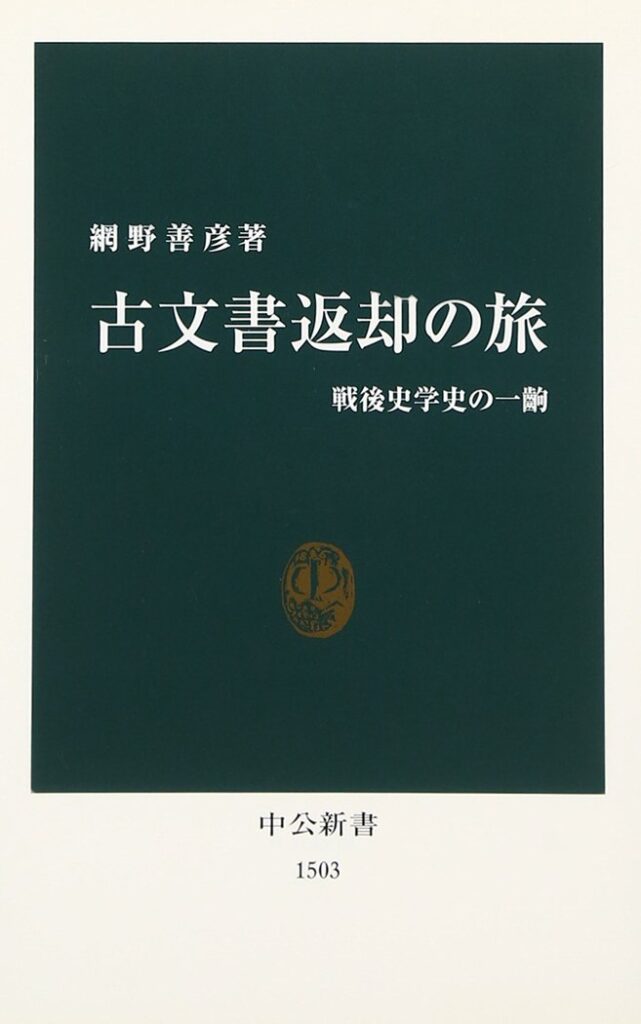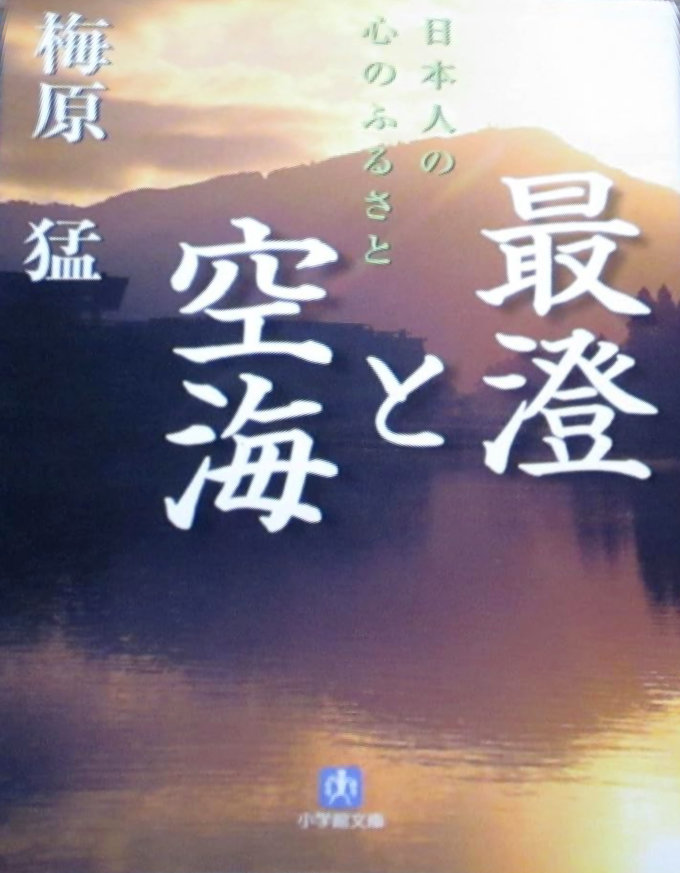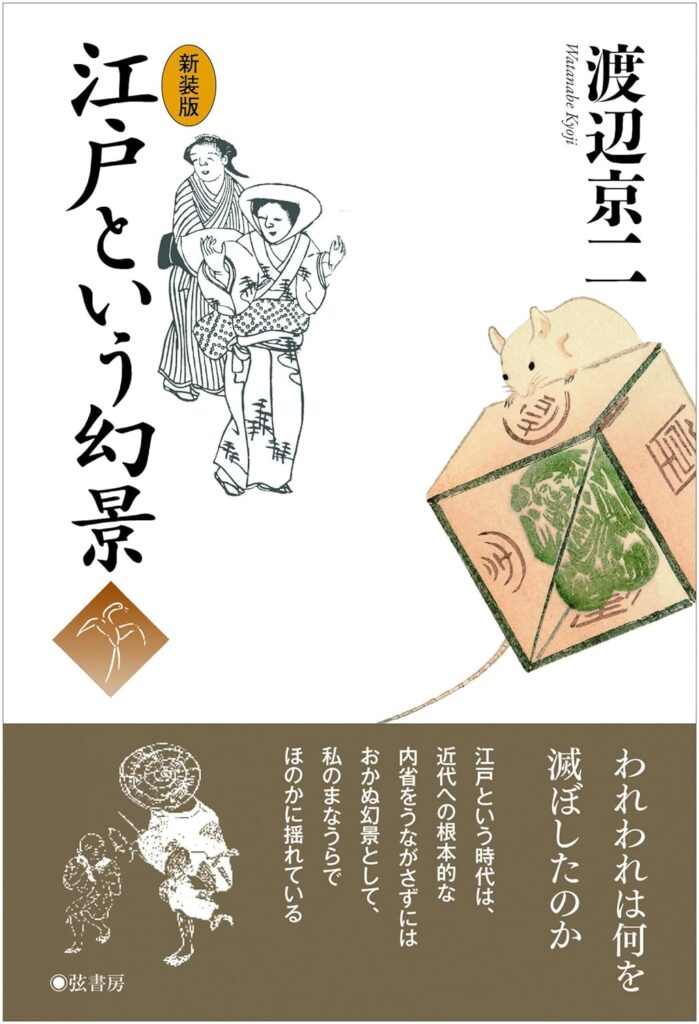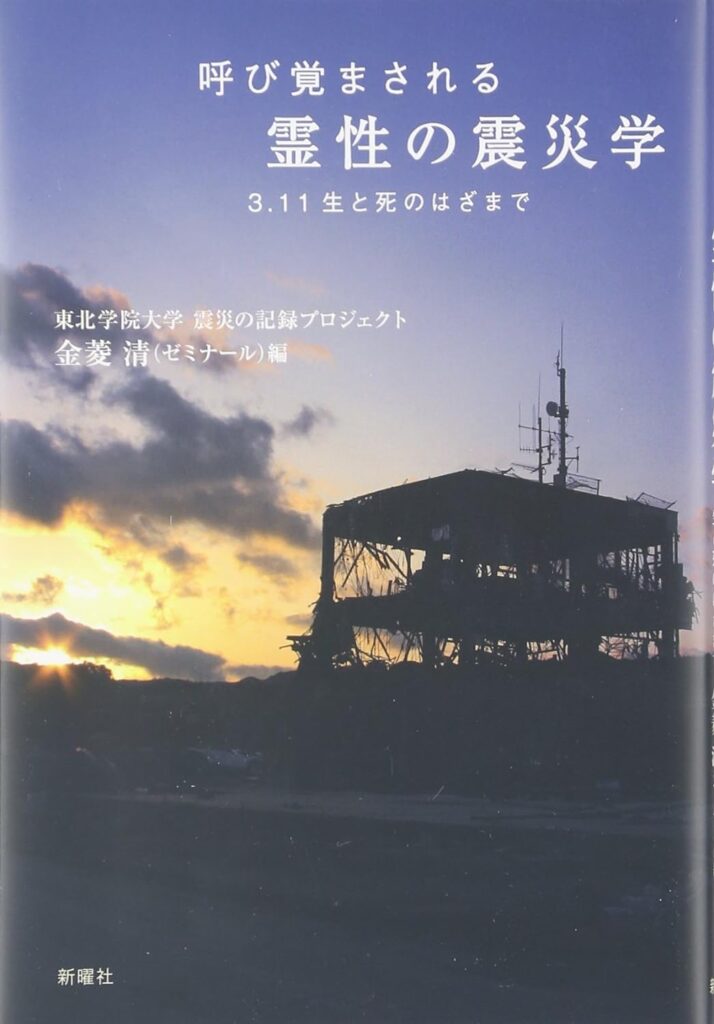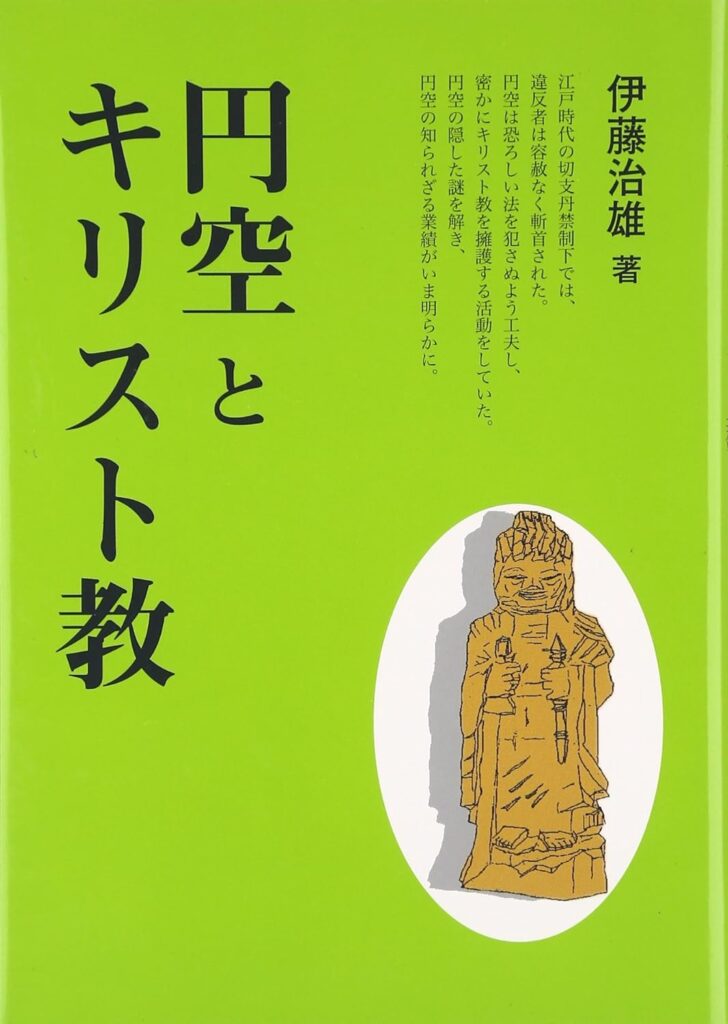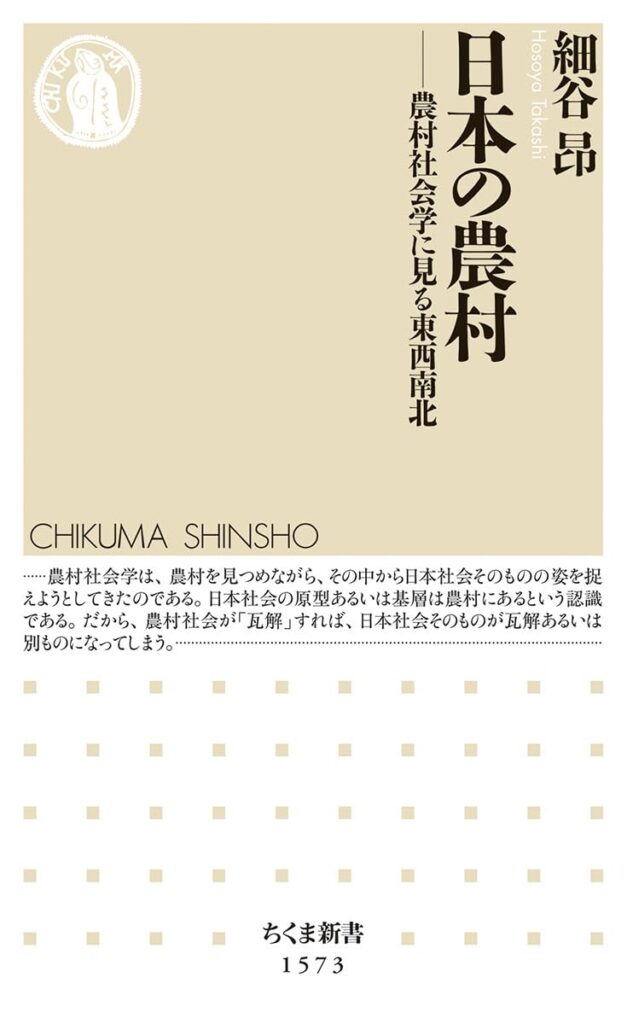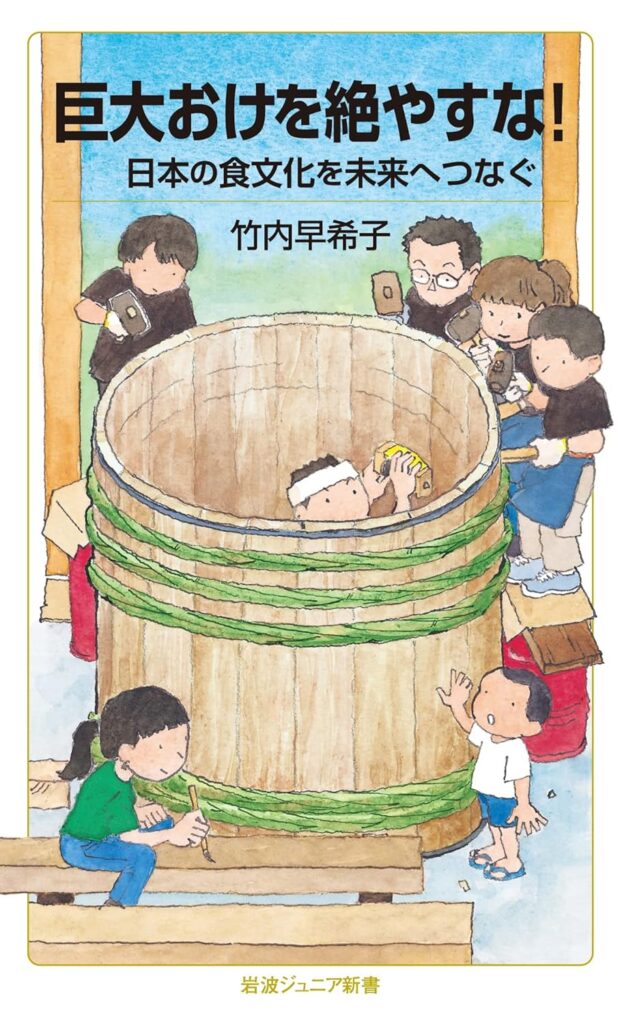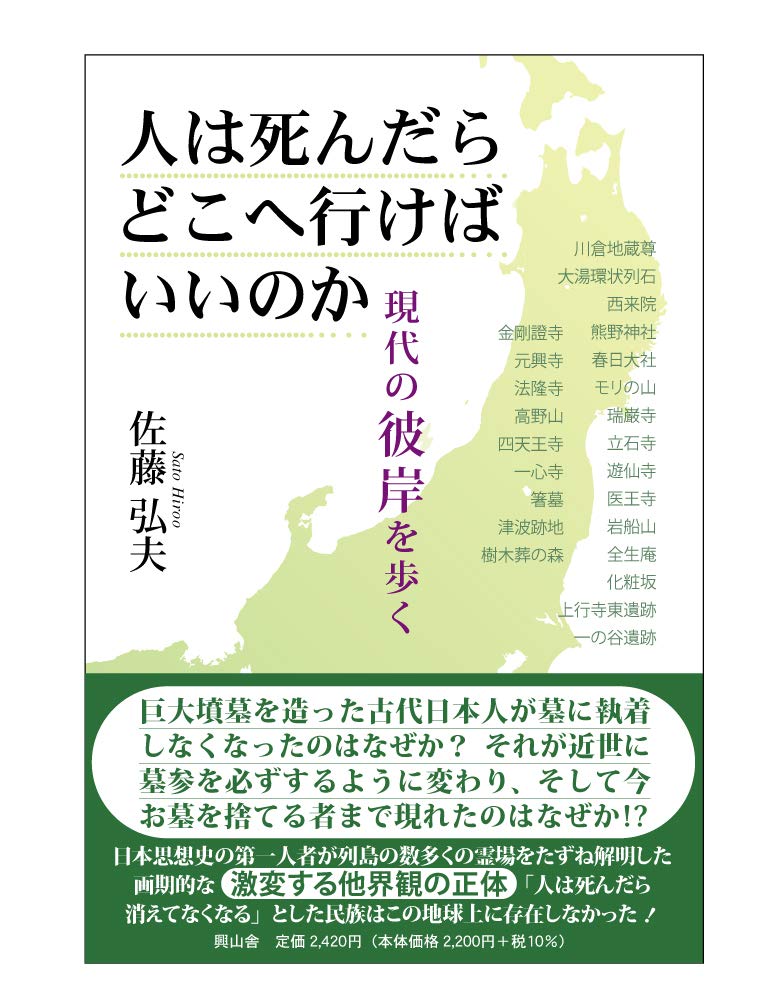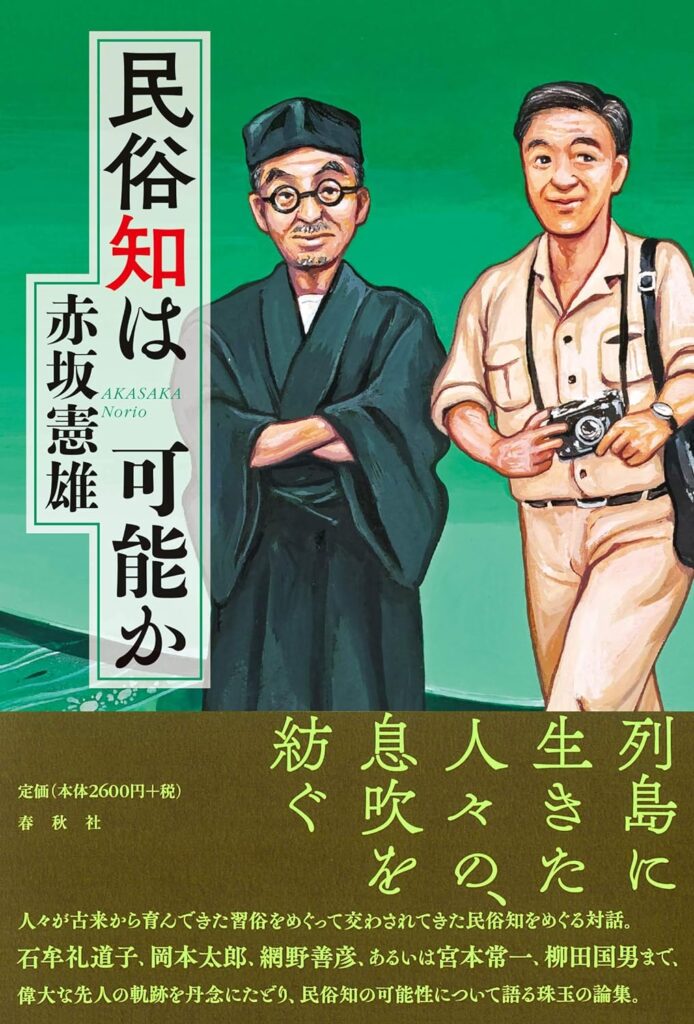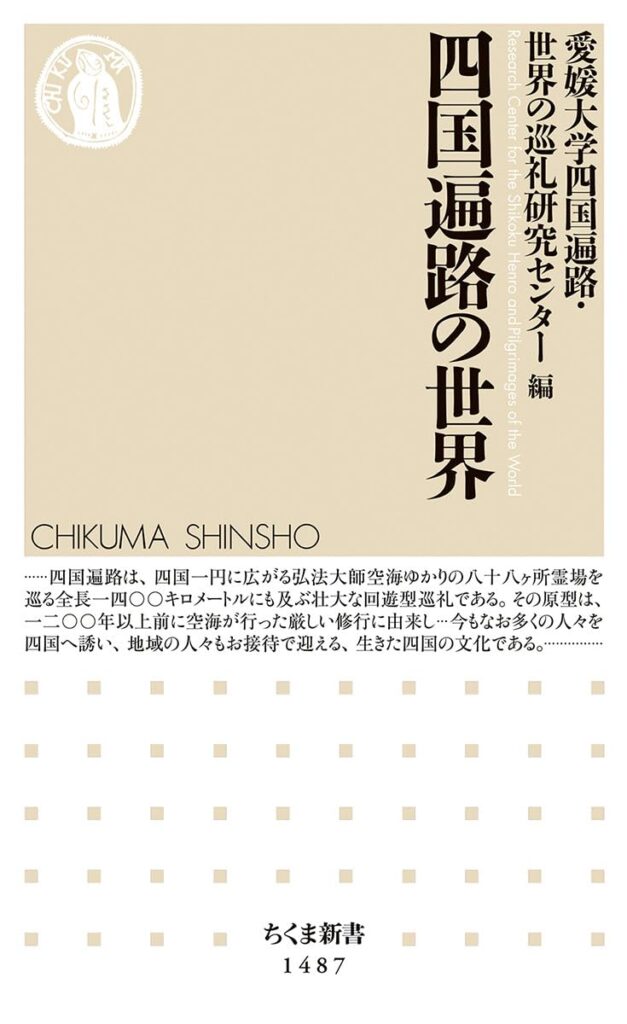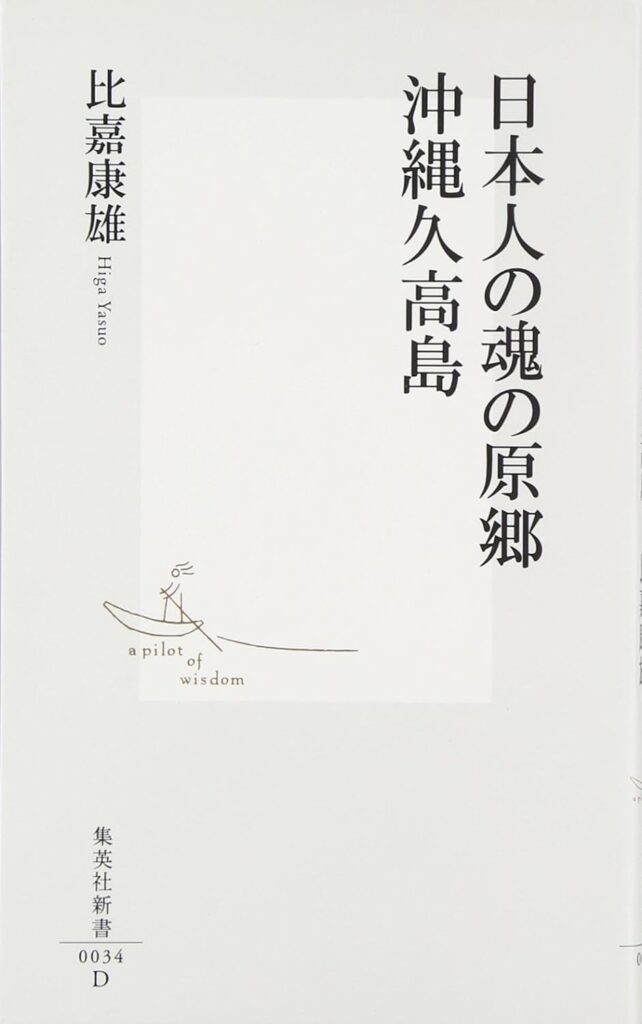04民俗・食– category –
-

能登早春紀行<森崎和江>
■中公文庫250209 海女漁のある村では、女を不浄視して船に乗せないということがほとんどない。女性を不浄視する社会は、死をも穢れとする。森崎は、性も死も切り捨てるのではなく、生命の一部としていつくしもうとした。だから鐘崎の「海女」に興味をおぼ... -

渡辺京二論 隠れた小径を行く<三浦小太郎>
■弦書房250201 渡辺京二の人物論や文学論は、渡辺自身がその人と同調して、なりかわって自分の内側から自分の思想として論じてきた。著者の三浦もまた、渡辺に直接会ったのは数えるほどしかないのに、作品を通じて渡辺になりきって内在的に渡辺の思想を... -

小さきものの近代1<渡辺京一>
■弦書房 241226 これまで読んだ著者の作品とくらべると、微に入り細をうがちすぎてわかりにくい部分があるが、江戸時代に生まれた日本人と、明治以降の教育でそだった日本人とは異民族といえるほど文化や習俗が異なることや、尊皇攘夷や維新の評価などが... -

水の心<大重潤一郎監督>
1991年につくられた27分の短編。もとは宗教団体の依頼で撮影したものだという。 ヒマラヤの氷の峰から生まれる1滴の水がすこしずつ集まり、冷たい渓流となり、大河へとそだつ。インドの川では水を浴びて祈り、バリの棚田でも水の女神にたいして... -

民俗学 ヴァナキュラー編 人と出会い、問いを立てる<加藤幸治>
■武蔵野美術大学出版局240830 欧米には、異文化を研究する民族学博物館と、自国民の文化的多様性や習俗の地域差を研究する民俗博物館がつくられていった。そこでは各文化を個別に展示した。言語や宗教、物質文化、儀礼などの要素のセットで「文化」を展示... -

おらが村のツチノコ騒動記<今井友樹監督>
監督の故郷の岐阜県東白川村は、「ツチノコの村」であり、毎年、ツチノコをさがすイベントが催されてきた。監督も子どものころはツチノコの実在を信じ、捜索イベントに参加した。 ツチノコの村、の存在感は抜群だけど、大人になるにつれてはずかしくな... -

イモと日本人<坪井洋文>
■未来社240825 熊野古道を取材しているとき、旧大塔村に戦後まで「正月に餅をつかない」里があったきいてたずねた。小川という20軒ほどの集落だった。 後醍醐天皇の皇子、大塔宮護良(もりよし)親王の一行が鎌倉幕府に追われ、山伏姿で落ちのびてきた... -

にぎやかな過疎をつくる 農村再生の政策構想<小田切徳美>
■農文協240816 「にぎやかな過疎」は、石川県羽咋市の限界集落の移住者を撮ったテレビ金沢のドキュメンタリーのタイトルからとった。 人口減少は進むが、移住者や地域の人々がワイワイガヤガヤする様子をそう名づけた。今後の地域づくりの目標は「持続的... -

火山と断層から見えた神社のはじまり<蒲池明弘>
■双葉文庫240821 神社のはじまりは、火山とそれが生みだす「石」や温泉であり、旧石器時代までさかのぼるのではないかという着想がおもしろい。 火山活動によって、温泉が生まれ黒曜石や翡翠も生み出された。とりわけもっとも鋭利な石器だった黒曜石は石... -

農山村は消滅しない<小田切徳美>
■岩波新書240731 「限界集落」という言葉や、「増田レポート」が「消滅自治体」をリストアップしたことに違和感を感じてきた。一方、そう簡単にムラはつぶれないと、山下氏や徳野貞夫氏は論じる。筆者は基本的に後者の立場である。 農山村の空洞化は「... -

今日の芸術<岡本太郎>
■光文社文庫240702 岡本太郎は「芸術は爆発だ」のへんなおじさん、あるいはコメディアンだと幼いころは思っていた。 1950年代に書いたこの本を読むと、岡本が芸術のために必死でたたかっていたことがわかる。 家元制度などのかたちで、師匠の模倣... -

村の社会学 日本の伝統的な人づきあいに学ぶ<鳥越皓之>
■ちくま新書 20240627 封建制の地盤のように思われてきた「村」の積極的な意義をわかりやすくときあかす。 東日本大震災で原発事故から逃げてくる避難民のためにみんなで炊き出しをした。その仕事は強制でもなくボランティアでもない村人の「つとめ」... -

限界集落の真実 過疎の村は消えるのか? <山下祐介>
■筑摩新書 20130806 「限界集落」は高齢化によって消滅することになると1990年代初頭に予想したが、高齢化で消えた集落はほぼない。「高齢化→限界→消滅」の事例はほぼゼロ。これまでにも集落消滅はあったが、そのほとんどは、集落が元気で人口も若い... -

谷川雁 永久工作者の言霊<松本輝夫>
■平凡社新書 240613 谷川雁は1960年前後、吉本龍明とならびたつカリスマ的思想家で、「連帯を求めて孤立を恐れず」というフレーズの生みの親であり、「原点」という言葉を普及させた。 筆者は東大の学生時代に筑豊で雁とであった。柳田国男と折口信... -

美の呪力<岡本太郎>
■新潮文庫240607 1970年の連載中のタイトルは「わが世界美術史」。 美術史といいながら、印象派とかバロックとか分類して歴史をたどる本ではない。 最初にとりあげるのが、カナダエスキモーの積み石「イヌシュク」や霊山の石積みなどだ。 石積み... -

季刊民族学165 岡本太郎の民族学
■20240518 「芸術は爆発だ」というヘンなおじさん、というのがぼくらの子どものころの岡本太郎のイメージだった。 戦前にマルセル・モースに師事して民族学をまなび、帰納的で具体的な姻族学と、演繹的で抽象な芸術の双方で創的な世界をつくりあげた天... -

日本の伝統の正体<藤井青銅>
■柏書房20240518 日本の伝統っていうけど、実はこんな程度やで、という本。 商売柄けっこう知っていたはずだけど、知らない「伝統の暴露」もあっておもしろかった。 七五三は、徳川綱吉が、嫡男・徳松の健康を願った祝いをした1681年11... -

古文書返却の旅 戦後史学史の一齣<網野善彦>
■中公新書20240507 東海区水産研究所の一室で1949年、全国の漁村の古文書を蒐集・整理・刊行し、文書館・資料館をつくるという事業がはじまる。研究所の月島分室が担当し、日本常民文化研究所に委託した。 だが1954年度で水産庁は研究所への委託予算を... -

最澄と空海<梅原猛>
■小学館文庫 20240429 ▽仏教の流れ 釈迦の言行録の経典をもとに、500年ほど原始仏教(小乗仏教)がつづき、1世紀から3世紀にかけて龍樹らが革新運動をおこす。 欲望を否定して清い生活をしているだけではなく、大衆のなかにはいれ、と説き、大衆救... -

民博「日本の仮面――芸能と祭りの世界」
民博の「日本の仮面――芸能と祭りの世界」を見に行った。 能や狂言など、さまざまな面がある。それらをただ年代別やカテゴリーで分類してならべるだけでなく、「仮面」の意味をさぐる。民博の展示のおもしろさはそんな「意味」の抽出にある。 縄文時代... -

江戸という幻景<渡辺京二>
■弦書房 20240415 かつて江戸時代は封建的な遅れた体制だと評価されていたのにたいし、最近の江戸ブームでは、江戸時代の近代に通じる部分をとりだして「実は意外に近代的だった」と評する。どちらも近代を基準に過去を評価している。 渡辺は、江戸は、... -

呼び覚まされる霊性の震災学 3.11生と死のはざまで<金菱清編>
■新曜社 20240401 東日本大震災の被災地での学生のフィールドワークをもとにした本。 石巻市や気仙沼市のタクシードライバーに聞き取り調査をすると、幽霊をのせる経験をしている人が少なくなかった。。 石巻市は保守的で、ほとんど相手にしてくれな... -

円空とキリスト教<伊藤治雄>
■ブックショップマイタウン20240410 円空の木像は独特の魅力がある。天台宗の僧で修験道の修行者なのだけど、仏像だけでなく、柿本人麿、両面宿儺、青面金剛などなど、不気味ささえただよわせる神像や彼オリジナルの像もきざんでいる。 「仏僧」の枠に... -

日本の農村 農村社会学に見る東西南北<細谷昂>
■ちくま新書202403 南北朝時代以来つづいてきたとされる「村」が今、消えようとしている。能登半島地震は「村の終わりのはじまり」ではないかと思える。 「村」はそもそもどうやって生まれ、存続してきたのか? そんな疑問をもって本書を手にした。学者... -

巨大おけを絶やすな! 日本の食文化を未来へつなぐ<竹内早希子>
■岩波ジュニア新書 20240112 湯浅の醤油蔵でも、那智勝浦の酢の蔵でも「この木桶が壊れたら、もう新調できない。堺の業者しか残っていない」と聞いていた。 ところが、福島県の郡山の酒蔵で巨大な木桶を新調していた。それが小豆島で習ったという。いつ... -

映画「風の島」<大重潤一郎監督>
■20240115 1983年に沖縄の陶芸家・大嶺實清氏が西表島の沖にある無人島・新城島(パナリ)でつくられていた土器「パナリ焼」を復活させた際の記録映画。 パナリ島はシーカヤックのツアーで訪ねたことがあったが、無人島に古い土器文化があったことなどは... -

人は死んだらどこへ行けばいいのか 現代の彼岸を歩く<佐藤弘夫>
■興山舎20231201 人類の歴史において、死後世界は当然とされてきた。その伝統が壊れつつる。「直葬」がはやり、お盆を先祖との対話の時と考える人は少数派だ。これはおそらく、南北朝以来つづいた日本のムラの衰退と軌を一にしているのではないか。 この... -

民俗知は可能か<赤坂憲雄>
■春秋社 20231119 民俗学には興味があるけど、それが今に生きる知恵としてどういう形で生かせるのか、と疑問に思ってきた。この題名を見たら、買うしかなかった。つい最近亡くなった石牟礼道子から、日本の民俗学の原点である柳田国男まで、さかのぼって... -

四国遍路の世界<愛媛大学四国遍路・世界巡礼研究センター編>
■ちくま新書20231025 遍路道は世界遺産登録をめざしている。私が愛媛にいた2002年ごろからその動きはあったが、「ずっと先の話」と思われてきた。だが最近、外国人の遍路が急増し、世界の注目があつまってきたという。うれしいようなかなしいような……。 ... -

日本人の魂の原郷 沖縄久高島<比嘉康雄>
■集英社新書202310 久高島は、隆起珊瑚礁の小島で最高標高は17.1メートルしかない。畑地には石灰岩が露出し、農耕に適していない。水は、雨水をサンゴ石灰岩が吸収し、岩のあいだからしみでる水をためた井泉(西海岸沿いに9カ所、ほかに2カ所)をつかっ...