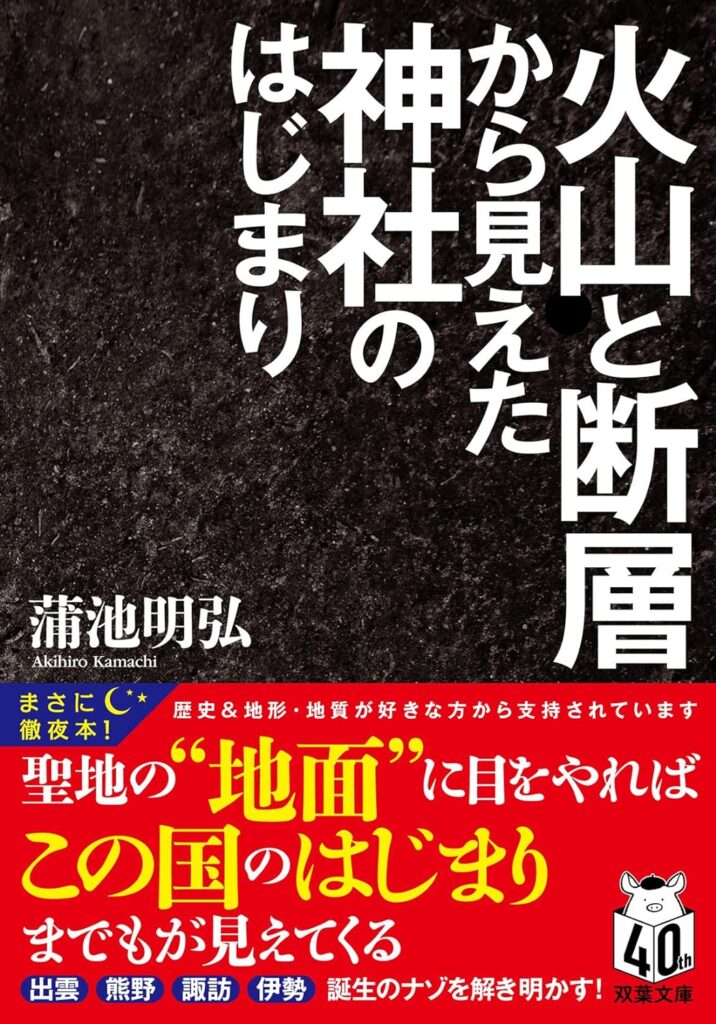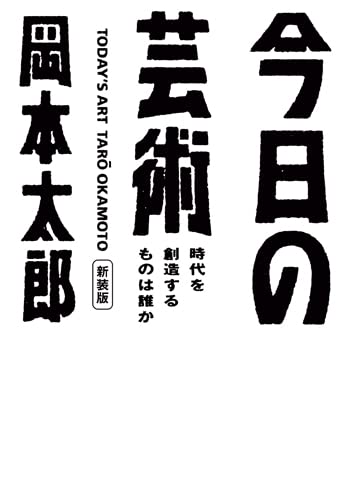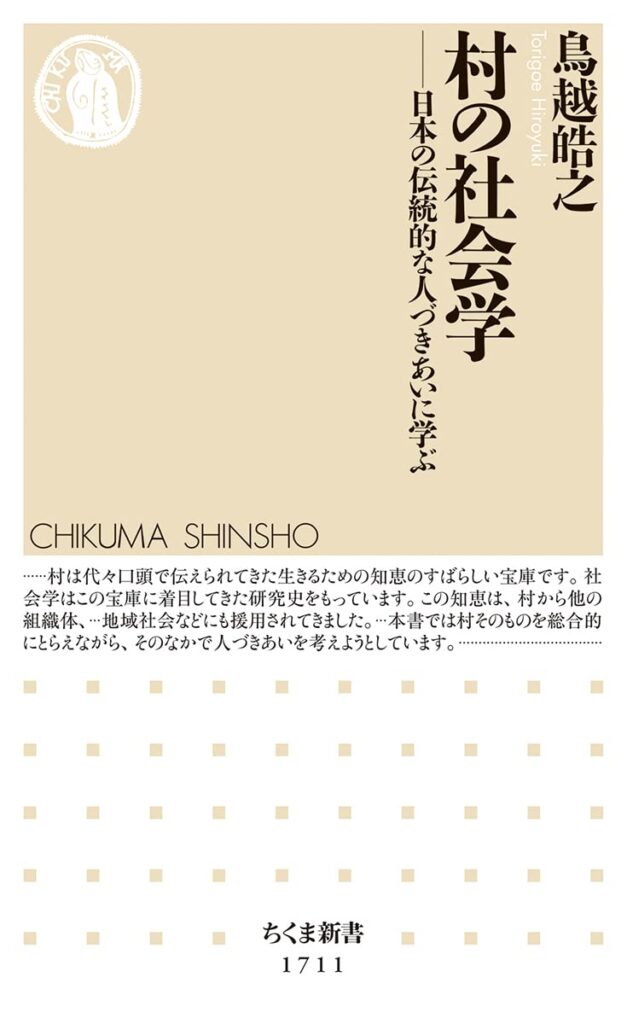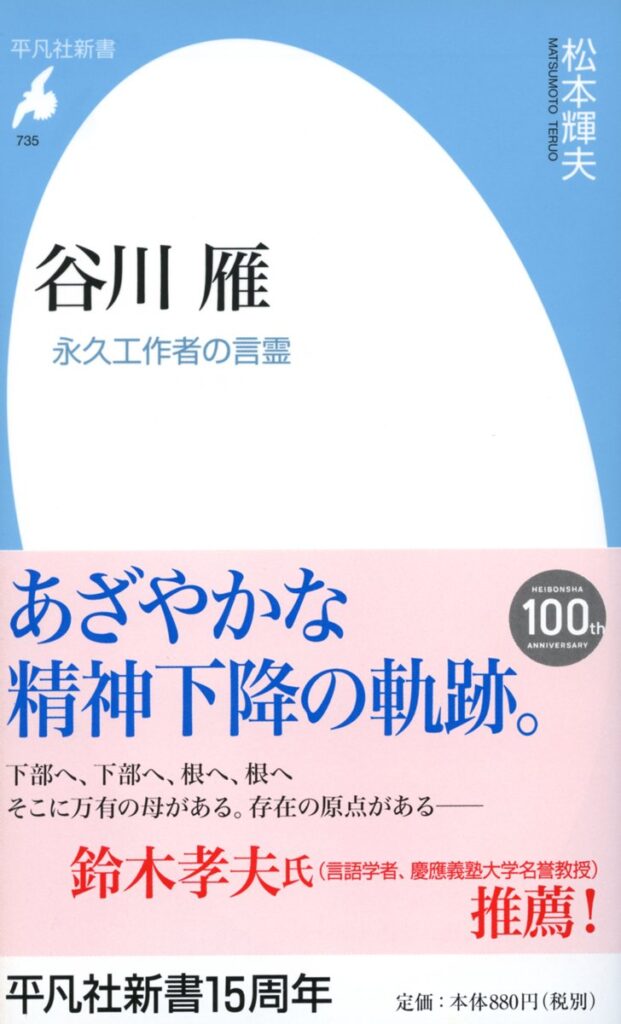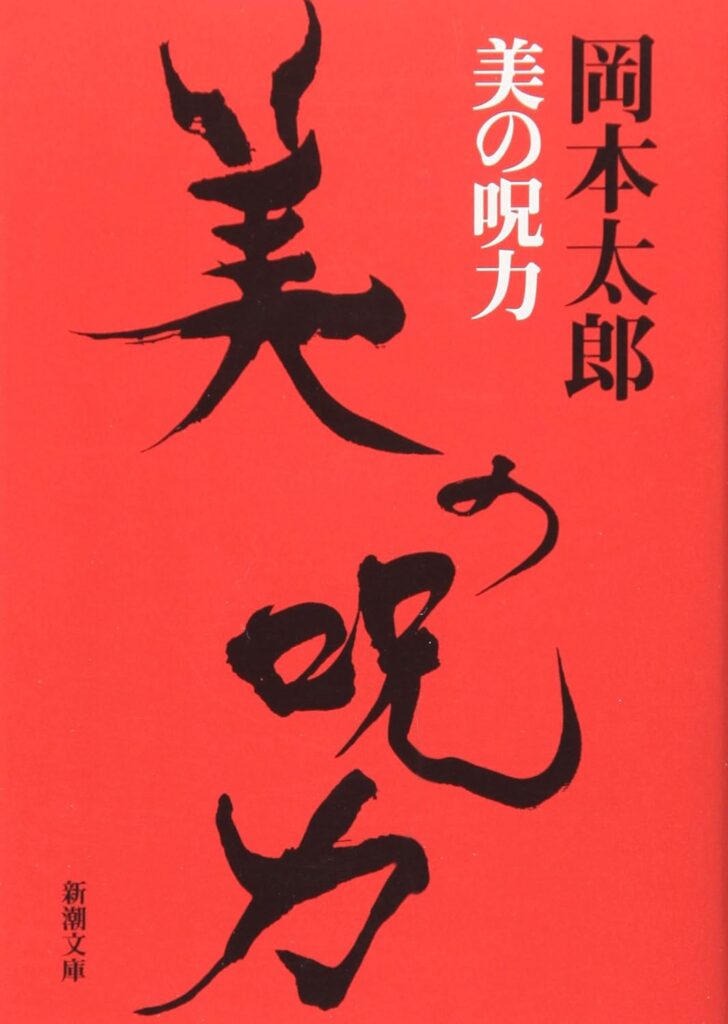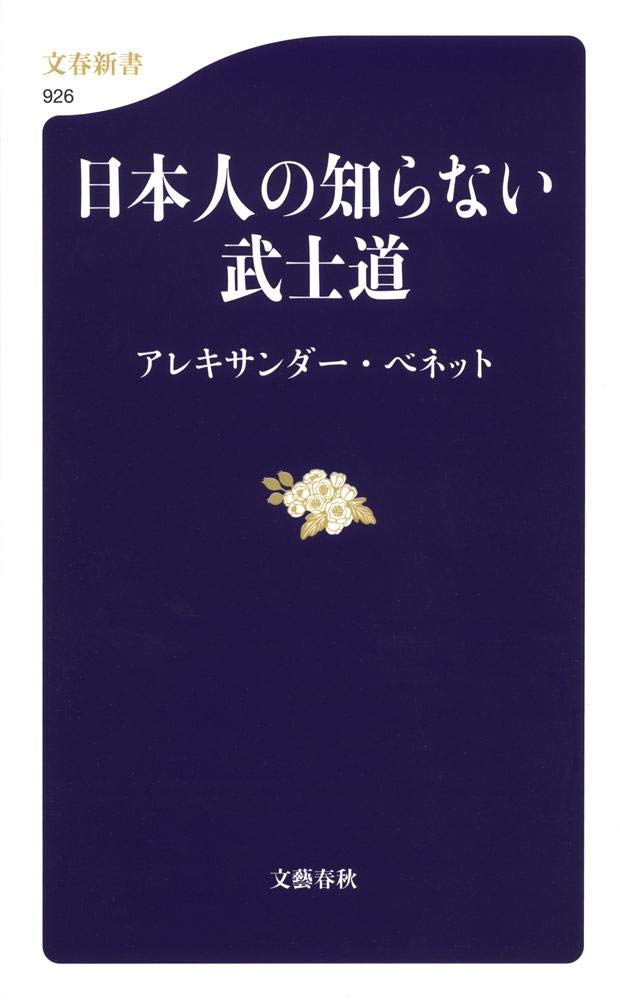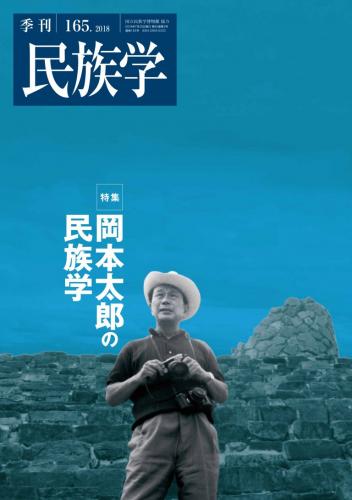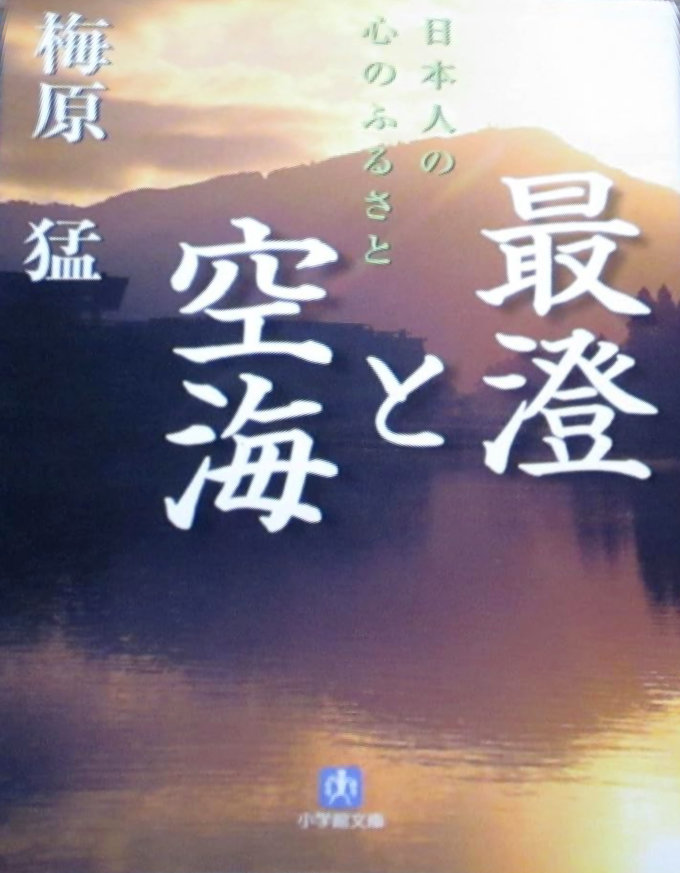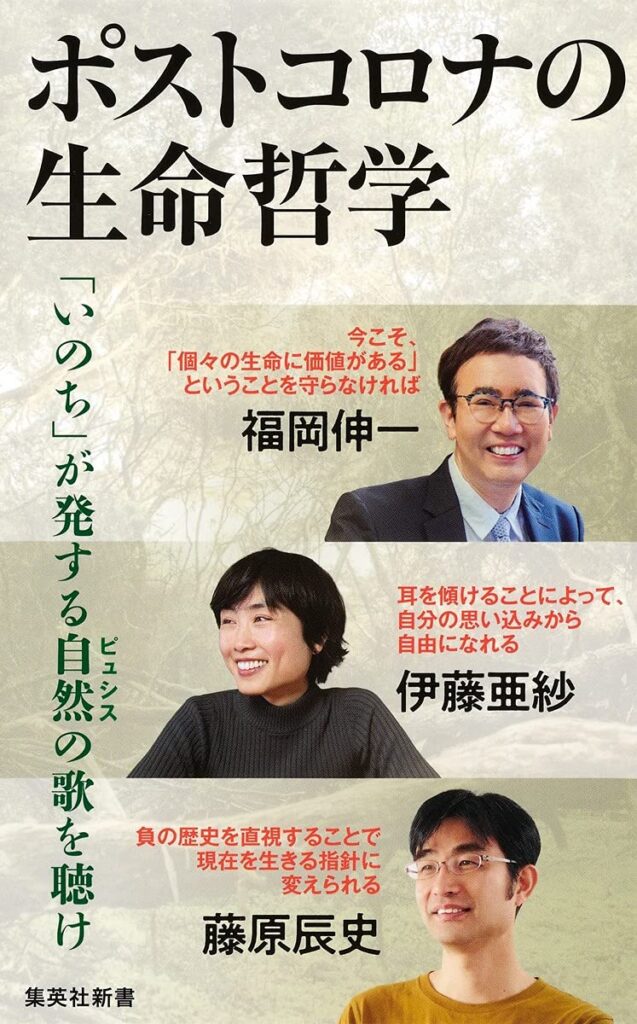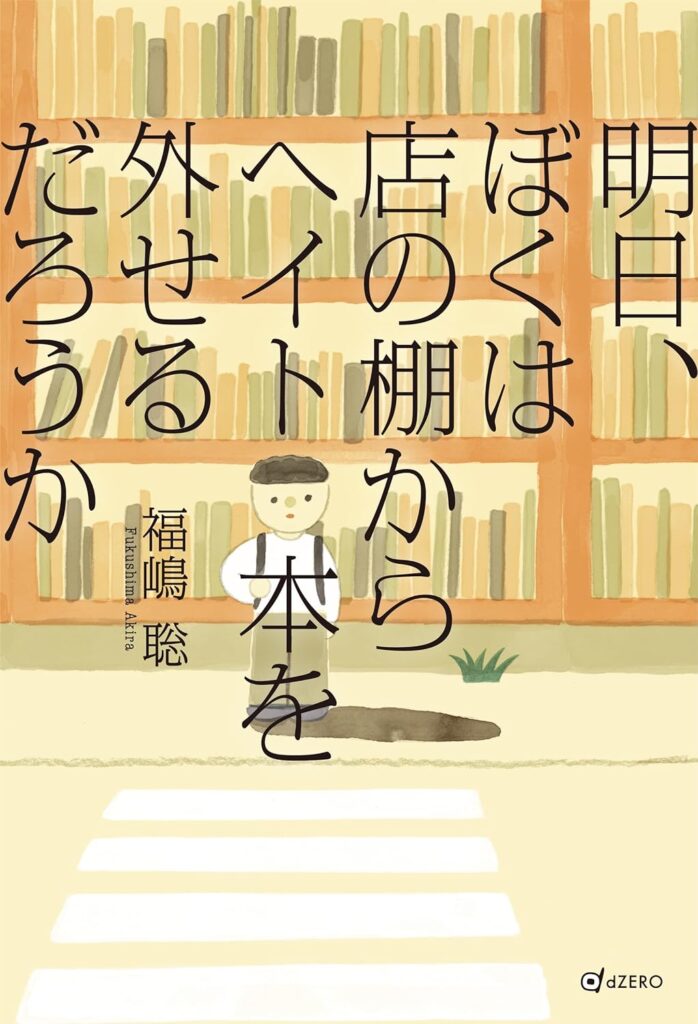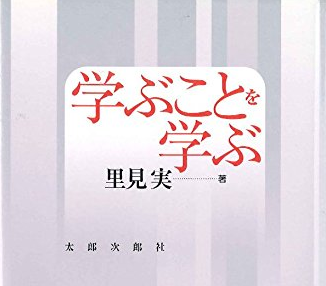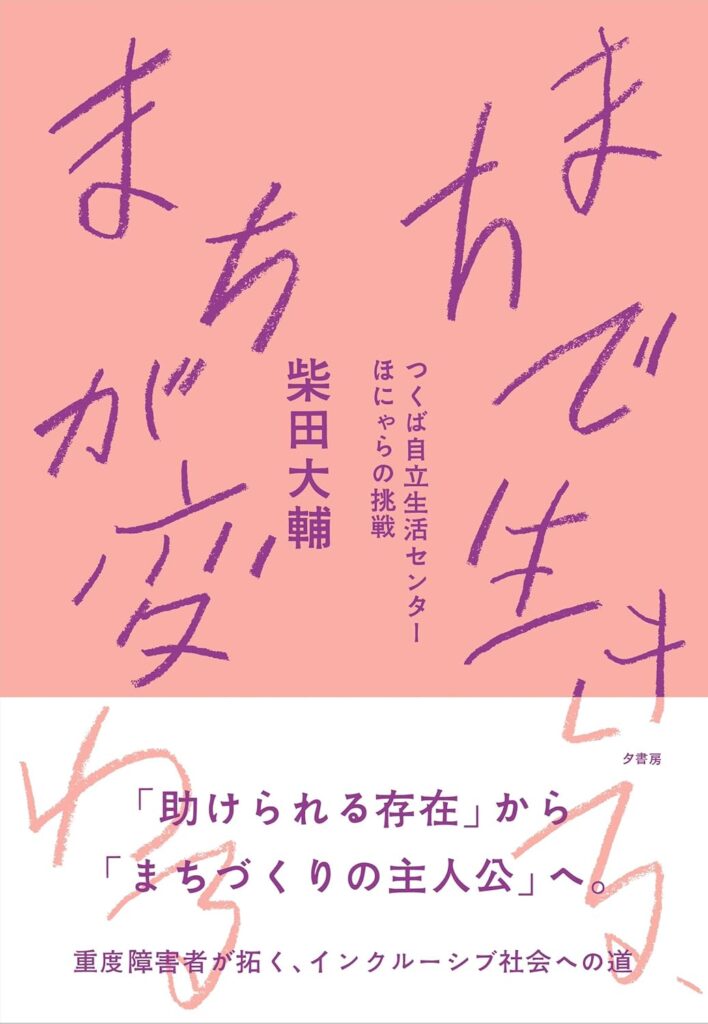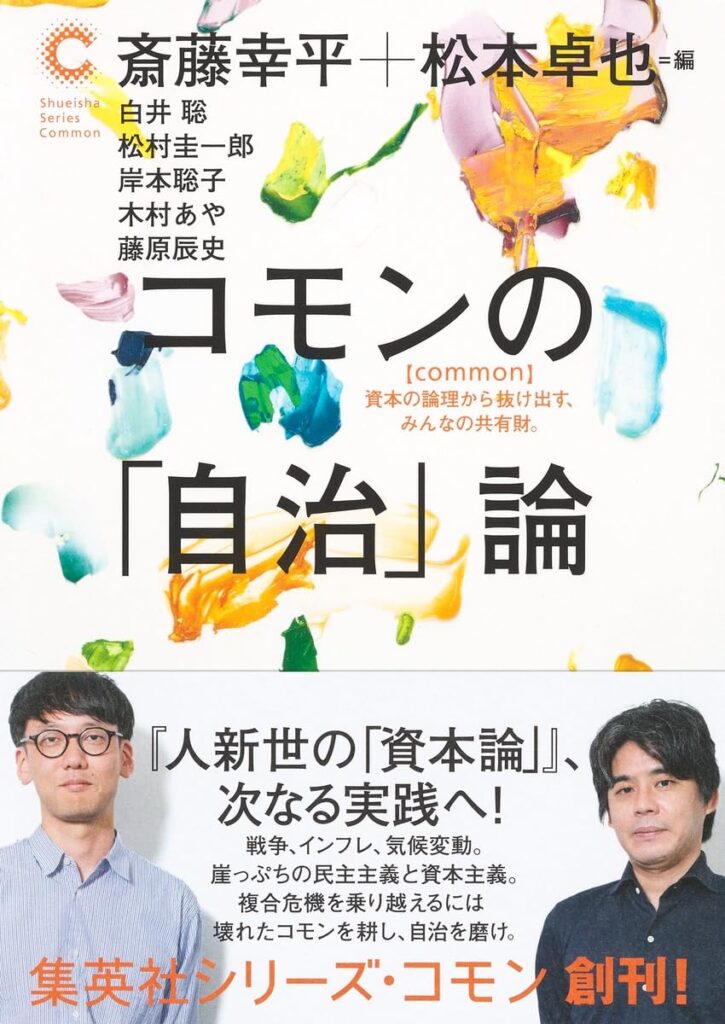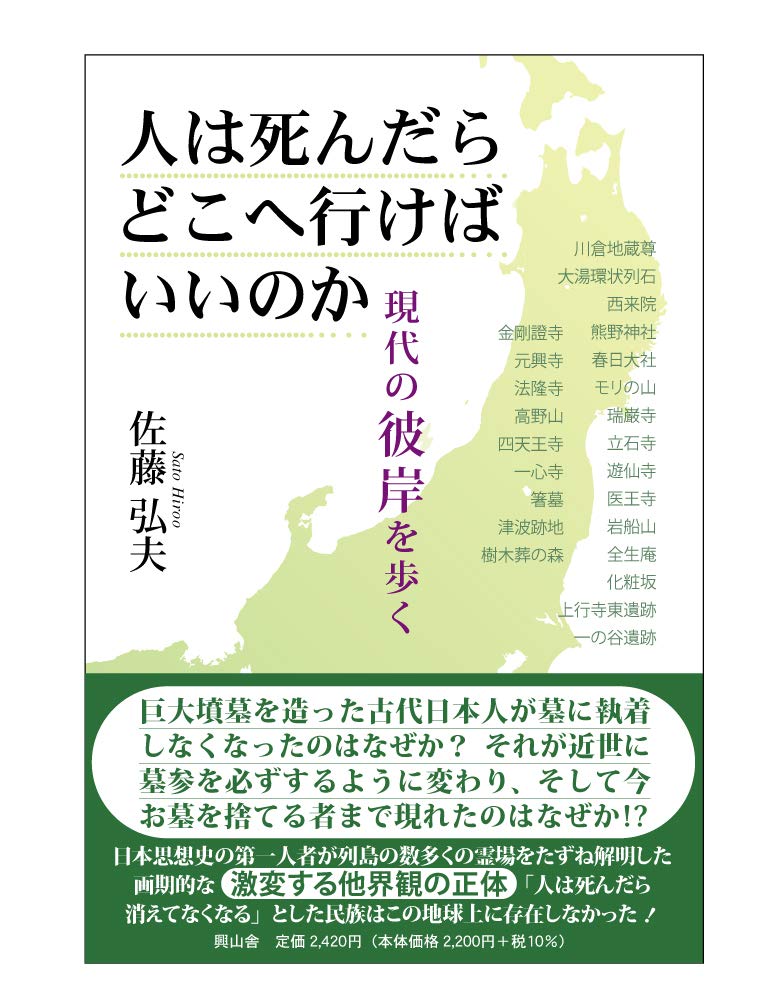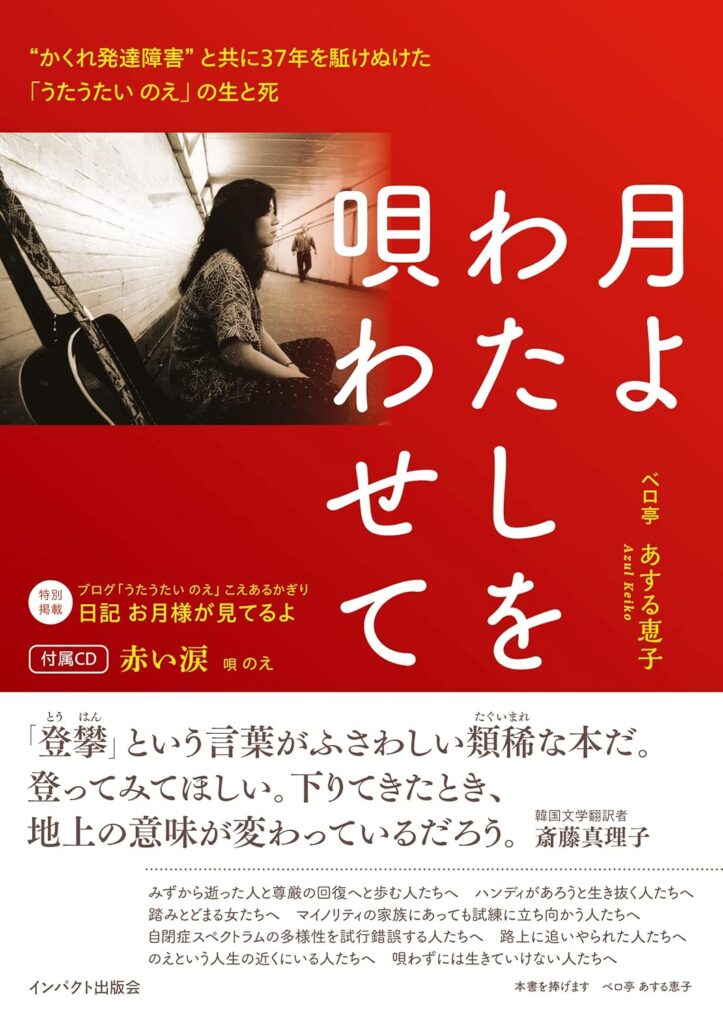01思想・人権・人間論– category –
-

火山と断層から見えた神社のはじまり<蒲池明弘>
■双葉文庫240821 神社のはじまりは、火山とそれが生みだす「石」や温泉であり、旧石器時代までさかのぼるのではないかという着想がおもしろい。 火山活動によって、温泉が生まれ黒曜石や翡翠も生み出された。とりわけもっとも鋭利な石器だった黒曜石は石... -

今日の芸術<岡本太郎>
■光文社文庫240702 岡本太郎は「芸術は爆発だ」のへんなおじさん、あるいはコメディアンだと幼いころは思っていた。 1950年代に書いたこの本を読むと、岡本が芸術のために必死でたたかっていたことがわかる。 家元制度などのかたちで、師匠の模倣... -

村の社会学 日本の伝統的な人づきあいに学ぶ<鳥越皓之>
■ちくま新書 20240627 封建制の地盤のように思われてきた「村」の積極的な意義をわかりやすくときあかす。 東日本大震災で原発事故から逃げてくる避難民のためにみんなで炊き出しをした。その仕事は強制でもなくボランティアでもない村人の「つとめ」... -

谷川雁 永久工作者の言霊<松本輝夫>
■平凡社新書 240613 谷川雁は1960年前後、吉本龍明とならびたつカリスマ的思想家で、「連帯を求めて孤立を恐れず」というフレーズの生みの親であり、「原点」という言葉を普及させた。 筆者は東大の学生時代に筑豊で雁とであった。柳田国男と折口信... -

美の呪力<岡本太郎>
■新潮文庫240607 1970年の連載中のタイトルは「わが世界美術史」。 美術史といいながら、印象派とかバロックとか分類して歴史をたどる本ではない。 最初にとりあげるのが、カナダエスキモーの積み石「イヌシュク」や霊山の石積みなどだ。 石積み... -

日本人の知らない武士道<アレキサンダー・ベネット>
■文藝春秋20240519 著者は剣道・居合・長刀を実践するニュージーランド人の武道家。 新渡戸稲造の「武士道」とは異なり、みずから武道をやっているからこそわかる身体感覚についての記述がおもしろい。 たとえば「残心」。「一本が決まっても、気を抜か... -

季刊民族学165 岡本太郎の民族学
■20240518 「芸術は爆発だ」というヘンなおじさん、というのがぼくらの子どものころの岡本太郎のイメージだった。 戦前にマルセル・モースに師事して民族学をまなび、帰納的で具体的な姻族学と、演繹的で抽象な芸術の双方で創的な世界をつくりあげた天... -

最澄と空海<梅原猛>
■小学館文庫 20240429 ▽仏教の流れ 釈迦の言行録の経典をもとに、500年ほど原始仏教(小乗仏教)がつづき、1世紀から3世紀にかけて龍樹らが革新運動をおこす。 欲望を否定して清い生活をしているだけではなく、大衆のなかにはいれ、と説き、大衆救... -

ポストコロナの生命哲学<福岡伸一・伊藤亜紗・藤原辰史>
■集英社新書 20240419 コロナをめぐってさまざまな悲劇があったけど、人影が消えた大阪の町は広々していて、空が澄んでいて、空気がおいしかった。あのときの不思議な感覚をもう忘れかけている。 コロナの経験から、なにを学べるのか。どんな変化があり... -

明日ぼくは店の棚からヘイト本を外せるだろうか<福嶋聡>
■dZERO 20240401 「ヘイト」をめぐって「うちはヘイト本はおきません」と宣言する書店はある。共感しつつも、それがどれだけの意味があるの? とも思っていた。 ジュンク堂につとめる筆者は、ヘイト本を徹底的に批判しつつも、書店から「はずす」こと... -

学ぶことを学ぶ<里見実>
■太郎次郎社20231226 テーラーシステムとフォード・システムの特徴は、労働過程における「構想と実行の分離」にある。働く者の「構想する」権利を拒むことによって、巨大な生産力を実現してきた。それによって、生き甲斐と自己実現につながっていたはずの... -

まちで生きる、まちが変わる つくば自立生活センターほにゃらの挑戦<柴田大輔>
■夕書房 20240221 たんなる「障害者福祉の本」ではない。自立生活に挑む障害者と、地域住民と、地域社会のダイナミックで感動的な成長物語だ。 かつて重度障害者は「就学免除」という名目で学校に通う権利を奪われていた。養護学校に行けるようになっ... -

コモンの「自治」論<斉藤幸平・松本卓也編>
■集英社 20240124 「人新世」の危機が深まれば、市場は効率的だという新自由主義の楽観的な考えは終わりを告げる。コロナ禍でのロックダウンのように、慢性的な緊急事態に対処するため、大きな政治権力が要請され「戦時経済」が生まれ、政治がトップダウ... -

映画「風の島」<大重潤一郎監督>
■20240115 1983年に沖縄の陶芸家・大嶺實清氏が西表島の沖にある無人島・新城島(パナリ)でつくられていた土器「パナリ焼」を復活させた際の記録映画。 パナリ島はシーカヤックのツアーで訪ねたことがあったが、無人島に古い土器文化があったことなどは... -

人は死んだらどこへ行けばいいのか 現代の彼岸を歩く<佐藤弘夫>
■興山舎20231201 人類の歴史において、死後世界は当然とされてきた。その伝統が壊れつつる。「直葬」がはやり、お盆を先祖との対話の時と考える人は少数派だ。これはおそらく、南北朝以来つづいた日本のムラの衰退と軌を一にしているのではないか。 この... -

火の国の女の日記(上下)<高群逸枝>
■講談社文庫20230924 高群逸枝の自叙伝。途中で亡くなったため、48歳から亡くなる70歳までは夫の橋本憲三が逸枝の日記などをもとにまとめている。「最後の人」の橋本は妻につくした聖人のようだが、この本でははじめ清らかな逸枝を翻弄するエゴイストとし... -

田中正造 21世紀への思想人<小松裕(ひろし)>
■筑摩書房20230816 水俣病の原田正純さん、震災被災地の農業をささえた新潟大の野中教授ら、現場からの発想と行動を徹底した人とおなじにおいがする筆者だ。そして、田中正造こそがその原点であると位置づけているようだ。 正造は伊藤博文とおなじ1841... -

究極日本の聖地<鎌田東二>
■kadokawa20230607 927年の「延喜式」で重要とされた「延喜式内社」2861社は、古代の「聖地」一覧だ。それらをもとに「聖地」とはなにかを考察する。 最初に能登の真脇遺跡がとりあげられていてなつかしい。 真脇遺跡は三方を山に囲まれる母の胎内のよ... -

21世紀の豊かさ 経済を変え、真の民主主義を創るために<中野佳裕・編訳>
■コモンズ 20230524国立民族学博物館の特別展「ラテンアメリカの民衆芸術」で、ラ米の民衆芸術は「多元世界への入口」と結論づけていた。「多元世界」の定義と背景を知りたくて、この本を入手した。 フランスやアルゼンチンの学者がつくった原本「21世紀... -

ひらめきをのがさない! 梅棹忠夫 世界のあるきかた<梅棹忠夫著、小長谷有紀・佐藤吉文編>
■勉誠出版20230501 私が学生時代、梅棹先生は雲の上の人で、2度か3度、講演会などで目にしただけだが、圧倒的な語りに魅了された。 梅棹は「あるきながら、かんがえる」という。彼が世界をどう見て、どのような調査をしていたのか。彼ののこした文章と... -

最後の人 詩人・高群逸枝<石牟礼道子>
■藤原書店202303 高群逸枝と石牟礼道子は出会ってはいない。でも石牟礼は高群を母か姉のように思い、逸枝とその夫の橋本憲三は石牟礼のことを後継者のようにかんじていた。 逸枝が亡くなった2年後の1966年、道子は逸枝と憲三の住まいだった東京・世田谷... -

新版 死を想う われらも終には仏なり<石牟礼道子、伊藤比呂美>
■平凡社新書 20230319 シャーマンのような石牟礼と、娘世代の詩人伊藤の「死」をめぐる対談。 いつも「死」の隣にいて、死のうとする人によりそい、自らも自殺未遂をくりかえした石牟礼だからこそ、伊藤の「死」についての直球の疑問に真正面からこた... -

評伝・石牟礼道子 渚に立つひと<米本浩二>
■新潮文庫20230317 はじめは新聞記者の文章だなぁと思って読みはじめた。ところがしだいに石牟礼道子や渡辺京二が乗り移ったように現実と幻の境をふみこえたり、もどったりする。 正気と狂気、この世とあの世、前近代と近代、陸と海のあいだの渚。 合... -

ドキュメンタリー「ただいま、つなかん」
■20230307 気仙沼市の唐桑半島にある鮪立(しびたち)という漁村はマグロ漁で繁栄し、「唐桑御殿」とよばれる豪勢な屋敷がたちならんだ。そんな豊かな漁村は2011年3月11日の東日本大震災の津波で壊滅する。 主人公の菅野一代さんの唐桑御殿も「全壊」... -

協同の系譜 一楽照雄<佐賀郁朗>2303
■日本農業新聞 農協の中枢にいて政治とも密接なつながりもっていた一楽照雄がなぜ、保守よりも革新に近い、ある意味で農協と敵対する有機農業研究会をたちあげたのか、以前から不思議だった。 この連載は、戦前から「協同組合主義」を体現し、協同組合... -

死は存在しない 最先端量子科学が示す新たな仮説<田坂広志>
■光文社新書230213 最先端の量子論では、過去も現在も未来もゆれうごいていて絶対的な「今」もない。「物」も実在せず「出来事」だけがあるという。「時間は存在しない」(カルロ・ロヴェッリ)にそう書かれていた。だとしたら「死」すらも存在しないので... -

ナチスのキッチン「食べること」の環境史<藤原辰史>
■共和国20230212 日本の公団団地やマンションのダイニングキッチンや「システムキッチン」は、20世紀前半のドイツの合理的キッチンがモデルという。そのキッチンはアウトバーンと同様、ナチスがつくったものだったというストーリーかと思ったらむしろ逆だ... -

時間は存在しない<カルロ・ロヴェッリ、富永星訳>
■NHK出版 時間や空間の大きさは絶対的であるというニュートン力学は、アインシュタインの相対性理論によってくつがえされた、ということは知っていた。では時間とはなにか? 生と死とはなんなのか? 「死後の世界」をどう解き明かすのか? この本... -

三木清 人生論ノート 孤独は知性である<岸見一郎>
■NHK出版230114「人生論ノート」は高校から大学にかけて何度か読んだが、理解しきれなかった。 三木清の出身地、龍野を訪れたのを機に、今度は解説書をよんでみることにした。 三木は結婚翌年の1930年に共産党に資金提供したとして逮捕されて法政大教授... -

月よわたしを唄わせて かくれ発達障害と共に37年を駈けぬけた「うたうたいのえ」の生と死<あする恵子>
■インパクト出版会20230113 ガラスのような感性をもち、37歳であの世にいってしまった「うたうたい」のえさんの足跡を、おなじ感性をもった18歳年上の母がたどったストーリー。 ガラスのような感性が全編にはりつめていて、緊張を解けないのだけど、なぜ...