■兼農サラリーマンの力<古屋富雄>栄光出版社 201308
==============
会社に勤めながら農業を兼業するライフスタイルを「兼農サラリーマン」と位置づける。サラリーマンをしながら農業ができるよう、農地を簡単に借りられて販売できる態勢をつくる。
神奈川県南足柄市の農業委員会でつくったこうした仕組みを紹介する。
▽34 ドイツのクラインガルテンや旧ソ連のダーチャがモデルになっている。クラインガルテンから生産される農産物は、市場の3、4割を占めるほどに都市部では定着している。
利用者が集まるクラブハウスは共同で建設し、個人が利用するラウベ(キッチンや休憩がっできる約25平方メートルの小屋)は個人が建てる。
▽38 ドイツ 州単位の農業大学校。2年間教育を受け、マイスターを取得した農家には最高4000万円超の補助金が支給される。
▽69 南足柄市の農業委員会では、平成19年4月「南足柄市基本構想」を作成、20年10月、「南足柄市新規就農基準」を施行。21年9月「市民農業者制度」を施行。
これを参考に大阪府が平成23年7月に「準農家制度」を導入。農業生産に意欲のある市民に3−30アール程度の農地を貸し出す制度。
鯖江市でも。
▽89 「農業マイスター」に絞った直接支払いを実施するには、農業関係者の理解が必要。国民の支持も受けなければならない。ドイツでは「クラインガルテン」により、市民の農業への理解を得る環境をつくった。わが国でも南足柄市の農業参入システムにより、同様の環境づくりができるのでは。
農業関係者以外の理解者を増やすこと。そのパイオニアが「兼農サラリーマン」
▽95 1949年に制定されたイギリスのパブリックフットパス。歩行者に通行権が保障されている小径で、「歩くことを楽しむ道」。農場や牧場などの作業路を公共の散歩道として認めている。その長さは全土で17万キロ。イギリスでは、農地そのものを国民の共有財産だという理念にもとづき、農村空間そのものを共有化した。
パブリックフットパスが全国に広がり、グリーンツーリズムが新たな農村のビジネスとして発展した。今ではグリーンツーリズムによる収入が農家の年間収入の3割をしめるほどになっている。
▽107 条件不利地では、野菜類や果物類の栽培はせず、農作物の力に任せる農法を実践する「有機農業」が適している。木々類と山菜類を組み合わせ、農地を立体的に活用。木々類は、八重桜やタラノキ、山菜類はフキ、ワラビ、ウドなど。
▽139 兼業農家の新たなライフスタイルを提案。農業の継承を定年後と家族間で決めておいて継承させるビジョン。定年後の安定した経済基盤を、年金などで準備できるサラリーマン生活を送り、定年後に向けた農業技術の習得や地域コミュニティとのかかわり方などを、積極的に学ぶ姿勢が醸成される。「定年チェンジ・ファーマー」は、単に定年後に農業をするという就農形態とはちがい、親から子へ、子から孫へと継承される就農形態。
▽154 「食料自給率は、食べものを祖末にしない意識によって消費量が減れば高まる。さらに農業以外の人が農業参入して生産量が増えた場合もアップする」消費の面から食料自給率が向上できる。そのためには、誰もが農業に参入できる仕組みの推進を。農家以外の市民に「農と食」の理解を深める施策を法制化するべき。
▽158 農地法での農地の貸し借りは、親類縁者以外には事例はほとんどない。いったん農地を貸してしまったら、借りた側に権利が移動してしまうという先入観。93年に制定された農業経営基盤強化促進法では、貸し借りの契約が市町村が契約当事者であるため、借受ける側への権利移動は発生しない。=権利移動のない農地の貸し借り。
南足柄市は、まず、平成20年10月に、農家になるための仕組みとして「南足柄市新規就農基準」をもうけ、その補完的な担い手として「市民農業者制度」を21年9月に策定。
▽186 国民に開かれた農業参入の仕組みを法制化するべき。専業的に農業をする経営体には、対象を絞った直接支払い制度を。一方で、国土全体の農地の維持保全の必要性からは、小規模でも農業に参入したいと望む農家以外の農業参入者を受け入れる施策を。その結果、ドイツのクラインガルテンやロシアのダーチャの事例が示すように、国民全員で農業への理解や食料の大切さを共有する環境が構築できる。南足柄市の「南足柄市新規就農基準、市民農業者制度」や大阪府の「準農家制度」などを全国的に展開すべき。
「農地の社会化」によって農への理解を広める。




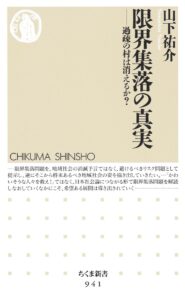
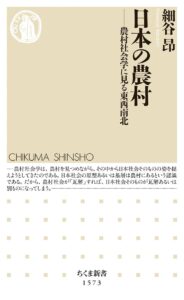


コメント