ファンタジー中心の今までの宮崎アニメにはない作品だ。
零戦を設計した堀越二郎が主人公。1歳ちがいの堀辰雄の小説「風立ちぬ」のストーリーを取り入れて、悲恋のストーリーを物語のもうひとつの柱に据えた。
少年のころから空に憧れた二郎は、東京帝大に入り、関東大震災で少女を助ける。何年かあと、軽井沢で、絵を描いているその少女・菜穂子に偶然再会し婚約する。菜穂子は結核を病んでいた。
飛行機の技術者である二郎は、当時の最先端である戦闘機の設計を担当する。非力な国産エンジンをつかって機動力のある飛行機をつくるには、極端まで軽量化するしかない。素材を徹底して見直すとともに、最先端の技術と、美しいフォルムを追求して空気抵抗を減らした。
サナトリウムにいた菜穂子は、二郎のいる名古屋に出てくる。残された時間を2人で過ごすためだった。上司の黒川に仲人をたのんで結婚する。いつも帰宅が遅い二郎だが、1日1日をいとおしむように2人ですごす。二郎に気を使わせないため、菜穂子は頬紅をつけ化粧して元気を粧った。
当時としては究極の戦闘機をつくりあげ、試験飛行のために二郎が家を開けたとき、菜穂子は置き手紙を残してサナトリウムに帰っていく。自らの一番美しい姿を二郎に見せて、ともにすごし、去っていった。
まさに堀辰雄の「風立ちぬ」の「節子」だ。宮崎アニメ独特の性格づけをされた菜穂子は、たんに美しいだけではない、はかないようだけど芯が強い、未来少年コナンのラナのような存在感になっている。
美しい戦闘機をつくる、という技術屋の物語だけではなく、堀辰雄の世界を組み合わせることで、奥行きと透明感を与えている。トーマス・マンの「魔の山」の主人公であるハンス・カストロフと同じ名をもつ老紳士も軽井沢のホテルに登場する。彼は、軽井沢を外の世界と切り離された世界と見て、そこでは、中国の戦争も満州のことも日本の将来の破滅も忘れられていると説く。
そういえば「魔の山」も、戦に明け暮れるドイツで、そこだけが時間がとまったようなサナトリウムの日々を描いていた。もう一度、読みたくなった。
この作品を「戦争賛美」という人がいるらしい。「喫煙シーンが多すぎる」という批判もあるという。
戦闘機を描くことが「戦争賛美」ならば、現実を扱わないメルヘンしか子どもにはみせられないことになる。この作品の文脈を見れば「戦争賛美」ではないことはわかる。また、当時の男たちの喫煙率は8割か9割だったのだから、喫煙シーンがなければ嘘になってしまう。
戦艦や戦闘機の模型はとても魅力的だが、実際に使われてしまうときのことまでは想像できない。だからといって、戦艦の模型を規制をすればすむものではない。
美しい飛行機をつくりたいという夢が、戦争につながってしまう社会のあり方の悲しさを描いている、と思った。
ただ、このアニメは子どもに理解できるとは思えない。結核という病気、サナトリウムという場の意味、飛行機の細かな技術などなど、大人が見るととてもおもしろいのだけど、子ども向けとはいかなさそうだ。
目次






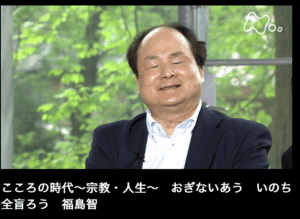

コメント