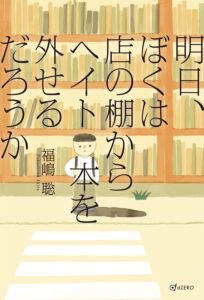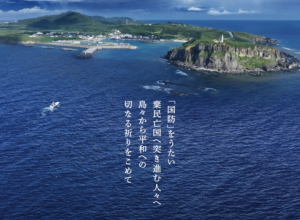|
毎日新聞社 20060408 「9条」というと、護憲と改憲という二分法的な論じ方ばかりだが、こんな論じ方もあるのかあ、と新鮮だった。とくにオダジマンの論は目から鱗だった。 |
![]()
□内田
▽「日本は陸海空軍を有し、自衛のため、国連安保理事会の議決に従って、武力を行使することができる」と変えたい改憲派の意図はどう考えても「戦争ができるようになりたい」のほかに解釈のしようがない。9条をそのように改訂するということは、「戦争をしてもよい条件」を実定的に定めるということだ。どれほど合理的で厳密な規定であろうとも、戦争をするためにクリアすべき条件を定めた法律は「戦争をしないための法律」ではなく、「戦争をするための法律」である。例えば刑法199条は「殺人罪」について、「人を殺してもよい条件」は規定していない。改憲派のロジックは「自衛のためまたは公共の福祉に適する場合を除き」という限定条件を刑法199条に書き加えろと言っているのに似ている。
▽人を殺さなければならない場合がある」というのは現実である。「人を殺してはならない」というのは理念である。どこの相剋する現実と理念を同時にひきうけ、同時に生きなければならない。どちらかに片づければすっきりすると政治家は言う。だが、「すっきりすること」というのはそんなに重要なことだろうか。
▽自衛隊はその原理において「戦争ができない軍隊」である。その存在に国民があまり反対しないのは、憲法9条の重しがあるからである。9条という封印が自衛隊に「武の正統性」を保証しているからである。
▽現実には9条を廃止しても軍事をめぐる事情は今と少しもかわらない。依然として自衛隊の軍事行動は一から10まで米軍の許諾を得てしか行われない。アメリカは9条廃止を黙認するだろうが、それと引き替えに、国防予算増額と、その過半をアメリカ製の高額な兵器の定期的かつ大量の購入に充当することを要求するだろう。……「普通の国」になったとたん、アメリカの「従属国」であるという否定しがたい事実に直面するだけの心理的成熟を日本人は果たしているといえるか。
□町山智浩
▽ドイツ憲法は、世界でも最も改憲に対して厳しい憲法なのだ。79条3項に「憲法第一条および二〇条に定められている諸原則に抵触する憲法の改正は許されない」。大学や学校で憲法を批判する自由すら認めていない。
▽中曽根試案「我ら日本国民は……独自の文化と固有の民族生活を形成し発展してきた」読売の改正案も「日本国民は、民族の長い歴史と伝統を受け継ぎ……」。「民族」と「国民」のちがいもわかっていない。これらの試案が実現したら、世界はもはや日本を「国民国家」として認識しないだろう。イスラエルですら「すべての国民に、民族・信条・性別の分け隔てなく社会における平等と良心・礼拝・教育・文化の自由を保障する」
□小田嶋
▽9条に限らず、憲法の条文は、いずれも「理想であって現実でない」話ばかりだ。25条も空文。納税や教育だって無視してる人はいる。表現の自由なんてモロに絵に描いたモチだ。……それでもそうした理想は高く掲げられなければならない。
▽「日本人には、国のために死ぬ覚悟があるんだろうか」 君たちの言う「国」というのは何を指してるだ。国土、国民、あるいは国家体制か? 国体か? 私の死がどういうふうに私の国のためになるんだ? 国のため、というときの「ため」は実質的にどういうことなんだ? 防衛?それとも版図の拡大?経済繁栄?
「公」の思想? 「公」という字をよくみてごらん。ハムというのは死んだ肉で出来ているんだぜ。