戦後なくなった「道徳」という科目が正規の科目として復活した。
「おはようございます!」とあいさつするとき、
①あいさつの前に頭を下げる
②あいさつしながら頭を下げる
③あいさつをしてから頭を下げる
どれが正解でしょう?
こんな珍妙な「道徳」を大まじめに教える。
教育を通して日本に誇りをもつ子を育てる……と安倍晋三がこれまた大まじめに語る。自分の仲間だけをひいきして、都合の悪いことはごまかして、公的資料まで改竄させる。美しい国の誇りある国民ってそういう人のことを言うのかな。悪い冗談にしか思えない。
「新しい歴史教科書をつくる会」が結成され、従軍慰安婦など、加害の事実を教科書に記すことを「自虐史観」と呼び、右派政治家が跋扈して「従軍慰安婦」「強制連行」という言葉そのものが教科書から消えていく。
「日本書籍」の教科書は東京で最大のシェアだったが、「慰安婦」を書きつづけたことで不採択となり倒産した。
日本書籍の倒産をきっかけに、ほかの教科書会社も加害の歴史を取りあげにくくなった。
そんななか、「学び舎」が、歴史問題も正面からとりあげる教科書をつくり、私立進学校などで採用された。採択した学校には、匿名で同じ文面の抗議はがきが送りつけられた。日本会議系の政治家らが関与していた。
大阪の中学で加害問題も教えていた女性教諭は、その授業内容が報じられるといっせいに学校に抗議が殺到し、維新の松井市長や吉村知事は「偏っている」と圧力をかけた。学校からは「これからは慰安婦問題は扱わない、と約束してくれ」と言われた。講師は拒否した。結果的には「授業内容は問題がなかった」とされたが、「校長の許可なく校内で取材を受けたこと」を理由に訓告処分となった。
杉田水脈は、科研費を使って慰安婦問題を研究する阪大教授を攻撃し、炎上を引き起こした。
戦後制定された教育基本法では、教育の政治からの独立をさだめたが、第一次安倍内閣による法改正によって、首長や政治家からの圧力を「民意」として正当化した。
教科書は、政府見解を反映するべきだとされ、「従軍慰安婦」という言葉は「慰安婦」に書き換えられ、「強制連行」は「動員」に書き換えられた。
教育の右傾化は、大ざっぱには知っていたけど、ひとつひとつの右傾化が、歴史のなかでどう位置づけられるのかは理解していなかった。1990年代からの変化を、声高な主張ではなく具体的な事実で描いている。
戦前、当初の朝日新聞は反戦を掲げたが、在郷軍人会を中心に不買運動を展開し、部数が激減したことが転向の最大のきっかけになった。権力からの弾圧よりも民意による不買運動が大きかった。
日本書籍の倒産、政治の教育への介入、それを「民意」と支持する世論……それによって冒頭のような荒唐無稽なことが教育現場でひきおこされる。
現実はすでにホラー映画に近づいている。そのことを浮き彫りにするドキュメンタリーだ。
目次






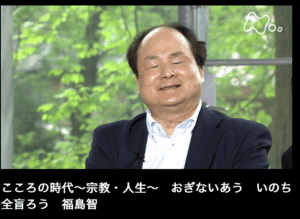

コメント