■環境リスク学 不安の海の羅針盤 <中西準子>日本評論社 20110425
下水道で工場排水を処理するのが当たり前といわれていた時代に、浄化効果がないことを実証してやめさせた。大規模な流域下水道が効率的とされていた時代に、配管が長くなるからむしろ効率が悪いと指摘。田舎では個人下水道がよいと提案して合併浄化槽を実現させた。そうした行動は主流を批判するものだったから、学会からも行政からも干された。
90年代にダイオキシン問題が起きたとき、母乳は危ない、とか、近海魚は危ない、といった論がはびこり、だったら粉ミルクや肉ならよいのか? と疑問に思った。筆者はそれを「リスク論」で数値化して説明してくれる。
母乳を飲むリスクと母乳をやめるリスク、近海魚を食べるリスクと肉を食べ過ぎるリスク……を比べて、どちらが平均余命を縮めるか比較する。
さらに、土壌中のダイオキシンの発生状況を調べると、近年はどんどん量が減っており、現在あるダイオキシンの大部分が農薬が原因であることがわかった。たしかに焼却炉からのダイオキシンは微増しているが、農薬由来のものに比べればわずかなものだった。大規模な焼却炉やRDF発電などに巨額のカネを使うよりも、そのカネをほかのリスクを減らすために使った方がよいことがわかったという。
ダイオキシンやがん、水銀、喫煙……といったさまざまなリスクを「余命をどれだけ縮めるか」という一つの尺度で比べることで、どこにどれだけの予算をかけるのが効率的か、政策の優先順位が見えてくる。
その視点から見ると、健康へのリスクが最も大きいのは喫煙で2番目が地中のラドンで、ダイオキシンや環境ホルモンなどのリスクははるかに小さいという。
「リスク論」は1960年代にアメリカで生まれた。それまでは「○○グラムまでは安全」という線引きをしていたが、たとえば放射線は、わずかな被曝でも健康に影響があるから「この線までは安全」という線は引けない。そこで、どの程度の線量を浴びたらどの程度の発がんリスクがあるか計測し、ほかのリスクと比較し、そのリスクを減らすためにどれだけの予算が必要かを比べることで、許容量の線を決める。また、DDTのような薬品を使うことによるリスクと、その使用をやめることによる病気発生のリスクを比較する……という手法が確立されていった。
なるほどなあ、と思った。
ただ、筆者は、現代の技術を考えたら原発はもう少し推進してもよい、とか、遺伝子組み換えも全否定するべきではない、とも主張している。その部分は私は賛成しかねる。私が必要以上に不安を感じているのか、筆者が何らかのリスクを見落としているのか……。
==============================
▽12 下水処理場問題で村八分に。学会に行くのにも旅費が出ない。学生や院生を差別する
▽18 工場排水を下水処理場に入れるなという住民運動。当時、国は、工場排水を下水処理場で処理する方針だった。それが頓挫した。当時は自民から共産まで、企業に任せてもだめだから、自治体や国が責任をとるほうがいいと考えていた。
▽20 流域下水道も規模が大きいから経済的といわれていたが、渡しは、下水道では規模が大きいほど長い管きょが必要になるので、不経済になることを徹底的に証明した。
▽ 合併処理浄化槽も、当初は建設省はせせら笑った。当時は個人下水道という処理装置はこの世になかった。1982年に駒ヶ根に提案。85年には認可された。
▽40 異種のリスクを比較するため「損失余命」という尺度を採用。
▽45 政策の効率。政策によってどのぐらいリスクが削減され、そのためにどのぐらいの費用がかかったか計算。
▽47 環境のリスクに、種の絶滅リスク。
▽56 ダイオキシン対策としてのごみ処理の広域化、巨大化は疑問。小規模でもダイオキシン対策は可能。……ダイオキシンでガンになる、などと言われていたから驚かれた。旧厚生省は、ダイオキシンの85%が生活系のごみ焼却炉から排出されていると発表したが、実際はかつての農薬散布のほうが大きかった。
▽63 私たちの体のダイオキシンのかなりの部分は農薬起源だと99年に発表。三井化学の担当者「告訴する」と息巻き、ダイオキシンは危ない、と大騒ぎしていた学者たちは三井化学の側についた。……農薬の袋の写真をネットで公表すると、農水省の反論はピタリと止まった。このサンプルがある限りだれでも追試ができるから。
旧厚生省は、発生源を調べることなく、思い込みで、焼却炉についての非常に厳しい規制値をつくった。大規模化、広域化をうながし、RFD発電の効率がいいというキャンペーンをした。ところがRDFはあちこちで事故を起こしている。(自分もだまされた〓)
▽78
▽81 非常に越すとがかかる政策を1つ実施する費用で、安い方の対策は何万倍もできることがある。医療対策も環境対策も安全対策も共通の尺度で評価することでわかる。
▽87 環境ホルモンの人間に与えるリスクは小さい。……生命保険会社や損保会社の経営が破綻しないのは、リスク予測がうまくいっている証拠。
▽89 身のまわりにあるもののリスクの大きさを比較すると、最大のものは喫煙。また放射線元素のラドンのリスクも大きい。
日本ではレントゲンによるリスクが高いと英国オックスフォード大学。全がん発症者の3・2%が検査被爆によるものとなっている。ことに歯医者は、必要ないのに相当撮っている。……昔は、レントゲン技術者は死亡率が高かった。
▽93 以前はあるレベル以下なら安全で、それを超えたら危険と考えた。ところが、放射性物質は、閾値(その量以下は安全という値)がない。どの領域も安全でなく、ゼロにならないリスクがある。そういうことから、リスクの大きさとベネフィットを考える見方が出てきて、リスクをある程度許容しなければ、という考え方が1960年ごろから米国で出てきた。革命的なことだった。
▽98 カネミ油症は、PCB混入で起きたが、重大な症状はPCBそのものではなく不純物として含まれていたダイオキシンであると考えられている。ダイオキシンでは、カネミ患者の健康影響を調べれば、直ちにリスク評価のためのデータが集まる。
▽99 リスクで視る視点が、規制を弱めてしまうという批判。そういう一面もあるが、多くの人が気づかないリスクを発掘し、規制することもある。すべてのリスクをゼロにすることはできない。結局気づいた大きなものだけを規制することになり、ほかのものは、見ないふりをすることになる。
▽103 水俣病とがんを比べる。損失余命で比較。がんの損失余命は12.6年。メチル水銀中毒患者は1.85年だった。……損失余命で比べると、一番大きいのが喫煙。ディーゼル排ガス、ラドンとつづく。
▽109
▽110 リスク評価で一番大事なことは、新しいリスクを見つけること。
▽117 ベトナム戦争でのダイオキシン裁判。裁判官は和解を勧める。その理由として、退役軍人への影響はほとんど証明できないし、やろうとしても難しい。企業の責任を追求するにも、膨大な動物実験が必要だ。しかし、何らかの暴露があったのは事実だ。だから、補償しろ、というのではなく、福祉施設のようなもので、裁判のために使うと予想されるお金の何分の一かを使った方がいい……と勧告する。
水俣病も、リスク評価という考え方からすれば、とてもひどい人がいれば、そうでない人が延々といる。どこで切ってどこまで補償するかという議論ばかりしているから、延々と争う。……暴露を受けた人全体が享受できるようなかたちでお金を出すとか、そういう発想はできないものか。……10年以上ここにいてメチル水銀をたくさん食べた人はみな、ある程度安いお金で介護施設に入れるようなものを要求したら……。基準線の上か下かという議論は空しい……と提案したが……。
▽122 ベトナム枯れ葉剤のダイオキシン 実は濃度の測定値もない。……ダイオキシンによるがんはあったとしても、極めて小さい。
▽133 損失余命でも、差別問題が噴出することはある。若者1人死ぬことは、年寄りが6,7人死ぬのと同じ価値ですよ、ということになってしまう。限られた資源のもとでは、誰かが救済され、だれかがされないという現実があり、それが、評価への批判になりやすいという事実をふまえないといけない。
▽134 客観的なQOLの評価法はあるか。自分自身がこういう人生で10年生きるのと、リスクはあるけれども違う人生で何年生きるのと同じ価値かということを本人に選ばせる方法=タイム・トレードオフ(時間得失法)。
▽148 新聞もテレビも……ダイオキシンの85%は一般ゴミ焼却炉から出ていると書いている。ではなぜ、魚介類の濃度が高いのか、それはどこからくるのか、環境中のダイオキシンの発生源は何かという視点で研究してきた。
▽153 カネミ
▽155 1973年から25年間に母乳中のダイオキシン類は半減していた。ごみの焼却だけがダイオキシンの原因だと主っていた人には理解できない結果だった。……かつては農薬の不純物がダイオキシンの主たる原因であり、それが現在は禁止されているから、母乳中のダイオキシンは減少する。
▽156
▽165 環境ホルモンの空騒ぎ。
▽179 BSE問題で米国に要求すべきは、感染数がいずれのレベルにあるのか、危険部位除去はどこまでできるのかをはっきりさせること。それがわかれば、全頭検査が必要かどうか……とるべき対策は決まる。
BSEの全頭検査は、リスク論からいえばナンセンス。
▽182 リスクの大きさを明らかにし、削減策の効果夜行立を説明しつつ、対策を提示すること。
▽184 RDF発電所は、エネルギー利用効率も低く、維持管理には手間がかかり、かつ、危険きわまりない施設であることがわかった。……ごみ焼却炉のダイオキシン対策は、それほど急を要する問題でもなく、小型焼却炉でできないものでもない。……
▽192 いま疑われている物質の危険が本当なら大変なのできるだけ回避しようという「予防原則」と、禁止したときに、もしかしておきる逆影響をどのように「予防するか」という両側の予防原則が必要。……水俣病でも、熊大研究班は原因物質として最初にマンガンをあげ……。この時点でマンガンを禁止するべきだったのだろうか。原因は水銀だと分からない時点で、何が可能だったかを論じてはじめて有効な予防原則が導きだせる。
では、水俣病でもっと早く防ぐ方法はなかったか。それはあったと思う。排水が多くの異変を起こしていることについて、一定のはどめがかけられてしかるべきだったろう。チッソ以外の汚染源がみつからないような状態で、チッソの工場内の調査ができないというのもおかしい。必ずしも原因物質を特定しなくても、排出源はわかった筈だ。
▽202 日本の環境科学で一番足りないのは、数値解析の技術。
▽241 原子力が夢の技術とは思わないが、わが国のエネルギー状況と今のような管理技術を考えれば、もう少し利用されてもいいと思う。残念ながらリスク不安が大きく、原子力発電所の建設が市民に拒否される状況が続いている。遺伝子組み換えも、少なくともいくつかの作物について、当面大きなリスクなしという判断ができる程度になっている。しかし、遺伝子組み換え作物のすべてが十把一絡げにして市場から閉め出されている。
▽247 リスク評価というのは、その時点で言うことが大事。後になれば、誰でもわかる。わからない時点で、リスク予測をし、皆の誤解を指摘し、社会に訴えることこそが価値。




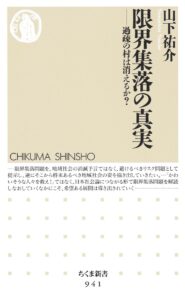
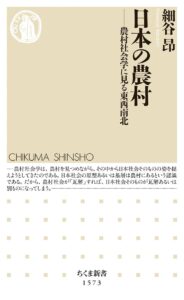


コメント