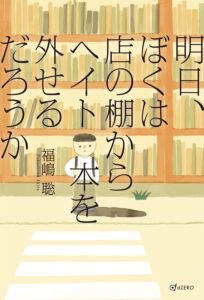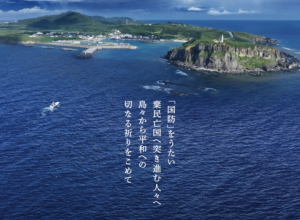文春文庫 20061120
□小林多喜二の死
好きな子ができて、入れ込んで、逃げられて……といった書生っぽくて情けない多喜二が、すさまじい拷問をともなう左翼弾圧を目にして、その実態を描き、特高ににらまれ、最後は自分自身が殺されるまでを描く。
最後に逮捕された際、
「おい、もう、こうなったら仕方がない。お互い元気にやろうぜ」
と仲間に声をかけ、それを聞いた特高たちが、寒中丸裸にして、ステッキで打ってかかった……という。
「決して拷問したことはない。あまり丈夫でない身体で必死に逃げまわるうち心臓に急変を来したもので、警察の処置に落ち度はなかった」と警察側はあくまで拷問を否定し、解剖さえ妨害しつづけた。
大事なのは、あの暗黒の時代でさえも、タテマエでは拷問が禁じられていたということだ。国会で「拷問はいかん」と追及する議員もいた。だが、政府側答弁は、
「左様な事態のあるということを信ずることができませぬ」
「政府としては、存在せざる事実を前提として、これにたいして所見を述べる必要はありませぬ」と木で鼻をくくったように逃げつづけた。
圧倒的な権力を背景に、平気でウソを言い、それが通ってしまう。それって、大量破壊兵器がなかったことを追究されて「フセインが見つからないからといって、フセインがいないわけじゃない」などといった、小泉らの開き直りと一緒じゃないのか。
----抜粋-----
▽1914年 選挙で革新勢力がめざましい進出。が、田中内閣は、労働農民党と表裏一体の関係にある非合法の日本共産党を中心に左翼全体への大弾圧。……治安維持法の改正で、最高刑10年を死刑に改め、特高警察の網を全国に張り巡らせた。この「死刑」への改正が、のちの転向者の続出につながる
▽作品での拷問の詳細な描写。「非国民」共産党員に対するテロは半ば公然と官憲に許された。「天皇陛下の命令」という「使命感」によってその凶暴性を倫理化することができた。
国会で追及するが……、政府側は「左様な事態のあるということを信ずることができませぬ」「政府としては、存在せざる事実を前提として、これにたいして所見を述べる必要はありませぬ」
(戦前でさえも拷問は禁じられていた。タテマエはあった。追及する議員もいた。それでもいけしゃーしゃーと言い抜ける。今と同じではないか)
▽蟹工船 船内の労働者が過酷な労働条件と監督の虐使に耐えかねてストライキをはじめるが、護衛の駆逐艦からの干渉でそのストライキが押し潰されるまでの話。その一部によって、のちに不敬罪に問われる。
▽それまでのプロレタリア文学は、花ざかりの理論はあっても、それを一般に承認させるだけの実作がなかった。「蟹工船」は、初めて普通の分断にプロレタリア小説の強い陣地を獲得したといえる。
□京都大学の墓碑銘
「あの人はちょっと問題あるから」といった部分を狙い撃ちし、「あいつさえやめればこれ以上は干渉しないから」と言って、周囲と分断する。でも一度、弾圧の事例をつくってしまえば後は同じ手法をくり返される。……よくあるパターンである。
滝川事件でも、法学部以外では「滝川教授ひとりがやめればすむ」という空気が強かった。「大学の自治は破壊されても、いつかは回復するときもあろう。総辞職をしては元も子もなくなる」という意見も根強かった。
だが、実際は事件後、大学当局も権力寄りになり、学生の弾圧は厳しくなり、「京都帝国大学新聞」に対して、今後滝川教授問題についての批判行動の一切を禁じる、と命令するにいたる。
そして、滝川ら京大7教官の追い落としに成功した蓑田胸喜ら、「原理日本」系の右翼理論家は、勢いを駆って、美濃部達吉、田中耕太郎、宮沢俊義らへの攻撃に移っていったという。
--------抜粋など---------
▽大正7年、大学改革で、初めて総長の公選制が認められた。自由主義勃興の時流に逆らい得なかったあらわれ。しかし、デモクラシーの浸潤は、学生運動の政治参加によって必然的に反動的な風潮を誘発した。吉野作造の「新人会」に対して東大教授の上杉慎吉を中心とする国粋的な「興国同志会」
▽滝川の「客観主義刑法」が問題になる。当初は文部当局も、滝川の進退を正式に問題にしていたわけではなかった。
▽京大総長と文部次官の丁々発止。
▽議会では、「教育革新に関する建議案」。多数で成立。民主主義の形でファシズムを推進する。
▽事件後、法学部は3分の1に。学生の弾圧は厳しく。……「京都帝国大学新聞」に対して、今後滝川教授問題についての批判行動の一切を禁じる、と命令した。
▽戦後の昭和28年に滝川は京大総長に。
□天皇機関説
滝川事件の2年後の昭和10年。政友会が倒閣の具に使った「天皇機関説」攻撃はファッショの嵐となって、政友会の野望と関係なく、美濃部憲法をおしつぶし、雪崩のように政党政治自体をも破滅に追い込んだ。政党はおのれの策略でうんだファッショという巨人の手によって絞殺された--。
機関説の美濃部に反駁する上杉は、論理ではまったく反論できなかった。上杉は天皇の神秘性を唱え、美濃部に対して「尊皇精神」による道徳的な攻撃を加えた。どうみても議論の勝負は明白なのに、世論はそうならない。コイズミのめちゃくちゃな「憲法論?」が通ってしまった状況に似ている部分がある。
大正デモクラシーの自由主義の気風が、大不況による荒廃による共産主義の浸透、それに対する弾圧……といった過程をへて、国家主義に染めかえられていく。
天皇自身は実は美濃部の機関説に賛成だった。「天皇主権説をとって思想信念を以て科学を抑圧しようとすれば、進化論の如きもこれを覆さなければならなくなる」などと語ったと「本庄日記」にでているという。だが、天皇の意思さえも無視して、天皇は神格化され、軍部は暴走していく。
伊藤博文らがつくった、タテマエ天皇神格説(顕教)・実質天皇機関説(密教)という国家体制を、「顕教」によって教育された国民の狂信的な支持を背景に、ぶちこわしてしまう過程だと、鶴見俊輔と久野収は後に説明している。
ちなみに、滝川事件のときに法学部教授が辞表を提出して抵抗したのに、美濃部に援助を申し出る教授は1人もいなかったという。
---------抜粋など----------
▽権力層や支配階級は美濃部を忌憚していた。が、それがにわかに表面に出なかったのは、当時の日本に漲っていた自由主義の風潮に遠慮していただけだ。……
昭和初年の浜口内閣による緊縮政策が空前の不況を誘い、農村の疲弊、都会の失業者の増加は共産主義の受け入れを促した。だが、共産党への相次ぐ弾圧は、それまで支配していた民主主義的風潮を根こそぎに国家主義へ変えてゆく絶好の機会になった。
▽ワシントン条約は、軍令部が承認していないから無効だと海軍は主張した。が、浜口に意見を求められた美濃部は、海軍の軍縮に関する問題は政治問題であり、軍令部の口を出すべき事柄ではないと答えた。この意見を参考にして海軍を屈服させた。……
▽陸軍省が昭和9年に「国防の本義と其強化の提唱」というパンフを出すと、美濃部は反論の筆をとる。「『たたかいは創造の父』とあって、戦争賛美の文句で始まっている。……戦争は創造とは逆にこれを破壊するものである。……学術や産業は全く度外視され、一に国防にのみ国家の生成発展が依存するように論じられている……世界を敵としてどうして国家の存立を維持することが出来ようか。それは結局国家の自滅を目指すものである。国際主義を否定する極端な国家主義は、かえって国家自滅主義に陥るのほかはない」
▽滝川事件に火をつけた蓑田は、滝川を落とした余勢をかって、美濃部の機関説に向かった。平沼系と、軍部をとりまく右翼の意向を代表したものだろう。
▽貴族院で美濃部を糾弾したのに対し、美濃部が弁明演説。説得力がある名演説で、拍手がわくほどだった。……だが……執拗な攻撃に対し、内閣側もしだいに折れていく。陸軍大臣は右翼となれあって「美濃部博士の憲法議論は、軍人精神というものと符号しておらない」と答弁。岡田首相は当初は「学説は学者に委ねる」といいつづけていたが、次第に軍部の空気と右翼系議員の圧力に押されて「美濃部学説が社会に影響を及ぼすときは何らかの処置をとることについて最も清朝考慮する考え」と言うようになった。これが、攻撃側の突撃路になった。
▽政友会は、単純にも岡田内閣打倒のみに機関説を攻撃した。目先の獲物を追うて断崖に足をすべらせ政党政治を自滅させるのだ。
▽天皇は「軍部が自分の意に従わずして天皇主権説を云うのは矛盾ではないか」と下問したが、出光海軍武官は、ときどきの事務上のことで天皇の意志にそむくことがあっても、陛下は論議に超越して静観されたい、という趣旨を述べた。……軍人たちが天皇の意志とは違って方針を望み、それを天皇の名において行うなら、彼等は自ら天皇機関説を肯定しなければならなくなる。
▽伊藤博文は、明治憲法を作るときに、天皇の大権を国務大臣が輔弼するという道をつくった。天皇の命を受けて政務の代行をするというのだが、その責任はすべて輔弼の臣下が負う。伊藤は実質的に機関説論者だったが、外装的には、天皇神権説の支持者だった。ドイツ人医師ベルツの日記「伊藤のいわく『皇太子に生まれるのは全く不運……大きくなれば、側近者の吹く笛に踊らされねばならない』と。そういいながら伊藤は、操り人形を糸で踊らせるような身振りをしてみせた」(〓岩波文庫「ベルツの日記」)
……天皇の神格を「顕教」、機関を「密教」になぞらえた久野・鶴見によれば「軍部は顕教による密教征伐、すなわち国体明徴運動を開始し、伊藤の作った明治国家のシステムをメチャクチャにしてしまった……顕教によって教育された国民大衆がマスとして目ざまされ、天皇機関説のインテリくささに反発し、この征伐に動員される……」(「現代日本の思想」)
□陸軍士官学校事件
▽陸の長州閥、海の薩閥
陸軍は大正末期まで長州閥がおさえていたが、田中義一を最後に人物がいなくなり、岡山の宇垣に任すことに。宇垣閥は、政治的軍政で縦の統制主義が強かった(:統制派)。薩摩系を継いだ真崎・荒木などの佐賀閥は、反政治・反現実・精神主義で、武断的国粋主義の色彩をおびる(:皇道派)。
荒木の神懸かり的言葉は、青年将校の人気を煽る
▽永田鉄山軍務局長 官僚の中堅層と結んで、国策を立案させ、その結論を軍の威力で政府に実行させる。このときに参加した官僚は、岸信介ら。このときの彼等の立案がのちの「国家総動員法」や「電力国営」などの政策になる。世間は軍部に協調する彼等を「革新官僚」と呼んだ。
▽永田は、相沢に殺される十数日前、関東軍の満州国に対する内面指導は早く打ち切る必要があり、朝鮮は軍備と外交とを除き、国内自治を許す方向に持っていく必要を痛感したと語った。