宝島新書 20091201
戦前、農水官僚は小作人を応援し、議員らは地主とつながっていた。
戦後、小作人を基盤にした農民組合を無力化し農村を保守地盤にするために農地改革が実施され、全員が「地主」になり、保守の金城湯池となった。
農地改革によって生まれた自作農は、食糧増産に多大な貢献をしたが、農水官僚はさらに「強い農業」をめざすため、農業基本法を制定し、専門農家を育成しようとした。だがこれは頓挫する。
食糧管理制度は食糧難の時代に安く食糧を提供するための制度だったが、その後、米価を引き上げ生産者の所得を保証するための制度になる。
農協は米価を引き上げを要求する。米価を維持するために減反が増える。価格が上がるから需要が減り、さらに減反……という悪循環になり、日本の米生産は縮小していった……という。
「強い農業」は実現せず、大半が勤めながら週末農業をする第2種兼業農家になっていく。「農業」を成長させるには、専業農家を後押ししなければならないのに、減反は専業も2種兼業も同様の削減幅を押しつけ、専業では食っていけなくなる。一般のイメージとちがって、兼業のほうが専業よりも豊かなのである。
日本の農協は、戦前の農会?を食糧管理制度の受け皿にするために転換させたものだったから「協同組合」的な要素は希薄な、国-県-市町村という縦割り組織だった。国が米を買い取る際、国からのカネは農協を経て農家にとどく。農家はそのカネをそのまま農協に預金し、肥料や農薬、機械を購入する。こうして政府のカネを仲介することで農協の金融部門は巨大化した。農協の金融部門にとっては、動かすカネが高額であるほど手数料がもうかる。だから、米価は高いほどよいし、肥料や農薬などを独占的に販売した。本来、共同購入によって市価より安く農家に販売するべきなのに、むしろ高値で販売する。そのかわり、政府から補助金をとってきた。こうして農協は農家のためではなく農協組織のために運営され、肥え太った。
農協の組合員の大半は兼業農家である。だから、専業農家を重視する、という発想は浮かばない。むしろ多数派である兼業農家のために働くことで政治パワーを培った。
さらに、「農民のため」には、営農指導が重視されるべきなのに、農協内部では営農指導の部署は赤字の「お荷物」なのだという。稼ぎ頭の金融部門は農業関係の融資よりも不動産融資などでもうけていた。もはや「農業」協同組合ではなくなっている。
「食糧安保」や「自給率」を農協が唱えることも噴飯者だという。食糧安保にもっとも必要なのは、いざというときに米や野菜をつくれる「農地」の保全である。なのに、米価の引き上げと減反と農地転用によって、農地を削減するようなことばかり農協はしてきた。
「くさい米」騒動は、ミニマムアクセス米が原因だった。700パーセントもの関税をかるかわりに外米を輸入し、長期間保存したためだった。中国などの米価格は上昇しているから実は関税は40%で十分であり、関税率によって決まるミニマムアクセスの量ははるかに少なくてすむという。
では今後どうすればよいのか。食糧管理制度による農産物の価格維持ではダメ。関税は引き下げて農産物価格を安くするかわりに、農業を主たる収入源とする専業農家に直接保証するEU式にすればよいという。だから、民主党のばらまき型の「戸別補償」は愚の骨頂なのだという。
農業基本法による商業としての農業路線が、日本の農村を疲弊させたという山下惣一らの主張に共感してきたから、まったく逆の視点が新鮮だった。もう一度、山下惣一らの本を読み、比較してみよう。
===========抜粋・メモ==========
▽13 カドミウム米は、食用として流通しないよう、粉砕して、着色した。今回の汚染米は、丸米として売却した。農水省の責任は大きい。汚染米問題の根幹は高い関税で農業を守る農政にある。ミニマムアクセス米を長期間保管することでカビが生える。さらに、毎年1トンあたり1万円の保管費用がかかる。
▽19 国産米の価格は60キロ14000円。輸入されている中国米は1万円。すでに800%の関税など必要ない。さらに減反をやめれば国産米の価格は低下する。そうやって海外の米より安くなればミニマムアクセスは必要なくなる。汚染米もなくなる。
▽22 明治初期から1960年まで、農地面積600万ヘクタール、農業就業人口1400万人、農家戸数550万戸を維持していた。ところが05年には人口252万、戸数285万戸に。しかも大半が兼業。
▽27 平地では、田植えや稲刈りを短期間で終える必要があるが、中山間では、標高差を利用すれば、田植えと稲刈りに2,3カ月かけられる。家族経営でも10-20ヘクタールの稲作を実現できる。(平均的農業経営規模は1・3ヘクタール)寒暖の差で味もよくなる。
▽37 戦後しばらくは食料政策は乏しい食料を均等に配分する消費者政策だった。米価は国際価格より低く設定された。農工間の所得格差是正のため、60年代以降に高米価政策へ。
▽48 品種改良で単収を上げればコストは下がるが、ますます減反面積を増やさなければならない。だから、単収増加のための品種改良はタブーになった。単収は60年400キロから67年480キロに2割増加したが、それ以降は40年かけて530キロへ1割しか増えていない。粗放農業のカリフォルニアより3割も低い。減反をしなかったEUでは、穀物単収は増加した。
▽55 基本法は、社会党は「貧農切り捨て」と反対した。農協系統も同調しなかった。
▽57 食管制度とともに農地制度が農業を衰退させた。52年制定。不耕作地主発生を防止し、賃借権の解約制限などで小作権保護を図ろうとしたが、賃借権が強化されたため、農地は貸し出されなくなった。他方で、転用規制はザルだったたえ、宅地などへの転用期待が高まり、宅地価格と連動して農地価格は高騰した。土地売買による規模拡大も困難になった。
▽67 小作人の立場の農村の社会主義運動は、昂揚し、日本農民組合は46年の28万人から1年後に125万に拡大した。だが農地改革が進展するなかで目標を失い急速に衰退する。保守勢力の金城湯池に。
▽78 60年以降、肥料・農薬使用料は急増。組合員に高く売るほうが農協の利益になる。54年当初は輸出向け価格と同水準だった硫安の国内向け価格は86年には輸出向けの3倍になった。肥料価格が高くなると、農協は高い販売マージンをえられる。肥料資本と農協との癒着構造。農協による肥料取り扱いシェアは55年66%、03年は90%。
▽82 農業の補助金は、一部の例外をのぞき、複数の農家や農協が協同で行う機械・施設などにのみ交付された。零細農家が5軒集まれば補助対象だが、大規模専用農家単独では補助は受けられない。
農協は補助事業の受け皿になった。農協が高い農業機械を販売しても、その値段の半分の補助金がつけば農家は安く購入できる。国の補助金は、農家が農協加入するインセンティブとなった。
兼業農家は、販売拡大意欲をもたない。減反によって実現される高い米価維持は兼業農家には望ましい。また、農地切り売りで利益を得た。農協法の組合員1人1票制では、数が多い兼業農家の声が反映されやすい。農協にとっても兼業とむすんだほうが政治力維持になる。
▽88 農協は巨大独占企業。組合員相手に宝石から墓石まで売る総合商社。
▽97 准組合員制度も問題。農協の融資に占める農業への融資は、60年代までは5割を超えていたが、07年3月末では6%。准組合員らを対象とした住宅ローンやアパート建設融資などが増大。「不動産協同組合」になっている。
▽110 農業基本法 (諸悪の根元とおもっていたが……実は)
▽112 戦前の農林官僚には貧しい農民を救おうという使命感があった。……「組織のための組織」は農協だけではない。
▽128 農協は組織維持のため農家戸数維持が必要だ。多数派の兼業農家の利益が目的となる。与党政治家も農民票が必要だ。
……農政トライアングルは、食料安全保障を主張しながら、その基礎となる農地を転用し、自給率を低下させつづけてきた。それが個別農家の利益になるからだ。ある議員によると、地元選挙民から頼まれた農水省への口利きの多くは、補助金の箇所付けと農地転用許可という。
環境などの多面的機能の主張も、OECDもすすめるように、市場価格維持とは別の保護手段である財政負担による農家への直接支払いを採用するべきなのに、市場価格を維持する関税が必要という主張にすりかわる。多面的機能の半分以上は、洪水防止や水資源涵養など水田についてのものなのに、水田を水田として利用しない減反政策を進めている。
▽133 農村部では一度選挙基盤が確立すると、個別の利益に左右されないケースが多かったから、農村部に国家全体をかんがえる大物議員が出現した。ところが今は……
小選挙区も
▽140
▽147 農水省の担当課長として、制度設計した。「中山間地域等直接支払い制度」
▽149 戦後の農地改革 松村謙三農相 農村の秩序維持というだけでは、地主層から反論が予想されたため、食料増産という大義名分をもちだして保守勢力を説得した。
▽153 最近は、農協が冷遇してきた大規模農家層が着実に伸びている。10ヘクタール以上の層は00年からの5年間で3・4%も増えている。
零細農家を相手にする非効率な農協の農産物販売や農業資材などの経済事業は大幅な赤字。農協は信用事業や共済事業で穴埋めしてきた。
貯金残高は、農業縮小の見返りとしての農外所得や農地転用代金の預金で莫大になるが、貸出残高は農業縮小のため縮小。貸出先がないから、バブルの時代には、住専に多額のカネが貸し出された。
▽167 人口7千万人だった戦後日本では、農地が500万ヘクタール以上あっても飢餓が生じた。61年に609ヘクタールあった農地の4割超の260ヘクタールが減反や転用で消滅した。現在は463ヘクタールの農地があるだけ。食料安全保障はますます危うく。
▽169 農地を農地として利用するからこそ農地改革が実施された。なのに、宅地に転用してもうけた。農地法は公選法と食管法と並ぶ3大ザル法と呼ばれた。農地転用による莫大な利益が農協に預金されて農協は発展した。
▽178 水田は土壌流出を防ぐ。千葉県市川市は水田維持のために補助金を交付している〓。なのに国は、水田をなくすための減反補助金を出している。
▽184 米の関税778%は見せかけ。減反を廃止し、EUのように農産物価格を引き下げ、影響を受ける農家に直接支払いをしたらよい。減反廃止で14000円の米価が9500円に下がり、需要は1000万トン以上に拡大する。零細農家は農地を貸し出すようになる。14000円と9500円の差の8割程度を主業農家に財政で補填すればよい。米流通700万トンのうち主業農家のシェアは4割だから1700億円ですむ。これは減反のために払っている補助金とほぼ同じ額。兼業農家の収入はサラリーマンをすでに上回っている。
日本が米にかけている関税は60キロあたり2万円。(これをタイ米の安い価格で割って778%という数字を出している)。中国産の短粒種の輸入価格は最近では1万円。国内米価は14000円だから、関税は100%もいらない。40%で十分。減反をやめて主業農家に直接払いをすれば、財政的負担は変わらず、価格低下で消費者もメリットを受ける。ミニマムアクセス米の拡大も必要なくなる。
▽190 消費者負担による価格支持ではなく、納税者負担による直接支払いを。
▽192 民主党もばらまき。自民は対象農家を4ヘクタール以上に限定したのはよかった。だが、兼業でも面積を集めて集落協同でやればよいとしたから、借地で規模拡大してきた主業農家から「かしはがす」という事態がおきた。
民主党もマニフェストが後退。対象者を絞るという要素がなくなっていった。減反の必要性も言い出してしまった。
▽197 米価格を下げたうえで、対象農家を主業農家に絞って直接支払いをすれば、グローバル化にも人口減少にも対応できる。なのに、農協は価格引き下げにも政策対象農家の限定にも反対する。兼業農家に不利になり、政治力をそぐことになるからだ。
▽199 農協内部で「営農指導」は、赤字部門とかぜいたく事業とかいわれて冷遇され、合理化の対象となってきた。営農指導員は85年19000人から05年には14000人に26%減少している。指導しても農協として見返りの少ない中山間地からは真っ先に撤退している。
▽202 主業農家が自らの組織をつくることでJA農協を利用しなくなれば、零細な兼業農家のためだけの農業関連事業は赤字が拡大し、縮小せざるをえなくなる。農協にとっても不採算部門を切り捨てて、信用・共済事業に特化したほうが有利で、農業関連は専門農協によって実施されるようになる。そのときこそ、1900年の産業組合法施行の実施に関わった柳田らが描いた「真の国民・農業者のための農政」が実現するだろう。




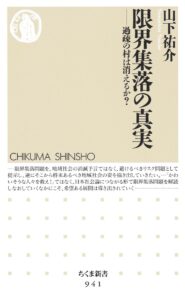
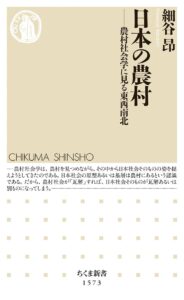


コメント