平凡社新書 20091230
レヴィ=ストロースは2009年に100歳で死んだ。
構造主義というのは、歴史やら進歩やらを否定し、時代によってさまざまな変化があったとしてもその社会を規定する「構造」は変わらない、という、いわば宿命論に近いと思ってきた。
だが左翼活動家としての若きレヴィ=ストロースの歩みを知ると、彼の思想が俄然、熱を帯びてみえてくる。白人中心の進歩史観や西欧文化中心主義を徹底的に批判し、先住民族の文化に共感を寄せるそのスタンスはおそらく、青年期に培ったものだった。彼は社会主義を捨て去ったのではなく、弱者に身を寄せる思想を咀嚼することで構造主義を生み出した。そのなかで、西欧文明がいつのまにか見失ってしまった「野生の思考」の豊かさに気づいていった。まさに「闘う」人だったのだ。
90歳のときにこんな講演をしている。
--(老いてしまって)ひとりの人間の4分の1あるいは半分でしかない現実の私と、全体の理念をまだ生き生きと保持するバーチャルな私とが存在しています。バーチャルな私は、著作の計画を立て、章立てを考案し、現実の私にこう言います。「さあつづきは君がするのだ」。すると、もうそうはできない現実の私がバーチャルな私に言います。「それは君の仕事だ。全体を見ることができるのは君なのだから」。今の私は、このおかしな対話のなかで日々の生活を送っているのです。--
自らの老いをただ嘆くのではなく、自分から引きはがして観察し、対話し、経験しつくそうとする精神の構えは、まさに「闘う人」である。
入門書にしては少々難解だが、青年時代に焦点をあてることで、新しいレヴィ=ストロース像を浮き彫りにしている。
======================
▽22 人間の「感覚的なるもの」と「理性的なるもの」の対立を克服する方法が「神話」ではないか、という問い。「神話」においては感覚と理性が結びつき、表裏一体となって人間の生きる世界の意味を開示する。感覚にとらわれることから脱却することで理性的になるという西欧思想の常識をくつがえす。現代の人間が見失った世界との接し方として再発見する。
神話が語る感覚を通じた世界とのかかわりあいのなかに、主観を超えた、人間に共通な生きることの条件を成り立たせている「論理」を探究する。感覚に内包された論理が、すでに知性をあらかじめ構造化している。
▽25 体系に手が加わるとばらばらに崩壊してしまうが、構造はその均衡状態に変化が加わった場合、変形されて別の体系になる。……構造とは「変われば変わるほど変わらないもの」(=変わり方、は変わらない?)。変化することで「崩壊」に向かう「歴史」とは対照的な何か。……歴史に翻弄される自分の世界を離脱し、異なった世界をめざすこと。
▽127 ヤコブソンの音韻論をもとに親族の基本構造を導きだす。
固有の表意作用はもたないが、表意作用を形成する手段となる音素と同様、インセストの禁止は、別個のものとみなされる2つの領域のつなぎ目をなすと思われた。音と意味との分節に、自然と文化の分節が対応することになった。形式としての音素が、あらゆる言語に与えられているのと同様、インセストの禁止は、その否定的表現だけに限るならば、普遍的に存在し、これもまた空虚な形式を構成する。この形式によって生物集団の分節が可能になると同時に必須となって交換の網の目をつくりだした。音素の実在が音的個性のうちにあるのではなく、音素が互いに結ぶ対立的、消極的関連のうちにあるのと同様、婚姻規則の表意作用は、諸規則をばらばらに研究してもとらえられず、それらを互いに対立させないかぎり浮かび上がってこない。
……インセスト禁止という否定的な命令は、じつは他人に提供せよ、交換せよという肯定的な命令と表裏をなしている。人間集団のカテゴリー化と集団間のコミュニケーションを生成する。音素と同様、多様に見えるさまざまな「婚姻規則」のあいだには対立と交換すなわち構造が見出される。親族関係はアル意味では集団間の関係を生成する言語であり、この言語によって人間は自然の世界から文化へと移行する。
……自然に構造が刻印されることで文化が生成し、構造のあいだには歴史的変化とは室を異にする「変換」関係が見出されるという直観。
▽141 父系、母系の系譜意識に支えられた氏族への個人の帰属という原理が社会を構成するという「同一性」の論理という社会観に疑義を対置することになった。「同一性」が徹底されたものとして、デュルケームに代表されるトーテミズム論がある。神話的な先祖としての動植物であるトーテムと氏族集団の「同一性」の観念。デュルケームにおいては氏族成員の「血」の同一性、同じ血を流すことの忌避こそが「近親婚の禁止」の基礎とみなされていた。フロイトにおいては、トーテム供犠を食べることで「父」と同一化することと「近親婚の禁止」の発生が結びつけられていた。
レヴィ=ストロースは、トーテム祖との同一化という垂直の関係ではなく、女性の交換と循環による水平方向への関係の展開と伸張に注目したともいえる。(〓じゃあレヴィストロースは、「一族」概念の発生をどう説明するんだろう)
▽162 「野生の思考」へ。人間は火を獲得することで料理をおこなし、「自然」を離脱して「文化」に移行したのか。裸から着衣への移行をしるしづける装身具の起源と火の起源とは変換の関係になければならないだろう。
「生のものと火にかけたもの」「密から灰へ」
「食卓作法の起源」「裸の人」。
▽167 音韻論の「対立と相関の関係」が人間の五感すべてに拡張しうるものとされる。後に「神話論理」において料理(料理の火)は「自然に課される形式」のもっとも基本的な与件として神話分析の基軸になる。
▽171 ユネスコの反人種主義キャンペーン。「人種と歴史」というパンフレット。「自民族中心主義」を批判し、徹底した文化相対主義と西欧文化中心主義批判。
辛辣な白人への批判〓〓(若き日の情熱を思わせる)
▽186 「野生の思考」 トーテミズム批判 ブリコラージュ
▽208 火を獲得することで、人は生のものを食べることをやめ、調理したものを食べることになった。衣服を作り出すことで、裸でいることをやめ自然から文化に移行した。「食」「衣」の起源は、神話のふたつの重要な主題なのだ。だから衣服や装身具の起源を語る神話は、火の起源の神話と相互に変換の関係になければならない。火を使うことで人になったとすれば、火を使う対象としての素材、すなわち動物、食用植物の起源を語る神話もまた変換の網の目に組み込まれていないとならない。(どこの地域にもある〓?)
▽233 「大山猫の物語」 インディアンが腕を開いて白人を迎え入れたことは明らか。征服者の態度は正反対だった。……霧は料理の火と同様、天と地を分離する。風は火を消す水と同様に、霧を吹き払う。ふたつの体系のあいだには形式的な並行性がある。
▽251 ……他者を「野蛮人」とみなすばかりではなく、時には神として迎える謙虚さをそなえること、他者のもらす聞き慣れぬ物語をも自らの物語のなかに吸収し見分けのつきにいほどに組み入れること。……(他者と遍路と……〓)


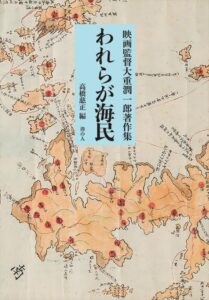

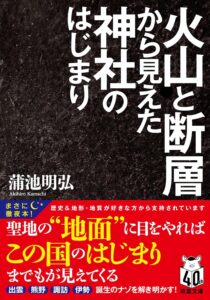

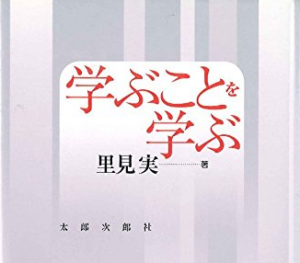

コメント