■知恵の森文庫 20051230
「放送禁止歌」というと、キヨシロウのパンク調「君が代」とかをイメージしてたけど、実は天皇制関連の「放送禁止」は岡林の「ヘライデ」くらいだという。
大半はもっとささい理由ばかり。
え? この歌も? という歌が次々にでてきた。
「土方」という言葉あったために放送されなくなった「ヨイトマケの唄」、「びっこの子犬」、渡辺はま子の「支那の夜」「金太の大冒険」「時には娼婦のように」……どれもささいな用語の問題で放送されなくなった。「網走番外地」は犯罪を肯定してるから、だそうな。
規制はしだいに過去のものまでさかのぼる。「五木の子守歌」「竹田の子守歌」は被差別部落を歌ったものとして禁止の烙印を押される。ちなみに「びっこ」とか「きちがい」といった言葉が頻出する古典落語の多くは放送できなくなってる。
だがよくよく調べると、「放送禁止歌」などは存在せず、「要注意歌謡曲」にすぎなかった。「これを参考に、放送するときは気をつけね」程度のガイドラインのはずが、いつのまにか現場の人々は「禁止」と思いこみ、信じこんでしまった。
解放同盟がうるさいから、という理由で放送されなくなった歌について、当の解放同盟に尋ねたら、むしろしっかりと歌ってほしい、という。
コワイから、めんどうをおこしたくないから、と表現はどんどん萎縮し、コワイものから遠ざかっていく。それによって差別を潜在化させ深化させてしまう。
まず自分の目で見よう、確かめよう、考えよう、表現しよう。そんな当たり前の呼びかけをするのでさえ、勇気が必要な今のマスコミの状況ってなんだろう?
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
▽なぎらけんいち「悲惨な戦い」 相撲を揶揄した。クレームが実際につく前に、やばそうだから蓋をしてしまおう、という感覚だった。
▽「どうしても『手紙』を放送したいと思うのなら、議論を挑んでくればいい。規制はマニュアルではありません」「そんな制作者はいましたか」「おりません。異論を唱えるという発想すら持っていない。ゆゆしき問題です」
▽長谷川きよしが歌った「心中日本」はタイトルが暗すぎるとの理由で発売禁止の措置を受け、結局「ノ」という送りがなを小さく刷り込んで「心ノ中ノ日本」として発売した。
▽アメリカの言葉言い替え PC(politically correct)運動
あらゆる差別的表現を政治的に正しく言い替える運動。「視覚的にチャレンジされている人」(optically challenged)「知的にチャレンジされている人」「異なった能力をもつ人」……いきすぎたPC、90年代に入ると少しずつ淘汰される傾向にある。
▽デーブ「偏見や妄想は知らない人に生まれる。僕は実際に部落内を歩いたし、話もした。メディアに携わる人なら、だれもが自発的にやるべき行為だと僕は思う」
▽「確かに糾弾はあった。……メディアは誰一人として糾弾には反駁せえへんのよ。みんなあっさり謝ってしまうんですよ。
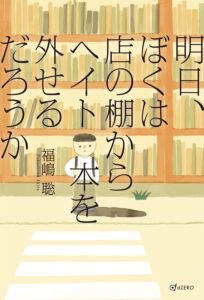
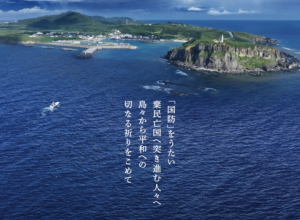

コメント