■原発からの命の守り方<守田敏也>海象社 20160318
安全性の保証もなく、避難態勢のチェックもないまま再稼働の動きが進んでいる。
そういう実態を解き明かしたうえで、原発事故や天災が起きたときの身の守り方を説いている。原発だけでなく津波災害などにも役立つマニュアルにもなっている。
原子力規制庁は「新規制基準に合格しただけで安全とは言えない」と言っているのに、政府は「新基準に合格した安全な原発から稼働させる」「再稼働の安全性の責任は規制庁にある」と言う。どちらも安全性を保証しないのに、再稼働が進められている。
避難計画は、政府も規制庁も計画作成を自治体に命令するだけで、審査もしないし責任も取らない。
福島の事故当時、近藤駿介・原子力委員会委員長のシナリオでは、半径170キロ圏内が強制避難区域になり、東京23区を含む250キロ圏が希望者を含んだ避難区域(任意移転)になるとされた。米国は半径80キロ圏から自国民の退去を勧告し、フランスは「フランスに帰国するか東京から離れた方がいい」と勧告した。原発事故では最大級の退避行動をとったほうがよい。米仏の対応こそが合理的な判断だった。
福島事故の避難対応は旧ソ連よりも甘かった。ベラルーシやウクライナでは、年間1ミリシーベルト以上の地帯は避難権利区域で、5ミリシーベルト超は強制避難区域とされたのに、福島では5ミリシーベルトを超えても避難区域にされず、20ミリシーベルトまで居住可能地域とされてしまった。
原子力災害が起きたときは「とっとと逃げる」ことが大切だ。その際、壁になるのは次の三つのバイアスだ。
まず、危機そのものを認めず事態は正常ととらえてしまう「正常性バイアス」。デパートで火災報知器が鳴っても「誤報じゃないの?」と思ってしまう感覚だ。二つ目は、危機において周囲の行動に合わせてしまう「集団同調性バイアス」。三つ目は「避難範囲が広がったらパニックになる」などと恐れる「パニック過大評価バイアス」だ。
東日本大震災のとき、津波で車が流される映像を見て深刻さは理解したが、あんなゆっくりの水の流れが数千人を殺すとは思えず、大半の人は逃げられたろうと思い込んでしまった。正常性バイアスにはいとも簡単にはまってしまうのだ。釜石市では、津波の予想到達地域の人はほとんど逃げ出したが、到来が予想されなかった地域に死者・行方不明者が集中した。ハザードマップで水が来ないとされる地域で「水害がない」と思い込んでしまうほうが危険なのだ。
正常性バイアスによる心理的ロックを解除するには避難訓練が必要だ。釜石東中学は津波到来地域外だったが、サッカー部員の生徒たちが「津波が来るぞ、逃げるぞ」と叫んで走り出した。隣の小学校では3階に逃げていたが、中学生について児童も駆け出し、大人もこれに従った。そのおかげで助かった。
火災報知器が鳴ったら「逃げよう」と叫んで部屋を出る。そうしたら、多くの人の避難を促すことになる。火事かどうか確かめてから避難をはじめては遅いのだ。
水害などで、行政の避難勧告や気象庁の特別警報に頼りすぎるのも危険だという。伊豆大島の災害時、特別警報は出なかった。広島土砂災害でも特別警報はなく、避難勧告も土石流発生後だった。
自然災害に関して東京は「世界一危険な都市」らしい。「大潮の満潮時にゼロメートル地帯の堤防1カ所を破壊すれば、日本は機能を失う」からだ。
江戸幕府は、江戸を洪水から守るため利根川を付け替えた。堤防決壊を防ぐため、あらかじめ決めた場所から越流させた。泥の流入を防ぐための防水林がもうけられ、水の勢いを減らし林に泥が落ちる仕組みにした。こうした管理は、地域社会に任されていた。
ところが西洋のテクノロジーを採用した明治政府は、巨大な堤防で洪水を押しとどめる方向に転換した。水害のたびに堤防を巨大化させ、利根川は多くの流量を抱えこみ、洪水規模も堤防も拡大していった。破堤は「あってはならない」とされた。
川の管理の主体も、流域住民から地域官僚の手へ、一級河川は国家官僚にゆだねられた。かつて川の管理にかかわっていた住民は、意見を述べる場もなく、負うべき責任もない傍観者にさせられた。中央集権化のきわみである原発を生みだしてきた電力の歴史と似ている。
では原発災害にどう備えるべきなのか。
まず、避難のルートを決めておく。ふだんから車のガソリンは帰宅前に補充しておく。老人ホームなどの施設は、遠隔地にある同様の施設と防災協定を結び、避難先を決めておく。
福島の事故では、政府が深刻な事態を発表したがらないことがわかった。メルトダウンを発表したのは事故から2カ月後だった。圧力容器に穴を開け、格納容器底部へと燃料が落下するメルトスルーを認めたのは2013年12月だった。
だから「電源喪失」「冷却機能のダウン」と聞いたら、即刻避難を開始する必要がある。さらに政府が避難勧告を出した場合は、過酷な事故が起こっていると考え、できるだけ広範な地域で「とっとと逃げる」べきだという。
福山議員は、想定された最悪の事態を公にしなかったことを「正しかった」と述べている。本当は危機なのに安全だと言い続けたことが自己肯定され、追及もされない。だから、過酷事故では政府の安全宣言を信じてはならず、念には念を入れて「とっとと逃げる」必要があるという。
4章では放射能の何が危険なのかを説いている。
放射能は「半減期」が長いのがやっかいと思われるが、単位時間当たりの被曝量を考えると短いものがおそろしい。
放射線が飛んでくると、電子がはじき飛ばされて分子が切断されてしまう(電離作用)から、放射線値が高いところではロボットも壊れる。激しい細胞分裂を繰り返している粘膜などが放射線が受けやすい。だから、口内炎や下痢が起きる。
とくに怖いのは内部被曝だ。取り込まれた場所から球状に被曝するから、被曝の具体性も被害もあまりに多様なのに、ICRPは、同じエネルギーであれば、同じダメージを人体にもたらすと断言し、内部被曝特有の危険性が過小に評価されている。
首相官邸のホームページによると、チェルノブイリ事故の死亡者は急性障害28人、小児甲状腺癌15人の計43人だ。IAEAの報告に基づいているが、IAEAの場合、これに加えて事故の影響で死亡する人の数を約3960人と見積もっている。官邸のHPは世界でもっとも被害を低く見積もっているという。
逆に、もっとも多く見積もっているのは、アメリカのニューヨーク科学アカデミーから出版された「調査報告 チェルノブイリ被害の全貌」で105万1500人と推計している。汚染地域では、1985年以前は80%の子が健康だったが、今日では健康な子は20%に満たないという。
内部被曝の影響が過小評価されることで、原子力施設の社会的容認論が唱えられ、さらに、放射線値が十分に下がっていない福島の被爆地への帰還の強制につながっている。
いざ原発事故が起きたとき、放射能の影響を防ぐ安定ヨウ素剤は、原発の5キロ圏内では配られている。だが、福島原発事故のとき、放射線医学総合研究所が「指示が出るまで勝手にヨウ素剤を服用してはいけない」という文書を発表し、県の「放射線健康リスク管理アドバイザー」の山下俊一氏は「30キロほど西に離れれば、被曝量は1ミリシーベルト以下でヨウ素剤配布は不要」と強調し、ほとんどが服用されなかった。積極的に配布したのは三春町ぐらいだったという。そのせいで被曝した人々の被害は今後きちんと追跡されるのだろうか。
原発事故が起きたときにヨウ素剤がなければ、40グラムのコンブを煮出して煮汁を飲めばよいという。マスクをして、帽子をかぶり、ゴーグルをつけ、うがい、手洗いをすることで大気中の放射能を防ぐ。花粉症対策と同じだ。
原発は、普通に稼働しているだけで危険だという研究結果もある。アメリカのJMグールドは原発から160キロ圏内で、さまざまな疾病が起こっていることを統計学的知識を総動員して明らかにした。ドイツの調査でも2007年に、「通常運転されている原子力発電所周辺5キロ圏内で小児白血病が高率で発症している」と報告されている。
日本でも、原発近くに住む福井の僧侶が「葬式をあげた人はみんなガンで死んでいる」と話し、本人もガンで死んだ。原発とがんなどの疾病の関係も、軽視してよい問題ではないのだ、と気づかされる。
=================
▽ 再稼働を審査する原子力規制庁は「新規制基準に合格しただけで安全だとは言えない」と名言している。なのに政府はそれを無視し「新基準に合格した安全な原発から稼働させる」「再稼働の安全性の責任は規制庁にある。自分たちではない」と言い放っている。安全性をだれも保証しないのに、再稼働が進められようとしている。
規制庁は、半径30キロの自治体が避難計画をつくるときのひな形として「原子力災害対策指針」を打ち出しながら、計画に対する責任は各自治体にあると語って、何の審査もおこなおうとしない。政府も同様。避難計画はだれにも審査すらされないことになっている。
無責任な原子力の推進体制。
▽近藤駿介・原子力委員会委員長の「近藤シナリオ」。チェルノブイリ原発事故時の避難基準を採用すると、半径170キロ圏内が強制避難区域になり、250キロ圏が希望者を含んだ避難区域(任意移転)になるとされた。250キロ圏というのは東京23区がすべて含まれる。この圏内の人口は3千万人。
そのシナリオでさえ最悪は想定していなかった。
▽27 4号機の燃料プールが干上がるという事態を免れたのは、たまたま隣接する原子炉上部にまで水がはってあったから。シュラウド交換のためだった。その作業が遅れたたおかげで助かった。もし水が抜かれていたら…絶望的な破局の一歩手前だった。
▽31 「早ければ今夜にも原発が爆発する」という認識が政府にあった。だが市民にはまったく伝えられなかった。「原子炉は壊れることはない」「にわかに健康に被害はない」と繰りかえした。それが現実だった。
▽33 福島原発事故では五十の壁を突破する放射能の膨大なもれだしが起こったが、燃料プールにいたっては、脆弱な建屋の壁があるだけ。水が抜ければたちまち危機に瀕してしまう危険きわまりないものであることが社会的に明らかになった。
▽35 燃料プールには日本中で1万729トンもの使用済み核燃料がある。プールはどこもいっぱいになり、一部では燃料体を入れる間隔を詰めて容量を増やしたりしている。
▽39 「日本が受注しなければ、中国や韓国が落札してしまう。中国や韓国の核技術は安全性が低いので日本がやるべきだ」と述べている。
▽41 1ミリシーベルトは安全値ではない。10万人が1ミリの放射線を浴びたら、5人ががんで死ぬとされる。ICRPがこの数字を出している。「危険性が40分の1に見積もられている」とアメリカの化学者ゴフマンは主張。2011年のウクライナ政府報告書では、チェルノブイリで被災した250万人の調査から、がんだけでなうk、心臓病をはじめ、あらゆる臓器の病気や多種類の病気が発生していることが報告された。しかしICRPなどはこれを認めない。
…ベラルーシやウクライナでは、年間1ミリシーベルト以上の地帯は、避難権利区域。5ミリシーベルト超の地域は強制避難区域。ところが日本では5ミリシーベルトを超えても避難区域にされていない。それどころか20ミリシーベルトまでが居住可能地域とされ、避難している人びとをそおに呼び戻そうとする政策までが強まっている。
▽49 ベントは、作動の練習のしようがない。世界ではじめて福島で作動が試みられたが、電源喪失で、開かない。1,3号機は圧縮空気を送り込んで開いたが、2号機は最後までベントができず、格納容器の激しい破壊と膨大な放射能漏れを起こした。
想定外の事態に備えたこの後付け装置はうまく働かなかった。それも貴重な教訓。
▽60 政府も規制庁も避難計画に対する監督の役割を放棄し、責任を地方自治体に押しつけてしまっている。避難計画をつくれという命令と、作成をしばりつける「指針」はあっても、政府の側からは審査もしないし責任も取らない。
▽燃料プールの安全対策は、核燃料をおろして乾式管理に移行する以外にないが、それも運転から数年間のプールの中での冷却が前提になる。つまり原発を再稼働してしまうと対策の立てようがない。
□2章
▽
原子力災害に限らず、あらゆる災害への対策にも応用できる。
▽「とっとと逃げること」が核心。
▽「正常性バイアス」 危機に直面したときに、危機そのものを認めず、事態は正常だととらえてしまう心理。火災報知器が鳴っても、「これ誤報じゃないの」と思ったりする。
「集団同調性バイアス」。危機に直面したとき、判断力が働かず、周りの行動に自分を合わせてしまう。
「パニック過大評価バイアス」 危機をきちんと認識できてはじめてパニックも起きるが、正常性バイアスが強いから、危機を危機として認識できない人が多いため、パニックはそう簡単に起こらない。
2003年の韓国の地下鉄火災の例。
(阪神の震災のとき、死者100人、行方不明100人とか出てきて200人も死ぬのかと思ったが、甘かった。東日本のときも、車が流されるのを見てはじめて大きいことに気づいた。あんなゆっくりの水の流れが人を殺すとは思えなかった。希望的観測をしてしまう。)
▽71 日本人は自分を守る意識が低い。食料などの備蓄が世界で最も少ない国。
▽73 バイアスによる心理的ロックを解除するのに有効なのは、訓練。どこにどう逃げるか決めておく。シミュレーションをしておく。
▽76 ハザードマップで水が来ないとされる地域で「水害のない地域」と思い込んでしまうほうが危険。
▽79 率先的に避難を。火災報知器が鳴ったら「逃げよう」と叫んで部屋を飛び出す。そうしたら、多くの人の避難を促すことになる。火事があるかどうか確かめてから避難を開始すると、そのぶん時間が浪費されてしまう。
▽81 釜石市。津波の予想到達地域の人はほとんど逃げ出していたが、到来が予想されていなかった地域に死者・行方不明者が集中的に出た。
釜石東中は到来地域の外だったが、サッカー部員の生徒たちは「津波が来るぞ、逃げるぞ」と叫んで走り出した。隣の鵜住居小学校では3階に逃げていたが、中学生が「津波が来るぞ」と叫んで、小学生も中学生につづいた。まわりの大人もこれに従った。
…サッカー部員たちは率先避難者になった。小学生や保育園の子、お年寄りをも助けた。あらかじめシミュレートされていた。
▽88 山里の植林で山を再生したおかげで、山々の保水力が復活したことが、生活の安全性を増した。
▽94 行政としては、想定外の災害が発生しうることを考えて、早めの避難を勧告する以外ない。「空振り」になったとしても、行政の方を責めないでいただきたい。伊豆大島の災害のとき、気象庁は特別警報を出せなかった。
広島土砂災害74人が亡くなった。このときも、避難勧告を土石流の発生まで出せなかった。出したのは発生した後の午前4時半だった。気象庁は「特別警報」も発しなかった。
(〓行政まかせはだめ)
▽98 東京は世界一危険な都市。「無人機が1機、大潮の満潮時にゼロメートル地帯の堤防を1カ所破壊すれば、日本は機能を失う」と、土屋信行は指摘。
スイスの保険会社がまとめた「自然災害リスクが高い都市ランキング」。東京と横浜がセットでトップ。大阪・神戸(4位)、名古屋(6位)もトップテンに入っている。
▽102 江戸幕府の利根川付け替え。江戸を洪水から守る。利水を発展させ大規模に新田を開発する。伊達からの防衛のための大外堀としての役割。
江戸時代は、堤防決壊を防ぐため、あらかじめ決めていた場所から越流させていた。泥の流入が怖いから、越流地点には防水林がもうけられ、水の勢いを減じると同時に林に泥が落ちる仕組みが設けられた。
…これらの管理が多くの場合、地域に任された。
ところが西洋のテクノロジーは逆。明治政府は、巨大な堤防を築いて洪水を押しとどめる方向転換した。水害のたびに堤防を巨大化させ、利根川はどんどん多くの流量を抱えこみ、洪水の規模は大きくなるばかり、堤防が壊れたときの対策がない状態。破堤は「あってはならない」とされ、一度発生すれば大惨事に発展する。(原発と同じ〓)
川の管理の主体も、流域住民から地域官僚の手へ、さらに一級河川は国家官僚にゆだねられた。かつては川の管理にかかわっていた住民は、意見を述べる場もなければ、負うべき責任も亡い傍観者の位置に置かれてしまった。
□3章
▽113 米国は半径80キロ圏から自国民の退去勧告。フランスは「放射線物質を含んだ風が東京に飛んできている可能性が高いので、直ちにフランスに帰国するか東京から離れた方がいい」と勧告し、帰国者のための専用機も用意した。横須賀の米軍艦船も、次々と出航した。
近藤シナリオでは、4号機からの放出だけで半径170キロが強制移住になる寸前だった。フランス大使館の判断は間違っていなかった。(それが現実的判断〓)
…原発事故の場合は、大げさと思えても、最大級の退避行動をとったほうが無難です。
▽116 三陸海岸では、多くの町で、津波の際に避難する高台を決めてあって、それぞれが一目散にそこを目指すことにしていた。たくさんの命を全体としてもっとも効率よく守る知恵。(紀伊半島は?〓)
…いざというときに持ち出すものを決めておく。自分にとって一番大事なもの。「そこに二度と帰れないと考えた方がよい。その方が一番大事なものを持ち出せる」
…どのような手段で、どのルートを通って逃げるか。
…災害時の脱出手段が車になる方は、家に帰る前にガソリンを補充する習慣を。
▽123 福島の老人ホームであったことを取材した「避難難民」(相川祐里奈さん)。福島原発事故では、避難の途中で1800人以上の方が亡くなった。原発関連死〓。…職員がどんどん減り、利用者への介護の質は落ち、残った職員に負担が増えて追い詰められ、さらに亡くなる方が増えつつ職員が減る。
…30キロ圏内の施設には、原発事故の際の避難先を自主的に決めておいていただきたい。離れたところにある同様の施設と防災協定を結んでおく。
…不足する物質のなかでももっとも困ったことは、経管栄養剤ととろみ剤が手に入らなかったこと。
▽127 すべての人が逃げ出すことなど、とてもできない。避難弱者にとって、あまりに過酷な事故が原発事故。
▽130 政府は本当のことは言わない。「電源喪失」「冷却機能のダウン」は、即刻避難を開始しなければならない合言葉。原発敷地外で放射線値が上がったとされる場合も、何か深刻なことが始まっていると考えて、避難を開始したほうがよい。このほか、政府が避難勧告を出した場合、すでにかなり過酷な事故が起こっているのは間違いないので、できるだけ広範な地域で「とっとと逃げる」ことに踏み出すべき。
▽135 注水不能となった15条通報から2時間42分もたってから、緊急事態宣言が出た。避難指示は4時間47分も遅れた。政府は、15条が発令されたら、直ちに避難指示を出さなければならないことを知らなかった。
…危機に際しては自分の勘も大事に。「危ない」「不安だ」と思ったらその直感に従って。
▽137 原子炉は外から見えない。メーター類で制御するが、大事故ではメーターが真っ先に壊れる。福島でも電源喪失でメータ類がダウンして原発の状態がわからなくなった。…だれも把握できないまま急速にメルトダウンが進行した。メータが壊れたときも、正常性バイアスが働きがち。事態が把握できなくなっているから、すぐに最悪の場合を想定して対応するのが合理的だが、そのような判断には至りにくい。はっきり確認されてからでないと、公にされない傾向にある。
…メルトダウンを起こしていると、政府が把握したのは、事故発生から2カ月も経っていた。
(マブチの本)…それまで東電は「燃料の一部損傷」は認めていたものの、それが溶けて下に落下するというメルトダウン(炉心溶融)にいついて「可能性が低い」としてきた。
…2013年12月13日の会見では、「燃料の大半が原子炉圧力容器の中にとどまっている」としてきた従来の見解を放棄し、ほとんどが圧力容器に穴を開け、格納容器底部へと落下してしまったという推測を発表した。メルトダウンだけでなく、メルトスルーを起こしていた。…メルトダウンまでは2011年5月に把握したものの、メルトスルーが推論として出される2013年12月まで、より危険性の少ない状態として原子炉内を把握していたことになる。
…「ベントを行った1号機と3号機の格納容器は、水素漏れは起こしたものの、大きな破損はない」という立場をとってきたが、実際には、ベントをしたはずの1,3号機も格納容器が破損していた。たとえベントで放射能を含む蒸気を外に排出しても、なお格納容器が守れない場合があったことを示している。
…原子炉の状態は4年半以上経ってもはっきりと把握されていないこと、投入した冷却水がどこにどう届いているのか、ということすら把握できていない状態であることがわかる。
▽144 福山議員は、想定された最悪の事態を国民に伝えなかったが、それは正しかったと述べている。「パニック過大評価バイアス」から、目の前に迫ってきている危機を伝え得なかった。「破局は起こらない、いや起こらないでくれ」と祈っていたにすぎない。
…はっきりしているのは、危機に瀕しながら「安全だ」と言い続けたことが自己肯定され、その後にまったく追及もされないのだから、同じことが必ず起こるということ。
…危機に際して政府の安全宣言はまったく信用できないし、信じてはならない。過酷事故のときは、絶対に政府を信じず、念には念を入れた安全対策をとってください。「とっとと逃げる」行動をとってください。
□4章
▽157 半減期が長いものはやっかいだが、単位時間当たりの被曝量を考えると、短いもののほうが恐ろしい。
…被曝のメカニズム。原子同士の共有結合。そこに放射線が飛んでくると、電子がはじき飛ばされて分子が切断されてしまう。「電離作用」。だから放射線値が高いところでは、ロボットも壊してしまう。
…DNAは細胞分裂のときに二重の鎖を解き、一本の状態になるので、このときがもっとも放射線に弱くなる。激しい細胞分裂を繰り返している粘膜。放射線被曝で口内炎や下痢が起きやすいのは、粘膜がもともと細胞分裂が激しいかrあ。
脳の海馬体もダメージを受けやすい。新しい知識を書き込むために細胞分裂が激しく行われているから。被曝によっても記憶の減退などが起きやすくなる。
▽168 α線、β線、γ線。α線やβ線は到達距離が短い(その分破壊力がある)。外部被曝で内臓まであたるのはほぼγ線に限られる。これに対して内部被曝は、3つともすべてに当たる。取り込まれた場所から球状に被曝する。身体の任意の一点にウルトラ・ホットスポットができるようなもの。
▽173 内部被曝は、被曝の具体性も人体への被害もあまりに多様であるのに、ICRPは、被曝における放射線の当たり方の具体性をまったく無視し、同じエネルギーであれば、同じダメージを人体にもたらすと断言してしまっている。「シーベルト」という単位で表しているが、同じエネルギーに換算してしまうと、内部被曝の特有の危険性が見えないなってしまう。危険性が過小に評価される。
▽179 チェルノブイリの被害の見積もりの格差。世界で最も被害を小さく扱って発表しているのが日本政府。急性障害で28人がなくなり、小児甲状腺癌で15人が亡くなったとされる。首相官邸によると死亡者数は43人。IAEAが提出した報告に基づいているが、IAEAの場合、これに加えて、今後、チェルノブイリ事故の影響で死亡する人びとの数を約3960人と見積もっている。官邸のHPではこれが書かれていない。もっとも被害者を多く見積もっているのは、アメリカのニューヨーク科学アカデミーから出版された「調査報告 チェルノブイリ被害の全貌」で、105万1500人と推計している。〓
汚染地域では、1985年以前は80%の子が健康だったが、今日では健康な子は20%に満たない。重度汚染地域では、健康な子どもを1人でも見つけることは難しい。
▽185 原爆被害とにアメリカ軍は調査を独占し、軍以外による研究を禁止した。この間に、およそ10万人以上の被爆者が亡くなった。その多くのデータが、広島・長崎の被害調査に反映されなかった。
…放射線被曝、とくに低線量内部被曝の影響は著しく過小評価されている。これをもとに、原子力施設の社会的容認論が唱えられ、さらに昨今では、放射線値が十分に下がっていない福島県内の被爆地への、人びとの帰還の強制にすらつながっている。
□5章
▽ 安定ヨウ素剤。原発の5キロ圏内では配られている。
▽194 福島原発事故のとき、積極的に配布したのは三春町ぐらい。国が所管する放射線医学総合研究所が「指示が出るまで、勝手にヨウ素剤を服用してはいけない」という文書を3月14日に発表した。さらに18日には、県の「放射線健康リスク管理アドバイザー」山下俊一氏が「30キロほど西に離れれば、被曝量は1ミリシーベルト以下でヨウ素剤配布は不要」と、医師たちを前に強調した。県立医大は、県民に山下発言をそのまま伝えて、安定ヨウ素剤の服用を勧めなかった。しかし、医師たちが密かにヨウ素剤をのんでいたことが、後に明らかになった。(フライデイ)
▽195 三春町はヨウ素剤を配布。取りに来た町民に、その場で飲むことを勧めた。
▽200 ヨウ素剤が足りないときは、海産物から撮ればよい。コンブを煮出して煮汁を飲む。40グラムのマコンブからだし汁をつくれば十分の量を取れる。ただし乾燥昆布をそのまま食べると、水分を吸収して便秘になりかねない。高齢者はそのまま食べてはいけない。
▽210 大気中の放射能を防ぐには、インフルエンザや花粉症と同じ。マスクをする、帽子をかぶる、ゴーグルをする、うがい、手洗いをする。
▽213 市民放射能測定所。全国で100カ所を超えた。測定して放射能がたくさん含まれていることが明らかになったものの放射線値がどんどん下がっていった。業者側が対応した。これは測定所が各地で立ち上がった最大の功績だった。
…内部被曝を防ぐ大事なファクターとして、測って安全を確保することを重視してほしい。一度は市民測定所に食材を持って通って下さい。
▽216 1950年代から60年代の核実験の残留放射能によって、私たちの多くがすでに深刻な被曝を受けている事実。これも内部被曝の脅威を低く見積もるなかで強行されてきた。
…二人に一人ががんになる時代。寿命が延びたからと言われるが、本当だろうか。核実験による被曝の晩発性障害が出てきているのではないか。
▽218 肥田舜太郞 多少でも免疫力を上げることに効果があることは、自分に合うことを選んで一生つづける。一つでもいい。きめたものを全力で行う。放射線被曝語の病気の発病を防ぐのです。 …長老に聞いたことをまねる。「食べ過ぎない」「ゆっくりかむこと」
▽221 原発は普通に稼働しているだけで危険。アメリカのJMグールド他「内部の敵」。グールドは原発から160キロ圏内で、がんをはじめさまざまな疾病が起こっていることを、統計学的知識を総動員して明らかにした。ドイツ・連邦放射線防護庁の調査でも2007年に、「通常運転されている原子力発電所周辺5キロ圏内で小児白血病が高率で発症している」という報告がもたらされている(KIKK研究所)。
▽223 政府や原子力村によって、内部被曝を過小評価した「安全論」が振りまかれつづけている。避難を叫ぶ人、実行する人が、かえって悪いかのような言い方までがされている。被害者を加害者にすり替える悪質な言説。
▽227 大きなインパクトを与えてくれたのが、率先避難者として、決死の避難を敢行した人々でした。日本中に散っていって、その地域の人々と結びつき、地域での脱原発運動に大きな影響を与え、脱原発の声が日本中に響き渡ることに本当に大きな貢献をしてくれました。
…福島の人々がもっとも他の地域の人々を救ってきている、ということ。
□6章
▽242 有効なのは、安定ヨウ素剤の事前配布。すでに半径5キロ以内ではおこなわれているからそのやり方を踏襲できる。医師の説明が必要とされているが、その過程が、町を挙げての放射能に関する学習の場となる。
▽245 原子力災害対策を、水害や土砂災害対策とセットで話すことが大事。リアリティが増すから浸透しやすいし、地域としての災害対応力を上げることができる。
▽254 放射能に被曝して逃げた来た人がいたら…「病院には入れないでください」「まずシャワー室をつくって、放射性物質を洗い流してあげてください」「その際、使った水は流れずにすべて回収してください」
□あとがき
日本の原発がとまるなかで、それまで日本に濃縮ウラン燃料を売ってきたアメリカの大手核燃料会社が倒産した。原発を民衆がとめてきたことが、「国際原子力村」に大きな影響を与えており、世界全体が核の悪夢から脱する日を近づけつつある。




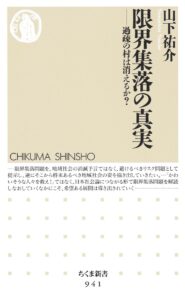
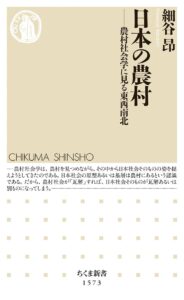


コメント