■熱狂なきファシズム<想田和弘> 河出書房新社 20141123
共感できる内容が多い。映画人でありながら、今の時代の流れを「熱狂なきファシズム」と危機感を抱き、憲法の意味について積極的に発言する。見習うべき態度だ。
さらに、彼の提唱する「観察映画」の考え方もなるほどと思う。最初に筋書きをつくって、それに合う材料を集める、一般的なドキュメンタリーではない。あらかじめ筋書きはつくらない。撮影のなかに新しい発見がある。編集作業でもあらかじめテーマ設定はしない。ピンときた断面を無造作に寄せ集めて、そのなかからわいてくる発想に基づいて構成していく。そうすれば予定調和に陥らない。一定の価値観を視聴者に押しつけることになるから、ナレーションや音楽も入れない。
文章でも同じだ。決められたデータだけを集める取材では、新しい発見はない。わかりやすくするために「ナレーション」を入れたい誘惑を感じるが、それも廃さなければ広がりのある文章にはならない。「わかりやすさ」を求めすぎると、読者が受け身になってしまう。でもどの程度までわかりやすくかみ砕くべきなのか。その加減がとても難しい。
「観察映画」の立場からいうと、マイケル・ムーアのブッシュ批判映画は評価できない。言いたいことが先にあって、それにあう素材だけをつなぎあわせているからだ。
そのスタンスも共感できる。
「永遠のゼロ」のメロドラマとしてのできを評価しつつ、その危険性を指摘した文章もおもそしろかった。
だがこの本じたいは少々退屈だった。共感できる内容とはいえ、「言いたいことがまず先行している」文章になっているからだろう。おれが自分で書いてこれ以上のものを書けるとは思わないけど。
=================
▽20 自民改憲案の分析と批判。「公益及び公の秩序」が個人の人権より優先される。「緊急事態」では、内閣が法律と同一の効力を有する政令を自由に制定できる。ナチスの全権委任法と同じだと指摘する専門家も。
▽45 日本国憲法で「公共の福祉に反しない限り」というのは、「他人の人権を侵さない限り」という意味。「個人の人権を制限できるのは、別の個人の人権と衝突する場合のみ」という考え方。
自民改憲案の「公益及び公の秩序」という表現は、「国や社会の利益や秩序」が個人の人権より大切だということになる。何が公益で、どういう行為が公の秩序に反するかという問題は国によって恣意的に解釈される恐れが否めない。
▽70 「選挙が近いから」という理由で、特定の政党名や候補者名を挙げることを自粛するテレビや新聞。法的根拠もないのに遠慮している。
▽112 死は生とセットで、死を見つめながら生きないと人間は駄目になるのです。
▽130 芸術の最も重要な役割は、既成の世界観や価値観に風穴をあけ、「世界の見え方」を更新することにある。
▽258 是枝裕和 自殺した官僚、山内豊徳を描く。もとは生活保護行政を告発する凡庸なドキュメンタリーをつくろうとしたが、山内の存在を知って、方向転換した。「水俣病患者を苦しめる冷酷非道な官僚」という紋切り型を脱した。その勇気。ふつうの記者にはふるえない。
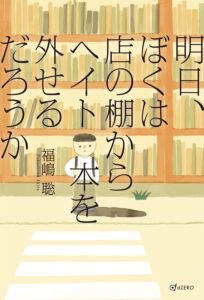
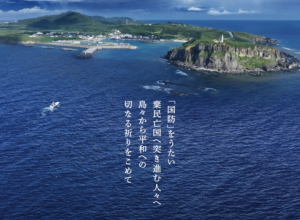

コメント