小学館文庫 20050124
久野収だったか、鶴見俊輔だったかが、こんなことを書いていた。
明治のはじめ、天皇教をつくりあげた明治政府のリーダーたちにとっては、表向き(顕教)は天皇を神としたが、裏(密教)では合理的な政策をすすめるための「道具」ぐらいに思っていた。
それが時代とともに主客転倒し、天皇を心底から崇める世代が力をもち、「道具」が本当の神になり、合理的な思考を失わせ、ついには戦争へと突き進む……
この本はその過程を具体的事実を積み上げて丹念に描いている。
国会で軍備拡張に反対されると、政府は天皇に「内廷費を削ってでも軍事費に充当したい」と言わせて切り抜ける。維新の元老たちには、天皇を思いのままに動かせる力量があった。
田原はもともと保守的な人だ。戦前を「悪」と決めつける風潮に違和感を感じている。「悪」と切り捨てることで、泥沼の戦争に陥った原因を探求する道を閉ざしてきた、と見るからだ。
負けるとわかっている戦争になぜ踏み込んだのか。そんな疑問を抱き、江戸末期までさかのぼって細かい事実を収集する。本に登場する学者の多くは保守派と色づけられている人だ。
「論」にはしらず、「悪」と決めつけず、戦前の政治家や軍人の「やむをえない」選択の積み重ねの末に破滅に陥っていくさまを描いている。
例えば伊藤博文は、日露戦争に反対し、韓国を真に独立させたいと願ったが、新世代の政治家たちに押し切られたという。軍人には選挙権がなかった、という事実も新鮮だった。
大正時代、左翼運動が盛んで、国家主義が若者に人気がないことを、右翼は危機感を抱いていた。まさに60年、70年安保の時代のようだった。政党政治は、原、浜口内閣は軍部をおさえることに成功していた。
だが浜口がテロに倒れる。満州事変という暴走がおきる。汚職が相次いで政党と財界への不信が募る。メディアも政党に冷たい。首相を決める役割だった西園寺は、政党内閣を続けられなくなった。政財界を敵とした「昭和維新」という発想が次第に力をもっていく。この過程、「平成維新」とか小泉内閣とかの流れと似ていないか?
2.26事件時には、実は経済は好転し、軍やファシズムへの国民の警戒感も募っており、クーデターを起こす必然性はなかった。「このままでは統制派にやられる」という青年将校たちの単純な思いこみによる暴走だった。
だが、事件によって、天皇や西園寺が頼みとする人物が一掃されることで、軍部が政治に露骨に介入するようになった。
その後、クーデターの恐怖によって、ずるずると軍に押し切られていく。満州事変も日中戦争もそう。
大本営設置は、本当は軍部の力を抑えるためだった。政党を解散し一国一党とした近衛新体制も、政党の足のひっぱりあいをなくし、国民的な勢力をつくることで、軍部に対抗するのが当初の狙いだった。東条を首相にしたのも、「毒をもって毒を制す」との意図があった。だが、すべては裏目に出た。
帝国議会さえも有名無実化してしまう国家総動員法案では、さすがに議会は紛糾したが、クーデターの噂がひろまり、政友・民政両党本部が右翼に占拠され、社会大衆党の委員長が襲撃されるなか、政党が萎縮するかたちで成立した。革新官僚と軍部が結託し、近衛人気を利用したもので、政党と経済界の強い抵抗を押さえ込んで実現させた。
その後は、国際情勢についての情報力のなさ、軍部の暴走などが重なって、軍部でさえ勝てると思っていなかった日米開戦に至ってしまう。
軍は戦争をしたがる組織である。軍があることで歯止めがきかなくなる。愚かな政治家ばかりだったとしても「民主主義」のシステムを維持することの大切さを思う。
------------------------
□和魂洋才・富国強兵
▽不平等条約改正は、日清、日露戦争に勝った後。
▽福沢諭吉 官軍との激闘を前に江戸城は騒然となった。そのなかで諭吉は「戦いになったら、自分はいち早く逃げ出す」と公然といってまわり、主戦論派が怒るのをおもしろがっていた。「学問のすすめ」のなかで独立心について「・・・国の中で独立した境地にない者は、外国人に対しても独立の立場では接することができない。独立の気力がない者は国を売るなど、悪事を働くおそれがある」と「一身独立して一国独立す」と説いた。忠義忠臣を、痛烈に批判する。忠君などというものをまるで問題にしていない。和魂=忠君愛国にはなっていない。
▽源氏物語では「大和魂」は世渡りの術、処世術、生活の知恵といった意味だった。……本居宣長によって再発見された平安王朝的な「やまとだましい」を、一挙に「雄武」なるものに転せしめたのは、平田篤胤だった。
西郷や大久保、木戸らは、徹底して現実主義的であり、天皇も将軍も攘夷も開国も手段でしかなかった。だからこそ、幕府を倒したあとは、大開国主義に転じた。維新後の幹部らは、「和魂」など考える余裕もなく、あらゆる面でひたすら洋才であり、精神も理論もすべて欧米追随だった。
▽伊藤博文が、明治21年に帝国憲法制度の根本精神について所信を開陳した。西欧の国々には、キリスト教という機軸があったが、日本にはそうした宗教はない。だから皇室崇拝を新国家の機軸にしようと力説していた。いわゆる天皇教のルーツはここにある。 憲法では、天皇崇拝、忠君愛国は徹底し得ないと不安がった。教育という切り口で、天皇を頂点とする道徳体系で国民を縛ろうと考えた。それが、超法規的に国民をしばる戒律、教育勅語だった。
□自由民権
▽龍馬は二院制の議会を考え、「庶民」参加まで考えていた。龍馬が生き続ければ、普通選挙がもっと早く導入され、天皇は現在のような象徴的存在となっていたはず。
▽自由民権運動には地租の軽減を求める地主層も流れ込んだ。政府は、新聞紙条例や讒謗律で言論弾圧をした。さらに、集会条例を公布し、集会を警察官を解散できるようにした。
▽自由党など野党は、1892年の総選挙でも、与党の137人に対し163人と多数を制した。海軍の造艦計画に反対したが、天皇に「朕ここに内邸の費を省き(内邸の予算を削っても)」などという詔勅を出させた。野党は屈服した。
□帝国主義
▽政府が行き詰まると天皇を使うのが維新政府の常套手段だった。
▽日清戦争は、日本が強引に策謀をめぐらせて戦争に持ち込んだ。だが伊藤にも陸奥にも侵略戦争という認識はなかった。韓国が列強から侵食されれば日本にとって大脅威になるから、日本が韓国を保護し、面倒と見なければならないと、確信していたはずだ。
▽日露戦争は侵略か防衛か 伊藤はロシアと戦争をするのは反対だった。日英同盟にも待ったをかけた。勝てるわけがないと思ったからだ。だが、小村や桂らの第二世代に押し切られた。マスコミも、非戦と主戦論が交錯していたのが「戦争やるべし」にかわっていく。「反戦」報道では、部数が激減したからである。
▽日露は日清の10倍以上の戦死者。奉天の会戦で勝利したが、兵も弾丸もつき、児玉源太郎は「一刻も早く戦争をやめてほしい」というために帰国した。日本海海戦も完勝したが、海軍幹部らは、日本の体力の限界だとわかっていた。ロシアは、少なくとも陸軍に関しては敗北感はなく、逆転勝ちを考えていた。が、第一次ロシア革命という内憂によって戦をやめた。だから、敗北意識はなかった。
▽日韓併合 韓国で反日運動が盛り上がった1895年、日本の軍隊と壮士たちが、大院君を連れ出し、王宮に乱入し、ミンピを虐殺した。1904年。
伊藤は「自治育成政策」で、韓国の国家としての近代化・文明化を本気ではかろうと考えた。だが、抗日運動はますます激化した。韓国の皇帝は、そうした運動を裏で支えた。伊藤がいくら韓国のため、と考えても、その政策の中心には日本人がおり、韓国人には日本人がやりたい放題やっているとしか思えなかった。日本政府の中枢のほとんども、韓国経営は日本の国益のためと考えていた。伊藤は無惨に孤立した。
1907年の第3次日韓協約で、総監は事実上韓国の統治主権者(独裁者)となった。外交権も内政権も奪ってしまった。1909年は伊藤はハルピンで狙撃されて死亡。1910年、韓国併合条約が調印された。
□昭和維新
▽日本では左翼運動が盛んで、国家主義は学生・若者たちにまるで人気がないことに、右翼の大川周明らは危機感を抱いていた。
▽明治憲法体制では、天皇に拒否権があるが、実際には使えない。意見がまとまらないとき、まとめたのは、元老だった。だが大正中期には元老たちは力を失った(大正11年、山県有朋死去)。元老に近い役割を果たしたのが政党だった。
原敬は衆議院を押さえただけでなく、軍の中にもシンパをつくっていた。浜口雄幸もよくやった。だが2人ともテロの犠牲になった。原と浜口の時代が、政党内閣(政友会と民政党の二大政党)の全盛時代だった。
原も浜口も軍部を押さえていた。軍隊はあくまで防御技術者集団だった。だが、浜口がテロに倒れた翌年には満州事変という軍人の暴走が起きている。政党政治は急速に色あせ、どう見ても政党が維新の担い手には見えなくなっていった。
▽世界恐慌に対して、政府が有効な手だてをとれなかった。
1930年のロンドン軍縮条約で、米英10に対して日本が7を求めたが、達成できなかった。海軍のなかに不満がたまり「政府が勝手に調印したのは統帥権の干犯だ」と攻撃した。そのとき、野党の政友会が海軍の味方をして「統帥権干犯だ」と主張し、軍の政治への介入を誘導する役割を演じてしまった。このときの政友会総裁は犬養毅だった。この騒ぎのなかで1930年11月、浜口首相は狙撃された。
▽5.15事件。幼稚なテロだったが、影響は深刻だった。当時、最後の元老の西園寺公望が首相を決める役割だったが、政界財界人はテロに脅え、マスメディアも政党政治に極端に冷ややかで、政党内閣を続行させられず、海軍大将の斎藤実を首相にせざるをえなかった。
▽斎藤内閣は農村救済に力を入れ、32年の臨時議会で、1億7千万円の農村救済予算を組み、土木工事や桑園整理、米国貯蔵倉庫設置などの助成をおこなった。35年には農村不況はほぼ解消した。高橋是清蔵相の低金利政策によって、35年には、恐慌の傷跡はきえ、高度成長に向かって走り始めた。
▽33年の国際連盟脱退。松岡は交渉に失敗し本人も失望していたのに、日本では凱旋将軍を迎えるのような喝采が待っていた。
当時の列強は、満州問題に介入する気持ちはなかった。ソ連は、日本の脱退の寸前まで、日露不可侵条約を結ぼうと提起しつづけていた。それを断ったのは日本側だった。
イギリスが35年に中国の貨幣制度改革をやるとき、英国は、日本も一緒に金を出さないかと言ってきた。条件は中国に満州国を黙認させるということだった。だが、これも日本は断ってしまう。
明治の政治家たちは、コトを行うときに、必ず事前に欧米の国々に謙虚に相談し、了承を取り付けている。だから、日韓併合でさえも、欧米の国々の支持が得られた。ところが満州事変以後、政府は、欧米の国々への配慮も相談する謙虚さも失って独走している。その結果、世界で孤立し無惨な敗戦を迎えたのだった。 ▽昭和に入ると言論は封殺されていたと思いこんでいたのだが、少なくとも日中戦争が勃発するまでは、制限付きの言論の自由は生きていた。
軍部批判を軸として、政民連携政権を作る動きもあり、実現しそうだった。が、帝人事件が起きた。財界人たちが、次々に拘引された。斎藤内閣は総辞職に追い込まれた。事件は、政財界の信用を決定的なまでに落とした。だが後に、帝人事件の関係者は全員無罪となった。
▽天皇機関説 35年、激しく攻撃し始める。もっとも激しかったのは、皇道派の真崎甚三郎だった。彼は、天皇機関説の自由主義的な匂いが気に入らなかった。具体的には、西園寺公望や牧野伸顕内大臣たち重臣らだった。さらに、軍や右翼は、政党政治をつぶしたかった。岡田内閣は当初、攻撃をいなそうとしたが、議会第1党の政友会までが機関説排撃を始めた。民政党よりの岡田内閣を倒そうとはかった。「政府は崇高無比なる我が国体と相いれざる言説に対し直ちに断固たる措置を取るべし」という「決議案」を可決させてしまった。衆議院と政党政治の論理的根拠となっていた機関説を否定することは、政党にとっては自殺行為だった。
▽2・26の青年将校の話には、農村が悲惨な状態だとか、労働者が苦しみに喘いでいるといった具体的な事実は全く出てこない。きわめて観念的に、政党、財閥、重臣、軍閥などを非難しているだけ。35年には、経済は高度成長に向かって進み、クーデターなど起こさなければならない状況ではなかった。
36年2月20日、事件の6日前。総選挙では政友会は70議席減の171議席、反皇道派の旗幟を鮮明にしていた民政党は78議席増の205議席、さらに、5議席しかなかった社会民主主義政党が22議席と躍進した。国民は政党政治に愛想づかしなどしていず、軍ファシズムにこそ強い拒絶反応を抱いていた。
ではなぜ2.26は起きたか。「青年将校たちが追いつめられていた。このままでは統制派の天下だと」「彼らは社会の仕組みや問題点など何も知らなかった。そういう軍人たちがプリミティブな思いこみで、今の体制は悪いとなって、それが武器を持って兵を動かせるのだから危なくてしょうがない」(北岡伸一)。
▽2.26クーデターを起こす必然性は、政治・経済・社会情勢を点検する限りでは皆無といってもよかった。若い将校たちは北一輝などに洗脳された思いこみゆえに暴走した。だが、この事件の影響はきわめて大きかった。軍部は露骨に介入するようになった。事件が、天皇や西園寺が頼みとする人物を一掃してしまったからである。
▽事件翌年の37年7月、日中戦争が勃発する。だが、37年4月の選挙では、政友会は現状維持、民政党が議席減のなかで、社会民主主義政党が22から38議席に躍進した。軍部独裁色が強まり、日中戦争に突入へと直線で結びがちな時代に、実は冷静に軍部の跳ね上がりを苦いまなざしで見ていた国民が少なからずいた。だが、戦争が始まって、言論の自由も、資本主義も、何もかもが吹っ飛んだ。
▽石原らは、政府が全面撤退の方針を出せば、国籍を離脱してでもたたかう、と広言していた。さらに、橋本欣五郎たちのクーデター計画が露呈。もしも政府が不拡大政策に固執したら、クーデターで閣僚らを殺すことができるぞ、と示した。この恫喝は効いた。 幣原、若槻コンビは、政府を守るためにやむをえない判断だったのだろうが、国際的にも国内的にも明かな政策転換だと受け取られた。
石原は、柳条湖の謀略、吉林出兵、朝鮮軍の越境、錦州爆撃と、政府の不拡大政策を次々にぶちこわした。
▽天皇も関東軍が華北に攻め込むことを危惧していた。一度は停戦。それから37年7月の廬溝橋事件までの4年2カ月は、日中間の武力衝突は起きていない。したがって「15年戦争」というのは間違いだという説もある。
▽軍中央が「戦線拡大路線」をなぜとったか。一度軍事的痛撃を与えれば、中国側は抵抗を放棄するはずという、根強い中国蔑視があったのだろう。天皇に「本格的出兵をした場合、決着までどれくらいかかるか」と問われて、閑院宮参謀総長は「3カ月くらい」と答えていた。石原とその少数の部下だけが、「無益な持久戦争になる」と蒋介石の中国を正確に読んでいた。
廬溝橋では、現地の幹部は「不拡大、現地解決」方針で一致していた。現地軍が突っ走った満州事変とは正反対の構図だった。停戦協定もすませた。ところが、「内地から3個師団、満州から2個師団、朝鮮から1個師団の派遣を決めた」との知らせが届いた。
石原は不拡大論だったが、「国民党の正規軍が大量に北上している」という情報を示されて、「派遣やむを得ない」と判断した。が、それは偽りの情報だった。石原は「不拡大」のためにがんばり続けたが、孤立した。拡大派に「自分たちは満州事件における石原を模範にしている」といわれ、言葉を失ったという。
▽対ソ戦のため陸軍は軍備拡張していたが、ソ連の5カ年計画の成果がわかると、すぐには戦争できない状況だとわかった。そこへ廬溝橋事件が起きた。「中国ならたやすい」ということになった。…エネルギーが溜まりに溜まって、戦争しないで5年6年待たせるというのは、軍の立場からすれば非常識だった。
▽なぜ中国戦線はメドもないのに深入りしたか。秦郁彦「司令官とか師団長とかが新しく赴任するごとに、勲章や昇進狙いで、戦略的には意味のない新しい作戦をおこなった」
▽近衛内閣 米国との戦争にいたっては、はじめから勝てる見込みはなかった。全輸入額の34%が米国からで、とくに石油は80%を依存していた。なのになぜ。
内閣は軍情報があがってこない。閣議で閣僚がその不満を述べ、海相が説明すると「こんなところで、そういっていいのか」と杉山は怒鳴りつけた。閣議が「こんなところ」と一蹴された。
▽統帥権の独立を名目に、軍は作戦について政府にほとんど知らせず、閣議での報告は、新聞報道より遅かった。
近衛は内閣を投げ出したい衝動に駆られながら大本営を作るべく努力した。日清戦争のときに大本営をつくって、首相の伊藤博文や山県有朋が采配をふるった前例があったからだ。だが、できた大本営は、陸海軍は「統帥権独立」を盾に首相や閣僚が入るのを断固拒んだ。妥協案として、大本営と政府との間に連絡会議が設けられたが、形式的な機関にすぎなかった。
▽1935年、国家総動員法案を出した。戦争に準ずべき事変となった場合、国民の徴用、不動産、商業取引、物価、言論・表現まで、すべてを管理、統制できることになり、運用によっては帝国議会さえ有名無実化することが可能だった。 議会は紛糾したが、クーデター計画の噂がひろまり、政友・民政両党本部が右翼に占拠され、社会大衆党の委員長が襲撃されるなか、政党が萎縮するかたちで、国家総動員法は成立した。革新官僚と軍部が結託し、近衛人気を利用したもので、政党と経済界の強い抵抗を押さえ込んで実現させた。憲政史上初めての憲法違反ともいえる強引な改革だった。
▽近衛は、自由経済も複数党による政治も否定し、ヒトラーやスターリンのような全体主義国家建設をはかった。右翼からも左翼からも支持された。資本家、経営者、それと結びつく政治家を敵視。近衛をトップに据えた無血革命を国民をあげて期待した。
「近衛新体制運動」は、私利私欲による資本主義をやめ、経済に動かされる政治から、政治が経済を動かすという体制に切り替えることだった。露骨な貧富の格差や、金がらみのスキャンダルにうんざりしていた国民の多くが「変革」を強く求めた。
▽軍部を抑えるには、国民に根ざす強力な組織をつくり、それに軍部の活動を統制する法的権限を与えるしかないと近衛は考えていた。既成政党を破壊して1国1党にするのも、政党が足のひっぱりあいをして軍につけ込まれないためだった。
▽仏蘭がドイツに降伏して、蘭印・仏印が「空家」になった。まもなくイギリスも幸福するだろう。ドイツイタリアが領有してしまわないうちに、日本が駐留占拠して既成事実を作っておこう…と考えた。「バスに乗り遅れるな」が流行語になった。陸海軍も全面的に賛成した。
▽海軍は「対米戦争」に絶対反対すべきだったが、それをしなかったのは、「予算の拡充」を狙ったためだった。後に日米開戦への最終場面でも、海軍は「予算」ほしさに「対米戦反対」を表明しなかった。国益よりも省益を重視した。
▽松岡洋右は、日独伊三国同盟にソ連を引き込んでアメリカ孤立化を図り、有利な条件で日米関係の修復をはかろうとした。だれもアメリカと戦争を始めるつもりなどなかった。
だが独ソ戦が始まって、アメリカは交渉で強気に転じた。そんな時期に、「帝国国策要綱」を決め、「世界情勢変転の如何にかかわらず大東亜共栄圏を建設し、世界平和の確立に寄与する」「自衛の基礎を確立するため南方進出の歩をすすめる」「本号目的達成のためには対英米戦争を辞せず」と記した。乱暴でめちゃくちゃで勝手な理屈。
陸海軍はじめ日本政府幹部は、南部仏印進駐がアメリカをどれだけ怒らせるか、という情報をまるでつかんでいなかった。情報収集において決定的に劣っていた。
アメリカとイギリス、蘭印は、経済断交。日本は石油の8割をアメリカに、2割を蘭印やボルネオに依存しており、1滴も入ってこないことになった。石油貯蔵量は1年半しかもたないことになった。
「このままでは石油は1年半しかもたない。戦争の時期が遅れるほどじり貧になる」と陸海軍は対米戦を主張した。
木戸「(天皇が開戦に)反対であることはハッキリしているけど、それをやっちゃいかんということをおっしゃるわけにはいかない。・・・それでなかったら、カイザーやヒトラーみたいになってしまうんでね」。
▽近衛を含めた5人のなかで「開戦に踏み切れ」と明確に主張したのは東条1人だった。だが、東条の反対を抑え込んで日米交渉続行を決めると、東条は陸相をやめ、陸軍がかわる陸相を出さず、近衛内閣が崩壊することは、誰よりも近衛が一番よくわかっていた。
▽近衛の後継に、東久邇宮の名があがった。軍部を抑え込む点では、皇族内閣がいい、という判断だった。だが、天皇や木戸は猛反対してつぶした。「非常時に皇室が直接責任をとることになるのはよくない」という判断だった。日本が負ける場合を想定して、敗戦の責任を負わされ皇室が崩壊することを怖れたのではなかろうか。
木戸は、東条を首相におした。軍部の暴走を抑え込めるのは、陸軍で一定の信望を得ている東条しかないという理由だった。首相が軍部に反対すると、陸海相をおろして代わりを出さず、内閣が崩壊してしまう。だが東条が陸相を兼ねれば、思い通りのことができる。「毒をもって毒を制す」。現役軍人が首相につくのは明治以来はじめてだった。
クーデターや政府要人暗殺を恐れ、特高や憲兵隊を動員し、はねあがり分子を徹底的に抑えようとした。不幸なことに、開戦後はそれがそのまま、東条と考え方を異にする人物たちを取り締まることになった。
東条のもとには「米英撃滅」「弱虫東条」といった批判の手紙が3千通以上来た。東条も、戦争を強引におさえたら、内乱がおき、自分たちを全て殺して無秩序に戦争に暴走すると恐れたのだろう。
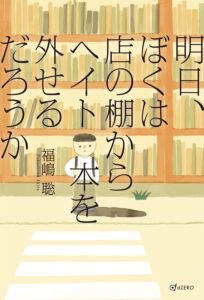
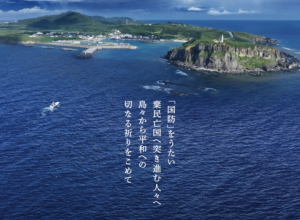

コメント