新潮文庫 199907
1988年、グアテマラの古都アンティグアに僕はいて、ドニャ・ルイサという喫茶店に通っていた。「戦争をみたい」といいながら、毎日ケーキを食べ、ビールを飲み、ノミがいたとはいえ、白いシーツの上に寝ていた。
92年に行ったときは、夫を奪われた先住民族女性の団体を訪ね、すさまじい人権弾圧を初めて知った。でも表面だけ。民政移管などうそっぱちだ、実質は軍 が力を持っていると知識でわかっていても、実感を伴わない。歴史上の体験談を聞くような気持ちでインタビューしていた。
そのころ、著者のジェニファー・ハーベリはゲリラの前線基地を訪問し、伝説的な司令官エヴェラルドに出会い、恋に落ちる。
軍の捕虜になって戻ってきたものはいない。拷問され、殺されるだけだ。虐殺の対象は、労働組合や学生、貧しい人を助ける教師や医師、教会のカテキスタ(伝道師)に及ぶ。エヴェラルドもかつて2人の恋人を戦闘と拷問で亡くし、多くの同志を失っている。
和平交渉のため、エヴェラルドはメキシコに出てくる。そこで再会し、テキサスの著者の故郷も訪ね、結婚する。つかの間の新婚生活のあと、エヴェラルドは 山に帰り、まもなく戦闘で行方不明になる。92年3月のことだ。その2カ月前、僕は彼が行方不明になった場所から40キロほどの村で、先住民族のおばさん の織物を見せてもらっていた。
軍の発表では「死亡」とあったが、エヴェラルドは捕らえられ、すさまじい拷問を受けていた。
著者は、エヴェラルドの行方を求めて、警察や軍の妨害や脅迫にあいながら、埋められたとされる遺体を発掘し、単身国防省に乗り込み、ハンストを決行する。軍は「ほかに女ができたのでは」、米国大使館も「要請はしているのだけど、わからない」の繰り返し。
だが後でわかったのは、エヴェラルドが捕らえられた時から、米軍とCIAは把握し、軍と共同で情報を吐かせようとしていた。米国は虐殺者とグルだったの だ。また、毎年何百人という人が権力の手によって捕らえられ拷問され殺されているのに、「人権」を標榜しているはずの米国は軍事援助さえやめようとしな かった。大使館の冷淡さと米軍トップの冷酷さに沸々を怒りがわいてくる。
だがここでふと気づく。日本はどうなのだろう。
内戦が終わるずっと以前、形だけの「民政移管」以後、ODAをばらまき、青年海外協力隊を送り込んできた。虐殺事件の現場のすぐ隣の村で陶芸を教え、拷 問を受ける人々がうめく施設の間近で農業を指導し、ODAで建設した道路を軍用車両がぶっ飛ばす。協力隊の個々人が悪いのではない。僕も、虐殺の村のすぐ わきでビールを飲んで踊っていたのだから。
虐殺の実態と「平和」な援助との冷淡な乖離と、そうした想像力欠如状態を意図的に作りだし、利用する確信犯(もしくは米国への従属犯)が日本にもいることが一番怖いことなのだと思う。
一方、死を間近に生きる仲間との琴線にふれるエピソードも盛り込まれている。 みなでローソクを囲み、亡くなった人々の思い出をかわるがわる語り、さめざめと泣く。そうやって死んだ人を自分の心のなかに生かし続けるのだ。
死者を大事にするからこそ、生をいとおしむと闘いに命をも差し出す勇気もわいてくるのだろうと思った。
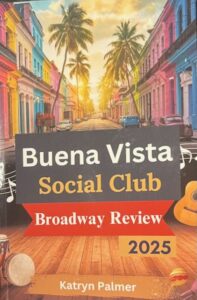

コメント