■キューバへ行きたい<板垣真理子>20171227
▽26 ヘミングウエイは革命前のキューバ共産党にもっともカンパした外国人だった。バチスタの再三の食事の招待にも応じなかったという。
▽31 サンティアゴ・デ・クーバは、1514年につくられ、1522年から1589年まで首都だった。海賊の集まる場所となり、フランスやイギリスが占領した時代もあった。
1804年、世界で最初の黒人の国としてハイチが独立。農園主がキューバ東部に大挙して渡ってきた。
▽32 セスペデス公園では毎週末に無料のコンサートが開かれていて…
サンティアゴの西20キロには、コブレ教会がある。聖母が祀られていて、ヘミングウェイの「老人と海」に出てくる教会のモデルになった。
▽39 トリニダ 建設は1514年。…見渡したいなら、革命博物館の塔の屋上。オレンジ色の瓦屋根と、遠くエスカンブライ山脈まで見渡せる。
この街の飲みものは、カンチャンチャラ。ラム酒に蜂蜜(糖蜜)とライムジュースを氷と一緒に混ぜたもの。
▽42 シエンフエゴスは、19世紀にフランス領だったルイジアナ州が、合衆国に組みこまれたため、多くのフランス系の人が移住してつくった街。フランス風建築も多い。
▽48 ハバナは、ポルトガルや英仏などヨーロッパ列強や海賊たちの標的となったため、堅牢な要塞が海岸線に次々築かれた。…1804年、仏領ハイチが独立し、つづいてラ米の植民地が次々と独立するなか、スペインはキューバを「最後の植民地」として死守しようと圧政をつづけていた。
▽ 1868年、セスペデスが武装蜂起して独立を宣言。マセオ将軍に引き継がれた。「第一次独立戦争」は10年に及んだが、スペインに鎮圧された。
1892年、ホセ・マルティがNYでキューバ革命党を結成。95年から第2次独立戦争。独立軍は勝利目前となったが、アメリカが介入し、米西戦争に発展。1902年に独立を達成するが、アメリカの支配下に入った。
▽50 ソン アフリカルーツは太鼓のリズム中心。スペインルーツはギターや歌。それらが合体した代表的なものが「ソン」。
トレス(複弦3対をもつ小型ギター)と、ギター、ベース、クラベス(木製の拍子木)、マラカス、ボンゴ、トランペット。
▽52 アフリカにわたって、1960年代後半、爆発的な勢いで広まった。「アフリカのソン」
キューバのソンがアメリカに渡ってジャズと影響を与え合ってNYで生まれたのがサルサ。
▽54 ルンバ 歌は、ソンとはちがい、アフリカを彷彿とさせる地声の魅力で、太鼓と響き合う。…ルンバの源流は「サンテリーア」にあると言われる。ナイジェリアからベナン共和国の一部に暮らすヨルバの民のもつ多神教。
▽50 アフリカ文化が顕著に残っているのがブラジルやキューバにある、ヨルバ系の文化であり、宗教である。ブラジルではカンドンブレ、キューバではサンテリーア。
▽ 67 ソ連崩壊による打撃。人々の生活と同様、精神的生活にもゆとりをもたらすことが必要になり、1991年に開かれた第4回共産党大会で、宗教信者の共産党入党が認められた。翌年、「宗教的自由の保障と政教分離」が改正憲法で定められた。
▽72 シンクレティズム(宗教混淆) ハバナで近い場所では、旧市街からフェリーで渡った「レグラ」がある(行かなかった!)
…教会内部にはさまざまにシンクロした神々の像もある。愛の女神オチュン(オシュン)もマリアのひとりである、カリダのマリア(慈愛の聖母)とシンクロしている。
…サンティアゴ郊外のコブレ教会。キューバの守護神が祀られていて、その姿は黄色い。オチュンと同様。カリダのマリアと結びついている。
▽95 キューバ人は集うのが好き。路上で、窓辺で、公園で…気楽に人を家に招待したり泊めてあげたりする。…冗談が好き、音楽好き、歌も好き…踊りも好き。「歌って踊れてラム酒が飲める国」
▽102 有機農業
スペシャル・ピリオド。トラクターや石油、農薬を必要としない、最新の研究に裏づけられた有機農業がはじまった。
キューバの有機農業をあらわす「オルガノボニコ」(ハイドロボニコ=水耕栽培にオルガニ=有機をくっつけた造語)
▽109 「自給率が高まり、以前は米国的な肉食中心の食生活が根づいていたが、野菜中心の食事になったことで、キューバの成人病(心臓病、糖尿病、高血圧)が減ったんだよ」
▽112 医師の数は2008年で7万1000人。10万人に対して600人の医師がいる。日本の倍以上。乳幼児死亡率は1000人に対して5.3人で合衆国の10分の1。
▽ ハイチには2010年の地震が起きる以前にも340人の医者が常駐。地震後は1000人近い医師を送っている。
…海外派遣の医師は、国内では「月何百ドルか」の貯金もされるが、それでも他国の高給の誘惑に勝てずでていく医師もでている。
▽114 識字率 革命前は23%だったのが、識字率も就学率も100%に近い。
▽年表 121 アンゴラ独立失敗後、混迷の地にキューバ軍を長期派遣。1988年の和平協定以降「革命の輸出」はやめ、医療援助などに転じていく。
1992年 危機を越えるためあらゆる政策が講じられる。有機農業とそれに伴う国有農地の民間(協同農業生産組合)への解放もそのひとつ。ドルの所持、自転車の奨励、観光客の誘致…
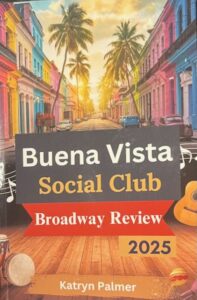

コメント