岩波書店 2001/1
1988年、はじめてグアテマラに行ったとき、マヤの人々は暗い、という印象を持った。
91年、前年に軍を住民達が追い出した町を訪ねたらみな明るく、あけすけに外国人に語りかけてくれた。3年前にもすぐ近くの村に行ったことはあったが同じ住民とは思えなかった。
なぜ「マヤの人は暗い」というイメージになったのか。その裏にある殺戮の経験が、これでもか、とばかりに出てくる。自分の家族が殺され、それを告発すれ ば殺されるから何も言えず、自分自身も人を殺すことを強制される。さらに、先住民族を動物扱いし、抹殺する思想が加わる。
さまざまな虐殺や強制連行があることは、その後の取材で見えてきた。だが、大学を出た超エリートが社会学や心理学、コンピューター技術を駆使して、反政 府の動きをとらえ、虐殺対象を選定し、拷問のやり方、殺し方までマニュアル化しているとは思わなかった。
例えば、新人の兵士にはまず囚人監視をさせ、次に誘拐部隊、さらに囚人の殴打、拷問観察、最後に殺害を実行させる。こうして従順な人物が残虐な工作員に転化していく。
優秀な官僚が最先端の学問と技術を使って殺戮の計画を練り上げ、まじめな兵士や自警団に組織された男たちが、人殺しの実行部隊となる。ナチのアイヒマン裁判を描いた映画「スペシャリスト」を彷彿させる。
バブルの時代に庶民に大金を無理に貸し付け、バブルがはじけると裏金融に債権を売り払い、借りた庶民を自殺にまで追い込む銀行員。他社との競争、上司の 評価を強いられることで被害者の家にまで踏み込むマスコミの記者。どちらも同じだ。命令をまじめに実行して中国人を殺しまくった日本兵も同様だ。
僕が一時かじっていた文化人類学でさえ、マヤの人々を殺戮し、村を崩壊させる方途として利用されていた(もともと侵略者の学問なんだけど)。学問を専門 化するのは大切だけど、生きていく上で何を大切にしなければいけないか、という部分が抜けてしまったらどんな専門知識も意味がなくなってしまう。
一方、80年代を通しての殺戮の歴史の中から、抵抗の芽も現れる。
それまで、23(だったったけ?)の言語に別れるマヤ先住民族には、「マヤ民族」というアイデンティティは希薄だった。それが、極貧からの解放と土地を もとめる闘いのなかで、「先住民であるが故に迫害される」という認識にたどりつく。90年代初頭は、先住民族としての集団的アイデンティティが明確に現 れ、権利運動が山場を迎える時期に当たる。
抵抗運動を担う主体は女性だった。
支配層は、軍と準軍事組織を通して「男性性」を鼓舞することで、強姦や殺戮まで人々を追い立てた。女性を殺し、強姦することは、口承でつながっていた文化を根絶やしにすることを意味した。女性性の排除は文化とコミュニティの崩壊を意味した。
一方、男が殺されるなかで、女たちが家族の長として自覚し、自尊心をもつに至る。強制失踪の恐怖を乗り越えるには、失踪者を探すことこそ唯一の方法であ り、人権をまもる闘いのもっとも力強いものとなった。失踪者の母・妻・娘・姉妹こそが社会を支配する暴力に敢えて立ち向かっていった。そうしてできあがっ たのが、「コナビグア」(連れ合いを亡くした女性の会)だった。それらの組織が、首都における組織的な抗議行動に発展するのは80年代後半になってから だった。
「女性問題」とか「フェミニズム」というのはそれほど興味がないし、何かというと「女性」を社会問題の切り口にするやり方はあまり好きになれないが、グ アテマラにおける「虐殺と再生」は「男性性vs女性性」と捉えられると思う。日本軍の蛮行もまさに男性性の現れだったのだろう。生命の論理と暴力の論理と のせめぎあいとも言えるかもしれない。
今まで6,7回グアテマラを訪ねて取材してきた、先住民族の人々の経験の断片が、もっともっと深い部分で一つになり、大きな流れとして見えてきた。というより、自分の取材の浅さが恥ずかしくなった。
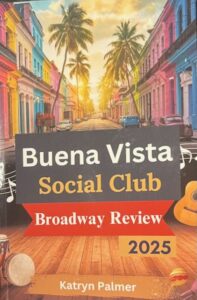

コメント