■知的生産の技術 <梅棹忠夫> 岩波新書 20110102
25年ぶりの再読。以前ラインを引いたところとまったくちがうところに心を動かされる。それだけ成長したのかな。それとも感性の退化か。
25年前の書きこみのなかんは、はずかしくなるような内容も。日本の手紙の形式をそろえるべきだ、という筆者の文章にたいして「おまえは全体主義者か」などと。私こそ、人を「全体主義者」か否かで二分するようなごりごりの感性(全体主義的な感性)だったんだなあ、とおどろいた。
パソコン時代になり、漢字変換ができるようになって、ひらがな化やローマ字化はもはや必要なくなったが、基本的なかんがえかたの部分はまったく古くなっていない。メモのとりかた。抜粋のしかた、論理のつくりかたなど、とても参考になる。
でも下記の書き抜きは、彼の文章を引用しており、独走部分をメモするという梅棹式にはなっていないんだよなあ。
=================
▽25 ダビンチはメモ魔だった。……わたしたちが手帳に書いたのは「発見」である。それも、短いフレーズではなくちゃんとした文章でかく。がらくた的な経験や知識がいっっぱいかいてある。
▽29 「発見」は、できることなら即刻その場で文章にしてしまう。みだしだけかいて、何日もおいておくと「発見」は色あせて、しおれてしまう。発見の感動がさめやらぬうちに、文章にしてしまわなければ、永久にかけなくなってしまう。
▽72 オープンファイルのフォルダーにいれるという操作も、台紙にはる、というのと同様、一つの規格化である。オープンファイルの棚は、新聞きりぬきの収容庫というだけでなく、いまでは、本とカード以外のすべての資料を収容する資料庫となっている。
▽82 蔵書は、UDCを基礎とした分類法で配列している。つんではいけない。かならず、たてる。
▽93 知的生産のための空間の機能を分化させる。仕事場と「事務所」と、資料庫と、材料置き場の4種類。仕事のための机と、事務のための机と、本棚およびオープンファイルの棚と、あとは材料のおき場をかんがればよい。机は2つあったほうがよい。
▽105 平均して週に2冊も本を読まない。1年間に100冊にもならない。本は一気によむ。ラインは鉛筆でひく(なるほど!)。読み終えたらノートをつける。
できあがったカードは、読書ノートではない。知的生産の素材だ。1冊の本からつくるカードはふつう3枚から30枚くらい。
よみおわって、鉛筆で印をつけた本は、しばらく、書斎の机の上に、つみあげてある。
▽113 読書ノートにかくのは、「わたしにとっておもしろいこと」であり、「著者にとってだいじなところ」はいっさいかかない。「わたしの文脈」のほうはシリメツレツであって、瞬間的なひらめきだ。これをしっかり定着しておかなければならない。読書においてだいじなのは、著者の思想を理解することで、自分の思想を開発し、育成すること。
▽116 引用の多い論文をかくには、はじめから本をよむときに「引用してやろう」という身がまえでよんでいる。わたしのようなよみかたでは、メモをとるのも「わたしの文脈」においてであって、著者のそれではないから……縦横に引用して何かをのべる、というのはじつはあまり生産的なやりかたとはおもえない。本は何かを「いうためによむ」のではなくて、むしろ「いわないためによむ」のである。どこかの本にかいてあることなら、わたしがまたおなじことをくりかえす必要はない。
▽152 手紙 形式が否定されてしまうと、各人の責任において、いきいきした名文をかかねばならなくなった。……形式を排して、真情吐露をとうとぶという風潮は、結果に置いては、手紙を一部才能人の独占物にしてしまった。普通の人間が手紙の機能をうばいかえすには、形式を再建するほかない。(〓型や構造の大切さ。中身は型によってつくられる)
▽155 名前 日付 本文 署名の形式
▽164 日記は毎日の経験報告。心の問題よりも、客観的で簡潔な記録。思想も感情も、客観的に、簡潔に記録する。日記は、自分自身のための、業務報告。
▽170 観察と記録との時間のずれは、みじかいほどよろしい。記憶はあきらめて、なるべくこまめに記録をとることに努力する。
▽192
▽202 こざね法 B8判の紙。きりぬき資料も、本からの知識も、つかえそうなものはすべてこの紙きれにかいてみる。……紙きれは分類してはいけない。分類ではなく、論理的につながりがありそうだ、とおもわれる紙きれを、まとめてゆく。
▽205 こざね法は、頭のなかのうごきを、紙きれのかたちで、そとにとりだしたもの。ばらばらな素材をながめて、いろいろとくみあわせているうちに、おもいもよらぬあたらしい関係が発見される。


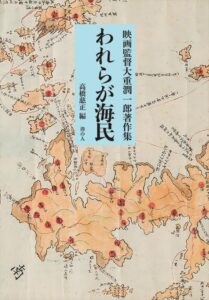


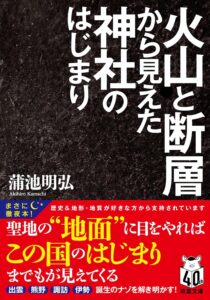

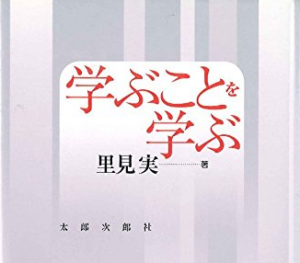
コメント