■街場のメディア論 <内田樹> 光文社新書 20100907
メディアはなぜ危機なのか。ネットや電子端末といった「外」の要因ではなく、メディア内部にこそが原因があるという。
メディアは「世論」を語るものという信憑と、メディアはビジネスだという信憑の2つがメディアの基盤を掘り崩しているという。
世論とは、血の通った身体をもった個人の「どうしても言いたいこと」ではなく、自分が言っても言わなくてよいこと、だれもが言いそうなことであり、誰もその言責を引き受けない。「誰でも言いそうなこと」を選択的に語っているうちに、そんなものなら存在しなくても困らないという事実に人々が気づいてしまった。
医療機関バッシングでは、記者が責任の明らかでない言説を前の記事を参照して反復しているうちに、それが世論として金科玉条になる。個人の責任と理性の関与が及ばない無限参照のなかで「定型」が形成されてしまう。
「ビジネス」という前提も誤りだ。本来、物書きとは「贈与」だという。贈与したものをだれかが「価値がある」と認めてくれてはじめて「価値」が生まれる。「ものそれ自体に価値が内在するわけではなく、それを自分宛ての贈り物だと思いなした人が価値を創造する」。だから、ビジネスとしてなりたたせよう、という発想自体がメディアの本質を誤らせている……
=============
▽26 天才は、自分の才能を「たいしたことない」と思っている。逆にあまり能力のない分野について「こういうことをしたい」というお門違いの夢を持っていたりする。コナン・ドイルは、スピリチュアリズムの伝道活動に大金を投じ、ニュートンの真のライフワークは錬金術とバイブル・コードの解読だと思っていた。……天才でさえ勘違いするのだから、「ほんとうにしたいこと」「自分の天職」で勘違いすることは不可避。「内面の声」に耳を傾ける暇があったら、まわりから「これ、やって」というリクエストに応じた方がよい。たいていの場合、自己評価よりも外部評価のほうが正確なんです。
▽30 人間がその才能を開花させるのは「他人のため」に働くとき。他ならぬ私が、余人をもっては代え難いものとして、召喚されたという事実が人間を覚醒に導く。……中教審の言うように「自己決定」するものではない。「他者に呼び寄せられること」
▽41 メディアの価値の判断基準は「よくよく考えれば、どうでもいいこと」と「場合によっては、人の命や共同体の運命にかかわること」を見極めること。
桑原武夫の人物評「頭のいい男やね。でも、ぼく、あの男と一緒に革命やろうとは思わん」……「革命」という危機的状況において、「学問の自由を守るために身体を張れる」ということ。桑原は、学者の知性を考量するとき、「危機耐性」を重んじた。
▽45 メディアの「危機耐性」とは、政治的弾圧や軍部の恫喝に屈しないということ。その抵抗力は「メディアには担わなければならない固有の責務がある」という強い使命感によってしか基礎づけられない。……「あのメディアとなら一緒に革命がやれると思える」かどうかをメディアの価値を判断するときの最後の基準にしたい。
▽63 メディアが「庶民の代表」みたいな言葉遣いをするのはおかしい。責任逃れをするときに「無知や無能」で武装するのはおかしい。
「被害者=政治的に正しい立場」というのは、「マイノリティ」「弱者の立場」であることが前提。だが、「資源分配のとき有利になるかもしれないから」とりあえず被害者のような顔をしてみせるというマナーが「ふつうの市民」にまで蔓延したのはかなり近年になってから。クレイマー
▽67
▽77 「患者さま」と呼ぶ病院 入院患者が院内規則を守らなくなった。ナースに暴言を吐くようになった。入院費を払わず退院する患者が出てきた。
患者さま、という呼称はあきらかに医療商取引モデルで考える人間が思いついたもの。
▽84 「なぜ、自分は判断を誤ったのか」を簡潔かつロジカルに言える知性がもっとも良質な知性。「世界」のてこ入れにどんな企画がよいかときかれた高橋源一郎は「『世界』の罪」というのはどうかと提案した。(市町村合併報道を振り返ったら、メディアのおかしさが見えるのでは〓〓)
▽92 メディアの医療機関バッシング。「記者が、責任の明らかでない言説を反復しているうちに、それが世論として金科玉条になる。……これは暴走。この過程に個人の責任と理性の関与、すなわち、自立した個人による制御が及んでいないから」……記者たちは先行する記事を参照して記事を書き……そういう無限参照のなかで「定型」は形成される。
▽96 固有名と、血の通った身体をもった個人の「どうしても言いたいこと」ではなく、「誰でも言いそうなこと」だけを選択的に語っているうちに、そんなものなら存在しなくても困らないという事実に人々が気づいてしまった。
▽99 メディアの定型性は、1 メディアは「世論」を語るものという信憑 2 メディアはビジネスだという信憑 の2つによってかたちづくられる。世論とビジネスがメディアを滅ぼした。
「世論」とは、「誰もその言責を引き受けない言葉」
▽106 「命が危うくなると知るやたちまちそれを否認する」ような言葉がどれくらい含まれているか、その含有率について、ときどき自己点検するべきでは。
▽107 ほんらいメディアは金儲けのためのものではない。「市場経済が始まる前から存在したもの」は商取引のスキームにはなじまない。宇沢弘文。
社会的共通資本は、わずかな入力差が大きな出力差を生み出すような種類のシステム(市場や政治)に委ねてはならない。それらは、入力変化に対する感応の遅い、惰性の強いシステムに委ねなければならない。
▽116 医療も教育も惰性が強い制度。簡単には変わるべきではない。だからメディアの攻撃が集中した。メディアの提言は、社会状況変化にすぐ即応できるような制度にかえろということ。つまり市場。
▽118 教育は専門家に委ねておけ。その起源が歴史の闇に消えて知られていない制度については、できるだけ謙虚に接したほうがいい。しかしメディアはそうした惰性的なものを許容しない。
▽145 本を書くというのは本質的に「贈与」。それを受け取って「ありがとう」と言う人が出るまで、それにどれだけの価値があるかは誰にもわからない。自分への「贈り物」と思いなす人が出現して「ありがとう」という言葉が口にされてはじめて、その作品に「価値」があったという物語ができあがる。
▽147
▽184 「ものそれ自体に価値が内在するわけではなく、それを自分宛ての贈り物だと思いなした人が価値を創造する」 「著作物それ自体に価値が内在している」というのが著作権保護論者たちの根本命題。彼らは、「贈与を受けた」と名乗る人の出現によってはじめて価値は生成するという根源的事実を見落としている。
▽203 〓〓〓


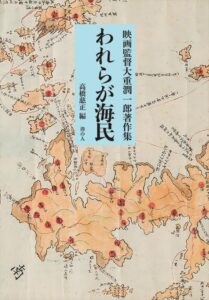

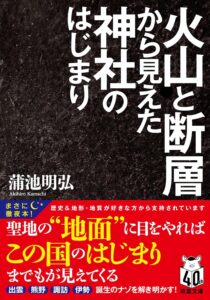

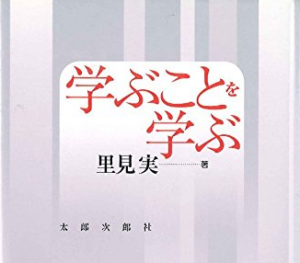

コメント