■文明は農業で動く 歴史を変える古代農法の謎<吉田太郎>築地書館
近代農法は石油に依存している。石油を使わず、100年前の技術水準で養える人口を計算すると、現在の35%の人口にすぎないという。江戸時代の日本はほとんどが農民だったが、3000万人を養うのがやっとだった。
石油なしには、十分な食料は生産できないのだろうか。
そういう問題意識から、古代文明を支えた農業技術などを再評価する。まさに世界農業遺産(GIAHS)の考え方だ。今後に生かすべき世界の伝統的農業技術を、すべてインターネットで調べあげて本にしてしまった。筆者の頭の良さにはほとほと驚かされる。
歴史上、石油遮断を経験した国が三つあるという。
ソ連崩壊で石油が入らなくなった北朝鮮は国民の3〜5%が餓死した。米国の経済封鎖を受けた大日本帝国は、自殺未遂をした東条首相を病院に搬送する救急車の燃料もなかった。
3つめはキューバだ。北朝鮮や日本と同じ状況に直面したがスムーズな「没落」に成功した。それは、社会的連帯と伝統知識が保全されてきたからだという。
筆者は、小農民が自給するために生態系回復にとりくむことからはじまったラテンアメリカを中心とした「アグロエコロジー」に注目する。
ペルーの標高3500メートルの高地では、畑のなかに運河を掘って水で満たすことで、霜害を防ぎジャガイモ栽培を栽培している。
メキシコでは北米自由貿易協定で、米国から半値のトウモロコシが流入して農地が荒廃した。そこで救いとなったのが、トウモロコシや豆、カボチャ、ハーブ、アマランサスなどをいっしょに植える「ミルパ」だった。トウモロコシ生産だけならモノカルチャーのほうが多産だが、全体の土地からの恵みはミルパのほうが多い。さらに、トウモロコシは15種、マメ5種、カボチャ3種というように、複数の品種が植えられているから天災にも強いという。メキシコ農民総合開発センターは、多くのムラで劣化した土地を回復させてきた。
「チナンパス」農法は水上菜園と呼ばれる。数年ごとに深さ1メートルの運河を浚渫することで窒素やリン、カリなどを畑に還元する。アステカ文明のティオテワカンの25万人に食糧を提供したのもチナンパスだったという。
ホンジュラスの「ケスングアル焼畑アグロフォレストリー・システム」は、木を切り倒さず、燃やさず、耕しもしない。1年目はソルガムや豆。その後、トウモロコシと豆、ソルガム、アワなどの混作をする。耕さず直播し、焼畑もしないから、表土は恒久的にカバーされ、二次林が再生される。
ボリビア・アマゾンの「カメリョーネス」は2007年に復活した古代農法だ。通常キャッサバの収量はヘクタール当たり15トンだが、古代農法を用いると最大100トンになった。米よりも生産性が高いことになる。運河に囲まれた、最高2メートルの高さになる「カメリョーネス」と呼ばれる盛り土を構築する。チナンパスと同様の農法だ。
アマゾンの「テラ・プラタ」もおもしろい。最近の研究で、アマゾン大地のかなりの部分に人工土壌があることがわかってきた。先住民が残したそうした土壌「テラ・プラタ」は、何百年間も保肥力が維持される。掘削しても厚さ20センチほど残せば、約20年で再生される。テラプラタには、他の土壌より70倍の量のバイオ炭が含まれ、それが養分を吸着して流失させず、微生物の住処にもなっているという。
ペルーのインカ文明は、急傾斜地にテラスを構築し、運河も整えた。だがスペイン人侵略による急激な人口減と強制移住によって衰退し、大半が放棄され、用水路も崩れてしまった。イギリス人女性が1977年ごろから、古代のテラス再建を手がけ、テラスでは土地の生産性が倍増することがわかった。用水路再建では、コンクリートではなく、粘土や砂、石、サボテンなど地元の原材料が使われた。
メキシコに2万種類のトウモロコシがあったように、インドにはかつて40万種の米品種があった。今も20万種あるという。「ジョハド」(三日月ダム)と呼ばれる伝統技術のダムは衰退していたが、1988年からその復活が取り組まれ、その数が375になった1994年には、40年代以来、モンスーン期以外は枯れていた川の流れが復活した。
スリランカの自殺は10万人当たり55人で世界で最も率が高い。農薬などの借金によるものだった。かつて世銀のアドバイスで、自給的米農業から高付加価値型の輸出作物へと切り替えを進めた。小規模農家をやめさせるため、稲作農家の支援をカットし、固定米価も廃止した。農地や潅漑用水が無料だから離農しないと考え、2000年には水の民営化販売計画も持ち上がった。
古代スリランカには、空海も学んだ世界で最も進んだ貯水池と潅漑技術があった。イギリスが1832年、民衆の協働作業による水管理システムを廃止したのをきっかけに貯水池の多くが放棄された。それでも乾燥ゾーンの米栽培は今も古代に築かれた潅漑システムに依存しているという。
中国の稲田養魚は、農薬と化学肥料で急速に衰退したが、その後再び復活してきたという。
魚がいれば、害虫のウンカが減るから農薬もいらなかった。ボウフラなどを食べるから、マラリアやフィラリアも減らしていた。だが、化学肥料や農薬を使えば、魚は必要ない。コメしか生産しなければ、田植え後は農業以外の仕事ができる。経済効率性に負けて稲田養魚は減ったという。
バリ島では、緑の革命によって、三期作ができる新品種に切り替えられたが、潅漑用水管理が混乱し、害虫が大発生するようになった。
バリでは、取水地点ごとにある「水の寺院」の僧侶たちが何百ものコミュニティの水を調整する役目を担ってきた。広範囲で作付け調整を行い、上流と下流が協力して同時に田を休ませることで定期的に害虫を防除してきた。緑の革命の失敗が明らかになり、一時は衰退した水の寺院は、政府の潅漑部局から認められるようになってきたという。
「極相林」は安定的な状態ではないという指摘も意外だった。実は外的ショックに脆弱で、嵐や山火事で攪乱されては再生を繰り返しているという。
複雑系の経済学によると、経済格差は必然的に拡大していく。だがそれは、不安定性を内在させることであり、限界点に達するとシステムは瓦解し、再び栄枯盛衰を繰り返す。システムの安定が長期的で広大であるほど崩壊の揺り戻しも大きい。グローバリゼーションの危険性はそこにあるという。
一方、伝統的な農民たちは絶えずその農法を改良し、きわめて多様な品種を開発してきた。それは、生産性よりリスク削減を重視し、自然や社会環境への柔軟な適応につながってきたという。
最先端の科学である複雑系が、伝統農業ともリンクする、というのが興味深かった。
==================
▽5 石油遮断を歴史的に経験した3国。それらの例をもとに、未来予想図を描くと。
ソ連崩壊で石油が途絶し、農業生産が大きく下落して国民の3〜5%が餓死した北朝鮮。もうひとつは米国の経済封鎖を受けた日本。自殺未遂をした東条首相を病院に搬送する救急車の燃料もなかった。
3つめは、キューバ。北朝鮮や日本と同様の状況に直面したにもかかわらず、スムーズな「没落」に成功した。社会的連帯と伝統知識が保全されてきたから。
古代技術の再興。住宅も灰や竹を用いたエコマテリアルづくり。古代ローマの技術をベースに開発した。(フェルナンド・マルティレナ博士)
□アグロエコロジー
▽13 有機農業が急成長しているのはラテンアメリカ。だが有機農産物のほとんどは先進国の需要を満たすもの。有機認証で付加価値がつくが、EUが認める認証基準を政府としてそなえるのはアルゼンチンだけ。国際有機農業運動連盟が認める民間認証機関も、アルゼンチン、ボリビア、ブラジルしかない。それ以外は多額の検査経費が必要になる。おまけに病害虫防除に植物エキスを遣うといった伝統的農法も認められない。
そこで、従来の有機とはちがう「アグロエコロジーの革命」が起きている。小農民が、自給するために生態系の回復にとりくみはじめる。そこからアグロエコロジーがはじまった。
…農民運動、ビア・カンペシーナ、ブラジルの小規模農民運動、キューバやベネズエラだけでなく、ブラジル・ペルー・ボリビア政府も農業開発戦略にアグロエコロジーを組み入れている。
□世界農業遺産
▽19 チリのチロエ諸島の農業、ペルーアンデスの山岳地農業、北アフリカのオアシス農業、イフガオ族の棚田、中国の稲田養魚がまず選定。
チロエはジャガイモ約200種の原種を保存。ペルーでは標高3500メートルでもジャガイモ栽培。畑のなかにスカコジョスという運河を掘り、水で満たすことで、霜害を防ぐ。
▽27 ビア・カンペシーナ〓を通じて、アグロエコロジーを評価する動きは、ラテンアメリカからアジアにも飛び火する。
▽32 アフリカ・スワヒリのムグンガ(アカシア)という窒素固定樹木。窒素がたっぷり含んだ葉を大地に落とす。
□メキシコ・ミルパ・ソラール
▽38 NAFTA実施で、米国の補助金つき輸出農産物の大攻勢で国産の半値のトウモロコシがなだれこむ。価格が45%も下落し、政府補助金はカットされ、荒れ地に。
▽41 救いとなったのは「ミルパ」。トウモロコシ、豆、カボチャ、ハーブなどをいっしょに植える。「メキシコ農民総合開発センター」のヘスス氏。世界農業遺産の候補。「おそらくこれまで人類が創造した中でも、もっとも成功した発明品のひとつ」とまでFAOが絶賛する農法。
トウモロコシ、リマ豆、カボチャを混作。シシトウなどの野菜やアマランサス、薬草、ケリテスと称される食用雑草を一緒に植えることも。リママメが窒素固定を行う。…トウモロコシ生産だけならモノカルチャーのほうが生産性が高いが、トータルとしての土地からの恵みはミルパのほうが多い。「モノカルチャー農場では多額の投資を行い1ヘクタールあたり8トンのトウモロコシが生産される。ミルパは1.8トンだが、緑肥や在来品種だけど、マメ、カボチャなどなんでももたらす。遺伝子組み換え種子とちがって、在来種子は、何世紀にもわたって食糧をもたらしつづける。
…たいがいトウモロコシは15種類、マメ5種類、カボチャ3種類、シシトウも数種類栽培される。メキシコや中米ではトウモロコシが2万種以上ある。多様な環境に対応させるために長い歳月をかけて種子選抜や種子交換を通じて育種がされてきたからだ。(里山農業ならではの多様性。自然、なだけではない)
▽44…在来品種をカボチャやマメと混作すると病気も出ない。
90日間も雑草だらけにしている。除草しても収量差がなく、土壌浸食も少なく、雑草が乾期の家畜飼料になるためだという。
▽47 ミシュテカ。古代の「傾斜の水路」。テラス、水路、カヘーテという小さな土製の貯水池からなるシステム。カヘーテには、畑から浸食された土壌がたまるから、定期的にさらって畑にもどす。
…化石燃料や化学肥料に頼らないかわりに、人力を活用することで、有機物や養分を循環させてきた。
▽49 メキシコ農民総合開発センターは、1989年以来、9つのコミュニテイで数百人の農民たちを組織することに成功。エル・プログレッソでは、100ヘクタールの劣化した土地を回復。…
…荒廃していたミシュテカは25~30%しか耕せなかったが、80%が耕作されるようになった。
ヘスス氏は、08年にゴールドマン環境保護賞を受賞。
▽水上菜園「チナンパス」。観光名所のショチミルコの水上菜園など2300ヘクタールしか残されていない。混作はミルパといっしょだが、休閑期がほとんどなく、年に3,4作物を連作できる。
トラスカラ州で今も行われているチナンパス農法。1-4年ごとに深さ1メートルの運河を浚渫することで、ヘクタール当たり窒素が1000キロ、リン10キロ、カリ120キロの養分が得られた。
通常のジャガイモ収量が1-4トン、トウモロコシ2.6-4トンであるのに対し、チナンパスでは、それぞれ8-14トン、3.5-6トンも。
今もチナンパスは、メキシコシティの観葉植物の45%を生産している。…このままでは失われる懸念が高い農法として、世界農業遺産が候補にあげた。
…同様の農法がユカタン半島の低地やスリナムの湿地帯、チチカカ湖でも発見されている。
…ティオテワカンは25万人の人口を抱えていたが、その食糧を提供していたのもチナンパスだったという。
▽ホンジュラスの古代農法 ハリケーンでも減収しなかった、西部のレンピーア州。レンカ族の伝統農法。1990年代前半にFAOが立ち上げたプロジェクトによって息を吹き返した。…伝統農法に取り組む地域はエル・ニーニョの後に倍増。ハリケーン被害も少なかった。「ケスングアル焼畑アグロフォレストリー・システム」。木を切り倒さず、燃やしもせず、耕しもしない。1年目はソルガムうや豆。その後、トウモロコシと豆、ソルガム、アワなどの混作。耕さず直播され、焼畑もしないから、表土は恒久的にカバーされ、二次林が再生される。日陰とならず、食用作物や飼料が養分の競争に負けないように、年に2,3度、新潮に樹木を剪定する。
…国際熱帯農業センターは、2005年には、土地条件の類似したニカラグア北西部でも「水と食料・チャレンジ・プログラム」を通して試験的に導入。成功し、従来の焼畑はかなり減った。コロンビアでも成功した。
樹木の正しい選び方や管理方法のこつを学ぶ必要。
▽67 ボリビアのアマゾン平原地帯のベニ県「カメリョーネス」。はじめて建設されたのは2007年。ケネス・リー財団が古代農法をよみがえらせた。通常の農法ではキャッサバはヘクタール当たり15トンしかとれないが、古代農法を用いると最大100トンもの収量をあげられる。三毛作も。(米よりも多い〓)。農法の原理はチナンパスと基本的に同じ。運河に囲まれ最高2メートルの高さになる「カメリョーネス」と呼ばれる盛り土を構築する。運河で水生植物タロペは肥料に、魚もとれる。
▽73 「テラ・プラタ」 アマゾンの生態系のほとんどは先住民によって人工的につくられたものだ、という説も(ダレル・ボージー博士)。先住民の環境知識を保全するため「先住民族知識資源センター」も設立。アマゾンの大地のかなりの部分に人工土壌があることがわかってきた。先住民が残した「テラ・プラタ」。何百年間も保肥力が維持される。掘削されても厚さ20センチほど残しておけば、約20年で再生されるという。テラプラタには、他の土壌に比べて70倍近くも多く、バイオ炭が含まれている。炭があれば養分が吸着されて流失せず、微生物の住処にもなる。
世界が注目。「私が1996年にアマゾンで働きはじめたときには、日系移民ぐらいしか、テラ・プラタの生産力の高さを知りませんでした。」(グレイザー博士)
世界農業遺産の候補にもあがっている。
「テラプラタは、骨や生ゴミなどを偶然加えることでできたのでしょう。大量の炭も料理や霊的な目的で低温の炎でつくられたもの」
▽83 ペルー インカ時代、何千もあった物流倉庫「コルカ」には、飢饉に備え、10年分もの食料が蓄えられていた。
ジャガイモ。収量を60%落とすやっかいなジャガイモシストセンチュウウによる病気。そこで休閑と非宿主植物が重要。
肥料は、モチーカ族が、ファヌと呼ぶ海鳥の糞を定期的に採掘して使っていた。ファヌをスペイン人がファノと呼び、これが英語では「グアノ」となった。ドイツの探検家によって窒素とリン酸が多く含まれることが判明すると、グアノ・ラッシュが起きて、掘り尽くされてしまった。
森は、皇帝自らが監視し、違法な伐採や燃やすことは死罪とされた。(江戸時代の紀州藩〓、加賀藩)
インカは、急傾斜地にテラスを構築。運河も整えた。だがスペイン人によって衰退し、テラスの756%は放棄されている。クスコ周辺の潅漑用水路のほとんども崩れている。壊滅的な人口減少に加え、強制移住でテラスを維持する労働力が確保できなくなったためだ。貧しい山村の人々が都市へ流出する拝啓には、農地が以前の人口を養えないという事情があった。
イギリス人女性アン・ケンドール博士が、古代テラス再建に情熱を燃やし、農村開発プロジェクト、クシチャカ・トラストを1977年に設立。…よく構築されたテラスでは、土地の生産性が倍増できる。…用水路再建では、粘土、砂、石、サボテンなど地元の原材料が使われた。セメントでは地震があれば割れてバラバラに壊れてしまう。
…モデルとしてのトラストのプロジェクトは1997年で終了。それ以降は、地元でNGOが結成され、各地区が国際開発機関から援助を受けて独自に活動している。
□インド・スリランカ
▽100 インドの農村で1997年以来20万人もの農民たちが自殺している。化学肥料や農薬などの借金が雪だるま式に増えた。
…在来の綿品種は天水栽培でき、食用作物とも混作可能だったが、遺伝子組み換え綿はモノカルチャーでしか栽培できないし、潅漑が必要。オオタバコガには抵抗性があっても、別の害虫が発生。以前より13倍も多く農薬を散布しなければならなくなった。
▽103 メキシコに2万種類のトウモロコシがあったように、インドにはかつて40万種の米品種があったという。今も20万種。
…なかには、フィラリアの治療に役立つ米も。
「インド知識体系センター」というNGO. 種子復活プロジェクト
▽111 アーユル・ベーダ 古代の技を復活
…2003年にバイオ農薬工場。8種のバイオ農薬を製造し、販売。
▽121 古代ダム 識字運動のためにムラに来たラジェンドラ・シン氏。「私たちがほしいのは水」といわれた。「ジョハド」(三日月ダム)と呼ばれる伝統技術。…1988年には7カ村でジョハド復活…。その数が375になった1994年、40年代以来、モンスーン直後以外は枯れていたアラヴェリ川は再び流れ出した〓。川が次々に復活。…国際的にもこの奇跡は注目されている。シン氏はマグサイサイ賞を受賞した。「コミュニティは創造的で、社会変革をもたらす潜在力があるのです」(〓コミュニティ論 日本でも可能性 内山節)
▽134 ローカルな資源と技術に基づいて、コミュニティの参画によって分散型の水管理をする。
…牛糞による種子処理。発芽を確実にする。
▽136 イチジク。生物多様性を維持する上で「かなめ」となる植物。イチジクを保存することは、果実を常食する鳥類繁殖に役立つ。
▽143 スリランカの自殺は、10万人当たり55人で、世界で最も率が高い。75%は農薬によるもの。緑の革命が関係している。トラクターや農薬代などの借金。
▽146 チリより以前からスリランカは社会主義政権が選ばれてきた。農業も手厚く保護されていた。これが1977年からがらりと変わる。世銀は、高付加価値型の輸出作物へと切り替え、米は輸入すべきとアドバイスをした。小規模な農家をやめさせるため、稲作農家の支援策をカット…固定米価も廃止、種子生産も民営化…農地や潅漑用水を無料で使えるために離農しようとしないから、2000年には水の民営化販売計画。
▽149 世界で最初に京大ダムが建設されたのはスリランカ。空海も(中国で学び)参考にした国土を埋め尽くす潅漑網。
▽153 満濃池は巨大なために818年に決壊し、機能していなかった。朝廷は空海をアドバイザーとして現地に派遣。空海は堤体を水圧にも耐えるアーチ構造にし、決壊を防ぐ洪水吐けを儲けることで、821年にわずか3カ月で工事を終えている。杖を地に突き刺すだけで水が湧き出すという、全国の弘法伝説は、スリランカの最新テクノロジーを目にした人々の驚きがベースとなったのかもしれない。
▽155 古代スリランカは、貯水池の多くは「ラージャカリヤ」と呼ばれる、村人が農閑期の40日を王のために働く賦役制度だが、強制労働ではなかった。
…貯水池の放棄は、それを維持してきたコミュニティの解体の結果。イギリスが1832年にラージャカリヤ制度を、封建的な民衆虐待と誤解して廃止した。それで一気に放棄された。
…スリランカの米の40%は、乾燥ゾーンで生産されているが、そのほとんどが古代に築かれた潅漑システムに依存している。…ほぼ1平方キロごとに貯水池がある計算になる。世界農業遺産が、古代スリランカの潅漑システムをリストのひとつにあげている。
…森林貯水池は、ジャングル内の野生動物に水を提供。それによって、ムラまで下りてこないにした。
貯水池に政府がアフリカからティラピアをもちこみ、ほとんどの魚が消え失せ、水田にすむ魚も農薬でいなくなり、魚がいなくなれば、マラリアを媒介するボウフラも生き残り、マラリアが深刻な問題に。
▽173 スリランカでは、すでに農業に利用可能な淡水の7割が開発ずみ。だが、伝統農法を用いれば、最大50%まで用水量を減らせる。
…太陰暦に従って栽培する。モンスーンの降雨パターンを観察し、太陰暦に基づく作付体系を構築してきた。
…不耕起マルチ栽培
…近代稲作で、湛水するのは、稲に必要だからではなく、雑草防除になるから。マルチで雑草が抑えられるのならば常時湛水しなくてもいい。しないほうが通気性が保たれ、根も深く育つ。
□ニューギニア高地の盛土農法
中東や中国とならぶ農業発祥の地のひとつでもあった。
現在の最重要作物はサツマイモ。人と豚の主食。まさにイモの島。
…マウンド堆肥農法。逆転層で霜害を防ぐ。マウンド内に入れられた有機物が分解する際の発酵熱も、地温を上げる。堆肥マウンド農法が開発されてから、休閑期は劇的に減った。焼畑農耕とちがって、集約農業が可能になり、森林を保全できる。
▽195 種子は普通3年経つと発芽力を失う。
…サツマイモは中南米原産。ニューギニア高地では、1700年頃にサツマイモが存在していたことがわかっている。以前の主食だったタロイモ、それを補完していたバナナと山芋を減らし、急速に食生活を変え、豚の飼育も可能になった。
▽中国の稲田養魚
稲田養魚。1959年には66万ヘクタールまで増えたが、1960年代前半からは、農薬と化学肥料で急速に衰退。再び復活し、2000年には153万2000ヘクタールに。
▽206 魚がいれば、害虫のウンカが17~28%も少ない。農薬散布も必要なかった。ボウフラなどを食べるから、マラリアやフィラリアなどの病気も減る。
2~34%、平均で11.8%の増収。
…農業遺産の指定候補地は、江蘇省、貴州省従江県、青田県の3カ所あった。だが酵素州北部では、2001年には1万3400ヘクタールあったのが、今は670ヘクタールになってしまった。理由は経済性。化学肥料や農薬を使えば、魚は必要ない。コメしか生産していなければ、田植え後は農場にいる必要はなく、、農外の仕事にも従事できる。総収入は稲田養魚のほぼ倍になる。
…青田県の竜現村が稲田養魚で有名になったのは、魚の質がよいからではなく、海外移住者が、欧米で自分たちの村をPRしたから。…若者は海外へ出稼ぎ。流出で、次世代継承は困難に。
▽212 バリ島 「スバック」というコミュニティの水管理グループ。
…緑の革命によって、1974年には棚田の48%が新品種に。3年後には70%に。新品種は早く育つから年に3期作に(イフガオ〓と同じ流れ)。だが、生産が高まったのは短期間だった。潅漑用水管理の混乱と害虫の大発生。
…予想される水量によってどの種類の米を栽培するか、さらに、水が不足しそうであれば、代替作物のパラウィジャを植えることも。…穂だけを刈りとり、養分が還元されるよう茎は残す(〓福岡さん、イフガオ)
▽218 何百ものコミュニティ間の潅漑を調整するうえで、「水の寺院」の僧侶たちに頼ってきた。
▽220 バリ島では、取水地点ごとに寺院がある。…どこの地域でも、潅漑の課題は、上流側が有利で川下に水を流すインセンティブが働かないこと。…広範囲で作付け調整を行い、すべて同時に休閑地とする場合にのみ、害虫を防除できる。下流側が同時作付けを拒否したら、上流側も被害を受けることに。上流と下流が協力しあうことはお互いメリットがある。水の寺院は、農民たちの作付けをシンクロさせ、水の配分を最適化すると共に、生息地を奪うことで害虫発生もおさえていた。
▽225 水の寺院は政府の潅漑部局からも認められ、バリ島のほとんどは、水の寺院の作付け調整力を取り戻した。
▽228 極相林は勝ち組ではない。一見反映しているようにみえて、外的ショックに脆弱。数十年スパンで、嵐でなぎ倒されたり、山火事が起きたりして攪乱されては再生を繰り返しているのが自然の森林生態系。
…複雑系の経済学が明らかにしたように、この世は平等ではなく、格差は必然的に拡大していく。だがそれは、不安定性を内在させることでもある。ストレスが限界に達した時点でシステムは瓦解し、再び栄枯盛衰を繰り返す。システムの安定が長期的で広大であるほど崩壊の揺り戻しも大きい。グローバリゼーションの危険性はそこにある。
▽240 伝統的な農民たちは絶えずその農法を改良してきた。そのひとつが品種改良。伝統農業は作物種の多様性が驚くほど多いが、それが、自然や社会環境への柔軟な適応につながってきた。生産性よりリスク削減を重視。
▽246 ゲーム理論。顔が見えるコミュニティレベルでは利己的な農民たちの行動が結果として交易に配慮した秩序を生み出すが、顔が見えないグローバル経済では利己的な行動は公益をこわす。ゲーム理論の結果を象徴するかのように、稲田養魚がグローバル化の中で衰退の危機に瀕しているのと同じく、バリのスバックも崩壊に直面している。「1599あるスバックのうち、今も活動しているのは20%だけ」
▽257 あとがき すべてインターネットで得た情報。
…近代農業は第一次大戦中の火薬と毒ガスをベースに開発された化学肥料と農薬から誕生した。要素還元主義的な対応で、緑の革命の失敗を招いた。
…最先端の科学である複雑系が、伝統農業ともリンクする。
…韓国は有機農業先進国。認証農産物の国産シェア率は日本の0.19に比べ11.9%。
…「こぶしの花が咲くときに○○を植えろ」といった農の歳時記。積算温度や降雨量が毎年微妙に変化することを考えれば、県の普及センターが作成した栽培暦よりも、風土に溶け込んだ生物指標のほうがはるかに正確なことは間違いない。〓(まるやま組)


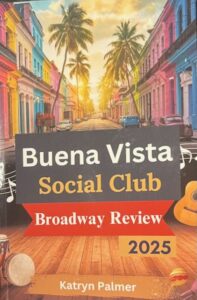


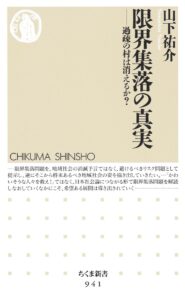
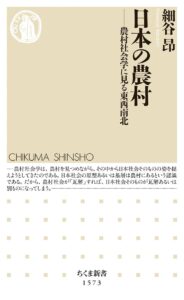

コメント