■草の根グローバリゼーション 世界遺産棚田村の文化実践と生活戦略<清水展>京都大学学術出版会 20150202
舞台はフィリピンの世界遺産の棚田の村。棚田観光の拠点のバナウエ町からさらに奥にあるフンドゥアン郡ハパオ村という。ルソン島の山奥の辺境だが、植民者のスペイン人に抵抗しつづけ、大戦末期には山下奉文将軍が率いる日本軍5万人余りが侵入して立てこもり、80年代になると新人民軍の拠点となった。グローバルな動きに翻弄されつづけてきた。
さらに村(338世帯、1750人)から、女性を中心に20年間に150人以上の村人が海外就労し、その現金収入が村人の生活を支えてきた。孤立した辺境ではなく、グローバル化の最先端にいるという。
筆者の同志であり研究対象でもあるロペス・ナウヤックは、植林運動を「グローバル・フォレスト・ムーブメント」と名づけた。グローバル化という状況のなかで、固有の文化を保持する先住民として誇りを持って生きていく実践だ。グローバル化から逃げるのではなく、それと対峙し、積極的に利用するチャンスとしてとらえている。
もう一人の主人公(研究対象)は世界的にも著名な映像作家キッドラット・タヒミック。アメリカの高等教育を受けて国連の高級官僚をつとめたが、自分を真のフィリピン人として作り直すためナウヤックを心の師とあおぐ。ナウヤックの生家があるハパオ村のパットパット集落に伝統的な家を建て、ドキュメンタリーを制作している。
東京やロンドンのような「中心」や、パワーエリートたちによる「上」からのグローバルとは異なる、辺境の先住民の側からのグローバルに着目した研究だ。世界システムの外部に位置づけられた先住民・原住民の側からグローバル化をとらえなおすことで、新たな視野と理解を開こうと試みたという。
研究の手法は従来の客観的な調査ではなく、自ら巻き込まれ、あるいは積極的に関与する「コミットメントの人類学」となった。分厚い研究書なのにルポライターが書いた文章のように読みやすいのはそのせいだろう。
山岳地帯の棚田の村について、農地管理や伝統文化、宗教、食にいたるま詳述するとともに、グローバル経済が村に及ぼす影響や、それへの対抗策まで描いている。日本の農村にも参考になる普遍性をもった内容になっている。
=======================
▽18 フィリピンでは2006年の時点で8500万人の総人口の1割にあたる800万人が海外に出て働いていた。海外へ送り出す短期契約労働者数は世界最多。仕送り送金は正規のルートだけで2006年度に120億ドルに達し、輸出総額の20%に相当した。
…海外に出る人たちの多くが比較的裕福な家のメンバー。大学や短大を出て英語力があることが海外就労を可能にする条件となっている。
▽20 グローバルな政治経済システムへの巻きこまれと反発・抵抗・交渉は、スペインによる植民地支配体制の介入とともにはじまっていた。
イフガオ州に隣接するヌエバ・ビスカヤ州の山地で移動焼畑耕作をおこない、首狩を軸として社会文化編成をしてきたイロンゴット族は、1960年代まで首狩をつづけていた。フィリピン革命や世界大恐慌、日本軍の侵出に対するゲリラ戦の活発化などで、平地民社会の治安維持が破綻するのに応じて、首狩が活発化した。
…戦後しばらくも、イフガオの外の世界に出て行くのはもっぱら男性だった。現在では女性が男性の4倍以上。
この20年、外の世界への意識拡大と、内世界への意識の延伸とがほぼ同時期に起きている。…何代にもわたって石壁をつくり補修してきた祖先の汗と、森の水と田の土と、神々の恵みによって支えられていることの再確認、再発見が導かれている。
…伝統的祝祭(トゥゴ)が1990年代のはじめに復活され…
□ロペス・ナウヤック
▽34 人類学の研究。その文化を生きる人びと自身を、その文化の全体像や真の意味について理解せず、明晰に語れない者としてきたに等しい。「オリエンタリズム」をひとつの契機としてそういういびつな関係に基づく人類学の成り立ちそのものに現地のインテリから激しい批判が投げかけられた。
▽42 バギオからハパオ村にもどり、植林をはじめる。「…森が失われたり灌漑用水が枯渇したりする問題が深刻になってきている。木彫りに適した樹木が急激に減ってきている。このままでは…」
▽46 ナウヤックがビジネスを夫人に任せ、故郷に戻ろうとした理由は、植林によってピヌゴや共有地の森を回復し、さらには破損した用水路と放棄されたままの棚田を修復し、再び耕作できるようにうすること。
…80年代を通じてフンドゥアン郡を実効支配していた新人民軍が撤退し、村に平和がもどった。
▽51 農耕儀礼の際に、モンバキ(祭司)が各世代の祖先たちの名前を逐一挙げて祈る。祖先の一人ひとりを思い、そのつながりのなかでイフガオとしてこの地に生を受けたことを自覚するのです(グアテマラ〓安藤〓)
…棚田の歴史は政府よりずっと古い。しかし、受け継いできた棚田を法律的には所有(登記)することができず、国有林保護地区の不法占拠者とされてしまっています。
▽52 ラモット町ナヨン地区にあるイフガオ州立農林大学〓に…
▽56 「グローバル平和公園」の計画 広島と長崎に行った。原爆の傷跡は見当たらなかった。しかし、ハパオには、戦争中に受けた傷跡が、そのまま残っています。だからこそ、「平和公園」に。なぜならここは日本軍が降伏した場所だから。ナプラワン山の霊的な力のおかげで、山下将軍が平和裡に降伏しようという気持ちになったのです。…世界中から観光客が来て、我々の植林運動に参加し苗を買って、記念の植樹をしてもらいたい。
▽59 カンニャオ祭り。神に祈り供犠をする儀礼。…キリスト教の神様も、イフガオの神様であるカブニアンも、エホバと呼ばれている神様も、すべて同じ方、唯一の神様です。どこにいようとどの言葉を使おうとも、同じ神様に祈りをささげているのです。(グアテマラ=カトリックと融合)
▽64 戦争中 ハパオ村に敗走してきた日本兵から逃れるため、1945年6月から2カ月ほど、村人たちや山中での避難生活を余儀なくされた。飢餓と病気によって多くの死者を出し、ナウヤックの弟も亡くなった。戦後すぐに母親も妹を流産した後になくなった。
…村人は今も戦争の経験を伝えている。しかし日本人やアメリカ人は忘れてしまったようなので、罪や責任を感じて誠実に対応してほしいとナウヤックはいう。謝罪や償いを求めるのではなく、未来に向けた和解として力を合わせて新しいプロジェクトを進めていくために力を貸してほしいという。
…1995年、原爆投下50周年の記念式典に、キッドラットとともに日本のNGOに招かれて参加した。
▽68 「伝統的」な精霊と祖霊の観念を保持していること、儀礼をさまざまな場所でとりおこなうこと、そして熱心なキリスト教徒であることとが、彼のなかで折り合いをつけて共存している。
▽73 日米決戦の最終地点とされてしまったことによって、山奥のハパオ村でさえもすでにグローバルな激動のなかに巻き込まれてしまっている。グローバル化に抵抗したり対抗したりするだけに専念するのは、アナクロニズム以外の何ものでもないことを熟知している。
□キッドラット・タヒミック
▽88 スペイン植民地支配。その内側にいる人びとをひとつの民族共同体として内発的に充填してゆくような古代文明や共通の文化を欠いていた。フィリピン人であることの自覚は、スペインとアメリカの支配さらには日本軍政、戦後はアメリカの新植民地主義に異議を申し立て、抵抗するなかで育まれた。
…古代王国や古代文明を持つことがなく、植民地から真に解放されたことがなかった過去は、輝きをもつことができない。
▽93 キッドラット 50歳の記念イベントとして1992年に世界1周の貧乏旅行をした。
マゼランといっしょにいたフィリピンのエンリケこそが最初に地球を1周した栄誉を与えられるべき。さらに、植民地主義の先兵たちに対する反抗=反攻の先達だった。
▽109 indigenous 先住の、とするよりも、「その土地固有の、土着の、自生の」という意味を強調するべき。indigenous peopleの訳語は、原住民とするほうが、その語の含意を的確に表現できる。
…イフガオは、スペインに対して最後まで屈服せず土地を失わなかったことを今でも誇りとしている。アメリカに対しては、軍事的に敗北したというよりも、その友好的な懐柔と宥和のアプローチにこたえて自ら武器を捨て版図に組み入れられることを甘受したが、生活の基盤である土地は堅持しつづけたと考えている。
▽120 ジープニーは、戦後に放出されたアメリカ製の軍用ジープのエンジンと車体の枠組みだけは残し、職人の手仕事で大幅な改造を加えて再生したもの。(現在では日本製の中古エンジンと、さまざまな中古部品で組み立てている)廃物利用、ブリコラージュ。
□文化の資源化
▽142 「2月革命」 自由な言論のなかで公正な社会変革を可能とするような「民主空間」を生みだした。しかし、「総合的農地改革法案」は骨抜きにされ…。
l991年にはピナトゥボ山噴火。政治的には米軍基地の撤退という事態を生みだした。
▽158 キッドラット フィリピン固有文化の核心を表象するものとして、褌を意味づける本質主義と映像は、イフガオやイゴロットのインテリの一部に違和感や反発を引き起こしている。
▽164
キッドラットが、古くから伝えられてきた知識を守り伝えてゆくためのコミュニティステーションを始めようとしたのは、衛星放送がコルディリェラ地域にも侵入してきたからだった。…ビデオを活用して村民の伝統文化への自覚を強化することを支援する活動。
「文化資源学会」が日本民俗学会のメンバーを中心として設立〓。
▽176 2009年7月、越後妻有地区で開催された「大地の芸術祭」に招待された。妻有の棚田の一画にイフガオ伝統家屋を建築した。
□共産ゲリラと人類学者をひきつける魅力
▽189 アメリカ植民地時代に入ってから、行政官や人類学者を魅了してきた。60〜70の原住民のなかで群を抜いて多くの調査研究がなされ、新聞や雑誌に紹介されてきた。
〓2007年時点でイフガオ州は11の郡と175のバランガイ(区・村)から成り、18万815人の人口を擁する。12年ほどのあいだに2割ほど人口が増加した。
先行研究 バートンの「イフガオの法」(1919)
コンクリンの「イフガオの民族誌的地図帳」(1980)
フィリピン大学アジアセンター教授のシルバーノ・マヒヲは、ハパオ村出身で東大に留学。
▽203 棚田は、祖先たちとの命の連鎖を支える基盤であり、それゆえ生者と死者たちからなる親密な共同性を体現しその存続を担保するものである。とりわけハパオ村は石組みの壁をもつ棚田の景観が美しいことで知られる。バナウエの棚田は泥壁。イフガオ全体では石壁の棚田の割合は30%ほどだが、ハパオ村では95%を越えている。
…バナウエからハパオへは、ジープニーで1時間ほどかかる。ハパオから10分ほど進めば、雑貨店のあるフンドゥアン郡の中心部のホッボン地区にいたり、さらに15分で、郡役場のある高台の下に到着。
▽206 共産党=新人民軍の20年の支配。ハパオ村にはじめて姿をあらわしたのは1970年代初頭。農作業を手伝い、医療や教育などのサービス提供、識字教育などをおこなうことで受け入れられた。
▽208 オイルショックで経済が低迷し、83年にペニグノ・アキノ氏が暗殺されて政治が混乱し、経済成長率はマイナスに。国軍推計では、81年に3000人だった新人民軍は83年には6000人、84年には1万2000人に。フンドゥアン郡でも80年代半ば過ぎには「戦略的均衡」状態に。
…84年からは郡の中心部に住む人びとは激減し、ゴーストタウンのように。
新人民軍の拠点となった理由。山奥に位置して接近しにくい、人々の手助けをして有効に振る舞ったため住民の支援を得ることができたこと、交通路の要衝に位置していること、ハパオ村を中心にして経済的に豊かだったこと。
…フィリピンでは80年代に入ってからのほうが、共産党が急速に勢力を伸張させた。
…人類学者にとっては、欧米の文化的影響や経済システムの作用が直接には及ばず、それゆえ非西欧的なものが保持されている地域だった。
…山奥でアクセス困難だからこそ、弱小勢力が逃げ込んだり、反撃の拠点を築こうとしてきた。だからこそ逆に、支配的な勢力は、辺境の地にまで軍事力を展開してきた。
□イフガオの抵抗
▽220 スペインに抵抗。
アメリカ人知事は、懐柔融和策で成果をあげた。
1944年10月に山下奉文将軍が第14軍総司令官として派遣された。が、着任早々にレイテ沖海戦で敗北。制空制海権を失った日本軍はマニアらからの撤退を余儀なくされた。バギオを経てイフガオ地域の山奥に複郭陣地を築き、2カ月あまりたてこもった。ハパオ村からアバタン村、さらにワンワン村にいたる渓谷を中心とするフンドゥアン郡の一帯だった。5〜6万人の日本兵を恐れ、住民は山中に避難。日本兵らは米やイモを奪って食料とした。避難した村人たちは食糧がなくなり、種芋まで奪われたため、翌年以降も深刻な食糧不足がつづいた。多くのイフガオが飢えと病気で亡くなった。
ピープルパワー革命でアキノが政権についた1986年以降は、新人民軍の活動が活発化した。
▽224 スペインにとってもうらからない植民地だったが、たばこ栽培がはじまってもうかるようになった。それでコルディリェラ地域への介入が再開される。
イフガオ。平地キリスト教民の村への襲撃や、イフガオの村落間での首狩血讐。
スペイン遠征隊に動員された平地民に対する強い憎悪と敵意が、その後も世代を超えて語り継がれた。
▽230 フィリピン革命のアギナルド将軍は、米と鶏を挑発して村人の反発を受けた。将軍を追跡するアメリカの300人は、気前よく代金を払った。
▽232 植民地支配者は、平地のマジョリティ民族との関係は緊張をはらんだものであったのに対して、山地のマイノリティに対しては友好的な関係を築いた。アメリカの軍人たちは、首狩を除く伝統的な慣行と文化を尊重し、彼らの庇護者たろうとした。ビルマのチン・カチン・ナガとイギリスの関係も。
▽235 アメリカ人とイフガオ女性との関係は、慣習法のみにもとづく「現地妻」だった。なのに、別れたあとも好意的な評価。その理由はイフガオ女性にとって、アメリカ人から経済的支援を得られること、家事労働の負担がきわめて軽い、社会的地位を得られるため再婚する際に有利、娘宿における結婚前の性関係が自由であり、離婚と再婚も簡単におこなわれていた…。
▽236 イフガオは日本軍が最後の2カ月余りを立てこもって、多くの爪痕を残した。…私自身も当初は、山下財宝をさがすためにやってきて、村人たちの話を聞きまわっていると臆され誤解された。
…レイテ沖海戦も当初は「大勝利」とされた。この誤報によって大本営はレイテ島での陸上決戦を決定し、兵員と物資の最大投入を決定した。
…山下は、敵のレイテ湾来攻わずか10日前に着任した。「地上戦はルソンのみ」と大本営で確認して着任した。ところが…台湾沖航空戦で大戦果をおさめたので、レイテ地上決戦も可能になったと判断し、方針を変更してレイテ地上決戦も行うよう指導しつつあったが、フィリピン沖海戦にも大戦果をおさめた旨を知って、本格的にレイテ地上決戦を指導した。(防衛庁戦史室1970)
▽240 パレテ峠の陥落が必至となったころ、5月15日にはイフガオ山地への入口に位置するキアンガン村へと移った。6月17日には山中のバクダン集落へ。23日にはさらにアシン川中流のハバンガン集落へと移動した。そこが度重なる撤退の行き止まりであった。
…はじめは土民と協調してゆくために、遠慮して手をつけなかった籾庫も、飢える日本人のためにやがて空にされ、斜面に植えつけられた甘藷も瞬く間に掘り尽くされました。…食糧不足と飢餓、マラリア、赤痢で多くの人命が失われたのはイフガオの側でも同様だった。
…棚田の稲穂が収穫の直前。多くは収穫できぬまま放置して山中に逃げた。…
▽253 キアンガンにある、戦争追悼廟 Kiangan War Memorial Shrine と、イフガオ博物館。
▽255 スペイン植民地支配のあいだ、屈服しなかったことが逆に武力介入を招きつづけた。アメリカ支配の時代を経て、日本軍そして新人民軍も軍事拠点を築いた。…二大勢力が対峙対立する接触・臨界面を生みだすという点で、グローバル大の軋轢が焦点化して出現する特異点でありつづけた。イフガオは、「今も昔も、あるいは昔から、山奥はグローバル」なのである。〓(能登は昔はグローバルだった。もう一度)
□棚田と木彫り
▽269 富裕層は、谷底近くに位置する広い棚田を複数有し、貧困層は山腹上方の狭い棚田を保持するか、あるいは棚田を保持しない。村落の共有地に焼畑を開いてサツマイモを植えたり、親族から棚田を借り受け収穫折半の苅り分け小作として耕作したりする。
…海外で稼ぎや木彫りビジネスで成功して経済的な余裕があると、まずは子どもをバギオやマニラ首都圏の大学に送ることを優先し、ついで鉄筋の家に建て替えたり、あるいは棚田を購入することが多い。棚田は、その生産力よりも象徴的価値が重要であるため、その価値を理解する買い手はイフガオに限られ、売り手と買い手はともに村内あるいは近隣村に住む場合がほとんど。
(〓棚田の価値。シンボルとしての価値という物語が生きている。白米や金蔵は?)
▽270 1990年代の前半の調査では、棚田の平均的な耕作面積は1戸あたり0.5ヘクタール。総労働力の3分の2を投入し、収入寄与率は2分の1だった。85年から95年の棚田1ヘクタールあたりの平均終了は2.66〜2.88トン。多くの家庭では自家米は3〜6カ月ほどの家内消費量にしか相当しない。各世帯の年間の平均収入は2万2558ペソで、78%が政府が定める貧困ライン以下だった。平均が3万3838ペソの北部ルソン山岳地帯諸州のなかで最貧である。
…ハパオ村の世帯ごとの平均月収は1万2200ペソ。郡内の9つの村のなかでもっとも豊かで突出。もっとも貧しいバンバン村の5倍ほどになる。
▽272 コンクリンによれば、…合計で22段階の農作業と、関連した23の農耕儀礼がおこなわれていた。
1〜2月に田植えをして、7,8月にかけて収穫する。
▽274 下の方の田は1枚の面積が広いが、上にゆくにつれて狭くなり、最上段の棚田では幅が1、2メートルしかない。
…バナウエ地区で調査したエダーによれば、灌漑用水の不足を主たる要因として、すでに1970年代から棚田耕作の生産性が落ち、離農者が出るなどの困難に直面しはじめていた。用水の枯渇の原因は焼畑の伐採、木彫りの用材確保、燃料用の薪集めなどによる森林の減退だった。
ハパオ村でも、バナウエと似たような問題を抱えはじめている。…イフガオ全体としても、2001年には耕作放棄・転作による棚田の荒廃などを理由として「危機遺産」に指定された。一番大きな問題は、耕作が重労働でありながら収量が低いために若者たちが後継者となりたがらず、労働力が不足していること。…高等教育を終えた若者たちのほとんどは、町や都会に出てはたらきたいと願っている。高齢化と後継者不足。
▽276 棚田の上方にはピヌゴまたはモヨンと呼ばれる私有林がある。棚田は周囲の自然環境、とりわけピヌゴと一体となった密接な環境連環のなかで維持されている。
…フィリピンの土地所有制度は、すべての土地は一義的に国有地とした上で、しかるべき手続きによって個人や法人の所有を認めてきた。…イフガオの人々にとってピヌゴは、棚田とともに幾世代にもわたって受け継がれてきた祖先伝来の私有財産である。なのに法律的な所有権は認められていない。
…イフガオのピヌゴは他の原住民社会とは異なり、個人の私有財産であるために、先住民権利法が想定する集団的所有の概念とそぐわない。ピヌゴ〓湧水の源、煮炊きの燃料、建築材、木彫りの木材。
…ピヌゴは多くの場合、下方の棚田と一体のものとして相続される。子どもたちのあいだでは長幼の序が重んじられ、棚田とピヌゴは、伝統的には、そして現在でも、原則として長子が相続する。(上大沢〓)
…しかし、ピヌゴは所有者が自由勝手に処分できるわけではない。バギオやマニラに移住したり、近隣州に生活の拠点を移したりすると、ピヌゴの日常的な維持管理をおこなうことが不可能になる。その場合には、村に残るきょうだいや親族でピヌゴの維持を積極的におこなうものが実質的な所有者と見なされるようになる。
…ピヌゴは「私有林」と訳されるが、ナウヤックは「人間がつくった森」であることを力説する。(〓人工林、というより里山ということ)
▽283 ハパオ村と周辺のピヌゴおよびビリッドの森は、状態が比較的よい。90年代はじめごろまで新人民軍ゲリラの影響下にあり、過剰な伐採が制約を受けたこと。観光開発がバナウエを中心にとどまっていて、いまだ及んでいないこと。焼畑にイモを植えていたのが、現金収入を得て足りない米を買うことへとスタイルが変化したため、放置された焼畑跡地の植生が回復しつつあること。
逆に90年代になって森の衰退が進んだのは、新人民軍がいなくなったこと、海外出稼ぎで得た現金で家を建て替えたり新築したりして、家屋の建築資材のための伐採が増えたこと。キリスト教徒学校教育の浸透によって、森の精霊への怖れが軽減したこと。
…ナウヤックの植林運動は、当初は、村人たちが手弁当で協力した。共有作業で育てた苗は、私有するピヌゴに植林された。だから除草その他の生育管理も十分に手が届いた。(私有、の意味。上からの共有はダメ=ニカの例)
▽289 焼畑の比率は下がり、棚田からの収穫米で足りない分は、村やバナウエの商店で米を買っている。
▽290 木彫り産業は、アメリカ植民地化の早い段階にはじまった。バギオを避暑地として開発する土木プロジェクトを開始。道路や家屋建設で、土砂崩れを防ぐために崖斜面に石垣を組む職人として、イフガオをはじめとする山地民らが多数雇われた。イフガオの人々ははじめは石工として働く機会を得たが、やがて、木彫りの椀や盆などをアメリカ人が珍重し、購入するようになった。
□出稼ぎ
▽294 香港に滞在中のハパオ出身の女性たちの相互扶助組織。「在香港ハパオ・フンドゥアン海外就労者協会」を1995年に設立。35人の発足メンバーのほとんどがハパオ出身。ほぞ全員が住みこみのお手伝い。
出稼ぎによって、現金を獲得。その結果、村民の生活と意識が表面的には平地キリスト教民の暮らしぶりに似たようなものへと急速に変わりつつある。家を建て替える際には、コンクリートブロックの壁とトタン屋根を基本とする平地民の家屋のスタイルを踏襲することがほとんど。だが、内面的にはイフガオとしての覚醒が教科され、それを確認するため郡の主導によって、伝統的な祭礼が大々的に復活されている。各家では、農事暦にかかわる儀礼が衰退するいっぽうで、結婚式や葬式などは逆に多額の費用をかけて儀礼と共食を伴うようになってきている。
…ハパオ村から海外出稼ぎに出た人の総計は160〜170人を優に超えるだろう。総人口の1割近くとなる。フィリピン全体の出稼ぎ者の割合とほぼ等しい。海外就労者は女性が圧倒的。
(多くが大学を出ている。教育学学士…)
▽324 村の富裕層に属する家で特徴的なのは、子どもたちが大学の看護学科を卒業することにより、看護師としての海外就労が可能になっている…。専門職として社会的地位を給料が高く、確かなキャリアコースと考えられている。
▽326 海外の職探しと渡航手続きには、専門の斡旋業者を頼る。渡航費用の総額は、出稼ぎ先の月給のおおよそ半年分から1年分に相当する。
…ハパオ村では1990年代から出稼ぎが顕著になる一方で、伝統文化への関心とイフガオであることの自覚が強まってきている。きっかけは、NPAの実効支配が終わり、生活と社会の再建が急務と考えたフンドゥアン郡長らの働きかけだった。92年に、現代版のトゥゴ(伝統祭礼)をはじめた。…川をはさんだ綱引き、浅瀬での相撲が主な行事だった。新人民軍の支配がすすむにつれておこなわれなくなっていた。〓
「伝統の再創造」
ただ、農事暦と結びついた儀礼や労働交換・共同作業など、生産活動と直接結びついた伝統的な慣行はこの20年ほどのあいだに衰退してきている。
▽332 フンドゥアン郡でトゥゴ祭が復活したのは、前々郡長だったアンドレス・ドヌアンSr. の尽力。3つの目的。観光産業を盛んに。存続危機にある文化復活。そのころには伝統文化を積極的守ろうなどという人はほとんどいませんでした。3つめは、若者たちが文化の存続を意識的におこなうきっかけとするため。前郡長はバナウエでハーフ・ウェイ・ロッジというゲストハウスを経営していました。
▽336 フンドゥアン郡だけでなく、キアンガン町でもほぼ同時期に伝統儀礼が復活した。ゴータド祭の復活は、〓テディー・バギラットが、95年に30代の若さで町長に当選したときにはじめた目玉政策のひとつだった。バギラットはその後イフガオ州知事に当選(2001~04)。落選後は「イフガオの棚田を守る運動」のディレクターとして、IKGsのパートナーとなり「グローバル」とともにJICAの草の根プロジェクトに協力した。07年に州知事に再選。10年からはイフガオ選出の下院議員になっている。
イフガオ州でもっとも早く伝統儀礼の復活をはじめたのは、バナウエ町。マニラから大型バスであがってこられるようになったころの1979年にインバヤ祭がはじめられた。「インバヤ祭の目的は、人びとに文化や伝統を守ることの大切さを自覚してもらうこと」
…多くの祭りが80~90年代に復活されている。
▽338 海外にまで遠く働きに出て行くことと、自身の民族的・文化的ルーツを目に見える形で確認し演ずることとが、ほぼ同時期に生じている。〓棚田を中心とする生業および景観に深く根ざし支えられ、自然環境の融合として自覚されている。そうした自覚が、グローバル化によってあらためて強化されている。
グローバル化の進行とは、必ずしも世界を同質化してしまう家庭ではない。逆に「個別主義を推進し…グローバルに多様性を推進するものだ」
…民族文化の真正性や土着性への関心の高まりとその誇示は、グローバル化の潮流に積極的に乗り出してゆくために不可避な自己確認と、それを支える基盤の可視化と自覚化、強化であり…グローバルな競技場において、異なるが敬意を払うべき文化を有する対等な他者との認知を要求するための戦略として理解できる。
(能登は? 船員たちにそういう意識があった? 外にでた人たちは?〓)
▽フィリピンの海外出稼ぎは70年代中盤から奨励されてきた。83年のペニグノ・アキノ元上院議員の暗殺をきっかけとして、経済が大幅なマイナス成長となり、大量の人々が海外に出稼ぎに出た。
…国民の大多数が日常的な英会話に不自由せず、ハパオムラでも大学卒業者ならば英語の読み書き会話ができる。出稼ぎに飛び立つ者の大半は裕福な家のメンバーであり、大学レベルの高等教育を受けている。
彼らは高等教育を通じてグローバルなネットワークの一端とつながり、海外での就労機会を自ら積極的につかんでゆく。
□山奥どうしの国際協力 参与する人類学
▽346 参与観察。コミットメントの人類学。「巻き込まれ」から「コミット」へ。(民俗学も〓)。
…兵庫県山南町(篠山市)のIKGsというNGO.フィリピンと日本の山奥の団体どうしの交流。双方の地域の活性化に役立っている(〓日本の側にも役立つ。能登も海外と結びつくことで何らかの変化が出てくる?〓 ネタになる?)
▽351 グローバル化という流れに積極的に便乗し、田舎や辺境からグローバル化していく企ての一例、あるいは住民主導による草の根のグローバル化の一端とみることができる。
▽351 戦後の開発戦略の流れ 近代工業部門を軸として国民経済全体の発展を目指す戦略。貧困問題はトリクルダウン効果によって解決すると考えられた。70年代に入ると、「人間の基本的ニーズ」Basic Human Needsにこたえるものへと変わり、コミュニティ開発アプローチなどが提唱された。しかしオイルショックで途上国が財政破綻し、80年代には構造調整政策の実施を迫り、民営化を推進。その結果、「人間の基本的ニーズ」アプローチは後退した。90年代には「人間の自助自立と社会正義の実現」をめざすアプローチとして社会開発が重要視されるようになった。それが90年代になって主流となり、経済開発とならんで社会開発が開発の二本柱となった。
…80年代の末頃から、東南アジア諸国ではコミュニティによる造林と管理・持続的な活用が、森林環境保全にもっとも有効だと認識されてきた。
…それまではトップダウンで植林プロジェクトをして失敗した。請負造林プロジェクトは外部の者が請け負い、汚職と腐敗で失敗した。→コミュニティを基盤とする森林管理戦略が採用。
…フィリピン林政は、国家による資源管理から住民参加型の資源管理へと方向転換がされた。
…請負造林は、地域住民は日々雇用される労働者にすぎなかった。全造林事業の9割近くが、失敗。
→住民による既存の林野利用を尊重し、コミュニティを基盤とする森林管理戦略が採用されることになった。…もともとイフガオは棚田の上の森をピヌゴと呼んで私有し管理する制度により、個々人の権利と責任を認めると同時に、他の村人もその管理に関心を持ち共同体規制の下に置くという独特の資源管理をしてきた。その意味では時代を先取りしていたとお言える。(〓半公共空間)
▽356 女性の織物。事業展開し資本蓄積。バナウエにおける工芸品の商業化はフィリピンの他地域や他国の事例のように女性を必ずしも周辺化するのではなく、地位向上を可能にするスペースを開くことを強調する(ミルグラム)。
…開発や保健プロジェクトじたいが、アキノ政権が、新人民軍に草の根レベルで対抗するために採用した、低強度紛争戦術と補完し合っていた。…と指摘。
…(キアトコウスキー)政府などの対処方法は、貧困を生みだす社会権力関係と分配という根本問題から目をそらし、個人あるいは家族、とりわけ家事と育児の責任者としての女性へと問題の所在を移し替え、巧妙に責任を転嫁したうえで、個々の女性にその自覚と対処を強要するのである。
(地区診断versus個人)
…バナウエ町は、マニラやバギオと直通バスが運行されており、イフガオ山岳部でもっとも豊かな町となっている。
▽361 ゴンザレス 棚田耕作が深刻な危機に直面している要因について、ゴンザレスは、キリスト教や近代的政治システムの浸透により、モンバキや伝統的リーダーが影響力を失い、共同作業のための指導力を発揮できないこと(グアテマラでも)。教育を受けた若者が農業に関心を持たないこと(能登も若者が出て行く)。農業外収入の増加や平地への移住という選択肢があるため農業への動機づけが失われつつあること。森林の管理保全が不十分なこと。などを指摘。棚田耕作を支える社会文化システムが衰退しつつあることが問題の根本にある、と。
▽363 ピナトゥボ火山噴火1991。毎年の雨期のたびに、降り積もった灰や砂が押し流されてきて、多くの集落が埋もれてしまった。
▽364 〓山南町は、薬草栽培の長い歴史をもつ土地。「漢方の里づくり」を地域振興のひとつの柱としていた。嫌われものの葛の活用を考えていた。これをピナトゥボに送ろうと。〓公民館の委員たちが中心となって、「田舎にいながらできる国際貢献」として葛の採取キャンペーンを展開。IKGsというNGOを発足。…1999年から2003年まで、高校生が現地に滞在してキャンプをした。
▽370
▽389 「グローバル」の植林。規模が大きくなり、ボランティアは少数派になり、植林は賃労働になった。そのため、除草が不十分で枯れてしまうケースが多かった。活着率は50~60%程度だろうとのことだった。さらに、ナウヤックが2002年にラガウエとラムットのあいだのダンハイ地区の国道に面した土地を購入して転出してしまう。
SITMoの事務所はキアンガンにある。
▽399 IKGSは、バギラットが代表をしているSITMoをカウンターパートに選び、…植林プロジェクトに加えて、バナウエ郡ウハ村にエコツーリズムのための伝統的家屋様式の宿泊ロッジを4棟建設。運営を担当する若者を養成した。宿泊客は2007年で200人超程度だった。観光客を継続的に誘致できるシステムが確立できていないことが課題として残されたままプロジェクトは終わった。
フンドゥアン郡長の協力を得て、ドジョウ養殖プロジェクトも実施した。〓
ドジョウは戦争中に日本人が持ち込んで増えたといわれており、棚田に水を張っているときは各家が細々とドジョウの養殖をしている。〓
キアンガン町につくられたドジョウ養殖池。フンドゥアン郡庁舎近くに養殖センター。
生産システムはできたものの、販路の開拓確保と輸送システムが確立されなかった。安定した販路開拓にフィリピン側は無力だった。(→〓〓今の課題は?)
▽409 政府のプロジェクトは、棚田地区へのアクセス道路を整備することで観光客誘致を図ることを重視した。耕作者自身にとってのインセンティブを高める具体的なアイデアとプランが欠如していた。棚田は効率が悪い。ホテルやレストランで働くほうがよっぽど収入を得られる。政府の肝いりで上から棚田の保全と観光を推進するほど、貧富の格差は増大し、棚田耕作は困難となる。
…ナウヤックの植林運動と社会開発の企ては、森と棚田のエコシステムによって支えられている伝統的生活の基盤を保持し、文化的アイデンティティを強化しようとする試みだった。環境と経済、文化、社会のすべての面において総合的な発展をめざすもの。社会開発という、新しい開発アプローチを先取りしていた。
□地域ネットワークの再編
▽418「下からのグローバル化」「草の根のグローバル化」の重要性。資本のおこすグローバル化の弊害への対抗策となりうるのが、国境を越えて活動するNGOのネットワークであり…
ハパオ村は古くから、グローバル大の勢力と対峙してきた。この20年ほどの狭義のグローバル化の特徴は、村人たちが自ら積極的に、大量に村外・海外に出て行ったこと。かつてのグローバル化は外から押し寄せる波であり、村人たちは陣地防衛戦を強いられた。近年のグローバル化は、生活を向上するために自ら積極的に打って出ていく出撃戦を展開している
(昭和30~40年代の出稼ぎとのちがいは? 船員も〓「打って出ていた」)
▽424 「コモンズの悲劇」市場経済において自己利益の最大化を追求することは、「神の見えざる手」によって社会全体の利益が達成するのではなく、悲劇が生じる、と。
一方、最近の主流は宇沢がいうように「コモンズは村や自治体が独立する重要な契機になっている」とみる。入会地は、共有する集落が共同体規制を働かすことで、再生可能な資源として維持管理されてきた。
▽430 ブラジル先住民カヤポ 大規模水力発電ダムに反対し、ビデオ映像を活用し、欧米NGOの支援を得て抗議活動を展開。全世界に向けた意思表明に成功して、世銀の融資中止とダム断念の決定を導いた。
第一世界と第三世界の住民とのあいだに、言語・文化・空間距離を越えて新しい連帯が生まれつつあるという新たな可能性。
(〓第一の側が第3から学ぶ形の交流が必要なのではないか〓)
▽432 2006年からはハパオ村のほとんどの場所で携帯電話が使える。携帯のテキストメールは、バギオ・マニラ首都圏、海外にいる人たちと結び絆になっている。通話料は高いから、通常は短いテキストメールでやりとりしている。
…ハパオ村を中心に、マニラ首都圏、リージョナルな香港やシンガポール、グローバルな中東やアメリカへと。彼らの考えるグローバルな世界は、親戚や知人たちの足跡が届く先々の都市と結ばれている放射状のゆるやかなネットワークとしてイメージされている。
…イフガオの人々。伝統的な洗骨儀礼と二次葬、祖先崇拝の儀式、威信財としての棚田購入(〓能登にはそういう感覚は? 外部の人が棚田に出資する、というのもひとつの威信財か〓)などの費用は、主として海外に出稼ぎに出た者たちの送金から捻出されている〓
▽434 国境を越え、地球大に広がるネットワークの拡散と表裏一体となって、ローカルへの回帰や再発見が導かれ称揚されていくという意味で、グローバル化とローカル化との共振的同時進行という理解が必要である。グローカル化。
(〓帰れるところのある人はローカル回帰できる。根っこを失った人たちは? 国家に吸収されるのか? 根っこのある安心感〓もっと地方とつながるべきでは? フィリピンの海外移住者も次の世代はどうなる?)
▽436 IKGs緑化協会と「グローバル」の連携協力。きっかけは、公民館の講演会で「葛を用いてピナトゥボ山噴火の被災地域を緑化しよう」と呼びかけたのを受け、実際に現地視察に赴いたこと。環境問題の関心と憂慮から。
(山南町側の交流のメリットは?〓)
▽440 遠隔地環境主義は、海外の環境問題を支援するだけでは道半ば。先進国の側で生活と社会を作り替えてゆくというブーメラン効果のなかに大きな可能性を秘めている〓(具体的には)
▽441 下からのグローバル化 レイナルド・イレート「キリスト教受難詩と革命」
辺境からのグローバル化 モーリススズキの「辺境から眺める」、中村哲「辺境で診る 辺境から見る」に触発された。
▽あおぞらピース・フォース 大竹明日香


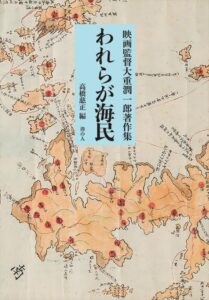

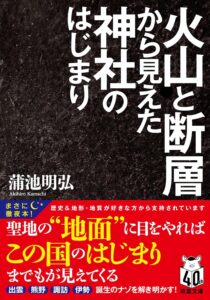

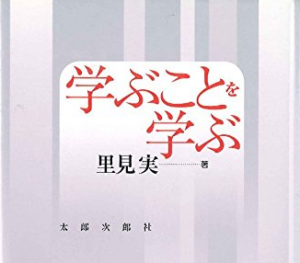

コメント