社会評論社 20050402
筆者はイラクで人質になり、「自己責任」のバッシングの嵐にさらされた。だが、テレビの画面からは頑としてゆずらない意思の強さが伝わってきた。同じようなめにあったら、私ならばめげて形だけでも謝ってしまうだろう。彼はなぜこれほど確信をもって堂々と行動できるのか。そう思っていたとき、この本を知った。
筆者は陸上自衛隊の精鋭部隊の第一空挺団に入隊し、戦場に行きたくて右翼団体に入ってビルマに渡った。新右翼の一水会をへてサヨクに転向して、東アジア反日武装戦線の受刑者の救援運動や、中東にいる岡本公三の生活支援……。普通の人間の何倍もの密度の時間を駆け抜けている。これらの体験を「論」ではなく、かっこうの悪いことを含めて自分をそのままさらしているから面白かった。
「暴力」と直接対面する経験のなかで、「非戦」の思いを強めたという。
抽象的に「平和」を唱える運動や護憲運動にはない具体性と重量感がある。
彼の生き方から私は何を引き出すか、というと、ハタと困って、うつむいてしまうのだが。
---------------
▽跳びだし塔からの「跳び」。もしあのまま、とびだすことができずに訓練途中で辞めてしまっていたら、現在の私の人格はなかったであろうとさえ思うのだ。
▽御殿場の飲屋街 米軍の演習時期になると、真昼間でも若い米兵が道を歩く若い女の子に平気で声をかけ、絡んでくる。
▽カレン民族 95年、マナプロウ陥落。10万人の難民がタイ領内へ。
▽やくざ右翼をやめる。所詮、政治的求心力のない彼らは、構成員を繋ぎとめておくためには「義理と恐怖」しかないのである。自衛隊で合理的感覚になじんできた私にとって、やくざ右翼の面子などどうでもよかった。カレンに行くために彼らと接近した。ただ、それだけだ。
▽一水会の運動は、いかに世間から目立つかということに手段が集約してしまっていた。「目立てばよい」というものでしかなかった。
▽代々木公園のイラン人と語る。代々木公園はイラン物産展のようになる。
▽このときの私は「戦争は攻撃する者がいれば、守る者がいる。それは必要悪であり、殺す者がいれば殺される者もいる」といういうように、まるで自然災害であるかのように観ていた。なぜ戦争が起こるのかという問題意識がなかった。
▽一水会 武闘派が牛耳ること、外国人労働者を排除することなどへの反発。自己批判。
▽右翼活動に区切りをつけるには、天皇制批判が不可欠だった。「古事記」からしても、天皇の祖先は「まつろわぬ神々を初めとする国津神ら」を騙し討ちで殺し、その土地を侵略してきた内容が描かれている。我々日本人は、そんな歴史に対して悪びれることすらない。神武東征、琉球侵略、蝦夷反乱の盗伐、アイヌ支配…。そういう社会構造のなかで生じる弱者切り捨ての身分制。被差別部落の存在。こういう社会の矛盾を踏み台にして、天皇を価値観の頂点に掲げる社会が存在している。日本が侵略国家であることは、大和朝廷のころから。そういう日本国家と天皇家に「誇りを持って」生きている者すらいる。
▽拘置所 差し入れの委託業者が販売する品の値段は、市販の倍以上。そこで購入しなければ差し入れができない。 ▽野宿者支援にも。段ボール集めを手伝う。
▽岡本公三と同居。岡本はパレスチナでは英雄だった。重信房子が逮捕されたとき、黙ってうつむいて目頭をぬぐった。
▽軍隊の合理主義に身をゆだねるとどうなるか。「弱い者は切り捨て、強い者だけが生き残る」ということだ。このような、人間性を喪失した先にある社会は、人間の情緒的交流を遮断された「閉じた関係」しか残らない。
▽イラク入国直後は、立ち入り禁止の廃墟ビルを撮影しようとして「劣化ウラン弾で攻撃された可能性が高い。広島・長崎と同じ問題だ!」というと警備の民兵は「他の者が来たら許可しないが、お前は日本人だかr許可しよう」と案内までしてくれた。ところがわずか短期間のうちに、「敵」となる。
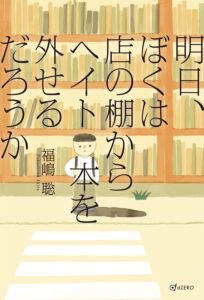
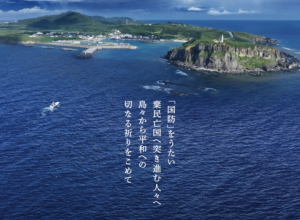

コメント