■放射能を食えというならそんな社会はいらない、ゼロベクレル派宣言<矢部史郎>新評論 20121229(速読)
「3.12」をきっかけに、市民が自らの思いを街頭で表現するようになり、さらに、自分たちで放射能を計測する動きが生まれた。
政府や原発容認派はシーベルト(空間放射線量)を重視するが、筆者は放射能そのものの量をあらわすベクレルを重視する。ベクレルに核種ごとの「実効線量係数」をかけて算出するシーベルトは「人体への危険度をあらわす」とされるが、その係数じたいがひとつの数式モデルにすぎず、推進派が民衆をだますためにあみだした単位ともいえるのだという。
「古い科学」は専門家が象牙の塔にこまったまま、市民を研究対象として位置づける。市民参加で計測するような「新しい科学」では、市民もまた研究の当事者であり、科学者もまた研究対象でもあるという複雑系の立場をとる。
「古い科学」の典型が、テイラー主義だ。要素を分解してそれぞれの効率を最大限に高める。トヨタの看板方式やQC運動などが依拠する考え方だ。だがそれぞれの要素を最大限効率化することで、全体のシステムはきしみが生まれ、労働者が次々に倒れる職場ができあがる。
「古い科学」は、分解して統合するというフランケンシュタイン方式であり、「新しい科学」は全体を全体としてみる漢方薬のような考えかたといえるだろう。
震災がれきの広域処理問題については、広域処理で使われた焼却場や処分場は、がれき処理終了後に、福島第一や今後廃炉となる各地の原発からでる膨大な放射性廃棄物の引き受け場所になる可能性がある、という。低レベル放射性廃棄物のリサイクルを既成事実とすることが最大の目的のひとつだと指摘する。
大学生の思考能力の減退 背景のひとつは、一次産業や商工業などの自営業者が激減したこと。自営業者がもつ「考えるハビトゥス」が絶滅しかけているのでは。
ソ連崩壊の真の要因はチェルノブイリだった。




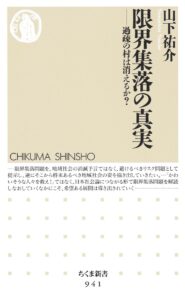
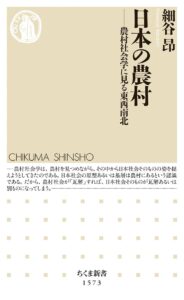


コメント