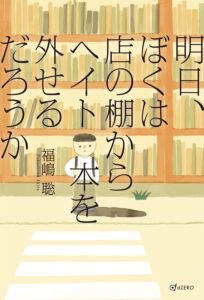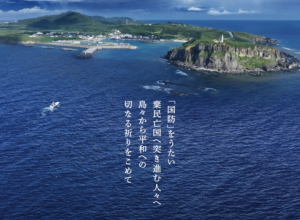ちくま新書 20060502
2005年秋の総選挙で自民党圧勝したことにショックを受けたのは、野党陣営だけではなかった。自民党に入れた人たちも「勝ちすぎ」と戸惑い、保守派の論客が「ファシズム」危惧する。
なぜそんな事態が起きたのか。だれがそんな事態をもたらしたのか。マスコミが悪いのか……。そんな疑問を解いていく。
テレビは「視聴者のために」と良心的に番組をつくっていた。だが、その良心的な番組じたいが、今回の結果を招いたという。
モダニズムの時代は、反権力・反エリートイコール大衆だった。「大衆のために」番組をつくっていれば自然に反権力になった。ポストモダニズムになってその構図は消えた。
大衆が保守化した、というより、より多くの人間が好む方向に自分をあわせるようになった。「勝ち組」「セレブ」に反発を感じるどころか、自分には手の届かない存在・偶像として憧れ、それに自己を重ね合わせようとする。逆に自分たちよりほんのちょっと待遇がいい公務員をたたく。その根底には大衆の「絶望」があるという。一方、知識層にはマヒが蔓延している。
戦前のドイツやイタリアや日本でファシズムが台頭したときもそうだった。たとえばドイツでは中道左派系の新聞が多数を占めていたが、ヒトラーの急激な伸張を「どうせ長くつづくまい」と見くびり、マヒ状態のまま大勢に流されていった。新聞は弾圧によって崩壊したのではなく自滅したのだった。
----抜粋・要約-----
▽保守派を代表する中西輝政さえ、週刊文春に「小泉人気で大勝した今の自民党は、ロイド・ジョージが率いたイギリスの自由党やヒトラー、ムッソリーニのファシズム政権と極めてにている。いずれもその後の国政に大きな混乱をもたらし、崩壊の道を辿った」と書いた。右左という従来の「軸」が、完全に混乱している。
▽「すべてをリセットしたい」「複雑なことは考えられない、黒か白しかない」と訴える人が精神医療の現場に現れれば、「この人の心理的エネルギーはかなり衰退している」と考える。心の健康度が問われる選挙なのかも・・・
▽郵政解散「参院が否決して衆院解散はおかしい」「政治的空白を作るのは無責任」と当初は解散、総選挙のプロセスに疑問の声が挙がっていたが、いざ選挙戦がはじまると、そうした「そもそも」論は消し飛んでしまった。いったんそうなったからには「この中でどう振る舞うのがベストか」を見極め、身の処し方を決めるしかない。「そもそもおかしい」などと話を蒸し返しても生産的でない。
この圧倒的な現実追従主義は、大儀なきイラク戦争に突入したアメリカを支持して自衛隊の派遣を決め、「自衛隊も出かけたからには次は憲法改正を」と言い出す日本政府にも通じる。多少の問題があっても、強行に実行してえしまえば「やったもの勝ち」で、誰にもとがめられることはない。
▽「セレブ」と自分とのあいだには、もはや自助努力ではどうにもならないほどの格差があることを実感しているからこそ、やっかむことも反発を覚えることもやめてしまったのだ。
▽ホリエモンを擁立したことじたいが、小泉自民にとって不利な材料になると書いたマスコミも少なくなかった。だが、マスコミの予想は大きくはずれる。都市部では、堀江は亀井にかった。
▽マスコミを動かすのは「民意」。「社会が欲情するかどうか」。オウムの元信者の別件微罪逮捕は報じても、数日後に不起訴で釈放されていることは決して報じない。
▽「ポピュリズムとは、普通の人々とエリート、善玉と悪玉、味方と敵の二元論を前提として、リーダーが普通の人々の一因であることを強調すると同時に、普通の人々の側にたって敵に向かって戦いを挑むヒーローの役割を演じてみせる劇場型政治スタイル」「ポピュリズムは、イズムと呼ぶほどの体系的理念をもたないことこそがその特徴であり、近年は、特定個人への信頼、アイドル化を特徴とし、政治のショービジネス化こそが・・・」
▽「郵政民営化ってそうだったんだ通信」 企画書 中村てつじ前衆院議員のhpで公開中 「郵政民営化・合意形成コミュニケーション戦略」案
構造改革とIQをふたつの軸とし、「構造改革ポジティブ・IQロー」という層について「具体的なことはわからないが、小泉総理のキャラクターを支持する層」と説明し、ここに重点をおく方針を記している。テレビ中心のポピュリズム政治を支持する層。
これまでの日本の近代的ポピュリストたちは、この層が支持基盤であったにもかかわらず、IQが高い層の目を意識し、その層の見解がじわじわと下の層に伝わり、結果的に彼らを動かすというやりかただった。今回は、「よくわからないけれど、とにかくおもしろい」と言ってくれる人たちにだけ、笑顔を向けて手をふる。
▽ワーグナーはヒトラーに愛された作曲家のイメージが強い。。小泉首相を伴ったシュレーダー首相は、戦後はじめてバイロイト音楽祭に出かけたドイツ首相となった。
▽「沈黙の螺旋」の4段階。(1)権力者が大声で「これが緊急の課題だ」と、誰も関心なかったことについて言う。だから当座は明確な批判や反論がでない。(2)批判がでてこないからその課題を正しかったとしてしまう。(3)遅れてでてきた批判は非国民的意見として排除する。(4)大勢に乗り遅れるのを恐れて批判がなくなっていく。雄弁は沈黙をうみ、沈黙は雄弁を生む自己増殖のプロセスのなかで、一方の意見のみが公的場面で支配的となる。つまり、最初に誰かが声高に「これが正解だ」と主張すれば、あとは「孤立への恐怖」が少数意見を自動的に排除していく。
▽ワイマールでは、3大紙という新聞をはじめ、その多くがリベラル左派であった。「1930年の選挙で107議席というナチスの大勝利に驚愕したが、景気が回復すればナチスは退潮するとたかをくくり、・・・ヒトラーを軽侮し、SAの暴力を恐れていた。投票日直前にナチスは何議席を獲得するか、という質問を受けて、・・・は36と予測。インテリの時局認識はこの程度だった」(加瀬俊一の「ワイマールの落日」)
1933年には、ヒトラーは政権を掌握し、新聞弾圧も始まったが、リベラル知識層はマヒ状態にあり、わずかに、どうせヒトラー政権は長く続くまい、と考えて、自ら慰めていた」
新聞は弾圧の結果、というより、半ば勝手に自滅していったのである。
ヒトラー政権誕生時の国民の目にワイマール体制はどう映っていたか。「女々しい小説が流行し、尚武の制止は消滅し、街頭は・・・暴力団に占領され、どこを見ても左翼のインテリが大きな顔をしてのさばっている・・・これが保守的国民の抱く不満だった」。
▽ファシズムも国家の内側においては、国民の平等を担保する。自国民に対しては「優しい」のだ。社会的弱者や負け組に対して国家は基本的にめんどうをみないという新自由主義的傾向を強めている小泉政権は、「優しさ」を欠いているので、ファシズムではないと。。。
▽かつて弱者とされたような階層が、むしろ保守的なマッチョな政治を強く支持する。 ▽ポストモダンに適合的な形態は、ネオリベラリズム。ネオリベラリズムは、福祉国家的な政策を批判して資本主義の自由な市場競争を肯定する。ポストモダニズムは、こうした「ポスト福祉国家的資本主義」の展開とともに。
あれほど到来を待ち望んだポストモダン社会が、こぞって演技やゲームに走り、権力に対して沈黙を決め込むしかない社会だった、というのは悪夢でしかない。
▽堀江をもちあげたことについて見解を求められて「あのメディアの持ち上げ方、何ですか。自分の持ち上げ方を棚にあげて、改革まで私の責任と批判している」 武部は会見で「道義的責任」を問われて「あなたはどう責任を取れと言っているのか」と逆に記者にくってかかった。「粛々と受けとめる」といった沈黙や留保、消極的程度は、自分たちにとって不利ということをよく知っているのである。
しかも強気の態度に出られると、少しでも思い当たるところのある人はとたんに弱気になる。小泉らに責められたマスコミは、すぐに自己反省をして見せ始めた。
「強く出れば相手は納得し、引き下がる」と悪徳商法さながらに攻めてくる首相以下の手口にまんまと乗ってしまっているのだ。
▽マスコミは、かつては「大衆」「流行」の側に足場を置き、結果的に権力や教養と対立する形となっていた。ところがその対立の図式が崩壊した今、マスコミはその立ち位置を「反・権力」の側に置く必要もなくなった。「庶民」「大衆」が権力や教養に対立する存在ではなくなった今、「多くの視聴者に喜ばれるもの」が結果的に「権力の思惑にかなうもの」になるという事態が生じている。