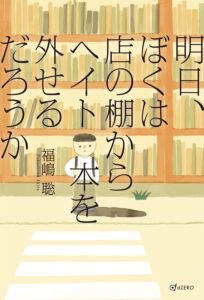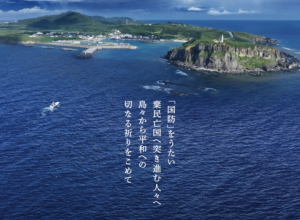角川 20060507
民俗学者の柳田国男からときおこす。
柳田は第1回普通選挙の結果を見て、旧来の地縁血縁によって投票していることに憤り、「明治大正史世相編」の最後に「われわれは公民として病みかつ貧しいのであった」と記した。
村的な共同体や利権、地縁血縁的な「多くの無意味なる団結」を抑制して個人をいったん自由なものにする必要があり、そうすれば「有用な組合」つまり「公共性」ができあがると主張する。(内橋克人の「有志共同体」という考えはこれに近い)
実際にそうした「無意味なる団結」は戦後も支配しつづける。だが、それが壊れて「自由」になったとき、人々は「有用な組合」に向かうのかどうか。小泉フィーバーを見ていると、「有用な組合」どころか、ポピュリズムに流れ込んでいるのだが。
「公民の民俗学」を主張した柳田はしかし、おかしな方向に転換する。
昭和10年前後のナショナリズムやファシズムの勃興期のなかで、日本人にしかわからない「心」の領域、形に見えない「伝統」を共有するのが「常民」だと柳田は言いはじめる。
こうして「公民の民俗学」はわずか数年で頓挫し、ナショナリズム的な「常民の民俗学」に変節していく。
筆者が目指すのは柳田が変節する前に唱えた「公民」の形成だ。それこそが憲法が目指した方向性だという。
「憲法前文」を子どもに書かせると、「私」という一人称からはじめ、次に違うだれかを認識し、最終的に複数形、集団を意味する語が選ばれることが多いという。この思考プロセスは、「われわれは1回群から離れて個人にならなくてはいけない。個を出発点にしながら最終的にある共同性に至らなくてはいけない」という柳田の「公民の民俗学」の枠組みと重なり合っていたという。
-------抜粋・要約-------
▽類似する昔話をずらっと並べていけば、ある共通項が見えてくる。これがつまり「原型」であって、それが歴史の過程で枝分かれしていったはずだという理論をもとに、本質的な要素を見出している。
柳田はこの重出立証法について「重ね撮り写真の方法にも等しい」と言っている。
優生学からでてきた考え方。ある特定の人種の顔写真を同じ構図でたくさん撮り、1枚の印画紙に重ね焼きしていく。そうすると、人種としての共通の部分だけが浮き上がった普遍的なその民族の顔が科学的に抽出できるという考え方だ。
ユダヤ人への偏見を人種の遺伝的特徴に還元するものだった。
これを民俗学に採用した。ある民族の特質を「心」のレベルで人種的遺伝的に定義していくという考え方自体が、重ね焼き写真の方法という進化論の直接的影響下にあった思考から導かれた産物だった。
つまりこの心的領域の遺伝こそが「伝統」と呼んでいるものや、日本人の本質、特性、共通性といった仮概念の前提になっている。
▽柳田は「心意伝承」という日本人に共通の心を提唱する。外国人には理解できないもので、これを知るのが民俗学の目的であると言うまでになってしまう。「公民の民俗学」がもっていた「個」から出発して、お互い交渉しあいながらパブリックなものを作り上げようという方向とは明らかに違う。
だからよく言われる「山人論」から「常民論」への転向より、より本質的転向は、公民の民俗学から伝統の民俗学へという転向だった。
▽愛郷心もナショナリズムに利用されてきた。昭和初期、郷土の復興、が唱えられる。恐慌の影響で農村漁村が非はいしたためにそれらを復興させていこうという社会運動がおきる。その過程で、文化的な伝統の回復が地方経済の回復のために利用されていく。そこで国家主体の民俗調査が必要になってきて、柳田民俗学が国策に堂々と合流するという運命になる。
現在の不況下において、地方の経済的な復興と郷土の文化的な復興が結びついていくとしたら、それは昭和初期と同じ道をたどっていることになる。
戦時下の都市伝説に、戦争で死んだ人の魂が村の神社に戻ってくる夢を見たというのがけっこうある。靖国神社ではなく「郷土の神社」だ。「郷土」はナショナリズムという問題を見せないで、国家が人を動員していく手段として作られた側面がある。
▽「島国根性」「単一民族」「日本人は個がない」という日本人論。
日本文化の進化論的な劣性を主張するローウェルの「個」の未成熟論が出発した日本人論。明治期の外国人によって語られていた俗論が、戦後にあんって日本人均質論としてでてきた。
「島国根性」も、もともとはイギリス人に対して言っていた嫌みの決まり文句らしい。実は「島」は開かれすぎていて困るぐらいだった。
▽「押しつけ憲法論」 日本の憲法制定時の状況は、イラク戦争後のイラクと同じ状態。占領下での民主化がすべて占領軍の思惑だ、と言い切ってしまっていいのなら、たった今、イラクで行われていることがイラクの人々への貢献であると口にする根拠のいっさいは失われる。仮に占領する側の論理に一国の利害しかないとしたら、それはただされなくてはいけない。日本国憲法のなかに占領する側の政治的都合を超えた理念があったのか、なかったのか考える必要がある。
▽9条の原型のひとつがフィリピン憲法。世界中の憲法を見比べ、つぎはぎして、草案をつづった。このとき、英訳された各国の憲法資料を提供した一人が政治学者の蝋山政道だった。
▽江藤淳「占領史録 第3巻 憲法制定経過」 鈴木昭典「日本国憲法を生んだ密室の9日間」〓〓
▽アメリカが押しつけたと言っても、書いたアメリカと、戦後日本の「同盟国」というより日本が属国にしてもらったアメリカとは実は違う。「押しつけ憲法論」は、後ろのほうのアメリカに都合のいい神話なんですよ。一見、日本のナショナルアイデンティティーの発露のように見えながら、アメリカの新たな「押しつけ」(改憲)を肯定するものでしかない。