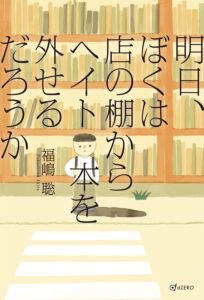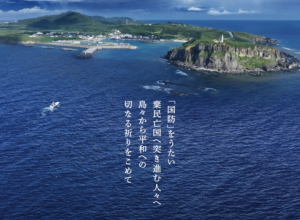岩波書店
歴史が100%客観的であるという考え方を著者はまず否定し、歴史には解釈的な側面と同時に情緒的な側面があることを認める。だが「つくる会」的な歴史相対主義に陥るのではなく、過去について真摯であろうとしなければならないと主張する。
過去と真摯に向き合うためには、異なる歴史表現メディアが、過去についての理解や感情にどんな影響を与え、わたしたちの行動にどう影響しているのかを考察しなければならない。この本では、歴史小説、写真、活動写真、漫画、ネットといったメディアについて分析している。
たとえば歴史小説は、「私」の人生を、社会全体・国全体の歴史と一体化するという役割を果たしたという。吉川英治の「宮本武蔵」が「精神動員」に即した寓話だったとははじめて知った。
写真は、歳月の経過とともに自分と世界がどう変化するかを認識させるから「記憶を歴史にする」効果を発揮した。
活動写真ではスピルバーグの「アミスタッド」をあげる。アメリカの歴史は常に自由と正義を求めつづけており、奴隷制度擁護はつかの間の逸脱だった、という印象を与えることで、建国の父祖から現代人までを含む「我々アメリカ人」を創りだす役目を果たしたという。歴代大統領の演説にでてくる「自由を求めつづけてきたアメリカ」という表現と同質のものだ。
漫画は、白土三平の「忍者武芸帖」が60年代の学生を唯物史観に目覚めさせ、小林よしのりが若者の歴史認識に影響を与えた例などをとりあげている。
【要約・抜粋】
▽つくる会教科書への批判は、事実の誤りや脱落をやり玉にあげていた。だが、個別の誤りや脱落を追及するうちに批判のエネルギーは、特定の出来事や文献をめぐる論議に細分化され、根本にある歴史学の問題にとりくむことが忘れられた。
▽ポストモダン、ポスト構造主義が影響力を強めている。あらゆる叙述は構成されたもので、異論の余地を残しうる、という事実を意識している。そのためにつぎのようなジレンマに直面する。「つくる会」の”間違った”叙述をそれにかわる権威ある”正しい”叙述に置き換える単純な実証主義に陥ることなく、つくる会を効果的に批判するにはどうしたらいいのか。
西尾幹二は擬ポストモダン主義を使って、「歴史は科学ではない……人間的解釈の世界である」という歴史相対主義を「新しい歴史教科書」にもちこむ。「国の数だけ歴史があっても、すこしも不思議ではない」と言う。「今の時代の基準からみて、過去を裁いたり、告発したりすることを」戒めながら、その一方で、むかしの日本の仏教芸術作品が「イタリアのドナテルロやミケランジェロに匹敵する」とする主張の根拠として現代世界共通の美の基準をもちだしてはばからない。
▽過去についての理解は、たんなる知的システムではない。純粋な知識と同時に感情と想像力をともなうものだ。
□歴史小説
▽平家物語のような叙事詩やシェイクスピアの芝居における時間の感覚は、変化の理解というより、痛みをともなったはかなさの意識である。リアリズム歴史小説はこの感覚を、社会という変化する物質世界の説明によって実体化するようになった。こうして国民は「社会」を構成する無数の人間の生と密接にねりあわされた歴史的側面をもつものとされる。ルカーチはこの変容がフランス革命とそれに続いたナポレオン戦争という出来事のなかで生じたとみる。その中核には、広範な社会参加という要素があった。はじめて歴史は大衆の経験、となった。……人間の精神や感情の内面を探るという個人としての人間の主観への新たな視座と、国の歴史の流れへの集団的関与の意識の高まりとがあいまって、歴史小説の生まれる余地を拓いていった。
リアリズム歴史小説は、現在に生きる読者と過去の人々とのあいだに新しいかたちの想像の繋がりをつくりだした。登場人物の人生と物語に浸ることによって、社会全体の過去とも一体化できる。個人の人生を綴りあわせて国のなかの社会変化という織物に織り上げることによって、小説の限界をこえる影響力を発揮して歴史そのものの叙述法にも影響を及ぼした。
▽島崎藤村は明治維新前後の出来事を描いた小説「夜明け前」を1920年代末から30年代初めにかけて書いた。司馬遼太郎の「坂の上の雲」は、1904年から05年の日露戦争の時代を1960年代後半に書いた。……歴史小説の理想は半世紀前をふりかえること……。
▽日本の近代歴史小説の先駆者鴎外は、史料に厳密に依拠している。英米の作家による歴史の再構成にきわめてにた歴史小説の伝統を確立し、この伝統が、戦後になって司馬遼太郎や井上靖などの作品が人気を博す土台になる。
1920、30年代には、歴史物語を時代の政治的関心事と符号するように書くようになる。吉川英治の「宮本武蔵」は、政府が30年代末に展開していた「精神動員」キャンペーンに即した寓話として仕立てた。小次郎がテクノロジー「技」を代表する一方、武蔵は優越的な国民精神の力を代表する。「小次郎が信じていたものは、技や力の剣であり、武蔵の信じていたものは精神の剣であった」。小次郎の拠点である巌流島に向かう武蔵の舟旅の劇的な描写が、海南島への日本軍の侵略とノモンハンでの初の日ソ交戦を報道する朝日新聞の記事と同時に、しかも並んで掲載されて、強烈な効果を与えた。
▽近代の歴史書と近代小説が、国家建設のプロセスにしっかり結びついている。
▽中国を舞台にした小説は多いのに、朝鮮はあまり登場しない。イギリスの大衆的歴史小説の風景でのアイルランドの不在と同様に、植民地支配の関係というやっかいなエコーを響かせずに朝鮮の過去をとりあげるのがむずかしいのである。
□写真
▽写真、映画といった新技術は、小説よりはるかに広範なインパクトをもつようになる。ほとんどが中流階級の枠内にいた小説をよむ「大衆」より、ずっと幅広い層まで届き、国や言語の境界さえ超える。
▽中国の戦争写真。南京虐殺にの写真に、「つくる会」の藤岡らが信憑性に疑いを投げかける。……「疑わしい」写真を並べることで、攻撃対象のすべてが等しく贋作あるいはウソの写真であると規定し、それらを戦時中の日本の雑誌から選ばれた「真実」の写真と対比させる。後者の出所、構成、ラベルについてはいかなる批判的吟味も加えない。
▽長崎原爆の山端庸介の写真。
▽写真アルバムを中心に記憶を再構成するなかで、それと気づかずに記憶の質をかえる。出来事を内面の経験から回想するだけでなく、対象化もするようになるのである。自分自身や家族を絶え間ない変化の一部としてみるようになる。色あせていく写真のなかに自分の顔を見てはじめて、歳月の経過とともに自分が、そして自分の住む世界が、どんなに変わったか認識するからである。写真アルバムは記憶を歴史にする。
▽マッカーサー 戦後日本で天皇のカリスマを戦略的に利用するには、裕仁とそのほかの軍事指導者たちとのあいだに明確な一線を引くこと、軍事指導者から平和を愛するよき家庭人へと天皇のイメージをつくりかえることの両方が必要だった。戦時中の写真の天皇は、たいてい軍服姿だが・・・・
□活動写真
▽スピルバーグの「アミスタッド」 現代のアメリカ国民までを結び、一致団結したアメリカの「われわれ」を創り出す。建国の父トマス・ジェファソンをアミスタッド事件と結びつけることで、現実のジェファソンが奴隷制度の熱烈な批判者からバージニア州でもっとも大規模な奴隷所有者のひとりへと変節したという現実をうやむやにする。
歴史を映画化したものが大ヒットすることで、そこから評論、インタビュー、テレビ、教材、本などが生まれる。歴史認識への影響を与える。
□漫画
▽はだしのゲン
▽アウシュビッツを描いたアート・スピーゲルマンは、動物の姿を借りて恐怖を表現する。
▽日本の漫画の絶大な人気のひとつの要因として、木版画の伝統があると信じられている。紙芝居の影響もあったろう。
▽漫画の視覚的可能性を国際的にも変容させることになる技術革新。その先駆者が手塚治虫だった。変容の鍵は、長編の誕生だった。物語やキャラクターの展開が容易になっただけでなく、特定の場面をたくさんのコマにまたがって大きく描くことで強い視覚的効果をあげることもできるようになった。
▽白土三平の「忍者武芸帖」は、忍者影丸の冒険をとおして16世紀の貧農たちの苦闘を描いた。60年代世代の学生の多くを唯物史観に目覚めさせたとしてよく知られている。
▽小林よしのり
アピールするのは、過去と現在を同時進行させられる漫画の力を活用しているからだろう。小林の漫画はたんなる過去の叙述ではなく、つねに現在についての論評である。小林の顔が自身の描く歴史をじっと見おろし、現在の敵、意見を異にする学者やメディア関係者、の大群とたたかいをくりひろげる姿が描かれる。描く漫画すべてに自伝を織りこむことで、歴史上の出来事を自分の名誉希求にみたててしまう。
▽過去についての特定のイメージを読者の心に押しつける一部の漫画芸術の「全体主義的」な力にいかに対抗するか。全体主義芸術は20世紀中葉の中央集権的な独裁国家で発達した。その手法のいくつかが漫画に生き残っている。……
□マルチメディア
▽サンフランシスコの「科学・芸術・人間理解のための博物館」exploratoriumは、山端庸介の写真を中心にしたウェブサイトを開いている。展示の一環としてインターネット・ディスカッション・グループをほっそくさせた。
▽幅広いさまざまな意見にもまれて、いかなる明確な意見の形成も拒否してしまう精神状態に陥るかも……。複雑な情報時代においては、おびただしい数の相反する叙述の集団にすぐに圧倒されてしまう。しかし、結論をエキスパートの委ねたい、という衝動は危険である。それは真空地帯をつくりだし、そこにすぐ最新のイデオロギーがするりと入りこんで埋めてしまうからである。漠然とした無関心と、メディアによって操作された大衆向けパフォーマンスにたいする狂信的熱狂とは、ひとつコインの表裏にすぎない。
▽従軍慰安婦問題問題での否定派のアプローチ。議論条件を再定義し、議論を意図的に狭めて、ひとつの特定の争点「日本軍によって強制的に連れてこられたのか否か」に絞る。次に、具体的な史料や証言を選択し、信憑性に集中攻撃をくわえる。特定の女性が軍によって強制的に徴集されたことに疑問を投げかけることで、ほかのケースにも疑念を生じさせ、暗黙のうちに軍の暴力の犠牲者としての「従軍慰安婦」のイメージを否定しようとする。ナチスのホロコーストも、南京も、アボリジニ虐殺も、すべておなじ二段階戦略がくりかえし展開される。