朝日新聞社 20070908
筆者は保守の立場から戦争を研究し、対談相手も保守的な人が多い。だから、外側や後世の視点からの批判ではなく、当時の視点から、軍の内側からの視点で「なぜあんな愚かな戦争をしてしまったのか」を論じていて説得力がある。
陸軍と海軍をくらべて海軍がリベラルであり、戦争にも反対していた、という論がある。たしかにそういう一面もあったが、海軍が自分の利益、予算獲得だけのために戦争に賛成し、「どうせやるならアメリカと戦力差が開かないうちに」とむしろ開戦を急がせていた。
明確な国力差があり、あてにしていたドイツは日本の開戦直後には負けはじめた。なのに、国内世論は「勝った」「勝った」ともりあがり、和平どころではなくなった。大衆を盲従させるための嘘が権力側にブーメランのようにもどってくる。
統帥権が諸悪の根源だ、という一般論にも異論を述べている。実は統帥権は軍の非政治化をめざしたものだった。大正になって藩閥の力が衰え政党が台頭し、軍の力が弱まるなかで「神聖な統帥権を害する」と既得権擁護のために主張するようになる。一方で、長州閥が占めていた中枢ポストに軍官僚エリートが進出する。政党政治が腐敗するなかで「自分たちで改革を」と軍が政治的になる。普通選挙から3年後には満州事変が勃発し、翌年には五・一五事件がおき、政府の不拡大方針を関東軍が無視して暴走し、軍中央がコントロールしようとすると関東軍は「統帥権の干犯」と拒否した。「統帥権の独立」が行政介入を排除する口実としてつかわれるようになった。
政治的中立確保→既得権擁護→政治に対する軍部の要求優先の口実、と意味が変化していったのだった。
-------------------
□半藤
▽海軍には、日本の艦隊の戦力がアメリカの7割あれば勝てる、7割のうちに戦争を始めないと勝てない、という考えがある。7割が守れるのは1941年の12月までという計算があった。どうせ戦争になるなら早くなってほしくてたまらなかった。
▽最初海軍は対米戦争に反対だった。が、いま賛成して政府と陸軍に恩を売っておくと、今後予算が通りやすくなると知恵をつけた人間がいる。
▽ドイツが欧州で勝つのをあてにして、戦争を始めたが、ドイツはその直後から負けだした。ところが日本の国内世論は勝った勝ったで和平どころではない。
しかも、開戦直後の12月11日に単独不講和を定めた日独伊三国協定を結んでしまい、日本だけ先に講和できなくなった。
□戸部 統帥権が国を滅ぼしたか
▽自由民権運動の政治的影響が軍に及ぶことを恐れて、軍を指揮する参謀本部を独立させて政府と切り離した。「軍人勅諭」も、「天皇の軍隊」とすることで政治の関与を排したかった。軍人が特定の政党を支持したり、政党が軍人たちに働きかけることを警戒した。「統帥権の独立」の本来の趣旨は軍の政治的中立性を確保するためのものだった。
日清・日露のときは、政治が軍事を制御している。軍人と政治家の出自がどちらも下級武士の出身。武士は政治エリートでも軍事エリートでもあった。藩閥政治の体制下では、政治は軍に対して優位を保ちつつ、両者が一体化していた。
大正になると藩閥の力も衰え、政党が台頭し、軍の力が弱まる。そのなかで「神聖な統帥権を害する」と、既得権擁護のために主張する。
軍官僚エリートが、長州閥が占めていた中枢ポストに進出。軍事テクノクラートたちは、政治的な配慮より、軍事的合理性や陸軍の利益を追求しがちになる。
▽政党政治の腐敗。「自分たちで改革を」と軍が政治的になる。さらに、政治の側も、海軍軍縮会議をめぐり政友会が「統帥権の干犯」と政府を攻撃する。それが浜口首相狙撃を招く。権力奪取のため、軍と組んでしまった致命的なミス。
普通選挙から3年後には満州事変が勃発し、翌年には五・一五事件。政府の不拡大方針を関東軍は無視して暴走。軍中央がコントロールしようとすると関東軍は「統帥権の干犯」と主張して拒否。軍の内部でさえ「統帥権」という言葉で反発するから、陸軍省が介入をはかっても関東軍は拒否する。「統帥権の独立」が行政介入を排除する口実として使われるようになった。
▽政治的中立確保→既得権擁護→政治に対する軍部の要求優先の口実
▽太平洋開戦時、開戦まで偽装外交するよう強いられた東郷外相が、「それでは統帥部は開戦の日をいつと定めているのか。それを知らなければ外交はできない」と尋ねると、海軍の軍令部総長だった永野修身が「それでは言おう。12月8日だ。まだこの日までには余裕があるから、戦に勝つために都合のいいように外交をやってくれ」と言い放つ。
このときまで首相兼陸軍大臣の東条も、海軍大臣の嶋田も正式には開戦の日を知らされていなかった節がある。
▽東条はじつに律儀。首相の仕事は総理官邸で、陸軍大臣の仕事は陸軍省でやる。参謀総長として執務するときは参謀本部にいって軍装まで着替えている。……優等生の官僚的発想。リーダーシップは発揮しようがない。
……明治のリーダーは、幕府を独裁体制として倒したから、軍事と政治の全権を握る幕府のような存在を許さなかったのでは。平民から選抜して軍事エリートを養成しようとした。……武士が持っていた政治的センスを欠く、軍事テクノクラートを生みだした。
□秦郁彦
▽南京事件 捕虜殺害 入城式後の殺害行為までを戦闘行為とは言いにくい。また、軍律裁判の条例もあったし、法務官もいたのに、南京では裁判もやらずに処刑している。戦争犯罪と言われても弁明のしようがない。
▽南京は組織的ではない。日本軍は伝統的に補給を軽視していたことが虐殺・暴行の一因になった……。苦戦のすえ上海を占領し、補給のないまま、大本営の制止もきかず一気に南京に攻め込んだ。「徴発」の名目で略奪を働き、居合わせた女性を強姦してしまう。憲兵が取り締まりを始めると、発覚を恐れ、兵士が口封じに女を殺してしまうケースが増えてくる。入城前に司令部は軍紀を守るよう厳命していたが、現実は混乱の悪循環。
……16師団長として南京に入城した中島今朝吾中将は「捕虜ハセヌ方針」と皆殺しを奨励したり、「略奪、強姦は軍の常」と嘯いていた。
……捕虜になった兵士数千人を農村にかえすため、集団で南下させた。ところがその隊列は第六師団と鉢合わせになり、2000人の中国兵が殺された。その跡地に南京虐殺記念館がたてられ「市民28000人が虐殺された」ことになってる。
□森史朗 特攻
▽特攻を始めた大西長官(敗戦後自決)、内地にもどって軍令部次長になると、「一億総特攻」という立場に大転換する。「日本は最終的に2000万人の特攻死を実行すべきだ」と東郷外相に言っている。そうなればアメリカはびっくりして、こんな戦争は「やめよう」と言うだろう、と。
フィリピンで米軍とゲリラ戦をたたかう。「最後の一兵まで比島を死守せよ」と大西が命令を下す。……15400人が山ごもりし、生存者450名という惨憺たるゲリラ戦となった。
□辺見じゅん
▽東条の孫の由布子さん 少し慎みがないと。憲兵や特務機関を作って権力を駆使したのは、まぎれもなく東条だった。そのために亡くなった方々のことを考えると、もう少しひっそりとされてもいいのでは。
▽大和の有賀艦長が羅針盤に体を結わえて最期を迎えたという定説があるが、事実とは異なっていた……
▽保阪 特攻隊員の多くは童貞で死んでいる……従軍慰安婦の存在も、批判派の論点を全否定するわけではないが、すべてがいまの考え方に当てはめられている。
批判的に見なければいけない歴史もあるが、ではもし自分があの時代に生まれていたら、どうやって生きていたか。それを想像することが、時代を理解することになる。僕が当時の人間で、戦争反対と言えるかと問われたら……。
□福田和也
▽チャーチルの戦時内閣は、24時間起居をともにして指導した。日本の海軍省は1942年夏に夜になると明かりが消えていた。……24時間体制どころか8時間体制で戦争を考えていたのではないか。東条は陸軍大臣として参内するときは軍服を着て、参謀総長のときは参謀勲章をつける。なんとも余裕。
閣僚や陸海軍トップが起居を共にしたのは、戦後の巣鴨プリズンがはじめて。
□牛村圭
▽東京裁判は、開戦責任と侵略戦争遂行の罪を問う法廷。ところが、日本側は自衛戦争だという理屈があるから罪の意識は認められないし、共同謀議もないから、検事団の主張するような責任は負いかねる、という意味で、無罪を主張した。だが、「敗戦という苦しみを与え国民に対して申し訳ない。そのことについての責任は負う」と彼らは思っていた。
▽「パル判決」は、勝者の裁きの不公正さをつき、無罪を主張した。しかし意見書をよくよめば、無罪はあくまで起訴の訴因についてであり、日本が行った戦争が正しくて被告達が過ちを犯さなかったのではないことがわかる。
□松本健一
▽44年7月にサイパンが陥落して東条内閣が総辞職。10月、11月くらいから本土爆撃が始まり、45年3月に東京大空襲となる。そのとき前線の兵隊が味わっている死を、銃後の国民が初めて実感した。
当時の国民の気分として、国民を死に追いやった国家指導者の責任を問う「戦争責任」の追及は終わらなかった。それを察知していたから、天皇はA級戦犯の靖国合祀に不快感を抱いていた。
▽ジャーナリストの桐生悠々の軍批判の立脚点は、明治天皇の「五箇条のご誓文」にある。
岩波茂雄も「御誓文」を部屋に飾っていた。日本の民主主義は「御誓文」に始まっているという言い方が、昭和天皇の言葉にもある。「人間宣言」の冒頭にも「御誓文」が入っている。天皇制下の民主主義をとりもどそうとした。
▽昭和天皇は皇太子時代の1921年に欧州外遊にいく。いかせたのは原敬。天皇は「カゴの鳥」でも「現人神」でも困る。統帥権をふりまわすような事態は避けたいと……。だから欧州の立憲君主制や民主主義、議会制度をよく学んでほしいと送り出した。
……帰国した天皇はイギリス風の立憲君主制を採り入れたいと考えた。憲法、議会の運営のもとに天皇という機関があることは正しいと言っている。(天皇機関説) ところが軍人出身の岡田啓介首相は「現人神説が正しい」と言ってしまう。
□原武史
▽明治天皇は、日露戦争を開始するときに相当嫌がった。むしろ皇后が天皇の尻を押している感じ。
□渡辺恒雄
▽志願して特攻にのぞんだと言われてますが、上官に命令されたんですよ。志願しないとぶん殴られるから出撃する。だけど怖くて途中で帰ってきちゃう人もいた。人間魚雷にいたっては、出陣すると外には出られなかった。
▽南方戦線はとくに相当数は餓死だった。「万歳といって死んでいった」という歴史観はおかしい。遊就館の歴史観はひどすぎる。
▽戦後のある時期の厚生省引揚援護局は、軍そのもの。軍がつぶれていくところがないから援護局にまとめて入れた。その課長補佐クラスが合祀名簿をつくった。援護局の旧軍人と靖国の宮司、総代会の青木一男たちがトライアングルをなし、見えないところで旧体制を復活させてきた。
戦後参院議員にまでなった源田実は、桜花という特攻兵器の命名者。それが自衛隊空爆長として残った。
▽新聞が、満州事変の初期の段階で「これはよくない」と論陣を張らなかった責任は大きい。松岡外相が国際連盟を脱退したとき、新聞社は共同声明をだし「よくやった、よくやった」という紙面づくりをしている。……京都学派は海軍に身を売るが、西田幾多郎は「このばかげた戦争、早く終わらせなきゃだめだ」と大きな声でいった。……そういう声はあったが、新聞社内には極めて少なくて、売ることばかり考えていた。
▽朝鮮半島と台湾をれっきとした植民地にして、満州も事実上植民地にしたんだから、「植民地解放戦争」では断じてない。だから「大東亜戦争」というネーミングに対して、非常な反感をもっている。
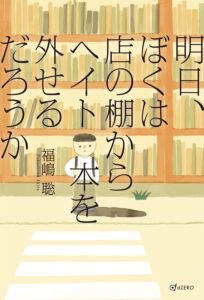
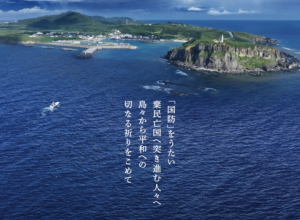

コメント