七つ森書館 20070729
農「業」はダメになるが、「農」は生き残る。農的生活は必要とされる魅力にあふれている。「業」として生き残るためには大規模化となるが、「農」には小規模のほうがよい--と説く。なるほど、と思う。「農業労働者」ではなく「百姓」のすすめである。
小規模多品種の百姓的な農業のほうが、生き残る可能性が高いことは、日本でもアジアでも中南米でも同じだ。選択的拡大という「業」を中心とする農業によって地域が崩壊してしまった。国の方針にさからったほうがむしろ良い思いをしている……。これらの指摘は私自身も実感していたが、世界各地の実例が豊富で説得力がある。
戦後民主主義的なものの評価も複眼的だ。「耕す者が土地を所有する」という原則が農地法によって確立され、それがぎりぎりのところで農村を守ってきたという。青年団などによる民主的な「改革」も評価できる。だが「改革」には負の側面もあった。結婚式を簡素化したり、夜ばいをなくしたり、若衆宿を廃止したり、フォークダンスを導入したり……と、悪いモノだけではなく豊かなモノをもふくめて「古いもの」を徹底的に排除してしまった。「いい収穫があっても『よくできた』というな、『よくつくった』といえ、と普及員の先生から徹底的にいわれた」というエピソードにいたっては唖然とするしかない。欧米的な合理主義によって、古くから農村にあったエコロジー的な要素を破壊することにもつながったようだ。
百姓の視点から経済や社会をみると、どれほど今の日本がゆがんでいるかがよくわかる。よっぽど地に足をつけて農村に暮らすか、丹念に取材してまわらないと、この本のような説得力のある文章は書けないだろう。
--------------------
▽農水省発表の02年度のゲタ 小麦68パーセント、大豆65パーセント、
コメ490パーセント
▽FAOによると、97-99年、穀物自給率は日本24%、韓国30%、北朝鮮69%。北朝鮮の飢餓は経済破綻して食料を買う金がなくなっただけの話。日本が経済破綻すれば即、飢餓。
▽商店街の衰退 こうしてみると商売人はもろい。逆に百姓は強い。
▽連合の「自然豊かな地方で暮らそう100万人故郷回帰・往還運動」
自由化を主張し、しきりに農業攻撃をしていたのに、口をぬぐって、余剰労働者がでたから農村へ、という。
マスコミの論調は株式会社が農地を所有できるようにするべき、というばかり。
▽ミカン消費量が激減。昭和50年ごろは年間19キロ。いまは6キロ代。たんに飽食の時代とか、では説明できない。日本の家庭からミカンを食べる場所、一家団欒がなくなったからでは。
昭和35年には世帯の3分の1が農家だった。45%が多世代同居だった。農耕社会だった。その後高度成長がはじまり、都市国家になっていく。ここから「なぜ日本に農業が必要なのか」という言葉がでてくる。都会の低賃金労働者にいかにやすい食料を与えるかが、農業の最大課題に。農業・食糧政策というより、労働政策だった。
「低賃金低農産物価格政策」 専門化・単作化。単一農産物を大量につくる産地が政策的につくられる。安いものを大量に、と。
▽戦後の農村の「改革」
結婚式改善(家で三日三晩続いていた式を、公民館での会費制に「公営結婚」)
「食べるための農業から売るための農業へ」
盆踊り改革 夜這いもやめて、若衆宿も率先して廃止運動をして、そのかわりフォークダンスをはじる。「古いものは悪いもの」という価値観が村全体を覆っていた。今から考えると、村をつまらなくしてしまった。
いい収穫があっても「よくできた」「よくとれた」というな、「よくつくった」といえ、と普及員の先生から徹底的にいわれた。百姓にとって主人公はあくまで自然だが、普及員は、これからの農業は自分が主人公なのだから「つくった」といえ、という。「できる農業からつくる農業へ」という合い言葉。
▽「意識化」 日本のNGOはあまりつかわないが、欧米NGOは使う。どぎつくいえば「洗脳」。
▽原節子とか高峰秀子とかは短足胴長でお尻は大きくて、農婦の役をしてもはいれる。浅丘ルリ子は完全に都会のメカニズムそのものという体型。あれでは百姓はできない。
▽宮本常一「忘れられた日本人」 村の古文書を貸すかどうかで、ああでもないこうでもないと議論する。こういう話のなかに、すでに死んでしまったじいさんの代の話まででてくる。決定のなかに、ご先祖様もはいっている。究極の民主主義。これに比べれば山下さんたちがやってきた因習打破の民主化のなんと皮相的なことか。
▽JAちちぶ 山間地農業だから大量にはつくれない。管内に10カ所ほど直売所をおいて、年間10億円売り上げている。だが、いまつくっているのは年寄りばかりで、このままでは生産が10年もたない……〓
若い人は「一姓」になってしまって。
▽東北タイの村を歩くと、えんえんと赤茶けた大地がつづくなかで、ぽつんとオアシスのように緑に囲まれた土地が目につく。雨をためる大小の池を掘り、池の周りに果樹、その下に野菜、池には魚。そして田という複合農業をやっている。リーダーがいて、いつのまにかそのまわりに農民が集まってきて、農民塾のようになっている。一昔前の日本の農村も、こうした人たちで支えられていたんだろうな。〓
▽山形の高畠町。米沢郷牧場〓 大型畜産をめざして借金まみれになった青年たちが、やはり単品生産で外部に依存する度合いが大きい農業はだめだと気づいて、もういちど複合経営からくみ立て直した農民集団。「自給できるものはすべて自給する」外からはできるだけ買わない。加工も販売も可能なかぎり自分たちでやる。
▽郵便局の合理化〓 トヨタ方式 越谷郵便局が導入。トヨタ社員が派遣され、秒単位で作業を見直す。仕分け作業も立ってやることに。1通あたりの仕分けは職員3.7秒、、ゆうメイトは5.3秒に。……年賀状が遅れたり、職員が突然死したり、集配回数が1日3回から1回になったり……。農業を合理化して自殺するようなもの
▽タイの「サマッチャー・コンチョン」(貧民連合) 「貧民」は、「貧しくなったのは最近」開発や農業の商品作物化、輸出型農業の奨励や工場の進出で、森がなくなり自給が壊れ、魚が取れなくなった。それまでも金はなかったが、飢えたり、娘まで出稼ぎに出すようなことはなかった。グローバリゼーションがうんだ貧困。
▽ミカン 選択的作物として奨励された国策作物。いちはやくグローバリゼーションの洗礼。植えるとき、「10年たったら左うちわ」が私の口癖だった。ところが昭和45年からコメ減反がはじまり、転作で田圃にミカンを植え、たちまち生産過剰に。さらに昭和63年に牛肉とオレンジの自由化。平成4年には果汁も自由化。ミカンを伐採すると補助金が出るようになる。
▽瞬間瞬間で農業はいいときがある。国にさからった農民はいい目にあっている。戦中、国家の命令にさからってミカンの木を伐らなかった農民はいっときの夢をみた。
▽直接払い WTOで農産物価格支持政策はダメに。それにかわって農民に直接金を払う。一種の生活保護。それを認定したプロ農業者にやる、といっている。一握りの農の業者をつくって国に取り込み、その他は棄民にする。
▽記録する大切さ 農民文学 山下世代がよく書いている。近代化以前の農業と以後の農業を両方体験している。佐藤藤三郎さんは「山びこ」、星さん、木村さん、斎藤たきちさんたちは、農民の文化運動を生涯にないつづけた詩人真壁仁さんの「地下水」の流れをくむ。その後の世代では、小川町の金子美登さん、三里塚の小泉英政さん、……全共闘世代。その後はいない。……若い感覚でいまの農村を書けばおもしろいと思いますけど。〓
▽百姓にとって土地は、先祖からの預かりもの。次の世代に渡すもの。百姓はリレーランナー。土地は減らさないようにして次に譲る。「生きているうちに少しでも金利をつけて少し増やして次に渡すのが百姓の生き方だ」と。
▽「耕すものに土地を」農地法は耕作者主義だけはかろうじて守ってきた。それがいま壊れ、株式会社の農業参入がはじまっている。とくに土建業。公共事業削減で。新潟の東頸城農業特区 土建業2社が7ヘクタール耕作しているが、07年度には100ヘクタールにするといっている。……外国資本や暴力団に農地が渡ることもありうる。経営が失敗して撤退する際、表土をはいで売り払ってしまった例も東頸城にある(p113)。〓
▽鳥インフルエンザ 無窓鶏舎を農水省が推奨。工業型畜産の象徴。そういう畜産がいまの危険な肉や卵をつくってきて、その延長線上に鳥インフルエンザも出現してきたのに。鳥インフルエンザを利用して、農家がやっている小さな畜産を淘汰しようとしているのでは?とも。安心して食べられる卵をつくっている農家が保健所にうるさく攻められて困っている。 無窓は病気がでたら、鶏はたちまち全滅。それを抗生物質で抑えている。
▽カンボジアはどこか落ち着きがあった。自作農だから。ネグロスでは、サトウキビだけの単一作物がどこまでも続き、百姓はおらず、地主と農業労働者しかいない。農場周辺の農業労働者の集落には声をのんだ。
▽FTA(自由貿易協定)やEPA(経済連携協定) メキシコとの交渉で豚肉が問題になった。が、メキシコの農民にとって豚肉の輸出は関係ない。アメリカがキロ200円でカナダからしいれてキロ400円で日本に売っている。農水省の「平成15年度食料需給見通し」にちゃんとそう書いてある〓。それが今度はメキシコを通って日本にくるだけ。
▽FTA。フィリピンから安いココナツが入り、タイ産が半値に、とタイ農民は怒る。逆に、フィリピン農民は、タイから安いコメや砂糖がはいってきて大変、と怒っている。カンボジアは、砂糖椰子からつくる砂糖が伝統産業として農村を支えていたが、タイからはいる白い砂糖に押されて需要が落ちこみ、値段も下がってしまった。
タイは、中国とFTAを結び、中国野菜が大量に入って大変なことに。
中国産FUJIという名のリンゴが東南アジアを席巻している。
▽イグサ農民の自殺〓 中国から輸入。イグサは日本しか使わない。畳需要が減ってるから6000-8000ヘクタールあればいい。が、中国では1万ヘクタールつくっている。日本の大手メーカーがむこうと直接つながっているから、イグサ問屋もつぶれる。元凶が日本メーカーであるのは野菜と同じ。
▽WTOでもFTAでも、農産物は余っているところから足りないところにいくならいいが、安いところから高いところにしかいかない。日本のような高いところで飽食の果てに捨てられ、そのぶん飢餓が拡大する。ベトナムでもタイでも、それぞれが生きていくために、対立しあうのではなく、農業を守っていく以外にない。
「アジア農民交流センター」
▽地場市場づくり〓 日本からタイへ。朝市が広がる。イーサン各地で朝市づくりプロジェクト。
山下さんの村、地元で作る野菜や魚を並べて年に何千万円と売れる。同じ手取りの金額を東京に野菜をだしてとろうとしたら、少なくとも3倍の量をださないといけない。
▽どぶろく作り 新憲法制定後のタイでも「酒造りは農民の権利」と運動。それまで独占企業がつくるまずい焼酎しかなかったが、あっというまに地場の酒が造られるようになった。「酒造り農民ネットワーク」という組織がある。「これまで外にでていた資源と金が村の中でまわる。グローバリゼーションに対抗する農民の運動だ」
▽有機農業は当初は普通の農民はなかなか踏みこめなかった。労働過重や収量低下で。宇根豊が、普通の農民でも可能な技術として「減農薬」という方向を提示した。
▽熊本市民の水瓶の阿蘇の地下水が年々減っている。その原因は減反〓。
阿蘇町の山口力男〓さんが都市市民とやっているグリーンストック運動。90年代はじめの牛肉自由化で、放牧の赤牛が危機に。野焼きの草刈りもなくなり、草原の存続も危うくなる。草原が荒れると、山の保水力が弱まる。そこで、都市の生活者が少し高くても赤牛を買うことに。……農業がダメになると環境も壊れる。
▽大分県大山町〓 一村一品発祥の地。平均4反5畝の谷間の村。この半世紀690戸の農家が1戸も減っていない。ここの女性たちがカリフォルニアにいって、面積の広さと所得の低さに仰天した。……梅の蕾がついた枝を飛行機で札幌に送り、ホテルやレストランの箸置きにする。虫が食った柿の葉を京都に送り、高級料理店でマットにする。土台は零細で、大規模化はしないが、その上の販売のところで創意工夫すれば生きていける。
▽伊万里の商店街「はちがめプラン」 旅館やレストランの生ゴミを分別して堆肥に。揚げ物から出る廃油で燃料に。食用油の原料の菜種は市内の農家で。会員が生ゴミをだすときは月に500円の処理費を払う。その半分を地域通貨の「ハッチ」で返す。肉屋や八百屋では2割までハッチで支払える。こうしてぐるぐる回る。
▽直売所〓 は大きくしたらダメ。直売所は少しあまるようにつくってお裾分けするところ。消費者ではなく生産者ニーズでやるべき。なければ売らなければいい。
近代化農業で切り捨てられてきた年寄り、女性、兼業農家の労働力が直売所によって生きてくる。
▽政府は大型農家に生産を集中しようとしているけれど、自給部分は含まれていない。自給農家を含め農家が300万戸あり、35万円ずつ自給すれば1兆円。農業所得は全体で3兆円ないから、すくなくとも3割は自給できる。こういうことの評価を農水省はしていない。これがあるから農家はやっていける(〓3万円の年金で暮らせるおばあさん)
▽山形県置賜の若手農民集団「ファーマーズクラブ赤とんぼ」 農業経営は個々に完結させながら、販売・加工を中心に共同のよさが発揮できる部分を協同でこなす。協同の部分は「業」に当たる。「農」と「業」に両足をしっかり下ろしている。(〓ニカラグア的協同農場は「業」に偏っていたのでは〓)
▽沖縄のゴーヤパーク〓 零細さを基礎に、二階部分で産業化。観光とゴーヤの加工。値段が高いときは東京に送り、安くなったら地元で加工。
▽集落営農も現場の知恵が生みだした。さまざまな農家が農地や機械、施設をお互い利用しあい、労働力をだしあいながら助け合う。
▽ブラジルの「土地なし農民運動」〓が三里塚を視察。「われわれも消費者と直接つながる仕組みづくりを模索している」 世界の農民は同じ問題にぶつかっている。日本の農民が地域で地道につくりあげてきているいろんな仕組みは、普遍性がある。小さな百姓が生きていくためのひとつのモデルをつくりあげている。
▽彼岸花〓 なぜ日本の田にだけあるか。奈良から平安にかけて全国で植えたらしい。花粉で増えないから自分では動けない。球根に毒があるからミミズもモグラもこない。畦が壊れない。ところが田が荒れると彼岸花はでてこない。草を払うとさっとでてくる。まさに百姓がつくる景観。〓〓
▽西洋タンポポがはびこって二ホンタンポポを駆逐した、というのはまちがいだという。二ホンは、土がやわらかくふわふわしているところを好む。セイヨウは、道路際とか線路沿い。人間の開発によって、二ホンの好む場所が次第に少なくなった。二ホンの土地が荒れた証拠。〓〓
▽トレーサビリティ 野菜などにICチップを埋め込む。パソコンを使えない農民はどうなるか。手間のぶんは価格に反映されるのか。このシステムの特徴は、大量生産・大量消費を前提としている。食の安全性を損なっている農と食の離れを問い直すのではなく、むしろ前提としている。少量ずつ多品種をつくる地場の生産者のものが、トレーサビリティにのっていないということで、地元スーパーから閉め出される動きも出ている。
▽ロシアのダーチャ 都市住民の9割は、郊外に掘っ立て小屋つきの農地(ダーチャ)をもっていて、ソ連崩壊で経済破綻しても、食い物があるからびくともしなかった。平均600平方メートルの土地の利用権が与えられている。〓〓定年後はダーチャで農的暮らし。
▽戦前の拡大主義 植民地の朝鮮や台湾からコメをもってきて米価を暴落させた。なのに困窮した原因を、日本が狭く農業が小さいからということにして、満州に農民を送り出す。「日本は狭いからだめ」という考え方が危ない。大正15年に1石40円だった米価が昭和6年には17円。 百姓が肥料代を払えなくて、稲刈り前の田を差し押さえられている。
今も、1993年と比べて生産者米価は6割。国際競争の時代と政府に鼓舞されて規模拡大した人は、米価2万円で計算して借金している。それがいまや1万円そこそこだから、借金をかえせない。つぶれる農業者が続出するだろう。




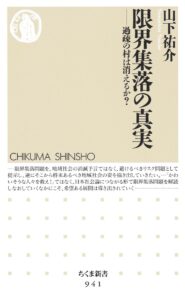
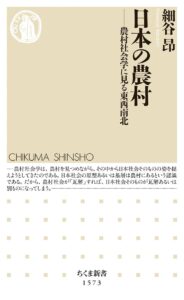


コメント