■災害に負けない「居住福祉」 早川和男 藤原書店 20120319
災害に強い「居住福祉」のあり方を、生産基盤や環境、文化までを含めて従来の「福祉」の枠にとらわれず幅広く紹介する。
神戸市は1970年代に大地震によって長田や兵庫区がほぼ全滅すると予測されたにもかかわらず対策を取らなかった。阪神大震災では、障害者や被差別部落住民の多くが犠牲になった。仮設住宅の多くが山中や人工島につくられ、ばらばらに入居させられることで孤独死や自殺が相次いだ。
旧西独では住宅総戸数の2割が社会住宅で、1977年現在、100万人以上の都市の土地の46パーセントを市が保有していた。居住は公的な責任という位置づけなのだ。西欧諸国は、基本的に高層住宅建設を中止し、既存住宅は中低層に建て替えている。三階建て以下の低層高密度のタウンハウスが望ましいという。
居住権を守るため、北海道伊達市は障害者の地域居住を支える民家を整えている。公的な保証人をたてることで大家も安心して貸してくれる。山古志村では、公営住宅を建てて農地などの労働空間を確保したから自力再建できない住民ももどってこられた。
能登半島地震の門前町では、8つの公民館が趣味の教室や配食サービスなどをしてきたことで災害時の避難所として有効に機能した。民生委員や健康推進員が福祉マップをつくって見回っていたことも避難に役立った。公共ホテルや国民宿舎、市立保育所は「公共」だったが故に被災者受け入れを続けられた。中越地震では「道の駅」の駐車場に仮設住宅の設置され、特産加工品をつくる施設で水や温かい料理を提供できた。
ふだんの福祉施設や地域活動などが災害時に大いに役立つことが証明されてきた。
寺社や農地、駅、公衆トイレ、地域社会の行事、公園なども居住福祉資源だ。
190店のうち6割の店でトイレを自由に使える巣鴨商店街、303のうち96カ所に車いす用のトイレがある岡山県の交番・駐在所。25の公衆トイレがある倉吉市。
中国・大連の有料老人ホームでは、入居者が働くことで賃金を稼ぎ入所料金が割引されている。ケアする者とされる者をわける西欧的福祉と異なる発想によって、入所者の生き甲斐づくりに役だっている。能登半島でも、被災者自身が協同する避難所は活気があった。
中越地震では、鎮守の修復がお年寄りにとって村に戻るかけがえのない条件だった。そのため、新潟県の復興基金事業は、鎮守・神社などの復旧をコミュニティ再建支援事業の中に組み入れた。
東日本大震災で被災した芸能の宝庫の大槌町では、大槌祭の復興に保存会連合会が動いた。「ひとつの集落の踊りの相談がいくつかの集落との祭りの話し合いになり、秋祭り、まちの復興の会議にもなっていった……」という。
=========================
▽7 「居住福祉」とは、まちや村や山里や海辺に根ざして生きてきた人々の生業を守る。地域の伝統文化を外からの力で壊さず、維持し発展させる。それらによって、人々の安全と暮らしを支える。森や農地や川や海辺を保全し、住居の保障、コミュニティの維持、福祉施設、公民館、幼稚園、公園、緑陰・・・保全などの生活環境施設を整備する・・・。
(生産基盤や環境、文化までを含めて幅広い概念)
▽20「神戸の冬を支える会」 神戸市政の犠牲。1970年代に大地震によって長田や兵庫区はほぼ全滅と行政内部で予測していた。なのに対策はとられなかった。
▽30 サイード 知識人の責務とは、いかなる権力にも権威にも奉仕しないこと。人間の悲惨と抑圧に関する真実を語ることが、所属する政党とか、国家への素朴な忠誠心などよりも優先されるべき。ものごとをただあるがままにみるのではなく、それがいかにしてそうなったのかも、見えるようになること。
知識人はアマチュアであるべき。専門家のように利益や報償によって動かされるのではなく、抑えがたい興味によってつきうごかされ、より大きな俯瞰図を手に入れたり、・・・特定の専門分野にしばられずに、専門職という制限から自由になって、観念や価値を追求する、社会のなかで思考し憂慮する人間のことである。
▽36 障害者や被差別部落住民の犠牲。
▽47 地上げなどによる強制立ち退きにともなう人々の死。
阪神の震災では仮設の多くが山中や人工島につくられ、抽選でばらばらに入居させられて、孤独死や自殺が相次いだ。ハビタット連合調査団「住宅復興は被災した土地で行うのが原則」
▽59 住居を失うことは、生存の基盤を奪われたことを意味する。(住居のある田舎の強み)
▽63 住居を社会的存在、公共の資産と位置づける制度は、日本の法律にも生かされている。建築基準法。
▽64 東日本では阪神とちがって、私有地での仮設建設を認めている。既存の民間住宅を仮設につかう「見なし仮設」
▽66 プレハブ仮設。1戸500万円?
▽71 北海道伊達市 障害者の地域居住を支える民家。当初は、伊達市長が家主と直接契約。アパート契約は本人だが、所長が連帯保証人に。公的な保証人がいるから安心して貸してくれる。
▽78 旧西ドイツの社会住宅 2人世帯用は寝室と居間。3人用は2寝室と居間・・・こうした住居基準は西欧諸国すべてに共通。
個人で社会住宅を経営。借家人をさがす苦労もない。家賃の支払いも市によって保障。1987年現在、住宅総戸数の2割が社会住宅。・・・1977年現在、西独の100万人以上の都市では、市域の土地の平均46パーセントを市が保有。
▽85 フランスのHLM(適正家賃住宅公団) 社会住宅
▽93 復興公営住宅の管理人に「集会所などを利用して、お年寄りも可能な軽作業ができないか。わずかでよいから賃金を払う」。管理人は「少しでも賃金を払うと最低賃金の決まりがある」などと融通のきかんことを言った。中国大連の有料老人ホームでは、入居者が働いている。賃金をもらえたり、入所料金が割引される。ケアするものとされるものをわけるのは西欧的福祉の発想。・・・被災者といえども、働く権利が保障されるのが好ましい(深見の住民たち〓)
▽109 住民主体の玄海島復興計画 淡路を視察し「行政主導による計画は失敗だった」「地域住民が1つになることが非常に重要」と聞かされる。外部の人間による委員会はつくらず、島民の意向調査やワークショップ、座談会などを通じて様々な意見を島づくり案に反映しながら進めた。
▽112 ・・・不評の菅政権だったが、少なくとも「阪神」での対応と比べると隔世の感がある。しかし、住民や市町村が復興の主権者となる「居住民主主義」が欠けている。
▽116 江戸川区の親水公園 96年に全長1200メートルの美しい水の帯が完成。2011年現在、親水公園は5路線9610メートル、親水緑道が1万7860メートルに達している。
ソウルの高速道路撤去、水辺と緑の回復は先駆け。
▽121 集合住宅はエレベーターを必要としない3階だて以下にする。長屋を近代化したような低層高密度のタウンハウス。西欧諸国は、一部例外をのぞいて高層住宅建設を中止し、既存住宅は爆破して中低層に変えている。
▽144 居住福祉資源 寺社や参道、農地、駅、公衆トイレ、地域社会の行事、公園、福祉施設、・・・すべて居住福祉資源を構成する要素。
▽151 入浜権 「体力のない子に、海でからだをやくように指導すれば、たいていの子が健康を回復してきたものですよ」
▽158 西陣の「くぎぬき地蔵」。境内で「上京健康友の会」が無料健康相談会を開く。岡山県井原市の「嫁いらず観音院」はウォーキングの場。
▽163 鷹巣駅前ちかくの談話室「げんきワールド」大きなトイレがある
巣鴨商店街は190店のうち6割の店でトイレを自由に使える。岡山県の交番・駐在303のうち96カ所に自由に使える車いす用のトイレがあり増え続けている。倉吉市には25の公衆トイレがある。
▽172 山古志村。帰還を実現。公営住宅によって自力で家を建てられない人が集落にもどれた。農地をはじめとする労働空間の確保。
▽173 能登半島地震の門前町では、体育館などに避難した被災者を順次小規模の施設に移して生命が守られた。8つの公民館などでは・・・。特別養護ホーム「あかかみ」被災者の収容は8ヶ月間までは無料。
▽176 門前町の「くしひ保育所」も輪島市立。規模が小さいから被災者も体調をくずさずにすんだ。弁当をあたためる設備もあった。公立だったことがよかった。
▽181 東北の震災で、発達障害者は、避難所にも入らず、自家用車ですごしたり知人・親類宅を転々とする人が少なくない。地域資源としての福祉施設。
▽185 門前町 8集落にそれぞれ公民館があり、そこに多くの被災者が避難した。さまざまな趣味の教室や、配食サービス、食事の会などをしてきたことで、地域住民の公民館への認知度が高く、災害時に自然に集まった。福祉関係者や民生委員、健康推進員は福祉マップをつくって日頃から見回り、居住者の特性を書き記していた。震災時にその人たちが担当区域に入り、高齢者などを公民館につれてきた。
▽188 公共ホテル、国民宿舎も活躍。その間、長期にわたって観光客を断った。公共的施設だったことがよかった。
▽193 「道の駅」の防災拠点としての役割。トイレがある。中越地震では、駐車場での仮設住宅の設置、無料温泉サービスなどの役割を果たした。特産加工品を併設していて食料を備蓄し、水や温かい料理を提供できる。
▽195 自校式の給食ならば、災害時も温かい食事を提供できる。センター式は、野菜類はしなびないように遠心分離器で脱水するから栄養分が抜ける。キャベツは次亜塩素酸で殺菌するから残留する。揚げ物が多くなる。食事をつくってから食べるまでの時間が長いから食中毒の危険も。
▽201 保健師 大槌町では、全国から141人の看護師があつまり、全戸訪問をした。
保健師数は激減。地域保健法の制定による保健所の集約化で、94年の同法制定前の保健所848カ所は2010年には494カ所に。介護保険法によって、要介護者や新生児の家庭訪問などは、保健所では39パーセント、政令市や市町村では53パーセントに減っている。その結果、被災地での保健師や全国からの支援に限界があり、「被災地保健師足りぬー1人で1000人担当」(朝日)と報じられている。
▽206 鎮守の森 中越地震 鎮守は地域共同体の守護神であり、集落統合のシンボル。その修復は、お年寄りにとって心がいやされ落ち着く、村に戻るかけがえのない条件だった。
新潟県の復興基金事業は、鎮守・神社などの復旧をコミュニティ再建支援事業の中に組み入れた。集落のコミュニティセンターであり、集会所と同じという位置づけだ。補助率は4分の3までで4分の1は集落が負担する。
▽211 祭りの役割。大槌町は芸能の宝庫。山口幸夫・日本社会事業大の呼びかけで、大槌祭の復興に、町の保存会連合会が動き出した。踊りの練習をかさねるなかで、肉親や家を失った人々に生きる勇気がもどってきた。「ひとつの集落の踊りの相談がいくつかの集落との祭りの話し合いになり、秋祭り、まちの復興の会議にもなっていった。・・・祭りは居住福祉事業、社会開発なのだ」





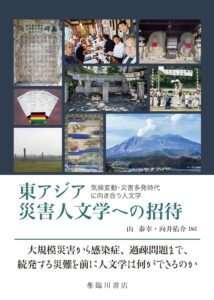


コメント