■映画の構造分析 ハリウッド映画で学べる現代思想<内田樹>文春文庫 20120214
映画を通して難解なラカンやフロイト、フーコーらの現代思想を知る本。どっちにしても難解ではあるが、なんとなくわかった気になれる。
フロイトの「抑圧」の説明はわかりやすい。トラウマは意識できないからトラウマである。氷山と同様、表に見える「自分」はごくわずかで、見えない部分こそ人格の本質だ。無意識部分の傷を直すには、見えない部分の葛藤を目に見える葛藤に変換する必要がある。そうした「すり替え」--文化人類学的な贈与と交換に近い働き--こそが精神分析の役割だ。「大脱走」は、フロイトの「抑圧」が下絵になっているという。
「意味のある」断片を組み合わせて「意味の通る」文脈を作り上げるのではなく、まず「物語」の文脈が決まって、その後に、細部が意味を帯びるようになる、という指摘は、「ナシとリンゴという実体があってそれに名前をつけたのではなく、名前をつけて世界を切り分けたことでナシやリンゴという意味が立ち上がった」という構造主義言語学の考え方と同じだから理解しやすい。そして、物語の「文脈」のパターン(=構造)は、全世界の物語を見渡しても100種類もなく、ありあわせのパターンを組み合わせることで、あらゆる物語はつくられている。作者の意図がどうあれ、物語はいずれかのパターンにあてはまり、むしろ作者が意識していない「鈍い意味」「反-物語」「脱中心的な力」が「物語」に干渉することで深みを生みだしているという。
さらにバルトは、作品をコントロールする「作者」の存在そのものを否定し、多様な素材がからまりあって、誰の意図によっても統御されることなく織上がったものがテクストであるとし、背後に隠された真理(=作者の意図)があるという作品観、いわば事物の裏にイデアというモデルがあるとするプラトン的な考え方を否定する。
各作品の解説は新鮮だ。
「エイリアン」は、フェミニストヒロインと家父長制的な男性性のあいだのデス・マッチという表の図式と、ヒロインが繰り返し陵辱され自立への努力が暴力的に押しつぶされるという古代的な恐怖譚という裏の図式が併存しているとする。
落ち着いたリーダーシップを発揮するナウシカのようなヒロインがハリウッド映画に現れないのは、少数の女が男社会の秩序を崩壊させた西部開拓時代の経験による強烈な女性嫌悪があるからであり、アメリカン・フェミニズムは、「男性の女性に対する嫌悪をさらに強化するためにアメリカ社会全体の暗黙の合意のもとに形成された呪鎮のイデオロギー」とまで筆者は言う。
「ゴーストバスターズ」が複数型なのは、アメリカの文化には、「信じかつ信じない」とか「正義漢でありかつ悪者である」というような重層的な人間成熟を評価する社会的基盤がないから、ゴースト=トラウマを扱う分析者は「チームプレイ」にならざるをえないからだと解説する。
なるほど、そういう解釈ができるのか、といちいち感心する。と同時にレヴィ=ストロースの物語の構造分析に触れたときの「たしかにそうかもしれないけど、ほんまかな」という気持ちも抜けなかった。
次のような指摘もなるほどと思った。
--「無知とは、自分が無知である、ということを他人は知っている」ということを知りたくない、という欲望の効果だから、「自分は他人より賢明である」と思いたがっている人間はもっとも簡単にこの欲望の虜囚となる。人を騙すには「自分は賢明である」とその人に思わせること。だましあいで勝ち残るには「出し抜かれたふりをする」ことで「状況を完全にコントロールしているのは私だ」と敵に思わせるのが一番。
--相手に語った「自分の過去」は、本当に私が「思い出している」のか、聞き手の欲望に反応して迎合的に「作りだしている」のか微妙だ。私たちは自分の過去、記憶、欲望について、宿命的に噓をつく。
=============
▽25 「意味のある」断片を組み合わせて「意味の通る」文脈を作り上げるのではない。文脈が決まらない限り、断片は「無意味」なまま。まず「物語」の大枠が決まって、その後に、現実的細部は意味を帯びるようになる。「意味がわかる」とは要するに、「ある物語の文脈の中に収まった」ということ。
▽27 物語が物語として成立するために経由せざるを得ない構造。物語の構造分析というのは、無数の物語は実は有限数の物語構造を反復しているにすぎないことをあらわにする。バルトの言葉では「私たちの精神の本質的な貧しさ」をあらわにする作業。
▽33 映画と文学の決定的分岐点。映画は、有料公開が前提だから、同時代の観客にリアルタイムで受け入れられ、ビジネス的なリターンが期待されない限り、製作すること自体が不可能。
▽34 バルト 作品を中枢的に統御している「作者」の存在そのものを否定する。……多様な出自と材質をもつ素材がからまりあって、いつのまにか誰の意図によっても統御されることなく、織上がってしまったものがテクスト。(背後に隠された真理がある、作者の意図がある、という作品観を否定。プラトン的な考え方を否定する)
▽52 バルトの映画論 「鈍い意味」 エンドマークへと向かって直線的に収斂してゆく映画の物語のなかに混ざりこみ、それを挫折させようとする「反対−物語」の力、脱−中心的な力。「物語をくつがえすことなく、別の仕方で、映画を構造化する」力をバルトは「映画的なもの」と名付ける。「映画のなかにある、記述されえぬもの、表象するだけで、表象されえぬもの」
物語は「反−物語」を滋養にして、「反−物語」の干渉と抵抗に遭遇して、巨大化し増殖し……意味は無意味なものに媒介されて深みを獲得してゆく。
「意味の亀裂」に、私たちは「橋」をかけようとする。前後のつじつまを合わせようとする。この「意味の亀裂」こそ、私たちの知性と想像力を激しくかきたてる「物語発生装置」
▽57 何か原因が「あって」、物語が動き出すのではない。何かがうまくゆかないとき、何かが「ない」ときにだけ、物語は語られ始める。
▽62 エイリアン フェミニストヒロインとこれを屈服させようとする家父長制的な男性性のあいだのデス・マッチという表の図式。
もうひとつ。古代的な恐怖譚の現代的なバージョンという意味がある。
ストーリーラインの水準における「秩序」と、映像記号の水準における「混沌」が併存。「フェミニスト・ヒロイン」、男性の攻撃的な性的欲望と戦う自立した女性への応援歌。一方映像記号の水準では「反−物語」が語られる。ヒロインは繰り返し陵辱され、傷つき、損なわれ、自立へのむなしい努力は暴力的に押しつぶされる。
▽70 明示的でフェミニスト的な主題、それを下支えする古代的な恐怖譚、そしてそれらを転覆しようとする「反−物語的」な性的記号といった複数のファクターが輻輳する構造になっている。
▽75 あるものを「言い落とす」 カウボーイには、メキシコ系もアフリカ系も亜細亜系もいたのに、白人しか登場しない。……ハリウッドの西部劇エキストラが、フロンティアが消滅した後の「もとカウボーイ」たちの重要な「再就職先」だった。……この「言い落とし」ゆえに、「アメリカのフロンティア開拓に黒人はまったくコミットしていない」という誤った歴史認識が広く定着したこと、この認識が20世紀のアメリカ社会に深い傷跡を残したことは確か。
▽「大脱走」
▽84 フロイトの「抑圧」「無意識の部屋」と小さな「意識のサロン」があり、その間に番人がいて、気に入らない者はサロンに入れない。番人が意識のサロンに入る事のできるものを選別しているという事実そのものが、意識の部屋からは見えない。抑圧とは、自分が何を抑圧しているか知らない場合にのみ効果的に機能する。無意識の心的過程で抑圧が活発に機能していることを「知らない」ということが大事。
抑圧された心的過程は、そのエネルギーを失わず、夢、妄想、神経症などの「症候」として再帰する。
これが「大脱走」の下絵になっている。いかにして「番人」の目をあざむく代理的表象に変容して境界線を超えるか、ということだけを描いた物語。
▽89 「父の審級」とのたたかい。「父の名」(=象徴操作)の拒否=「言語活動をしない」。「父」の目を逃れて「母」とむつみ会うこと、「禁じられた母性の奪還」。
この映画で排除されていた「女性」は、実は「トンネル」。おのれが意味するものの取り消しを求めるシニフィアン。
▽110 「人間はほんとうに隠しておきたいものを、どんなふうに隠すか?」それこそが探偵小説の永遠のテーマであり「抑圧」と立ち向かう分析医の永遠のテーマでもある。
▽116 ポーにおける「手紙」 無知というのは「うっかり見落とす」ことではなく、何かを「見つめすぎて」いる生で、それ以外のものを見ない状態。不注意ではなく、過度の集中と固執の効果。
「無知とは、いわば知りたいくないという欲望以外の何ものでもない」「知りたくない欲望」が働いていることを自分自身が知らない。これこそフロイトが「抑圧」と名づけた機制そのもの。抑圧の効果を免れるには、自分の目に「ありのままの現実」として映現する風景は、私たちが何かから組織的に目を逸らしていることによって成立しているという事実をいついかなるときも忘れないこと。
▽121 「手紙」は、秘匿されている限り、その保持者はある影響力を行使しうるが、いったん公開されてしまうと、もう何の力もそこから引き出すことができない。「大脱走」のトンネルも。「使わない限り」有効で、一度「使う」と無効になる。
それが「何であるか」という同定を忌避することで、物語の中枢を占め、人々を支配している装置のことをヒッチコックは「マクガフィン」と名づけた。「機能する無意味」「無意味であるがゆえに機能するもの」。ヒッチコックの場合、スパイ映画において「人々が命がけで奪い合うもの」のかたちをとる。その正体を知ることは、どうでもよい。
「マクガフィンにはなんの意味もないほうがいいということだ」マクガフィンは「我に触れるなかれ」というメッセージしか発信していない。「それが意味することの取り消しを求める」。それこそすべての人々を終わりなき欲望の運動のうちに巻き込むもの。
イエスは「触れるなかれ」と、地上的水準で「それが意味するものを否定する」ことによって、キリストとしての絶対的支配力を獲得することになる。
▽134 フロイト「無意識的なものを意識的なものに翻訳すること。無意識的なものを意識へと移すことによって抑圧を解除し、症候形成のための諸条件を除去し、原因となっている葛藤を、なんらかのかたちで解決されるはずの正常な葛藤にかえる」
分析家の成功、つまり転移の効果とは、「古い症候/病院となった葛藤」(古いシニフィアン)を「新しい症候/正常な葛藤」(新しいシニフィアン)と「すり替える」こと。〓
▽137 退蔵してはならない、交換せよ。それが人類学的な命令。分析者の仕事は「キープすること」ではなく「パスすること」。古い症候を新しい症候に。「古いシニフィアン」を「新しいシニフィアン」に。「何が書いてあるかわからない手紙」を「署名入りの手紙」にすり替える。そのとき、葛藤は解消し、症候はいやされる。
▽143 無知とは、「自分が無知である、ということを他人は知っている」ということを知りたくない、という欲望の効果。だから、「自分は他人より賢明である」と思いたがっている人間はもっとも簡単にこの欲望の虜囚となる。
人を騙すいちばん簡単な方法は、その人に「自分は賢明である」と思わせること。スパイゲームのようなだましあいで勝ち残るための要諦は「出し抜くこと」ではなく、「出し抜かれたふりをすること」。それによって、敵に「状況を完全にコントロールしているのは私だ」と思わせた者がゲームの勝者となる〓〓
▽154 「私のトラウマ」を語ることは原理的に不可能。その人の言語運用そのものが、その「言語化できない穴」を中心に編み上げられているから。「私」の人格はいわば「ある経験から組織的に目をそらす」というしかたではじめて成り立っている。〓
▽157 ふだんの生活でも、注意深い聞き手を得ると、堰を切ったように「自分の過去」を語り出す。そのとき私たちが語る「過去の記憶」は相手が変わるごとに微妙に変わる。その記憶は本当に私が「思い出している」のか、聞き手の示すかすかな「欲望」の信号に反応して、私自身が迎合的に「作りだしている」のか、それを決定することは困難。〓
私たちは自分の過去、記憶、欲望について、宿命的に噓をつきます。それらのうち、ある種の噓=物語は私たちの症候を緩和する力を持っている。
▽159 フロイトのトラウマ学説がアメリカに導入されたとき、アメリカ人はその複雑さにたじろいだ。分析しつつある当の分析家の欲望が患者の「トラウマ」を共同的に「お話」として構成し、それによって患者が癒える、ということを理屈として受け入れることができなかったアメリカ人は、一方に分析する主体を、他方にはトラウマを実体験として措定するという荒技に出た。外傷は「事実として」幼児期に存在したに違いないと考えた。 たぶん自分たちの国が先住民の虐殺と収奪から始まったというトラウマが深すぎて、それが「トラウマ概念の組織的な誤読」として症候化したのだろう。実体としての「デモクラシー」とか実体としての「正義」が存在するという特異な信憑が蔓延しているのは、おそらくその症候。
……抑圧されたものが症候として回帰するとき、それは必ず「不気味なもの」という形姿をまとう、というのがフロイトの洞見。これはハリウッド・ホラー映画にそのままあてはまる。なぜ、アメリカ映画があれほど大量のホラー映画を生産しつづけるのか。「抑圧されたものの回帰」についてのアメリカ的な決着のつけ方。
▽166 アメリカの文化には、ヨーロッパのように、一人の人間が「信じかつ信じない」とか「正義漢でありかつ悪者である」というような重層的な人間成熟を評価する社会的基盤がない。だから、ゴースト=トラウマを扱う分析者は「チームプレイ」という形態を選ばざるを得ない。効果的な「ゴーストバスティング/トラウマの物語的回収」を成功させようと思ったら、その仕事は複数形の「ゴーストバスターズ」によって担われる他にない。……悪霊に憑依され、それに「化身」したことによって、ルイスはすべての「言語化し得ぬ心的過程」を症候として表現することに成功した。この事件ののちルイスが自信にあふれた安定した人格の人物になったことは間違いない。
▽169 分析家自身の欲望が参加しなくてはトラウマの物語は成り立たない。
……人間が人間である限り、つまり抑圧があり、物語があり、欲望があり、それを解釈する言説があるかぎり、ゴーストは不滅。
▽184 過去の風景の記憶のなかに、自分自身が移りこんでいることが多い。「私が見たもの」の他に、そこに居合わせて「私を見ていた誰か」の視覚記憶も、出来事の物語的再現のためには不可欠。……私たちは「自分の肉眼が見ているはずのないもの」を自分の視覚記憶として思い出すことができる。
▽200 人間がそこから風景を見ている当の場所を肉眼は見ることができない。そこは「権力の座」である、とフーコーは語った。……すべての視線を一点に収斂する場所「パプティノコン」の看守塔に類する場所、それはすべての表象関係の成立を可能とする「空位」である。空位のもたらす秩序制定力は、それが不可視であることに基礎づけられている。「自分は見られることなく、すべてを見る」不可視の権力。(〓「他者」につながる)
▽211 「アメリカでは……である」という事態について、検証もぬきで「世界全体では……である」というふうに拡大適用するのは、現代アメリカ人に固有の思考上の「奇習」である。(湾岸戦争のときに「世界はもう待てない」と演説したジョージ・ブッシュ)
▽212 ハリウッド映画は強烈な女性嫌悪にドライブされている。これほど激しく女性を嫌い、のろい、その排除と死を願っている性文化を私は他に知らない。
▽215 宮崎アニメに見られるような、情緒が安定しており、ユーモアと知性があり、包容力豊かで、映画の最後まで「一度も男性主人公を怒鳴りつけない」女性登場人物というものを、ハリウッド映画人はうまく想像することができないのだ。
▽220 男だけの世界に女がやってきて、男たちの世界の秩序が崩壊する……それは西部開拓のフロンティアに頻繁に見られた光景だった。開拓の最前線では女性が圧倒的に少ない。それが「レディーファースト」というマナーの起源だと聞かされたが、女性嫌悪も、男女比率の圧倒的な差から説明できるのではないか。……「男だけの集団」に「希少性ゆえに決定権を持つ女」が侵犯してきて、男たちの「ホモソーシャルな集団」の安寧秩序を乱し、多くの男に「選ばれなかったトラウマ」を残したために、「選ばれなかった男たち」が女の悪口を言って、その傷痕を癒やすという自己治癒の物語が、フロンティアの全域で2世紀にわたって繰り返し語られたはずだ……
▽231 女性嫌悪の物語がアメリカ全体に浸透してゆくのは、フロンティアの完全な消滅と、開拓者たちが「神話の語り手」としてハリウッドの映画工場に参入してきた1910年以降だ、という仮説。(その以前は女性が主人公の映画も多かった)
▽237 アメリカン・フェミニズムというのは、「アメリカ男性のアメリカ女性に対する嫌悪をさらに強化するためにアメリカ社会全体の暗黙の合意のもとに形成された呪鎮のイデオロギー」ではないかと私は疑っている……


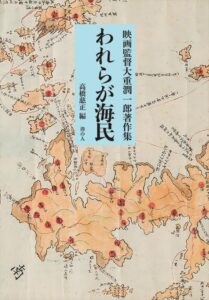

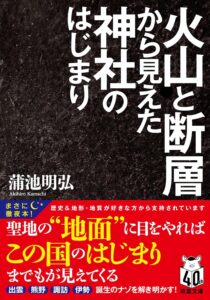

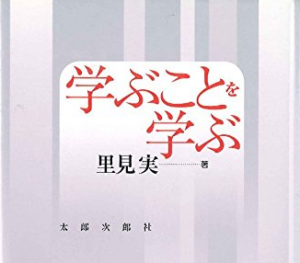

コメント