■ラテンアメリカ十大小説<木村栄一>岩波新書20110704
現実と幻想を行き来する不思議な世界をつくる中南米文学の歩みをわかりやすく解説している。
19世紀末、ニカラグアのルベン・ダリオを中心にしてmodernismo(近代派)と呼ばれる運動が起きることで、新大陸の文学は一人歩きをはじめる。
ヨーロッパの文学が試行錯誤の隘路に悩む20世紀、ラ米の文学は、どれほど実験的な手法を用いても物語性を失わなかった。言語が生命力にあふれている時代に生まれ合わせたためだという。
そういった「若さ」と同時に「古さ」にも特徴がある。
ガルシア=マルケスは、現実離れした事件が次々に起こる一族の歴史を書くため、非現実的な出来事を今見てきたばかりというようにしゃべっていた祖母の語り口を生かして「百年の孤独」を書いた。ラ米文学の幻想的な世界は、シュールレアリストの想像の産物ではなく、先住民族以来の古い伝統に根ざしていた。だから、一見わかりにくい展開でも浮つかなかった。
若い文学であるが故の物語性と、先住民族の伝統に根ざした幻想性のドッキングが20世紀ラテンアメリカ文学の特徴だった。
川をさかのぼることが時間の遡行につなげたり、自在に歴史を飛び越えたりする小説の作り方は、「歴史の欠落」(若さ)によるものであると同時に、ヨーロッパの直線的な時間概念への批判でもあった。先住民族に連なる円環型の時間の流れを再発見することで、新たな物語を紡ぎ出したのだ。
日本は高度経済成長以来、すっかり「直線的時間」に覆われてしまった感があるが、日本の田舎にわずかに残る伝統的な時間感覚をもう一度再評価するべきなのではないか、と思わせられた。大江健三郎の「万延元年の……」などはそんな意図をもって書かれたのかもしれない。
===================
□ホルヘ・ルイス・ボルヘス
▽31 「エル・アレフ」該博な知識、さまざまな解釈が可能な表現に満たされている彼の作品はよく難解だといわれる。さまざまな解釈に対して開かれた作品を書きたいという思いが込められている。(〓それが難しい)
□アレホ・カルペンティエル
▽45 「この世の王国」ハイチ。シュルレアリストたちが作り出そうとした驚異的なものは所詮小手先の技巧でしかないと酷評する。
ブードゥーを信じている黒人奴隷の視点に立つと、世界と歴史がまったく違って見えることに気づいた。
▽47 オリノコ川の源流を旅したときの体験をもとに「失われた足跡」。川をさかのぼることがそのまま時間の遡行につながるという特異な発想で書かれた。しかも空想ではなく、実体験にもとづいているという。
▽52 中米の独裁者を描いた「方法再説」。ロシア革命とキューバ革命をテーマにした自伝的小説「春の祭典」。
□ミゲル・アンヘル・アストゥリアス
▽56 魔術的現実。男が落馬して石に頭をぶつけたのなら、石が彼を呼んだのであり、溺れ死んだなら、川が呼び寄せたということ。「魔術的リアリズム」は、インディオ特有の想像力と深く結びついている。
▽61 1944年から外交官に。政変で亡命。搾取される農民の姿を描いた「トウモロコシの人間たち」。アメリカ企業を告発するバナナ三部作「強風」「緑の法王」「死者たちの目」。「大統領閣下」は独裁者小説の傑作のひとつ。独裁下で辛酸をなめた父と自分の経験をもとに書き上げた。
□フリオ・コルタサル
▽74 自らが体験し、生きた悪夢を言語化したものだとコルタサルが感じ取った。
▽78 悪夢を見たり、何かのオブセッションに取り付かれると、それを言葉で語ってはじめて、その呪縛から逃れられる……現実の世界と悪夢・幻想の世界がひとつにつながっているような作品を書くというのは、彼にとっては「悪魔祓いの儀式」
□ガブリエル・ガルシア=マルケス
▽94 「100年の孤独」 祖母のように何食わぬ顔をして幻想的な話を語ろうと思うんだ。……祖母の語り口を生かして幻想と現実の壁を取り払い、両者が渾然とひとつに溶け合った小説世界をつくりあげた。
▽99 独裁者を描いた「族長の秋」。シモン・ボリーバルの悲劇的な死を描いた「迷宮の将軍」。自伝「生きて、語り伝える」〓
□カルロス・フェンテス 「我らが大地」
▽111 日常世界のなかにぽっかり開いた異界に通じるドア、先スペイン時代の神が生きている世界と向き合う。そのとき、僕たちの生きている歴史的な時間が音を立てて崩れ落ち、まったく異質なメキシコ古代の時間が目の前を流れはじめる。
▽113 時間を直線とみるか、円とみるか。仏教もラテンアメリカの先スペイン時代の文明も、時間を循環し、円環するものとしてとらえていた。未来にユートピアを設定し、それに向かって突き進む近代の直線的な時間認識への批判。
人間の愚かな行為は、直線的な時間の中の一度きりの出来事なのだろうか。同じことが繰り返し行われているのではないか、という問いかけ。
▽119 円環構造の時間の再評価。たとえば日本の田舎に流れる時間の再評価は。
□マリオ・バルガス=リョサ
□ホセ・ドノソ
▽137 老いはすべてを奪いさる。失うものが多い人ほど音もなく忍び寄ってくる老いを恐ろしいと感じ、それが強迫観念に変わっていく。……悪夢に悩まされる。
□マヌエル・プイグ
▽154 共同体的な意識が希薄になると、お告げとしての夢は社会全体に対する予知・予言としての機能を失い、個人的なものになり、時には精神分析の対象になることも。叙事詩が書かれた時代は、外敵がいたから、否応なく共同体意識をもつ。人々の中に個人としての意識が目覚めて強くなるとともに、叙情詩が誕生する。
□イサベル・アジェンデ
▽170 ジャーナリスト。父のいとこがサルバドール・アジェンデ。クーデターの裏話を「精霊たちの家」(1982)で詳しく語る。〓政変後迫害される人たちの救済にあたり……職を失い、ベネズエラに亡命。
イサベルを突き動かしたのは、心の中にすみついた亡霊(クーデターによる犠牲者)であり、失われた世界を取り戻したいという願望。
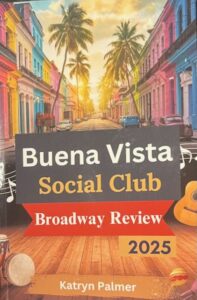

コメント