■「没落先進国」キューバを日本が手本にしたいわけ <吉田太郎> 築地書館 20110629
キューバは1970年代にソ連への依存が高まり、がちがちの中央集権国家になってしまった。援助によって豊かさが保障されていたが、ソ連崩壊で一気に矛盾が噴出する。経済はどん底まで落ち込むが、おかみに頼ることに慣れきっている国民は右往左往するばかりだった。
原発立地町村や、補助金に依存する日本の田舎と同じだ。カネを媒介とした中央集権構造によって人々は自立心を失い、自分の家の前の道路にゴミが落ちていても、役所に電話して片付けさせようとする。そんな依存体質がはびこっていた。
キューバはソ連崩壊による未曽有の経済危機によって、依存体質を脱却せざるを得ない状況に追い込まれた。
国全体にはびこる官僚制に風穴を開けるために使われたのが、ワークショップなどの手法だった。住民とともに地区を徹底的に調査し、問題点を抽出し、主体的な取り組みを生み出していく。まさに「地区診断」が全国規模で展開された。
農業も同様の経過をたどる。ソ連の援助によってなりたっていた工業生産型のプランテーション農業は破綻し、サトウキビの生産は激減する。とくに国営農場だった協同農場は荒れるにまかせる状況になってしまった。一方で、個人経営の百姓は自給型の農業をすすめ、種子の多様化に取り組む。研究者や行政が生産目標を決め、技術を教え、それに農家が従う、という形を脱し、農家自らが種子や農業技術の進歩にとりくみはじめたところに希望が生まれつつある。ここにも依存と自立(主体性)の構図が見える。
エネルギーも、学校や診療所にソーラーパネルを導入することによる分散化を試み、住宅建設も、 コミュニティレベルで住民参加で建築するプログラムを編み出して国際的に評価された。資材は、通常のセメントの半分以下のエネルギーでつくれるローマ時代のセメントを復活させた。
地域主権を確立するためのツールのひとつが、 地区内にある文化資源や環境資源を地図に落とす「グリーン・マップ」だった。現在54カ国で活用されているこの手法は、水俣の「地元学」とも似ている。地域を知ることで住民が地域づくりの主体となっていく。
いずれも地区診断、分権化、エコという共通点がある。
実はこの特徴は江戸に似ており、カストロのガバナンスは家康のそれに似ているという。江戸時代の前半は大規模開発と金銀の乱用によって経済的には発展していたが、天災が絶えなかった。金銀が枯渇することで、エコと分権と地域自治の仕組みがつくられ、経済的には大きくはないが教育レベルが高く、安定した「没落社会」をつくっていった……なるほど、と思った。
================
▽7 メキシコでは、石油価格の下落と金利上昇で対外債務を返済できなくなり、1982年に早くもグローバル化の影響を受け始めた。構造調整によって、国内農業が壊滅し、格差社会の再現がおきた。平均所得は12パーセントも下がり、実質賃金のはんぶは80年代の半分に。……米国の補助金つきの輸出農産物の攻勢で国産の半値のトウモロコシによって、国産価格は45パーセントも下がった。輸入量が12倍となり、25パーセント以上が外国産となった。
▽7 通商交渉での日本。CIAが諜報活動をしなくても、わざわざ貿易交渉の手の内を明かしていた。……「拒否できない日本」(関岡英之)によれば、米国の意向に沿う法改正や制度改正は、独禁法改正、持ち株会社解禁、NTTの分離・分割、建築基準法改正、労働者派遣法改正、人材派遣自由化、大店法廃止、健康保険での本人3割負担、郵政民営化、法科大学院設置、道路公団解散、ゆとり教育、姉歯問題の背景にも米国の干渉。生産緑地法改正で宅地なみ課税による都市農業の破壊も米国からの内需拡大に応じたものだった。「いまでもアメリカは日本を占領している。ただし、ソ連という脅威があったときは、占領政策はゆるやかだった。だから、日本人はそれをあまり意識することなく、経済成長に専念することができた」(「国家破産」藤巌喜)〓
▽15 電気がない農村の学校や診療所にソーラーパネルを導入し、コンピューターや教育テレビを利用できるようにした。……06年にエネルギー革命に着手。分散化をはかるため、06年には、1800以上のディーゼルと重油によるマイクロ発電プラントが導入され、停電の頻度も激減。再生可能エネルギー導入……わずか2年でガソリン消費量は20パーセント、灯油は34パーセント、天然ガスは37パーセント減った。2002年の二酸化炭素総排出うーの18パーセントが減った。
▽43 キューバには不動産業がない。「ペルムタ」という物々交換を通して新しい家をみつけようとパセオ・デル・プラドに集まる。
▽63 コミュニティの建築家プログラム。「世界住宅賞」受賞。アルゼンチンやウルグアイ、南アフリカ、メキシコ、ジャマイカ、ブラジルにも建築家が指導に出かける。
アルゼンチンのロドルフォ・リビングストンが開発した「家の手術」という参加型の手法がベース。彼の指導があった。
▽72 ソ連崩壊で資材入手が困難に。新しいセメント「リメ・ポッサラーナ・セメント」を開発。ローマ時代のセメント製法に着目。通常のセメントの半分以下のエネルギーでつくれる。サトウキビの茎の焼却灰を代替接合剤につかい、石灰岩を原料とする。「過去5000年の文明でもっとも多く使用された持続可能な材料は、赤煉瓦、木材、ローマ時代のセメント」「エコ資材」〓
▽76 石灰は原油から製造されていたが、生石灰を製造する釜が改良され、薪を燃料とした石灰がはじめてつくられた〓
▽78 竹林も再生。セメントに竹の繊維を混ぜたボードを使ええば、鉄筋でなくても頑丈な住宅ができる。
建設資材の地産地消。エコ資材は地元の工場でつくられる。輸送費がかからないぶん有利。〓外からの資源に依存し、中央集権的に管理される既存の住宅システムを、柔軟に動く分権型のそれへとシフトさせることにつながった。
▽83 マイクロ資金で住民自身にエコ資材を利用して家を建てさせ、エコ資材産業の雇用につなげていくという発想は、グラミン銀行にどこか似ている。
ハリケーン・ミシェルがニカラグアやホンジュラスで大災害を引き起こしたあと、再定住の際にエコ資材が役立った。ベネズエラにも。「世界アビタット賞」を受賞。
▽89 ローマセメントを復活させ、数千年前にエジプト人が使っていた焼却粘土れんがを救いだし、材木も竹を使って再発明した。〓
▽91 行政機構はがちがちの縦割りで、テーマごとに担当省庁がちがえば、ムニシピオ、ハバナ市、中央政府と縦にも中央集権構造。だから、住民ニーズに基づいて総合的に地区を改善する仕組みが必要になった。ワークショップでは、煩雑なムニシピオの官僚制度を迂回して、直接に国の事業さえ実施できた。
▽93 「地元政府が問題を解決してくれるのを座して待っていて、参加しようとしなかった。住民は何か約束してくれるなら集まると言ったが、経済危機で何も約束できなかった」……受け身な姿勢から活動的な姿勢に転換。住民たちが地区の環境診断をし、ゴミの投棄場所を記録する。……まさに地区診断〓
▽99 人口の都市集中。1963年までハバナの人口は増え続けたが、農村状態を改善する試みによって、60年代後半には、農村と都市のアンバランスはかなり是正される。70-80年にかけては、ほかの発展途上国の都市は人口が爆発していたが、ハバナは逆だった。ところが、「スペシャルピリオド」が始まり、地方は厳しくなり、集中がはじまる。
都市を安定させるには、農業政策が大切。
▽101 2007年、市民ジャーナリズム誕生。「ヘネラシオン・Y」〓
▽107 肉ばかりで野菜とらぬ食事。スローフードの有機大国という短期旅行者が抱きがちなイメージは誤り。ジャンクフードが多い食生活。
▽112 「有機農業が国を変えた」では、「94年に90年の55パーセントまで落ち込んだ生産が99年にはほぼ以前の水準に回復した」と書いたが、03年前後をピークにそれ以降はずっと生産が低迷している。……有機農業では自給できていないし、不足食料の最大の輸入元は米国なのだ。
▽114 農業低迷の理由。労働生産性が低く遊休化した土地。国営農場の改革で誕生した協同組合型の農場UBPCがひどい。
▽115 砂糖の1人あたり消費量は日本の4倍弱。消費大国だが、今は生産大国とはいえない。世界ランクも3位から10位まで落ちている。ソ連圏の買い支えがなくなり、ドル箱産業からお荷物の重厚長大産業に転落。作付け面積な90年の3分の1以下に。90年の818万トンが、07年は110万トンにすぎない。
政府は自給率向上を目指したが、他品目への転換は進まず、土地の多くが遊休化。
〓民間流通のかわりが、68年に創設された農業省外郭団体アコピオ。巨大機構で動きが鈍い。非効率な中央集権管理。(〓ニカラグアの例)
市場流通を否定した結果、驚くほど複雑な流通管理体制になっている。
行政機関が月ごとに農産物価格を設定し、この販売価格からさらに2-40パーセント差し引いた額が生産者に提示される。価格が統制されているから傷んだ商品も勝手に値下げできず、ある市場では、価値下落を評価するため専門家を呼び出し、専門家がきたときは、売れないほど劣化していた。ロスを一定レベル以下におさえたうえで、総売り上げ実績というノルマを達するため、熟れすぎたトマトに最高価格がつけられ、良質な商品が店頭から隠されるというばかばかしいことが起こる。腐った野菜に一級品の値段がついている……
▽120 砂糖省は、わざわざ省内に非砂糖担当副大臣をおいて、事実上2番目の農業省になっている。二重構造。
▽124 農業活性化のかぎは分権化にある。「地元段階での解決策につながる。ある州に適したことが、他州にいいとは限らない」
▽135 種子の多様化・自給。ぴなる・でる・りお大学の山岳学部。地域活性化を支援する山村内にある
大学〓。
▽141 種子フェアは、農民たちの交流の場として、失われた伝統文化を復活する一助に。有機農業は、経費が大きく削減できる。
▽142 参加型プログラムで女性も元気に 「今は朝起きると他の生産者と交流したい。ほかの人たちに見せたいと思うのです。……」
▽144 ……もっとも重要なプログラムの成果は、農村女性たちの自尊心だ。(からり〓)
▽149 「有機農業」の定義のちがい。キューバでは「安全」ではなく、アグロエコロジーであり、目的は持続可能性。最終ステップは、持続的生産のための人間を巻き込む思想と価値観の転換とされる。
有機=安全と発想する時点で、米国が主導する市場流通向けの有機ビジネスに巻き込まれているのかもしれない。
▽152 農民参加型品種改良。経済危機で肥料や農薬がなくなり、従来の高収量品種の力を発揮できなくなる。新たな種子生産の方策を求める試みが1999年からはじまる。……数十年来の近代農業で特に平地では遺伝資源の多様性は失われていた。だが、東部山岳地のように伝統農業が盛んな地域では、生物多様性や種子の知識は維持されていた。
……2人の育種家が、66種の在来品種のトウモロコシを集め……
▽156 農薬や肥料、燃料を考えれば、近代農業よりも、低投入型農法に適した品種改良を農民参加のもとで行うほうが、はるかに効率がよい。
……いったい農民たちはなぜこれほどまでに、役立つとも思えない品種も維持しようとするのか。「子供だってできが悪い子もいる。でもみんな私の子供なんだ。私は彼らを養わなければならない。品種だって同じことだ」
フェアでは、農民が自ら種を評価し、選べる。選抜が育種家だけにある能力ではないことが示された。
▽158 緑の革命の絶頂期には、農民にはどのような作物や品種を植え付けるかの選択すらほとんどなく、研究機関……地元指導者というヒエラルキー体制を通じて開発された「承認品種」で現場から遠い場所で育成された品種だった。(日本の普及所は? 産地化の弊害〓)
……あるコミュニティには、以前は4品種しかなかったが、今では100種以上の豆、100種以上の米、90種以上のトウモロコシが栽培されている。
▽162 伝統的な混作も一般的に。外部投入資材がない状況では、ほとんどの組み合わせが、モノカルチャーよりも生産的なことがわかった。サトウキビが伸びる前に豆を収穫し……(〓百姓化。モノカルチャーは機械化の条件でしかなかった)
▽168 防災 カトリーナは最小の規模だったが、アメリカで1836人の死者を出した。ルイジアナでは、州兵の3分の1がイラク軍事活動で救助をサポートできなかった。避難所では物資が不足し、食料は自己責任で持参するとされたため、衰弱死が相次いだ。
▽170 2001年のハリケーンミシェル。エルサルバドルでは02年に公共事業省を改革し、大型機械のすべてを民間に払い下げていた。だから、有事に活用できる機材が政府の手元になかった。土地利用規制も不十分で、危険地に貧しい人が居住。ダムを放水したことを周知せず、下流の集落の人がおぼれ死ぬ。
キューバではほとんど死者が出ない。
▽175 96時間前から警戒を発信。72時間前から特別報道が始まる。襲来に備えて飲用水を確保し、保存食を仕入れ、ドアや窓をしっかり閉じる。ハイテクだけに頼らず、電気が切れた場合を想定して、無線ラジオ協会の会員も備える。……暴風域に入ると漏電しないように電気やガスも止める。だから復旧も早い。
▽180 「避難経験を積めば、人々は避難することを望むようになります。大きな建物には警備員を出し、泥棒が入らないよう警官も配備される」
▽184 危険な建物を把握。アバナ・ビエハのムニシピオ政府は、地理情報システムGISづくり。
コミュニティレベルでも ハザードマップづくり。避難に当たって誰に手助けが必要か……把握。どの家が頑丈で避難所として活用できるか、家庭の状況も含めて掌握。(法吉地区〓)……ハリケーンの際重要なのは、公共医療サービスの維持。……専門医療よりも予防医療に重きを置くのは、格段に効率がよいから。(沢内村〓、佐久病院)
▽190 ハリケーン後、市民が助け合い、あっという間に住宅を再建する。ボランティアが盛ん。連帯精神。
▽195 防災教育は学校にとどまらない。訓練は職場でもされ、ファミリードクターも災害と関連する健康問題をどう予防すればよいかを教え、コミュニティの建築家もどう守るかを教える。人々は、防災で重要な役目を果たす主体が自分であることを自覚している。人々の間に「安全の文化」が築き上げられている。(「平和の文化」=コスタリカ 主体性をはぐくむ地区診断)
▽199 「地元学」 地区内にある文化資源や環境資源を地図に落とす「グリーン・マップ」。全体を俯瞰した地域づくりの合意形成に活用するもので、米国のモダン・ワールド・デザイン社を創設したウエンディー・E・ブラワーさんが92年に考案したまちづくり手法。いま54カ国500都市で活用。発想や手法は、水俣の「地元学」とも似ている。
▽200 マップづくりで学んだのは、課題を解決するには、必ずしも地元政府にやってもらう必要がない、ということ。やれることは自分たちでやるとの発想。農協では汚濁された池の水で灌漑していたが、やめさせ、小さなゴミ捨て場を片付け……という経験があったから、学校が破壊されたとき、政府からの援助を待たず、自分たちで屋根を取り換えた。たった1日で修理してしまった。
グリーン・マップは愛知県や東京でも。
▽206 「グリーン・マップに参加する子ども、お年寄り、コミュニティが変わっていくのが夢。環境教育がなければ人間は生物多様性を守れない。そして、豊かな生物多様性がのなかで環境教育もしなければならない」。多様性を守ることが、生活水準を高めることにつながる。(〓能登半島のケース)
▽213 ゲーム理論 囚人のジレンマ 助け合った方が生存に有利なことは歴史からも明らかに。ヒグモン「わかちあう利他主義のほうが、奪いあう利己主義よりも社会存続に有利だ」(贈与論〓)
▽214 「キューバの医療援助は、災害緊急派遣は別として、一般的には人道的国際主義などではない。ベネズエラ、南アフリカなど3分の2は、バーター方式で有償。現在の貿易収入の5割以上が医療サービス輸出となっている」。医療サービスの収益は年50-60億ドルに及ぶ。08年の統計では25億ドルを超す観光が外貨獲得のトップだが、資材購入費を差し引くと実収益は3割にすぎない。海外からの送金も10億ドル程度。今の経済を実質的に支えているのは、医療を筆頭とするサービス輸出。産油国からは外貨をふんだくり、貧しい国には無料援助で「信用」を買う。
▽226 中央集権が機能せず。複雑化した社会問題は、過去はともかく、今は、省庁間をまたぐ横断的な連携がなければ対応できない。……
ムニシピオとコミュニティとのギャップに橋をかける「人民委員会consejo popular」創設。日本の市町村合併の逆をした。「従来のように縦割りではなく、総合的な仕事の進め方を」
ワークショップによる民衆教育。地元住民が一番必要だと感じている課題を軸にネットワークを築き上げる。地区で重点を置くべき課題を特定し、ほかの組織や学校長……らをつなげてゆく役割を果たす。住民参加型で問題を診断することから始めるから、戦略的なコミュニティ計画もたてられる。
▽232 民衆教育のアイデアは、パウロ・フレイレの方法を適用した。
▽234 旧ソ連が崩壊し、物不足に陥るまで住民参加が起きなかった。創造性や自分の判断力を欠いた市民を形成してしまった。(〓日本は)70年に砂糖増産による経済躍進に失敗してから、とりわけソ連の影響は決定的に。さらに、自衛のため民兵を組織し、思想教育をしたことが、権威主義的な社会構造をはびこらせてしまった一面も。国民が団結したから生き残ったが、大政翼賛型システムは、検閲などのマイナスの反作用も。
▽235 輸入物の社会主義を批判。07年、「鉛の歳月」を批判する連続講座。
▽238 「トップダウンで硬直化した権威主義的なやり方が存続していることは認めますが、民衆教育は社会主義をリードする参加型のやり方に寄与できている」
▽241 芸術文化 芸術家は政府の無理解を批判。「もし、骸骨のフィデルを作品にしたら、たぶん展覧会は開けないでしょう。ですが、表現するのは自由だし、それで逮捕されることもありません」。……ゲバラの顔は腐るほど出くわすが、カストロの肖像画は室内以外は数えるほどしかない。存命中の指導者は出さないように法律で定められているためだという。「ソ連からの援助いこだわっていましたが、ふと気づくと依存状態にあっていた。パターナリズムはたいがい人間をだめにします」(71から76年)「ネズミ色の5年と言われています。優秀な作家でも同性愛者への差別がありました。」、ある時期から、人種差別やサボタージュ、同性愛など扱えないタブーが生じたのだ。この閉塞状況を経済危機が変えた、という。「革命以来、作家と国家の間にはじめて距離ができた。それ以前は、すべての文化産業を政府が統制していた。自由を得るには海外に機会を見いだすしかなかった。今は、政治領域ではまだタブーがあるとはいえ、文化芸術に政府が介入することは損失だとの議論が進んでいます」
世界的アーチストが庶民と同じボロ屋に住む。亡命すれば金持ちになれるのに……。
若手ミュージシャンでは亡命するケースが目立つ。
▽253 ハバナ海岸のマレコン通り沿いの「アルテ・マレコン」。08年にオープン。気鋭の作家の展覧会。「海外で1000ドルする作品もここでは300ドル」というが、ふつうのキューバ人は手が出ない。が、所有しなくても時間をかけて接せられる。「所有」から「レンタルの思想」
▽257 江戸との関係 江戸初期の日本は、グローバルな経済活動を東アジアで繰り広げていた。日本人町の現地駐在員に支えられた朱印船貿易は、ポルトガルやオランダを圧倒していた。
▽ 江戸初期は、列島改造ともいうべき大開発つづき、洪水も頻発していた。17世紀の世界の銀産出量のうち、日本銀が最盛期は3-4割を占めた。
金銀が底をつくと、かわって銅が登場する。ヨーロッパだけでなく、清朝も日本産の銅に依存していた。
▽260 江戸の文化と教育水準の高さ(=キューバ) 「すべての人が識字教育を受けており……」「下層階級の人ですら書く能力があり……」と書き残している。庶民も絵画を見たくなる。そこで開発されたのが版画だった。江戸の絵画は農村でさえ広まり、農村では芝居や演劇も盛んになる。
▽262 当時は、立身出世という概念はなく、子どもたちは村の未来を担う宝とされ……「若者組」「娘組」に属して集団規律を学んだ。(キューバのピオネーロ組織)
生粋の江戸っ子はほとんどが定職につかず、慶応4年の宮益街の調査では172人中69人が日雇いだった。……大工や商人も、夏場は暑いといって休み、冬場は寒いといって休み、役人でさ、勤務時間は午前10時から午後2時。長屋の月家賃が大工の日当程度と安かったからなりたった。火事の後は、被災者救助金が出て酒も握り飯も食べ放題。修復作業で仕事が増えるため誰もが災害を歓迎していた。
▽263 江戸時代より前は「自己責任のグローバル時代」だった。敵地住民を捕虜にして奴隷として海外にも売り飛ばす。……兵農分離がなされる前は、水や山林資源をめぐる利益が衝突すると、武士顔負けの戦闘がなされた。「万人の万人による闘争」。中世から戦国までは、新自由主義さながらの自己責任の原理。
江戸期に入って、戦争がなくなり、「貴賎の別なく文字に親しむようになった」。
▽266 日本はなぜスペイン・ポルトガルの植民地にならなかったか。世界最強の軍事超大国だったから。鉄砲伝来から30年後には、非西欧圏では唯一、鉄砲の大量生産ができる国となり、鉄鋼や鉄砲では、西洋を勝る生産国になっていた。銃の主要な輸出先はオスマントルコだった。
▽267 幕府の独創的な公平さを維持する構造。老中になれるのは10万石以下……というように権力と財力を分離した。「権ある者は禄少なく、禄あるものは権少なし」
権力者が貧しいと同時に小さな政府でもあった。18世紀の江戸中期は人口55万人いたが、町奉行所の役人は290人、市中をパトロールする定町廻同心は12人。40万人の大阪には定町廻同心は4人しかいなかった。これで運営できたのは、村掟や町式目によってボランティアによる民衆自治が普及していたからだ。だがその村権力は幕府や藩が制定した法制度や刑罰に依存していた。
コミュニティの自律は小さな政府につながる。だが、村やコミュニティ間の対決はより上位にある権威によらなければ解決できない。農村コミュニティの自治の原則を守りつつ、村同士の対決を公的権力が統治するシステム。中央革命政権という権威を保ちながら、地方分権化で住民自治を進めようというキューバにも通じるものがある。
▽275 ハバナ・ビエハ 革命前には取り壊し計画があった。ロイグ博士が1938年に「歴史官事務所」を創設し……しかし旧市街の修復・復旧が本格的にはじまったのは革命以降。……旧市街が世界遺産となった背景には、長年にわたる地道な努力があった。
▽282 経済危機。独立して経営し、海外から資金援助を引き出す。収益の60%は復旧用。40%は、住宅・医療・教育といった社会プロジェクトに費やされる。……観光者向けに飾りたてられた町を作り出しても、都市から生活を奪えば、シーズンオフにはゴーストタウンになってしまう。都市の暮らしのあらゆる場面でのルネサンス「総合的な回復」。市民生活の復興を歴史官事務所が優先させたわけもここにある。復興の主軸に文化を据え、その文化を創造して、運び伝える重要な主体を人間とした。
▽290 旧市街の復興を担う熟練労働者を育てるため、鍛冶屋、大工、洋裁などの失われた伝統工芸を復活させ、若者の雇用につなげている。〓「歴史的な考証性や庶民の楽しみを損することなく達成された、歴史的遺産保護の空前のモデル」……経済活性化と環境、福祉医療、教育、文化とすべてを織り込んだ街づくり。
▽299 「フィデルのガバナンスの発想は家康のそれと重なるよ」
▽301 ものすごく格差は広がっている。……でも……日本語ができる学生がボロ屋に住んで、サンダルを5年間もはいている。「普通の国の貧しい若者が、彼のように大学で外国語の勉強ができるでしょうか。サンダルが買えないことを目を輝かせて自慢げに話せるでしょうか……」
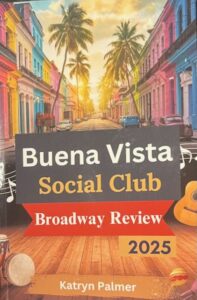

コメント