■町野今昔物語 <藤平朝雄> あえの郷しんこう会 20110615
旧町野村の郷土史や民話、伝説などをわかりやすくまとめ、地域を知らない人でも楽しめる。お坊さんが崖の道を13年もかけて切り開く話などを読むと、その道をたどってみたくなる。塩づくりの歴史と体験していたおじいさんの話などもおもしろい。
=================
▽12 平成9年、町野の5つの小学校が統合した。……金蔵小学校は、明治7年、慶願寺で開校し、最大生徒数は昭和6年の91人で、平成8年の閉校時は13人。
▽23 真言宗天王寺(広沢佑昇住職) 「能登石楠花寺」 昭和60年から石楠花の寺づくりの構想を練りはじめ、高野山のシンボルの石楠花を植えることに。献木を昭和62年からお願いし……花を見て献木者の心を思い、花どきが終われば、今年の花はこうだったとハガキにしたためる〓(石楠花が縁をとりもち、絆をつくる)
▽26 波の花 主に見られるのは、垂水の滝、曽々木トンネル手前、だっこ岩付近、窓岩の裏側
▽29 津波 1833年。輪島崎では、2,3軒の家が残っただけ。鳳至では大橋(いろは橋)から法蔵寺のあたりまで波が打ちかけ、水は住吉神社の鳥居あたりまで上がった。
▽31 金蔵 平成13年、「金蔵学校」が「石川地域づくり大賞」。
金蔵寺の名は、弘法大師が、中国で「金剛界と胎蔵界」の両部の密教を正式に継承したことに由来。……町野の先進地。郵便局も町野ではじめて開局。
▽42 アエノコト 徳成の中谷省一さん宅。
佐野寺のある佐野集落 地域おこしの特産「ゆず入り巻柿」が評判。その先には町野で唯一の造り酒屋の中納酒造。銘柄は「若緑」〓。
▽44 金蔵 古い歴史を伝える旧家の井池家。
▽46 十村役(他藩の大庄屋にあたる加賀藩特有の役名)
▽49 南家は、茅葺き屋根といろりのある美術館「南惣美術館」。古美術ファンに人気。
▽52 チョンガリ 「夜明けまで踊ったわいね。下駄のはが、明け方にゃすり減って平らになっとったわ」。輪島の三夜踊り、珠洲西海の砂取節……など、かつて奥能登には数え切れない盆踊りがあった。町野では圧倒的にチョンガリ。軽快なリズムとテンポ、泥臭くてユーモアたっぷりの歌詞。なかにはエッチな文句も飛び出して……
新しいチョンガリを、平成のまちのチョンガリを!
▽64 曽々木の寒中みそぎ 曽々木の青年団員は、8月17日の大祭では、輪島市でもっとお大きい10メートルのキリコを担ぎ出す。
▽69 時国家 壇ノ浦で敗れた平時忠は珠洲市大谷に流され、山間の地「則貞」で波乱の生涯を閉じた。今も時忠の墓所と伝えられる五輪の石塔が……。時忠の子の時国が後に町野川の下流域に出てきた。
▽71 上時国家(先代)は、完成までに28年の歳月を要した、と伝えられてきた。
上時国家は天領を管理し、下時国家は藩領を管理した。1軒の時国家を2軒の家に分立した。
藩政時代以前から、時国家が大きな船を所有して、回船業をしていた……多角的な経営者としての風貌をもっていた。「時国を支えたのは船による交易です」
▽88 町野町曽々木と珠洲市真浦との間は、「ひろぎ越え」とか「能登親しらず」と恐れられた。曽々木トンネル手前から、垂水の滝を越えるまでの600メートルほどの絶壁がつづくところ。岩場から足を踏み外し多くの人が亡くなった。曹洞宗「海蔵寺」の8代目住職が13年かけて道を開いた。1792年、完成。絶壁にとりつけられた道は、ようやっと人ひとりが通れる5寸ばかりの狭い道幅のところもあった。
「工事を助けてくれる天狗さん」はダイナマイト技術をもったポルトガル人で、長崎からつれてきて、寺の地下室で火薬を作らせていた、という伝承。
▽99 いわくら菩薩のみち 岩倉観音と千体地蔵をむすぶ700メートルほどの山みちを整備。岩倉山は、町野屈指のパワー拠点。岩倉寺は檀家のない寺で、岩倉比古神社との習合。
岩倉山の北西の中腹には、千体地蔵。標高170メートル。展望は日本海パノラマ展望台。
目次


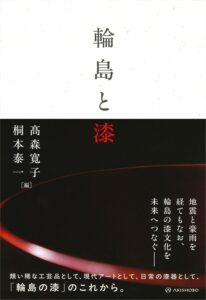

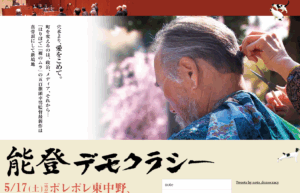
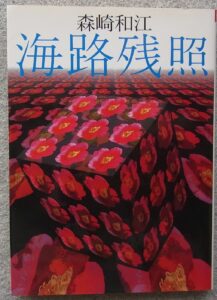

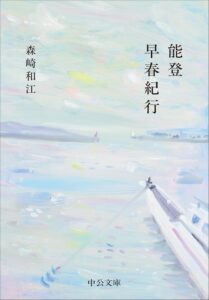
コメント