■奥能登の民家 民俗地理学的視点 <浜太一> 文芸社ビジュアルアート 20110610
ある地域の民家の特徴はどのようにつくりだされたのか。気候や地形といった地理的側面だけでは、川1本隔てて家のつくりが異なることの説明がつかない。歴史や民俗、支配体制などの要素も考慮して奥能登、とりわけ珠洲市の大谷町の民家の特徴を分析している。読みやすい本ではないが、大谷という1地区を取り上げるあることで、民俗や歴史まで総体としてとらえられるようになっている。
竹の間垣が多いのは、製塩の材料として雑木でも伐採が制限されたためであること。昭和49年ごろまで集落民の手で火葬にしており、冠婚葬祭などの接客や宗教行事(=オオヤケゴト)を重んじていたからこそ、ワタクシゴトが犠牲を強いられる間取りになったこと。戦後の近代化によって土間が小さくなり、水道の導入で井戸は床下に隠れて居間と台所の床高が同じになったこと。便所の糞尿は平成になっても肥料として活用されていたこと……。
どれも興味深い。
=================
▽17 地理学のみでは民家を把握しきれないということで、これまでの地理学による研究が批判を受けた。分布や地域的特色のみに傾注し、階層性や歴史の捉え方が手薄だということだった。
民家が、今までは、自然・風土規定説が主だったのを、川を挟んだ両岸で民家の形態が異なっていることにきづき、それが藩の境界線であることを知ってから、自然・風土規定説では説明がつかない、となり、「人的・文化的条件によって形態が規定されるのではないか」という仮説に。
▽28 大谷町の概要。
▽30 珠洲は、年間を通して雨が多く晴天の日が少ない。雪も多い。同緯度の太平洋側と比較すると、対馬海流が流れているため、気温は高い。……外浦の方が内浦より、冬・夏ともに気温が高い。外浦は、冬の季節風の影響を受けることが多く、夏もフェーン現象を受けることが多いから。
冬の防寒には、家の周りを茅などでぐるりと取り巻いたり、縁の下を板囲いする。囲炉裏で暖めた空気を逃さないよう工夫している。
▽45 能登は戦国時代も戦乱が少なく……このことが、立村当時の村の性格を色濃く残した理由。政治的にも改革されることがなかった。「名」が見出されていないことから、能登は強力な勢力を持った人がおらず、百姓たちが共同体的な集落を形成していたと考えられる。中世の特色を残した近世村落構造。
▽48 加賀藩は、時代やその土地に応じて、木材保護のために七木の制を定めた。木材を、城や道路・堤防・橋梁・用水の用材に当てるため。
▽50 竹も制限されたが、加賀ほどではなかった。そのため冬の季節風から家を守るための「間垣」は竹を編んで作られた。製塩のための燃料として雑木でも制限があったため、竹でしか作れなかった。
▽61 製塩 日本海側の製塩は、入浜式の瀬戸内式製塩に圧迫されて次第に衰えたが、能登では加賀藩の専売制の下で独自の発展を遂げる。4分の3を外浦が占めていた。
生産性が劣るため、明治以降は次第に衰退し、昭和初期には、外浦の西海村と町野村で存続するだけとなり、さらに昭和34年の第3次製塩整理で完全に姿を消すことになった。
▽68 製塩は、労働条件が悪く……昭和34年大谷町出張所が廃止され、収納価格の値下がりも追い打ちをかけ……大谷町では、このときの製塩業従事者は15人だった。製塩の廃止に伴い、業者は冬場に出稼ぎに出て、農繁期に帰省する賃金労働生活を繰り返すことに。
製塩にかわる産業として、葉たばこ耕作の要望が出され、試作の許可がなされた。現在は主要な産業として定着(〓今は? 葉たばこのかわりに……)
▽72 能登の祭り。時期は7月から10月上旬。夜祭りが基本。……大谷町はキリコを出し……9月に。
▽76 葬儀 昭和49年ごろまでは、火葬場で集落民の手で火葬にされていたが、現在は斎場ができており……。葬儀を終えて祖先に感謝するし、祖先崇拝は決して衰えない。隣近所の助けがないと葬儀も行えないことを誰もが知っている。だからこそ、つきあいを大切にしなければならないし、続き間も必要。このような間取りは、年に数回しかない冠婚葬祭を第一と考えられているため、日常生活においては使いにくいものだった。「オオヤケゴト」が家の中に入り込んで、ワタクシゴトは、譲歩と自虐的な自己犠牲が強いられた。(北側の台所。阿蘇の家の間取り〓)
▽79 平成になっても、電気を引いてない家がある。
▽80 大谷町など外浦では、井戸を掘って使用していた。内浦の飯田町などの町のためや、工業の促進をはかるため、外浦の反対を押し切って昭和27年に簡易水道を布設。昭和39年までに市全体に水道供給。一家に一つあった井戸は、モーターとともに床の下に隠れてしまう。
▽83 土間。大谷町でも昭和26年当時、近代化された民家といえば土間部分が小さかった。
▽85 台所 大谷町で改善が始まるのは昭和30年代。ほかより10年から20年の遅れが見られた。左官屋が、流し台や近代的なかまどを作る技術を得るまでに時間がかかった。昭和40年代に入っても、大谷町に冷蔵庫がある家は1軒のみだった。
水道やシステムキッチンの発達にともない井戸はモーターとともに床の下に隠れ、はじめて居間と台所の床高が同じになった。井戸で野菜や生ものを冷やしていたのが使えなくなった。冷蔵庫が入ると、それまでは必要な食べ物をその日のうちに食べていたのが、わざわざ冷蔵庫にしまうという不自然さがおこり、祖父母と若夫婦の間に意見の食い違いが起きたりした。
▽91 便所 子牛を売って生計の助けにするため、納屋の半分を牛が占めた。糞尿は半地下式のくぼみにワラと一緒に積み重ねられ……道路に面した屋根下に積み上げておき、田に堆肥の代わりにまく。匂いがあちこちからするから、家の中には大便所は設けられなかった。肥だめの上に人間の乗る厚板を2枚渡しただけだった。
水洗は、平成になってもまだ普及していない。大切な肥料として活用している。
▽92 接客重視の座敷。「一般民家の囲炉裏の横座と客座の間に交わされていた親しい交際を、近代の人間的な社交に発展させることなく、猫もしゃくしも座敷を構え……南向きの日当りのよい場所に座敷がしつらえられ、ほとんど使われないのに、常に家人が使う居間や台所は日当りの悪い、穴蔵のようなところにある」(〓阿蘇の家)
▽96 能登 封建時代に形作られた生活の名残や、浄土真宗を信じる土地柄のため、大きな仏壇と仏間を備えている。各家で冠婚葬祭の儀礼が重んじられていることから、社交的な間取りの形が色こく残されている。宗教行事と接客を重んじることで、家族のための生活が遅れる大きな原因となった。
▽99 浄土真宗 北陸に布教した蓮如。……重労働からの救いを、浄土真宗に求めたのでは。祖先供養が根付いているため、「仏間」を設けたとも考えられる。
▽105 製塩のための労働は重く、家を快適につくるのは不可能に近かった。浄土真宗が入ってきたことで、製塩作業の苦しみを救ってくれたのにちがいない。十村(地主?)などが接客間をもち、大きな仏間を持っているのを見て、農民も、持ちたいと思ったに違いない。
目次


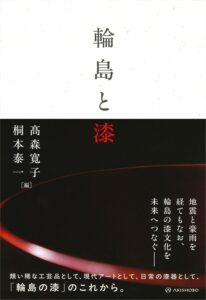

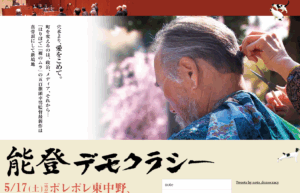
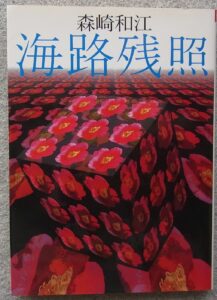

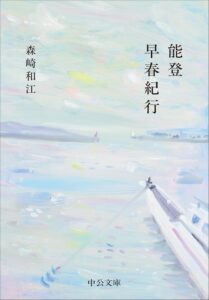
コメント