■TPP反対の大義 <農文協編> 農文協ブックレット 20110226
さまざまな視点からTPP反対論を展開する。農協の反対運動はタテマエ臭さが抜けないが、哲学や経済学など、深みのある論もあって勉強になる。
宇沢弘文は、「社会的共通資本」である「コモンズとしての農村」と位置づける。90年代の終わりから、社会的・文化的・自然的環境のなかで生きる生活者の集まりとして、政府も農業を位置づけはじめたが、実際の政策は、一般法人の農業参入や農地所有権解禁をすすめ、コモンズとしての農村を否定するものになっていると批判する。
田代洋一は、「GDPの一次産業の割合は1・5%だ。1・5%を守るために98・5%のかなりの部分が犠牲になっている」という前原誠司に対して、「アメリカは1・1%、イギリスとドイツ0・8%であり、日本より低いそれらの国々でさえ農業利益の追求に躍起になっている」と具体的な数字をあげる。「TPPは、日本にとって最も厳しい条件の日豪ETAと日米FTAとを一気に締結するようなもの」という鈴木宣弘の説明もTPPの恐ろしさを浮き彫りにしてくれる。
小田切徳美の論は農村の取り組みにわずかな希望を感じさせてくれる。
農林産物加工や農家レストランなどの「六次産業化」や、農地が集積され「集落営農」という日本独特の営農主体を含むユニークな構造変化が動き出していることなどに再生の方向性を見出している。「忘れてはならないのは『誇りの空洞化』。地域に住み続ける意味や意義を見出せない『心の過疎』」という指摘はまさにその通りだと思う。私が各地の現場を見て考えてきたことをもっとしっかりしたコトバで表現されてしまった。
楠本雅弘氏も、80年代に島根や富山ではじまり、07年から全国に広がった「集落営農」を高く評価する。しかも、効率的地域営農組織の段階から「社会的協同経営体」へと進化し、地域住民の「希望の拠り所」になっているとみる。
そう、コルホーズのような単純な大規模化・効率化ととらえてはならないのだ。地域コミュニティを基盤とし、地域の絆を高める方向に向かっているからこそ集落営農は一定の成果をあげた。ムラの論理と経済の論理の融合。社会主義的集団農場にはなかった「地縁」や「絆」を重視したことが効果を表したことがわかる。
「地域内再投資力の育成」を説く岡田知弘氏もおもしろい。
公共事業は単発であり、誘致企業は地域で生み出された所得を本社に吸い上げてしまう。そういった失敗から学んだのが「地域内再投資力」という考え方だという。まさに、地場の農産物を活用するために加工や販売を手がけるようになった「吉田ふるさと村」の取り組みだ。最先端の取り組みは、もっとも遅れていると言われる山村から生まれているということがよくわかる。
では個性的な地域産業をどうつくるか。「まずは、経済主体や地域資源を科学的に把握すること」という。調査(=地区診断)がすべての基盤になるのだ。そうした調査を基盤にすることで、地域内の産業ネットワークを構築し、地域内での経済循環を組織することが可能になる。雲南市の農商工連携の取り組みなどは、その実例であることがわかる。
沖縄のサトウキビを巡る論考も興味深い。本土からみると、米の大切さはわかるが、サトウキビ畑がなくなってもたいしたことがない、と考えがちだ。
だが、サトウキビが「地力維持作物」として沖縄農業の基盤になっており、サトウキビをなくすことが沖縄農業じたいを崩壊させることになることを知ると、その深刻さがわかる。
その地域の目線で、具体的に影響を観察することで、はじめてその土地に育つ作物や農村じたいの「価値」が見えてくる。「調査」は対策を具体化するためにも、反対運動の中身を育むためにも不可欠なのだ。TPPに反対しながら、自分の受け持ちの区域・分野の調査さえしようとしない団体が多いことの情けなさがよくわかる。
韓国では、90年代に膨大な農業投資をしたが農家負債は増えたという。その結果、「農業投資の無用論」が生まれた。さらに、経済危機による格差拡大によって、食料品価格の高さに不満をもつ消費者が増え、国民世論は農業保護から開放化へと移っていった。貧富の差が農業バッシングを生み出す構造は日本も同じだ。ギョーザ事件後、国産志向が高まったが、リーマンショック後その熱気は急速にしぼみ、以後日本の消費者は激しい低価格志向に雪崩を打ったままでいるという。
=============================================
□宇沢弘文
社会的共通資本としての農村。
工業部門では、商品化された労働力と、労働者の人格的主体との間には緊張関係が形成され、自己疎外が形成される。農業部門では、自らの人格的同一性を維持しながら、自然のなかで自由に生きることが可能になる。
農業は自然環境保全にも。
独立した生産・経営単位を一戸の農家として巨大企業と競争させれば農業は衰退する。農業において、独立した生産・経営単位としてとらえられるべきものは、コモンズ〓としての農村でなければならない。
……兼業農家は、その労働の果実の大部分を工業部門に吸収され、賃金のかなりの部分を使って、工業部門の産物である農機・農薬の購入にあて……兼業農家の割合が高くなるほど、農業部門が、競争という観点からますます不利となる条件がつくりだされる。
90年代の割り語呂から、定年帰農というかたちでコモンズを担う動きが急速に進展しつつある。このころから政府の農業政策は転換し、農業の概念を拡大して、社会的・文化的・自然的環境のなかで生きる生活者の集まりとして位置づけはじめた。農業基本法などの法的制度の改正というかたちになって表れた。……しかし、農業生産法人の要件緩和などを通じて一般法人の農業参入を許し、農地所有権解禁に道をひらき、コモンズとしての農村を全面的に否定するものになってしまった。
□田代洋一
▽22 TPPは民主党を反小沢派と小沢派に二分した。マスコミでは、日経がTPP促進であることは言うまでもないとして、反小沢キャンペーンで政局を動かしてきた朝日新聞が異常な肩入れをしており、船橋洋一の「通商国家論」に沿って、繰り返しTPP促進を訴えている。
▽ 10カ国のGDP総額の9割以上を日米が占めることになり、TPPは「事実上の日米FTAになる」(日経)
▽24 前原「GDPの一次産業の割合は1・5%だ。1・5%を守るために98・5%のかなりの部分が犠牲になっている」。同率はアメリカ1・1%、イギリス・ドイツ0・8%であり、日本より低いそれらの国々でさえ農業利益の追求に躍起になっている。
▽26 交付金の対象を規模により限定する自民党の政策を批判して、民主党は、全販売農家を対象にする戸別所得補償政策に切り替えたはずだった。2010年3月の食料・農業・農村基本計画でも……
□アメリカの対アジア戦略 服部信司
▽33 WTO交渉は、関税引き下げだけでなく、農業の国内支持(保護)引き下げをも交渉分野にしている。アメリカはWTO農業交渉において、自国の農業国内支持の引き下げに強く抵抗しており、そこから交渉が行きづまっている。FTA/EPA交渉の場合は、国内支持の削減は交渉の対象にならない。アメリカには後顧の憂いなく交渉にあたれる。
□真の国益とは 鈴木宣弘
▽38 FTAの本質は差別性。たとえば、NAFTAで米国は、乳製品をゼロ関税にしてメキシコにタイする輸出を伸ばして利益を得ているが、米豪FTAでは主要乳製品を例外扱いとし、豪州からの乳製品の輸入増を防いでいる。
▽40 農業だけではない。チリとのFTAでは、銅板が問題になった。マレーシアやタイとは、最後まで難航したのは鉄鋼や自動車。日韓FTAが中断している原因も、表面的には農業のせいだと言われるが、実は、部品・素材産業分野だ。日本からの輸入が増えて素材・部品産業に被害がでることを懸念する韓国世論。
「農業保護をとるか、TPPの利益をとるか」ではなく、「一部の輸出産業の利益のために失う国益の大きさ」を考えるべき。
▽43 日本側が重要品目の例外扱いを求めるかわりに、FTAの利益から取り残されがちな相手国の零細農民に対する優先的配慮を可能なかぎり行い、アジア農村の貧困解消に貢献することによってバランスを確保すれば、双方の利益を高めるFTAが成立する(タイやフィリピンとのFTA)
▽44 TPPは、日本にとって最も厳しい条件の日豪ETAと日米FTAとを一気に締結するようなもの〓
▽47 米国は「安く売ってあげるから非効率な農業はやめたほうがよい」といって世界の農産物貿易自由化を進めてきたため、少数の輸出国に国際市場が独占されつつある。
……メキシコでは、NAFTAで主食のトウモロコシ生産農家がつぶれ、米国から安く買えばよいと思ったら、こんど価格高騰で輸入も困難な事態に追い込まれた。〓〓
▽48 米国の農業保護……WTOルールは輸出国側に有利につくられている。輸入国に関税削減を強要しながら、輸出国側は多額の輸出補助金で安価に輸出している。
日本は、WTOルールを守り、農業保護削減義務を世界でもっともマジメに実行してきた優等生。政府の価格支持政策をほとんど廃止したのは日本だけ。農産物関税も11・7%と低く、農業所得に占める財政負担の割合も15・6%で、欧州諸国が軒並み90%を超えているのに比べてはるかに低い。なのに、「過保護な農業保護国」と批判され、農業関連予算も減額されつづけている。
□TPPと日本農業は両立しない 森島賢
▽56 TPPは、労働者の移動の自由化も重要な目的にしている。……そうなれば自由貿易圏内の労賃は同じになる。
▽57 15年前のガット交渉で、関税化という名前の輸入自由化のときは、対策費として5年間で6兆円の財政支出をした。しかし、自由化に耐えられる農業はつくれず、自給率を40%まで下げた。
▽58 現在ロシアは小麦の輸出を禁止している。それを当然な食糧主権の行使として、非難する国はない。……TPPに参加して食糧主権を放棄しようとしている。
□TPP論議と農業・農山村 小田切徳美
▽61 前原「1・5%」発言を批判 産業界が誇る自動車を中心とした「輸送用機器」でもそのシェアは2・7%。製造業全体でも19・9%。「犠牲」の対象と示唆される輸出は、GDPの17・5%にすぎない。
▽62 このような農業批判が、農山村批判、さらに地方批判という広がりを見せることに。80年代前半、「農業保護をやめればサラリーマンは豊かな生活ができる」という竹村健一や大前研一の本がベストセラーになった。00年代はじめの小泉政権の時は、農業批判にとどまらず、農山村を含む地方批判へと発展した。「過疎地域はますます過疎化するのはいいことだ」「人を大都市圏に集めれば日本経済は復活する」(増田悦佐)という露骨な論調も登場した。……そして、今回のTPP論議に伴う農業批判……
▽64 農山村を巡る新たな動き 農林産物加工や農家レストランなどの「第六次産業化」、さらに交流産業(グリーンツーリズム)。農業就業人口が2割も減り、小規模農家数の減少が加速化。農地面積は5年間で2%の減少にとどまったため、中・大規模経営に農地が集積される傾向は強まっている。……欧米型とは異なる、集落営農という営農主体を含む担い手によるユニークな構造変化に向けて動き出したと言える〓〓
▽66 農山村は解体と再生の攻防の最中にあり、今ようやくその中で、新たな再生の方向が見え始めたといえる。〓〓
したがって政府が行うべきは、北風を吹かせることではない。新たな方向を探るこれらの主体への強力な支援だろう。
忘れてはならないのは「誇りの空洞化」。地域に住み続ける意味や意義を見出せない「心の過疎」現象。それが極限まで至り、集落全体が諦めの気持に転化したのが、「限界集落」の本質である〓〓(あきらめ、を乗り越えるには〓)
□TPPと日本農業の構造問題
□世界貿易の崩壊と日本の未来 関曠野
▽74 自由貿易どころか、リーマンショック以来、世界貿易はどんどん崩壊している。関税の撤廃で対処できるものではない。活発な消費市場の世界的な消滅によって、09年度に12%という戦後最大の縮小を記録した。
▽79 日本は中韓両国のように、国内市場の狭小さや農民の貧困ゆえにアクロバット的貿易立国をやらざるを得ない国ではない。日本経済の輸出依存度は16%。貿易がGDPに占める比率は170カ国中で164番目。企業が国内市場だけで商売できるガラパゴスが可能な国は世界でも日本だけである。
TPPへの参加は、大企業の要求だが、大企業は稼いだ外貨をためこんだり海外で投資したりしていて国内の経済循環に貢献していない。中小企業がベテラン従業員を失うまいと必死で雇用を維持しているのに、トヨタやキャノンはさっさと派遣切りをやった。
さらにピークオイルの問題。人類の未来は長期的には農業中心の地域共同体にある。
円高で輸入が容易な今のうちに、エネルギーと食料の自給率を高める政策を国を挙げて推進する必要がある。
そうした方向転換は、中央政府に期待しないほうがいい。地方の、地域の人々の草の根の動きとしてはじまり、それが自治体を動かし、自治体が国を突き上げるかたちで始まるだろう。
□食料自給を放棄した例外国家への道を突き進むのか 谷口信和
▽85 メキシコ 1994年発効のNAFTA加入時の穀物自給率は80・6%だったが、15年かけて農産物関税を撤廃する協定に基づいて、補助金つきのアメリカトウモロコシの大量流入により、02年以降は65%以下にまで低下した。こうしたなか、06から08年の世界食料危機では、主食のトルティーヤ価格の高騰(半年で70%)により暴動が発生した。
□北東亜細亜における食料・農業協同の芽をつみ取るTPP <飯國芳明>
▽90 日韓台は食料純輸入経済圏。カロリーベースの食料自給率はいずれも50%を下回る。国際貿易ルールに沿った農業保護水準のさらなる削減が予測されるなかで、いかにして安定した食料を確保し、農村社会や環境の保全を図るかは共通の課題となっている。3国は、今や同じ目線で農業問題を語り、協同して解決策を模索しあえる関係を確立しつつある。
北東アジアで生じつつある協同関係は、モンスーン・アジアの経済発展とともに拡大・発展する趨勢にある。しかしこの動きは、TPP構想とは折り合わない。萌芽期にあるモンスーン・アジアの協同は、TPPにより分断され、協同の芽はつみ取られかねない。
□グローバル時代だからこそ地域内再投資力の育成と地域循環型経済づくりを <岡田知弘>
▽94 住民が地域に暮らし続けるには、その地域で雇用と所得が再生産されなければならない。その際、重要なのが「地域内再投資力」である。これは過去の地域開発政策の失敗から学んだ考え方だ〓。公共事業のような1回きりの投資や、誘致企業のように地域で生み出された所得を本社のある大都市に移転するようなことでは、その地域の持続的発展には結びつかない。(ふるさと吉田村の取り組み〓〓)
▽96 地域再生には? 99年改定の中小企業基本法をきっかけに、県レベル、基礎自治体レベルで「中小企業(地域)振興基本条例」制定の動きが相次いでいる。……帯広市では、条例制定を機に、自治体と中小企業、地域金融機関の協同によって、農商工連携をはじめとした具体的施策を充実させ、経済危機に対しても効果的に対処した。
▽97 個性的な地域産業をどうつくるか。まずは、地域経済を成り立たせている経済主体や地域資源を科学的に把握すること(〓地区診断)。墨田区のように、定期的に商工業事業所の悉皆調査をおこない、それをもとに、技術支援やマーケティング支援などを展開する。さらに、調査をもとに、地域内の産業ネットワークの構築が可能になる。異業種交流などによって、結びつけ、地域内での経済循環を組織することが重要(〓雲南市の農商工連携の取り組み)
▽98 住民が担い手である中小企業、農家、協同組合、NPO、地方自治体の協同によってネットワークが広げられ、地域内経済循環を高めることによって地域内再投資力が形成できる。
□道経連を含む「オール北海道」で反対する <東山寛>
▽101 北海道は06年に日豪EPAの影響を試算。
▽102 地域別試算をすることでリアリティを提供〓。
▽104 農業団体だけでなく、経済団体・消費者団体も足並みをそろえて「オール北海道」で運動。
□さとうきびを壊滅させ、沖縄農業消滅に直結するTPP <来間泰男>
▽105 サトウキビは、1トンのきびは1トンの葉や根を地中に還元するため有機物を提供する「地力維持作物」。土地改良直後のこなれていない土壌にまずキビを植えて3年ぐらいすると土壌ができてくる。
伊江島では葉たばこの収益が大きいからと、きびを減らして葉たばこを増産した。その結果、製糖工場は潰れた。そこで困ったのは、地力維持作物を失った葉たばこ農家だった。彼らは葉たばこ拡大の方針を転換し、きびを植えるようになり、製糖工場も復活させることになった〓。
▽109 サトウキビは収益性が低く、縮小の流れにある。TPPできびが消滅すれば、沖縄農業の消滅に直結する。TPP参加は沖縄農業不要論に他ならない。
(具体的に地域への影響を見ると、はじめてひとつひとつの作物をつくることの価値が見えてくる。地道な調査は反対運動にも不可欠だ〓)
□米韓FTA交渉における韓国政府の農業の位置づけを検証する
▽111 韓国のFTA交渉の特徴。「同時多発的で包括的推進」「巨大経済圏との推進」。韓国はEU、インド、アメリカといった経済大国とFTAを締結し、経済規模において日本のそれを圧倒。
▽112 ウルグアイラウンドの農業自由化にそなえ、92年から03年の間に、7兆円の投資をしたが、農家負債は増加。その結果、経済学者による「農業投資の無用論」が登場する。さらに、97年にはじまった外貨危機から所得の格差が拡大し、低所得層を中心に、食料品価格の高さに不満をもった消費者が増えてきた。これらによって、国民コンセンサスは農業保護から開放化へと移っていった。
(〓貧富の格差が農業バッシングを生み出す)
□農家は「自衛農業」でわが身を守る <山下惣一>
▽120 輸入米1キロあたり341円のマークアップ、関税率にして490%がゼロになって日本の米作りはどうなるのか。沖縄などのサトウキビの85%の高下駄を外したあと島の人々の暮らしをどうするのか。……
農産物の輸出は、それ自体を目的とするべきではない。自給率40%、足元の農業がガタガタで壊滅寸前なのにそんな場合か!……つまり、国産の安全でおいしい農産物は中国の富裕層に送り、日本の低所得層は中国産の安い米や多国籍企業が世界一安い食材と労賃で製造した安価で粗悪な食品を食わされるという構図になる。
□TPPに抗し、「社会的協同経営体」の広がりを <楠本雅弘>
▽127 80年代中頃から、中国山地の島根県や北陸兼業地帯の富山県で、「地域の知恵」として着想・実践されはじめたのが「集落営農」だ。その後、07年度からは政府の農政推進対象に位置づけられ全国的に広がった。
集落営農は、その後の実践・創意を加えて「社会的協同経営体」へと進化し……単なる効率的地域営農組織の段階から、地域住民の暮らしを支え、地域を再生するコミュニティ活動組織へと進化しつつある。地域住民の「希望の拠り所」。
(〓単なる大規模化ではない。地域コミュニティとしての大規模化だからうまくいく。ムラの論理と経済の論理の融合。単なる大規模化ではコルホーズになってしまう)
□市場の時間、むらの時間 <内山節>
▽128 一次産業の価値についての正論が通用しなくなってきている。農業などに係わったことのない人たちが多数派になり、農山漁村出身者が少なくなったことも原因。だがそれだけではない。農民団体は、自由化のたびに反対してきたが、この反対の動きのなかには、市場主義そのもので生きてきた団体が含まれている。農業とは何か、地域はどうあったらよいか、生産者と消費者はどう結んだらよいかといったことを真剣に考えることなく、市場のなかで自分たちの経営にとって不利になる市場開放がおこなわれようとしているときだけ、市場主義に反対するという現実が展開されてきた。そのことが、農民の動き全体に対する誤解を生み、不信感を拡大させてしまった。
……自然とともに労働してきた在り方が農村をつくり、様々な地域文化をもつ「むらの時間」をつくりだしてきた。「むらの時間」を大事にしていく都市と農山村の結びつきが何より重要になる。この試みをどこまで拡大・定着していけるのか。この脈絡のなかで語らなければ、TPP反対も市場の横暴と対決するものにはならない。
□協同はTPPを超える <蔦谷栄一>
▽134 地方経済の活性化のためには、地産地消や第6次産業化による農業の活性化は欠かせない。
担い手は大規模生産農家と自給的農家とに二極分化し、自給的農家に加えて市民農園・体験農園・定年帰農などによるたくさんの市民が地域農業に参画し、農業の裾野を広げていくと同時に、農業に対する理解者を増やすことが求められる。
……地域での農業は、生産者と消費者、農協と消費者グループとの連携により、農業と生活・暮らしを一本化させ、地域住民がこれを支持する地域社会農業でなければならない。……高齢者の介助など地域コミュニティを再生することによってお互いに助け合う。こうして海外はもちろんのこと、国にも、さらには現金経済にも極力依存しない自立的な地域経済を構築していくことが求められる。
(〓地域通貨の発想)
国主導による「地方の時代」ではなく、地域自ら、生産者と消費者を中心とする協同の力によって実現していくことこそが、究極のTPP対策。
□生活クラブ生協のめざす消費者像とTPP
▽136 ギョーザ事件後、消費者の国産志向は瞬時に頂点に達したが、リーマンショック後、その熱気は急速に衰えしぼんだ。その変化を日本政策金融公庫が統計的にまとめた。以後日本の消費者は激しい低価格志向に雪崩を打ったままでいる。
(格差社会は反農業になる〓)
(農商工連携や集落営農など、実際に目の前で起きて取材していることが実は最先端であることがよくわかる)




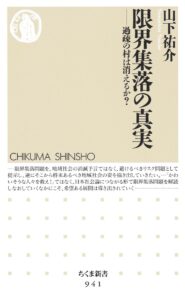
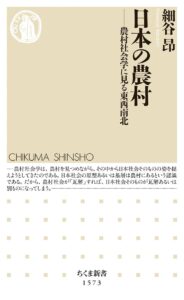


コメント