■200万都市が有機野菜で自給できるわけ 都市農業大国キューバ・リポート <吉田太郎> 築地書館
〓〓〓
日本では都市農地は年々減っているが、世界では都市農業の位置づけは正反対だ。
90年代、キューバはソ連崩壊によって未曾有の経済崩壊となった。それまで、砂糖やコーヒーを輸出して、コメヤ小麦を輸入する国際分業路線で、食料自給率は40%。大量餓死者を出しかねないなかで、ハバナ市民は都市農業を選んだ。日本の今と似ている。
農業労働者でしかなかったところに百姓文化が創造され、肉食中心から野菜中心へと食文化も変化しつつある。ニカラグアやハイチを見て、失われた百姓文化は取り戻せないと思っていたから、驚きだった。
ヒューマニスティックな哲学と、環境と調和した適正技術、行政とNPOのパートナーシップによる、コミュニティレベルに基づく合意形成や徹底した地方分権という社会制度がその背景にある。ソ連型の中央集権体制からの転換、世界でも注目を集めているコミュニティソリューションの導入なしには成し遂げられないものだった。
「科学」の在り方。専門家の在り方も問うている。
参考資料の量がすごい。すさまじい量の文献を読みこんでいる。
▽19 UNDP1989年の「生活水準の指標」で世界11位。アメリカは15位。1人あたりのGDPは日本の16分の1なのに。
▽22 キューバ人は自分たちがラテンアメリカの指導者というプライドがある。自分が苦しいときでも海外を援助する。
ハリケーンミシェルでも、300万人が避難したが、死者は5人だけ。危機管理の徹底〓。その手法は。
▽24 途上国の青年を教育するため1999年には「ラテンアメリカ医科大学」創設。98年のハリケーンミッチで、ニカラグアで政府の援助活動がおこなわれなかったことを踏まえた。
▽26 農業は大規模モノカルチャーに特化。農薬化学肥料の投入量はアメリカより多かった。……一時はキューバだけで、WHOを上回る技術者や医師を派遣。……ソ連からの援助による上げ底経済。
▽29 経済崩壊 経済封鎖 医薬品でさえも。停電つづき。交通麻痺。冷蔵や配送も停止。畑で腐る野菜。
▽38 〓ジョージタウン大学ラテンアメリカ研究センター
▽46 ゴミ捨て場を農地に。
▽65 革命以前は、野菜作りをしていたのは中国人と日本人だけ。革命後は、移民はこなくなり、誰もが医師やエンジニア、軍人になり、農業をおざなりにしてきた……(ニカラグアの状況も〓)
▽67 オルガノポニコ コンクリートなどでかこった苗床で野菜をつくる。土がない場所でもできる。雨で土壌や種子が流れることもない。
▽81 地区レベルの行政機関 コンセホ・ポプラール(人民評議会) コミュニティレベルの自治のため92年の憲法改正に基づき設立。コンセホや普及員に土地利用調整をゆだねることで、官僚的お役所仕事を一掃。遊休地は次々に畑に。
日本でコンセホに相当するのは農業委員会。都市農業の振興も、99年の「食料・農業・農村基本法」に明記された。
▽87 当初は園芸の知識は会務。小面積多品種の有機農法の経験はなかった。栽培技術のいろはを普及員たちが普及。96年から、安全性確保のため、全都市内で農薬と化学肥料使用をとりやめた。
▽90 ……新たな人間関係も生まれる。
▽94 普及員も分権化。管内を1日中、徒歩やバスで移動して指導する。現場を歩けば、農家の要望や事例が否応無く頭に入る。(〓地区診断、公務員のありかた)
日本も都道府県の農業改良普及員が農家指導をするし、大きな農協は営農指導員もかかえるが、有機栽培指導では後れを取っているし、農家以外の都市住民への指導も限界を抱えている。
▽103 コンサルティングショップという農業資材店。菌の培養……「窮乏するなかでの創意工夫が、逆に多くの資金や高度な機器がなければやれないというバイテク神話を覆した」。どんな僻村でも取り組める適正技術を生みだした。
▽105 研究者は現場を何ヶ月も泊まり歩く。……全員が毎日農村へ出かける。
▽112 最先端のバイオ技術と、ミミズ堆肥などを組み合わせ、適正技術を開発した。地域ごとの土着の栽培技術をうまく掘り起こし、農業の伝統的な知恵の再発見につとめたからだろう。たとえば、食虫アリをつかったアリモドキゾウムシ対策……世界でもはじめて。こうした発想は、机上の理論や実験からは出てこない。「とかく科学者というのは、これが正しいと思うと、個々の畑の特性を無視して同じようなやり方をとりたがるのです」〓
▽118 プランテーション農業が発達し、近代的農業モデルが推進されたため、豊富にあるはずの作物品種がほとんど失われていた。……熱帯果樹さえなかったし、メロンやカボチャも1品種しかなかった〓
▽ 127 コンサルティングショップの普及員。……日本でも県庁に所属する農業改良普及員とは別に、各農協が営農指導員を抱えている。普及員が土地の利用調整や地域農業全体のマネジメントをするのに対して、実際の営農指導は農協が中心。
▽128 在来品種復活……江戸時代は多様な品種保存や品種改良がすすんだ。稲では水戸藩では296種類、尾張では
407種類……クリは尾張で161種……適地適種が原則とされた。この努力は今のキューバにも通じる。コシヒカリなど優良品種への単一化を進めている現在の農政よりもはるかにエコロジカルで合理的。
▽134 闇市価格を下落させるため、94年から「農民市場」。キューバ版の「朝市・直売所」。農産物がペソで買えるようになり、ドルに対するペソの価値を高めた。94年7月に1ドル120ペソだったのが、96年春には21から23ペソに。
▽140 基本的カロリー源としてのジャガイモ、トラクターの代替となる牛や馬の肉の自由販売はできない。配給用の牛乳や乳製品の販売も禁じられている。輸出品のコーヒー、タバコ、ハチミツも。野放図な規制緩和を認めていない。
▽151 キューバ人は単なる経済的利益だけを求めてはいない。……「無償で土地を借りられるのですから、いくらかをコミュニティに還元するのは当然」。農産物を障害者施設などに寄付。地区への協力精神と社会的弱者を配慮した地場流通が、食糧危機のなかでも1人の餓死者も出さずにすんだことにつながっている。……1人暮らしの老人が、安く食事できるレストラン。3食の宅配も。
〓エルサル難民のコロモンカグア=セグンドモンテはどうだろう?
▽156 緑の薬品 薬品需要の2割をまかなう。薬草栽培には農薬も化学肥料も使わない。
▽176 農産物の窃盗。「近所の子に農園の作物について教え、農作業を手伝ってもらったお礼に少しだけ小遣いを渡し、農産物もお土産にあげた。こうした人間関係を育むことが窃盗予防につながる。菜園を塀で囲うよりもよっぽどいい」
▽182 食堂/学校などの生ゴミはすべて回収。堆肥や豚の資料源。ハバナ市の担当者は、永年生の果樹や樹木も植栽し、都市の生物多様性を高め、木材や燃料源も都市で自給できるようにしなければと考えている。
キューバの自然は豊穣だった。中央ヨーロッパで4000の植物種しかないのに、キューバでは同定されただけで6200種。……だが植民地支配、アメリカの支配で……森林面積も激減。
▽210 コミュニティレベルで意識を高め、森林復元や河川浄化をはかる。「意見をまとめ、合意を得るのが大変。住民懇談会を開いてニーズをくみ上げる。……公園プロジェクトのように大きいテーマになると、ほとんど意見がでない。スタート段階では上からの指導が必要だった」「ここで暮らす地区の住民参加がなければ、一歩も前へ進むことができない」というのが、専門家メンバーの見解だった。 ワークショップを次々と開催……トップダウンではなく、個人参加を促すボトムアップ方式。これはキューバでは初めての試みであり、他都市での持続可能な開発のモデルになるであろう。(〓地区診断、民主主義のツール)
▽222 1992年や95年「自転車革命がキューバを席巻している。……ハバナは今自転車に最も優しい都市となっている。100万台の自転車が中国から輸入され、国全体では5つの自転車工場が完成している」……自転車を安全を守るため、自動車の制限速度は引き下げられ……
▽234 小規模水力 1993年にカストロがミニ水力発電を奨励。風力発電も。
▽238 ソーラー。2000校の山村地域の学校をソーラーパネルで電化。
▽254 1960年代から農作業を通じて働くことの大切さを学ぶ農業教育を展開。このルーツもホセ・マルティにある。「朝にペンを持たば、午後には耕せ」。革命後、ほとんどの小学校に「学校菜園」が設けられた。(加藤歓一郎の産業教育)〓
▽256 92年の地球サミットで、持続可能な開発の実践において「Aプラス」の評価を受けた国は世界で2つしかなく、1つがキューバ。92年に憲法改正し、「……自然保護に献身することは、人民の責務である」
▽266 サンフランシスコの都市農業。CSO活動が盛ん。環境や農業、福祉やまちづくりのNPOが5000を超す。ヒッピー文化も「ホールアース・カタログ」もここで誕生。カウンターカルチャー運動の発祥地として、いまも世界の「エコロジー運動」を牽引している。
▽280 コミュニティソリューション サッチャーの構造改革では、失業問題は解消せず、地域コミュニティは崩壊し、社会格差が拡大した。イギリスの経済が活性化された本当の理由は、サッチャーの改革ではなく、コミュニティレベルでのパートナーシップの構築と、それに着眼したブレアの改革にある。ブレアが目指すのは人間の顔をした「サッチャリズム」。NPO重視。税を徴収し、福祉サービスの形で還元する従来の行政システムの限界をみすえて、ボランタリー精神をくみとり……行革の成果をいかしつつ、かつコミュニティに根ざし、民間とのパートナーシップにより、人々のやる気を喚起させながら諸問題を解決する。「第3の道」
……長い不況で民間やコミュニティレベルでの先駆的事例を生みだしてきた。家屋修繕や学童保育……といった社会サービスを請け負う「コミュニティ・ビジネス」は、サッチャーの政策で打撃を受けたスコットランドの人々が1980年代に自発的に作りだした方式。荒廃した市街地を再生する住民主導のまちづくり会社「ディベロップメント・トラスト」も保守党政権時代に誕生。
それらの事例を国のビジョンとして掲げたのが、ブレアの「福祉ニューディール政策」。中央集権型の福祉国家は、人々の依存体質を生みだしてきたが、新しい社会システムでは、あらゆる構成員が参加し、協力しあうことが欠かせない。パートナーシップを築くには、社会全体の信頼関係を高める必要がある。それをブレアは地域というコミュニティに委ねる。ブレアの政策のキーワードは、自立とパートナーシップとコミュニティ〓。
▽284 パットナム 人々の協力がうまくある地域と、相互に不信感を抱き合う地域との差はどこに? 地域コミュニティが蓄積してきた「民度」、すなわちソーシャル・キャピタルの差が決定的な要因ではないだろうか。これがパットナムの仮説だ。(〓島根でうまくいく場所=築きあげてきた絆=ソーシャルキャピタル)
コモンズの悲劇を回避する、フリーライダーが出にくいコミュニティの特色。
メンバー間の相互信頼性が高い。コミュニティとしての社会規範が働く、という2つをあげた。(〓金銭利益ではないコミュニティとしての価値観を育んでいるかどうか)
▽286 「ソーシャルキャピタル」もともとジェームス・コールマンらが提唱しはじめた。「通常は、カネ・モノ・ヒトが資本だと考えられているが、ソーシャルキャピタルは、人と人との関係性のパターンである。とらえがたいと考えられてきた関係性という要素の集合が、経済やその他の目に見えるメリットを生む源泉、ないしは、資源なのである」
金子郁容は、パットナムのコミュニティ論やゲーム理論の研究を踏まえる。
▽288 行政が強制力で統制する「ヒエラルキーソリューション」も、経済的に問題を解決する「マーケットソリューション」も、個人と切り離して問題を解決しようとする。コミュニティソリューションは、個人と積極的につながりをつけることで問題を解決しようと考える。……顔の見えるコミュニティに信用の「よりどころ」を置いたうえで、個人や社会の問題を解決していく……
▽291 キューバも、ブレアやサンフランシスコの改革と似ている戦略。コミュニティベースに市民とのパートナーシップを取り持つことで、効率性と社会的公正や環境保全を調和させていこうとしている。
▽293 キューバは「ソーシャル・キャピタル」が凝縮された社会。裏を返せば個人主義が認められない社会。大きな政府による福祉国家をソ連の援助で確立したが、経済危機で困難になる。そこで、コミュニティ組織をいかしたボトムアップ型の問題解決方法が選ばれた。
▽296 コミュニティベースの地域医療 =〓地区診断の徹底プラス地域のかかりつけ医。
▽300 医師が住民参加型の衛生活動や学習会を開催。地区のデータを報告書としてまとめるが、地域住民を集めて、問題点と改善策について討論会を行う。住民意識の啓発に役立つ。
60歳以上の老人には、公園をつかって子どもたちとの交流も勧める=世代間交流〓
新しい潮流をいちはやく
▽308 1980年代はソ連式の中央集権体制がはびこっていた。86年からソ連に先駆けてペレストロイカがはじまる92年には大幅な憲法改正。NPOや市民組織の強化を図り、市民参加と地方分権をすすめるため、選挙制度も改革される。
▽325 「自分の家が傷んでも、ペンキも塗らずに、ただ国がしてくれるのを待っているだけ、それがキューバ人だったのです」 綾町の話〓
▽321 キューバのNPO一覧 留学したらおもろいかも〓 フェリックス・バレらセンター 環境倫理の普及・教育。海外からの専門家や学生の受け入れも。
プロ・ナトゥラレサ 環境問題。小規模な水力発電の開発。
▽336 キューバ革命後、ゲバラの「新しい人間」をつくるため自営業を禁止し国営化。経済が混乱し、「理想主義」をカストロが自己批判して、ソ連をモデルとした体制を導入。それによって経済は回復した。が……
▽342 ソ連崩壊を予測してカストロは、農村でのボランティア労働や、都市住民の農村定住を促進。それによって食料生産は増加したが、ボランティア動員ではとても間に合わない。……95年からは、売り上げ利益の半分を働く人に分けることに。
▽346 国内生産と競合する廉価な作物の輸入を制限。国内農産物を買い支える。それが農業回復や都市農業の発展に貢献。
▽349
▽356 人類の半数が都市に居住。2030年には65%になり、特に中南米では80%をこすと、国連は推計する。(〓日本の経験の意味。農の復権の可能性は?)
▽358 都市の農業化は今や世界的な潮流。その重要性が認識されるようになったのは1990年代に入ってからだ。
▽360 都市農業の世界的発展。……カルカッタでは下水を利用して野菜を栽培し、魚を養殖することで、市民需要の3割をまかなう。カトマンズは、市民の4割が都市農業に携わり、野菜や果物の3割、肉類の1割を自給。中国でも……
▽366 ボリビアの水耕栽培。コロンビアも。ペルーはコミュニティ・ガーデンづくりが盛んで、籠の中で食用ネズミ飼育は5割以上が取り組む〓〓
ロシアは、3000万世帯が都市農地の所有者になり、全農地の4%にすぎないのに、ジャガイモの88%、肉類の43%、牛乳の39%、卵の28%が、自給菜園から供給されている。
▽368 LA11カ国。市民が農業に費やす日数は週1日から1.5日だけだが、それだけで食費の1割から3割節減でき、低所得者では収入の5-10%にあたる。
▽374 「権現様の頃のほうが、ずっと暮らしやすかった」と明治生まれの祖父の母。「多くの労力を投入することで都市農地がもつ高い生産性を活用する」。オルガノボニコに匹敵する集約的農業を、おそらく世界で最初に活用し始めたのが江戸。……灰は肥料。「灰屋」が巨富を築いた。明治10年当時、死亡率はアメリカの都市よりはるかに低いことにモースは驚き「日本では糞尿を肥料として使っている」と感心している。
▽380 江戸が循環型の自給自足社会になるのは、後期になってから。戦国時代から4代家綱までは、列島改造とも言うべき大開発が行われた。……大規模な山林開発が進み、洪水が頻発……環境の制約を無視してすすめられた国土開発は環境破壊というつけをもたらし、元禄時代には、それ以上の開発ができなくなる。
▽381 「百姓は布・木綿以外は着てはいけない」。これは中国系絹糸や絹織物の消費拡大を防ぐためだった。これらの輸入品を購入するために膨大な金銀銅が流出していた。膨大な貿易赤字。←輸入品国産化 持続可能なりさいくる型自給社会へ政策転換。→幕末には自給自足が確立。
▽384 江戸時代は、ゼロ成長のモデル。地球上でのフロンティアがなくなったのが現代社会であるとするならば、資源の徹底した循環利用をすることで、人口3000万人が自給自足できる循環型社会をつくりあげたことあh、世界的に見ても重要。これは、アメリカによる経済封鎖と、ソ連方式の農法による国土荒廃、地球環境問題というフロンティアの喪失に対して、キューバ政府が選択した持続型国づくりへの政策転換と似ている。
▽387 江戸時代 水力や木製機械では西洋に劣らず、農業技術がけた外れにすぐれていた。水稲収量は当時世界でも最高水準。綿作でも、一人あたりの労働生産性はアメリカが2・3倍大きいが、土地あたりの生産性では日本のほうが3・7倍大きい。
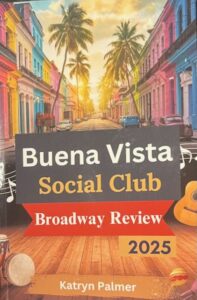

コメント