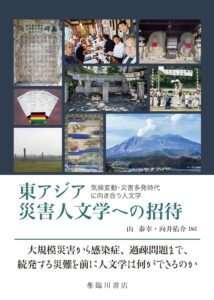東信堂 20061221
寺社や銭湯、商店街、駅舎など、町中にあるあたりまえの「場」を居住福祉資源として再評価し、紹介している。寺社は健康福祉ウォーキングの場であり、人々と語りあうデイサービスの場にもなっている。商店街もしかりだ。ほんのちょっと視点をかえるだけで、福祉社会への糸口が見つかること、中小都市こそ、そういった取り組みの可能性た高いことがわかる。
では、家やビルがひしめきあう大都会は、隣の人の顔もわからない新興住宅地や高層住宅は……。うーん。
-------抜粋など---------
▽嫁いらず観音
▽日田市・高塚愛宕地蔵尊
門前市では農産物直売。露店は21軒。12軒は氏子、9軒は近在集落の人。氏子の12軒は、毎日曜日ごとに1区画ずつ下がって順序がいれかわる。上ほど客が多いから。
露店通りは地域社会のコミュニケーションの場。
寺社は健康福祉ウオーキングの場にも。
▽京都・石川湯と泉涌寺湯 デイサービスに改装 懐かしさに心地よさ もちろん浴室は広々「元銭湯の売り」
▽釜ケ崎サポーティブハウス
▽岡山県では306の交番・駐在所のうち、71カ所に市民が自由に使える車いすトイレ。
▽草津・栗生楽泉園 交差点に赤外線センサーつきオルゴール50カ所。すべての住棟、病棟など70カ所に「音声表示器」「西1号棟角です」などとアナウンス。
はじめは針金に空き缶をつるす「盲導線」をはりめぐらせた
▽鳥取・山陰本線・八橋駅 無人駅に高齢者憩いの場 顔見知りの乗降客が声をかけていく。駅舎は、雨宿り、暖房、待ちあわせ、トイレといったさまざまな役割を果たす居住福祉資源。
▽旧JR大社駅 廃線で廃止。市民行事に利用。
▽岡山笠岡のデイサービス船「夢ウエル丸」
▽震災 5500人の9割は家屋倒壊。1割近くの焼死者も家が倒れなければ逃げられた。助かった人も、暖房も夜具も不十分な体育館などで900人以上が亡くなる一方で、老人福祉施設に救出された高齢者はほとんどが助かった。だが福祉施設も、神戸市では指定都市中最低水準で、かつほとんどが開発行政の一環として六甲山中にあり救済機能を十分発揮できなかった。……延焼を防ぐべき公園のほとんどは、人工島などの新規開発地などにあり、中央市民病院は人工島に移されていて負傷者の搬送ができなかった。
▽山古志村 仮設住宅では、村民は集落ごとに入居。診療所の医師や保健師も以前と同じ。阪神のときのように見知らぬ土地にバラバラに入居させられ、孤独死や自殺に追い込まれた人もいたのとは対照的。震災の復興対策を徹底的に反面教師とした。
▽高速道路を壊して清流をとりもどすソウルの清渓川。