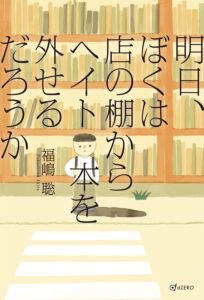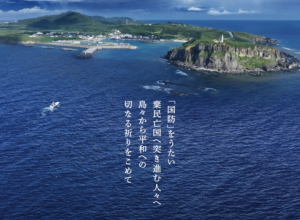毎日新聞 20061027
--冷笑、あざけりというものを殺そう。必死で考えようとする人間、それがだれであろうが、殺人犯だろうが、もはや「形骸」ときめつけられたような魂でも、その声、聞こえないつぶやきに耳を傾けたい。もう居心地のよいサロンでお上品に護憲を語りあう時代はとっくに終わっている。一線をこえなければいけない。一切の冷笑を殺し、万分の一でも実存をかけること。--
人一倍シニシズムであり皮肉屋である著者がまさに実存をかけていることがわかり、胸に突き刺さる。
イラク派兵の論拠を憲法前文にもとめるコイズミのインチキ。靖国参拝では「心の問題は誰も侵すことのできない憲法に保障されたもの」と述べながら、日の丸君が代では強制することを肯定するダブルスタンダード。おかしなことが大手をふってまかりとおってしまうことに怒りをぶつけ、「困ったことです」と口で語るだけの護憲派をも返す刀で斬りつける。コイズミの言葉を唯々諾々ときいた政治記者たちを「糞バエ」と排撃する。
でもその場に自分がいたとしたら有効な反撃ができるかどうか、と自問すると、自信がない。おそらく糞バエの一員になっていたのではないか。
オマエは今この危機の時代にナニができるのか、ナニをやろうとしているのか。……死を前にして生命の灯をぶつけている迫力にたじろがざるをえない。
——-抜粋・要約——-
▽レジス・ドブレ メディオロジーを提唱
▽小泉は、海外派兵の論拠を憲法前文に求めた。靖国参拝と中韓両国の反発にふれて「精神の自由、心の問題、これは誰も侵すことのできない憲法に保障されたもの」と述べた。いったい第二〇条はどうなってしまったのか。これまた後の世のありようを大きく左右しかねない憲法の意図的な誤用。
▽石川淳の「マルスの歌」発禁に。ファシズムを見事に表現することによってファシズムに抵抗したといえなくもないこの作品が、やはり日本的な思想風土を引きずっているように思えてならない。あるいはその達成こそが、日本におけるファシズム批判の限界を表していると感じる。限界とは、明快かつ剛直に、ストレートに頑強にファシズムと闘えないこと。物理的にもファシズムまたは鵺的ファシズムに抗えないこと。
▽……だれも命を賭けてまで抵抗なんかしてはいないと、私は思います。反動が際限なく拡大している。国家が人の内面に平気で入りこんできている。
▽戦後最大の恥辱 最悪の憲法破壊者であるファシスト(コイズミ)が、まったくデタラメな解釈によって、平和憲法の精神を満天下に語ってみせた。泥棒が防犯を教えるよりもっと悪質。ナチスは、一応は憲法遵守を偽装し、「民主的」手つづきで独裁を実現しようとしてワイマール憲法48条の大統領緊急令を利用したり、全権賦与法案を議会でとおすなかで独裁を完成していく。ワイマール憲法の権威をいっときは利用もし、世論を巧妙に欺いた。
コイズミの話を直接聞いていたのは政治部の記者たち。彼らは羊のように従順にただ黙って聞いていた。ファシズムというのはこういう風景ではないのか。……彼らの会社は巨額の費用を投じて「糞バエ宣言」ならぬ「ジャーナリスト宣言」などという世にも恥ずかしいCMを広告会社につくらせ、ひとり悦に入っている。
▽ワイマール憲法下のナチスは、どんな悪政でもできた。多くの例外的緊急規定をもうけて、政党の弾圧も自国民の抑圧も。……憲法はもはやぼろ布のように破壊されている。それなのに護憲学者たちは憲法をあたかもまだ健常体であるかのごとく語っている。彼等は有事法制反対にも自衛隊派兵反対にもたちあがらず「困ったものです」とリベラル面をして嘆いてみせる。
▽朝鮮半島の人々を殺した米軍機はどこから発進したか。平和憲法下の日本からだ。日本では目立った反戦運動もなく、戦火を利用してもっぱら金稼ぎをする。チョムスキーは、現実に戦後日本が米国の戦略的枠組みのなかでしてきたことに比べれば憲法改悪は「ささい」と語った。
▽あるマスコミのデスクが「『陛下』がないですけれども。私はいいですけどね、これは社内でとおるかどうか……」。自分という主体を隠して、同時になにかを無傷で最低しようとする。恥ずかしい語り口。ここに立派なファシズムがある。でも、彼等はリベラルなジャーナリストを自称する。憲法改悪はいけないといいつつ、組織内でたくみにバランスをとろうとする。恥はない。
▽江藤淳の遺書メモ「心身の不自由が進み、病苦が堪え難し。去る6月10日、脳梗塞の発作に遭いし以来の江藤淳は、形骸に過ぎず、自ら処決して形骸を断ずる所以なり。乞う、諸君よ、これを諒とせられよ」……この言葉には日本という国固有の精神の古層、もっと敷衍していえば、ファシズムの美学のようなものがあると私は思う。無様や恥をこの美学は嫌う。