■農村の幸せ、都会の幸せ <徳野貞雄> NHK出版 20100213
おもしろい。筆者は熊本大の教授で「道の駅」の名付け親でもある。過疎と高齢化に悩む農村だが、実は潜在的な力があり、住民みずからが地域の歴史や文化を再評価し、都会に出た息子たちを呼び寄せることで、再生の道はあるのだと説く。農村の可能性が見えてくるとともに、農村出身でないことを残念に思えてくる。
家庭から「生産」要素が失われ「消費」要素だらけになってしまったこと、〓〓、など今まで私が考えていたことは当然のように網羅したうえで、処方箋を突きつけている。こういう先生のゼミで勉強できたら楽しかろうと思う。
「農村の幸せ」がよくわかるが、逆に「都会の幸せ」についての言及は足りないと思う。
▽8 菊池養生園の竹熊宜孝さん 医食同源を主張する医師。「土からの医療」と称して注射より野菜を食べさせるのが好き。
▽18 中尾佐助の「栽培植物と農耕の起源」〓(岩波新書)
九州や出雲の古代国家から大和に政権ができていく政治闘争史は、稲作普及の歴史。天皇家は、生産性がきわめて高い稲作の技術者兼普及者だったのでは。稲作技術を教えるかわりに税を受けたのでは。……出雲は出雲で、斐伊川を軸に稲作地帯を形成し独自に力強かった。九州も同様。そうした地域・勢力に、稲作技術を持たなかった周辺が穏やかに吸収された。
▽23 小さな集落が連携してつくっている大字のムラ=自然村。ある程度の水準の自給自足的生活が可能な単位。室町時代に各地に形成される。室町期は農業の生産力が飛躍的に伸び、地域社会を自主的に運営できる仕組みをつくった。用水路やため池、寺、自治組織、正月や盆の行事、独楽回しやたこあげなども、この時期にできた。
このムラは、昭和30年頃まではっきり見えていた。だから昭和30年以前に物心ついた人は室町時代に行っても生きていける〓。かまどでご飯をたけるし……
今も、議員や農協総代の選出基盤はムラ。神社や祭りなどの氏子もムラでくくる。自治会の地域割も。
▽25 高度経済成長期に「専業農家」と「消費者」が誕生。
▽33 高度経済成長期以降に少年期を迎えた40歳以下の世代 テレビやテレビゲームは日本人の生活や遊びを一気に変えた。はないちもんめ、馬乗り、馬跳び、こま、凧揚げ、陣地とり、鬼ごっこなどは、室町期に成立している。〓昭和35年ごろまでは、遊びも室町期からほとんどかわっていなかった。
▽43 貯蓄をしないフィリピン人 日本のムラは「地域機能共同体」。ウェーバー 「合理的」な未来への「貯蓄」の精神が、集団的に訓練され、人々が共有しているか否かが、産業化・近代化の鍵を握っている。フィリピンは相互扶助が発達しており、共同体的性格が強い。が、日本の村落共同体とどこか違う。「井戸は、金を持っている人が掘ってくれるもので、貧乏な自分たちが掘るものではない」という意見。
日本のムラでは、相互扶助だけではない。ある共通の課題に対して集団的にまとまり、資金調達も含めて組織化され、高度な計画をつくり……学校までつくってしまう(〓久万〓その精神が失われているのが都会の個人主義社会、農村での孤立?)。そのための共同訓練としての、溝さらえや道普請、共有林の共同下刈り。活動資金として部落費も徴収する。ムラが法人的性格をもち、ある目標に向かって機能的に動く「地域機能共同体」。フィリピンやタイ、韓国の集落とはだいぶん違う。〓〓中米は?
▽46 日本の企業が成功したのは、ムラで機能的共同体の訓練、集団的にある目標を達成するための技術と精神を養ってきた人々がいたから。ムラの行動原理と精神がサラリーマンの原型をつくった。サービス残業もムラの苦役の延長。他社とのシェア争いに徹夜で働くのも、隣ムラとの水争いと同じ。共同体の生き残りのため。(〓だから企業はムラ社会、→個人というムラに引きこもる=広井)
▽51 乾燥地帯の農業は「保水農業」。雑草は生えないから、水を与えることが重要。大規模農業が可能。稲作は「除草型」。労働力を雑草を取る方に向ける。人手がかかり大規模化には向かない。対極にある農法なのに、日本の農政は、大規模化を推進してきた。
▽57 農協は販売組織ではない。市場にしか出さない。集荷組織でしかない。市場が販売業者に配分する。この流通過程のなかで、生産者や消費者には無関係な農作物の企画化や品質管理が発生する。流通業者の都合で、食べ物ではなく「商品」になっていく。規格化された農産物をつくり、コスト低減や安定的定量出荷を強要される。これらをクリアしたところが「産地」。産地同士が競争し、より安くて同質な農産物をつくらされる。競争に敗れた産地はつぶれ、農村は疲弊していく。
▽66 100年前、イギリスの食糧自給率は30%を割っていた。農村も疲弊していた。今の日本とほぼ同じ。イギリスは、農業を再生し、緑の空間や、町の景観、住居、福祉、環境に金を使った。その結果100%を超える穀物自給率を戻すことに成功。
▽77 米消費量激減。おかずの割合が高い。
▽88 日本の農業研究は、消費者の分類すらない。彼らはすべての消費者は価格と味だけで米を買っていると思っているから、いかに安くおいしい米を作るかの研究しかしない。消費者を分類して考えないことが、農学の最大の欠陥。
▽93 農業基本法農政の破綻。昔ながらの「農業生産力論」という経済至上主義的な発想しかない。価格・コスト低減・良品質化。だからなんでも農業基盤整備に話が向かってしまう。
平成11年に「食料・農業・農村基本法」をつくった。「食料」という言葉がでてきたのは、消費者が目に入ってきたと思える。「農村」は、地域社会のこと。3分野を総合的にやらなければならないということに変わったのは進歩。
政策的に新たに推進されているのが「農業の多面的機能の活用」と「食育」。これが、グリーンツーリズムや都市農村交流、農業体験などの事業につながる根拠になった。かつての農業指導者が全く無視してきた分野、自分たちがノウハウをもたないものを今になって一生懸命展開するところに苦しさがある。
▽99 一村一品運動のなかから、「関あじ、関さば」などが生まれた。だが、特産品はつくったけれど、それ以外の重要なこと、後継者対策や家族の縮小、地域運営問題などに目が向けられなかった。ただひたすら一村一品をやるだけで、大分県ではさらに過疎がすすんだ。そのせいで、20年間、日本の農山村の地域作りが政策的に停滞した。〓
一村一品は、普及員や農林行政マンにとっておいしい仕事だった……。強力な政策は、一方で他のものを見えなくする。
規模拡大も、産地間競争もダメ、一村一品もダメだった。とりあえず今元気な「グリーンツーリズム」でもやろう、という苦肉の策。その結果、安心院に視察に行ってばかり。
一村一品とグリーンツーリズムを比べると、前者のほうがすぐれている所がある。農家のお母さんたちがグループで活動をしたというところ。後者は、主役になれるのは、特定の条件をクリアした少数の人や都会の人間。
欧州のルーラルツーリズムとは似て異なる。
欧州の村では、必ず1軒2軒のパブやガイストなどの外食システムがあり、村の人が支えている。昼のランチもある。外食文化が発達していない日本の村落とは大きな違い。
日本のグリーンツーリズムは「ふれあい」を重視する。それが、「ハードルが高い」と農家の人に思わせているのかも。
▽107 農水省でグリーンツーリズムを担当しているのは、構造改善局の流れを汲む農村振興課。農業土木の担当セクション。自然科学的発想が中心で、グリーンを所轄するのは無理がある。
グリーンツーリズムは否定しないが、農村活性化=グリーンツーリズムという政策的な画一化がいちばん恐ろしい。
▽109 安心院にはリーダーの宮田静一さん。成功するかどうかは、それを自分の天職と思って仕事をする民間の人が何人いるかによる。
▽112 棚田オーナー マスコミは報道したが、都会の人を呼んだが、担い手にも農地保全にもならない。でも、オーナー制度はやめないほうがいい。それは集落の「新しい祭り(活動)」だから。高齢者だけで意気消沈しているより、都会の人をダシにした新しい祭りだと思えば、赤字でも腹が立たない。
▽116 5000人の町に50万人の交流客が来るとしても、その町にいるのは1日だけ。比較するべきは、5000×365=180万人。どちらが大切かはわかる。詐欺論的な都市農村交流論にはまったのが、商業関係者や町おこしのリーダー、役場の熱心な職員。「町の定住人口ではだめだ」と藁にもすがる思いで都市の交流客に期待する。熱心な行政マンは「夢のあるわがマチづくりだ」とさまざまなイベントを考え、交流施設を建ててきた。(〓双海町や吉田村の場合は〓)。
交流事業の限界と可能性を冷静に考える必要がある。観光客は文具店や電気屋にはいかない。土産物店や旅館など、地元経済の10分の1程度しかうるおわない。
暮らしに根ざした農村政策を。
▽120 家族の6つの機能。・生産共同の機能(昭和35年ごろまで) ・消費共同機能(自分で生産できない子どもも食べていける。家族規模が小さくなり、消費共同機能が弱くなると、老人の扶養をどうするかという問題が起きてくる) ・性的欲求充足機能 ・子どもの生殖と養育機能 ・生活拡充機能(炊事、掃除、衛生、娯楽……これを専門分業化して外注化したのがサービス産業) ・精神的安定機能=家族の愛(この機能は、独立しては成立しえず、他の家族機能が働いている所にしか成立できない。家族機能の一部を外部化している産業社会で家族の愛を維持するのは困難。だから古い家族のにおいがんこる農村に憧れる)
家を捨て、農業を捨て、マチにでたのは貧しかったから。これを解決する方法が、産業化・近代化。専門的分業化による生産力の向上と、そのシステム化が、現代生活の豊かさを生み出した。
▽125 社会の近代化とは、家族の持っていた生産共同機能と生活拡充機能を、専門分化したもの。その仲介をするのが学校教育。家族や故郷から人間を引き離して、効率のよい組織に変えていくのが学校。その結果、豊かな社会ができるが、今度は家族や故郷から引き離され、人々は孤立したり精神的に不安定になる。
▽132 今、日本で最も豊かな暮らしをしているのは、地方公務員。とくに農家で役場に勤めている人。兼業農家は非常に安定して、豊かな暮らしをしている。「農業」ではなく「百姓仕事」が生活のなかにあり、もともとの日本人の暮らしにかなり近い。
▽138 親族とのネットワークをつくって、親族を含めた大きな家族網をつくる。筆者も、義姉夫婦が母親の里近くの田舎に家を建て、その近辺に私たち夫婦、さらに義妹夫婦、義兄も……半径3キロ以内に4家族が住んでいる。……自分個人の世界や未来だけを見るのではなく、自分との関わりがある人々の世界と、自分が歩んできた過去にも、私たちの暮らしを支えてくれる大切な資源があるということ。あなた自身の家族や親族と、あなたの住む地域社会と故郷を見直して行動する、作業を始めるべき〓〓(個人の「生きがい」から関係性へ)
▽144 T型集落点検 夫婦同伴で公民館に集まり、葬式組程度の班に分ける。模造紙の地図に、同居家族の性別、年齢、続柄、職業も書き込む。都市に出て行っている子どもや孫も書き込み、Uターンしそうな子にチェックを入れる。これによって、誰が農地や山の相続を現実的にできるのかも見えてくる。それをベースに、10年20年先の集落の運営を考えていく。
10年後にこの集落がどうなっているかを皆で一緒に考える。(「集落点検」=地区診断)
実家の母親は、近くにいれば300万円分の価値がある。ベビーシッターや保育園の送迎、買い物、掃除もただでしてくれる。すごい「人間関係資源」。
▽150 江戸時代までの日本では、家の直系が4,5代つづくことなど滅多になかった。
▽154 「嫁」としか見ないことを嫌がる。お父さんがお母さんをちゃんと愛しているという暮らし方をしていない。それが嫌がられる。夫婦が輝かないと嫁も来ない時代。
「母ちゃんを愛しているから、(会社の飲み会で)一緒につれてきていいか」と勤め先で言える村であれば嫁は来る。広島県総領町〓「逆手塾」の和田芳治さん「夫婦伴遊び倶楽部」をつくった。「これが家内の和子です。いい女でしょ。私は惚れてます」と紹介してまわる。都市部でこういう夫妻が増える前に、農村の方で先に増やすことができたら、農村にも嫁は来るでしょう。
▽160 高知県十和村の元役場職員の川村一成さん。小学校区内の同世代の夫婦に「今晩がんばれ」とはっぱをかける。コンサルにも行政にも頼らず、「子どもを産めるのは地域の同世代の夫婦」ということに気づき、それを大胆に実行してもらうよう行動したこと。
〓島根県津和野町の農事法人「おくがの村」〓のリーダー糸賀盛人さん。集落ぐるみで子どもづくり。集落営農は、補助金獲得のためや生産効率をあげるためだけにあるのではなく、ムラの人の暮らしを守り、子どもを育てていくための集団的意思の確認の場として機能する。
▽167 50歳になった娘=おばさんを使う。おばさんは自分の親はもちろん、隣の家の一人暮らしのおばあさんの世話までしてくれる。こういうおばさんになった娘に交通費を出してあげるなどの政策をどう考えるか。……都市農村交流のターゲットを身内にする。帰れないならば故郷に通ってもらう。
▽170 熊本県小国町の江古尾の集落。外孫を呼んで面倒をみる。15人の孫が帰ってきた。都会の子だけの都市農村交流では、役員とリーダーしか動かなかったが、「イエ」の孫、「ムラ」の子が参加しはじめると、集落総出に。イベントが終わっても帰らず、夏休み中残っている子も。
▽186 福岡県は有機農業を引っ張ってきた。減農薬運動の宇根豊、合鴨農法の古野隆雄、消費者との交流活動「むすび庵」の八尋幸隆。
昭和45年ごろから、医師の安藤孫兵衛を中心に「健康と食」を軸にした有機農産物を求める動きが出てきた。当時は、山下惣一さんでさえ「有機農業は勇気農業だ」とスカしていた時期だった。
▽189 宇根さん「虫見板」。益虫でも害虫でもない「ただの虫」を見つけた。「昔の百姓は、『ここの田んぼには害虫が発生しよるけど、株あたり10匹ぐらいだ。……心配ない。でもこっちの田んぼに10匹いたら、ちょっと怖い』ということを皆知っていた」
忙しくて毎日田んぼを見られないから、害虫が発生したら、プロに聞こう、となる。百姓がプロでなくなり、普及員や農協指導員に聞く。しかし普及員にしても、あとから「農薬が効かなかった」と言われても責任を取れないから、いきおい過剰散布になる。
▽192 宇根さんの減農薬運動の成功 最初に実践したのは生活改善グループのお母さんたち。3ー5反の小規模農家。しかも都市内だった。これがもし専業農家が多い地域なら「もし失敗したら責任とるんか」ということになったかも。
「農と自然の研究所」を設立。福岡県前原市二丈町福井で活動。
▽195 合鴨農法の古野隆雄・久美子夫妻
合鴨農法の普及は、農家が自分でやらなければダメ。普及所や農協は、生産者にはチャンネルがあるが、消費者にはもっていない。
▽200
▽202
▽204 農業者やリーダーの分類。技術型リーダー(篤農家)、政治型リーダー(行政と交渉する能力の高い人=賃上げ闘争=価格安定化、労働条件改善=圃場整備などを交渉する)、経営型リーダー(農産物の販売力や企画力、現代の消費者や社会変化への対応のための組織の再編能力)、農の文化型リーダー(農の多面的機能を発揮し、直販や加工、農家レストランや食育運動などと連携)
▽210 大木町の「きのこの里」 女性と若者に冷たい農業・農村はつぶれる。地域の非農家の主婦たちも積極的に農業に取り込む。
▽213 昭和30年ごろの日本では食べ物代に3兆円を使い、その46%が農産物の代金として農家に戻っていた。昭和60年代になると、70兆円も使うのに、農家に戻るのは16%。現在では80兆円のうち12%程度10兆円。輸入農産物をのぞくと、国内の農家には5.4兆円にしかならない。
鳥インフルでは、卵価格下落で、かなりの養鶏農家がつぶれたが、食品会社はますます太った。消費者も政府も低価格と安全性だけを要求する。おいしいところは食品関連会社がもっていく。
生産だけやっていても16%しか戻ってこない。いくら規模拡大し、コスト削減しても、16%の中の話だからもうかるわけがない。
船方総合農場 牛乳の独自販売網をつくる。生産だけでなく、加工、流通、サービスをはじめた。
「道草リゾート」
▽219 平成元年に「道の駅」ができる。その源流は船方のミルクタウン構想にある。
▽222 「ぶどうの樹」の小役丸秀一さん 岡垣町。「ぶどうの樹」のほか、旅館「八幡屋」、レストラン「野の葡萄」などを経営。
ぶどうの樹のスタッフと農家は月に1回、食材・料理の検討会を開く。料理のためにどんな食材をつくるか検討するのではなく、農家がつくった農産物でどのような料理ができるかを検討する。「食から農」ではなく「農から食」。
▽226 中核兼業農家 自分の畑に「百姓館」をつくった。神楽の練習や、落語家を呼んだり、直販所を併設したり。
▽232 水俣久木野地区寒川の棚田 沢畑亨さん 都会の若者を「愛林館」に長期滞在させて、食事と焼酎だけで働かせる手腕。
▽233 「番頭さんの会」オーナーではなく、雇われている人たち。共通する組織がなく、孤立していた。そこで私が呼びかけて結成。「愛あるサギ師」
▽237 番頭さんの会の参加者らが、社会人院生として入学してきた。「トクノ・スクール」。学生が学校に来るばかりでなく、先生が学生のところに行く。実践型・現場型教育システムに参加を。〓〓




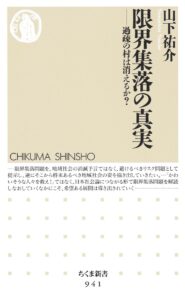
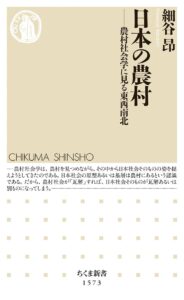


コメント